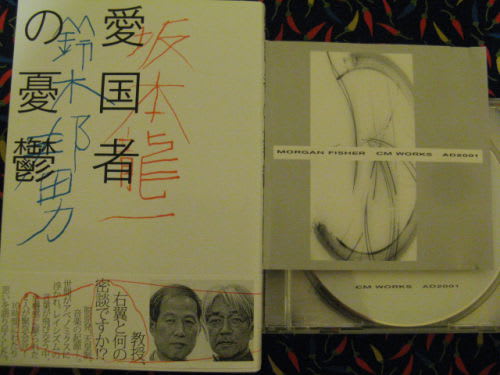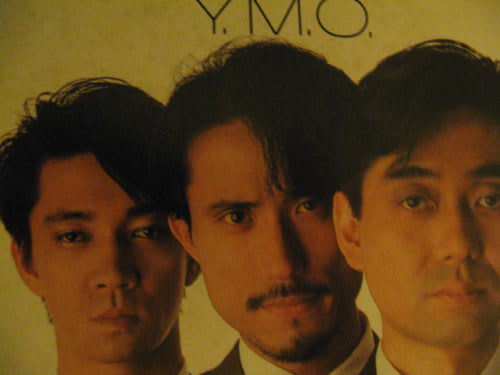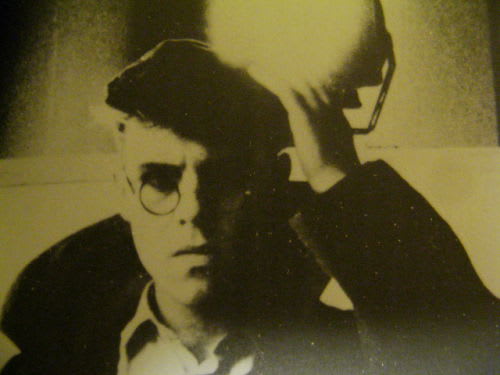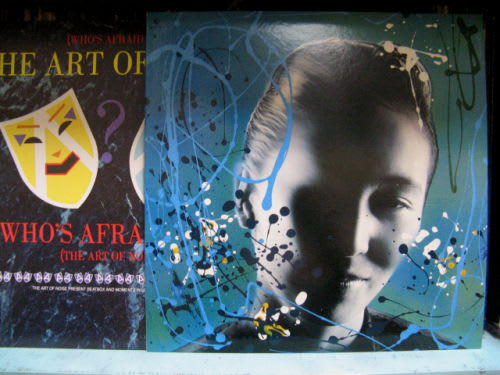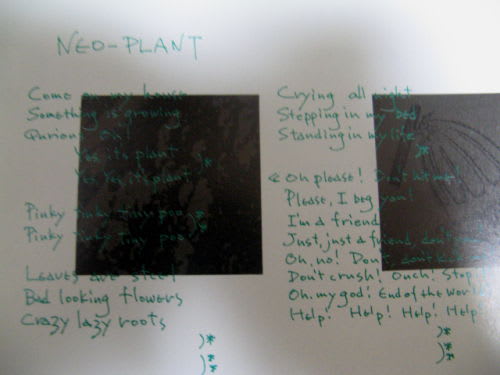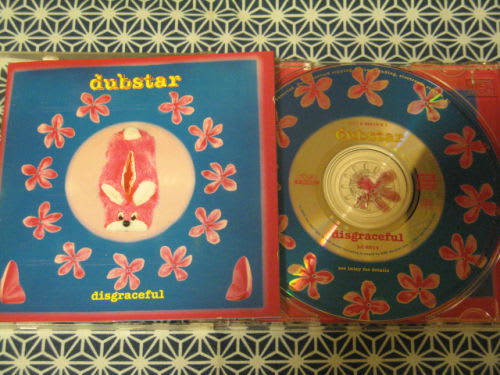1983年は、ニューヨークのヒップホップ文化が多様なポップミュージックに影響を与え、ニューオーダーの「ブルー・マンデー」「コンフュージョン」に始まり、ローリング・ストーンズ(の当時新作「アンダーカヴァー・オブ・ザ・ナイト」にまで)影響が伝播していた。
(と言っても、ストーンズメンバーがヒップホップを演じる訳ではなく、エッセンスとしてエンジニアが取り込んだものに過ぎないが)
そんな中で、1983年暮れ近くに発表されたホール&オーツの素晴らしきシングル「Say It Isn’t So」。
この曲には、東西?右派左派?限らずの喝采の嵐。
80年代初頭、彼ら二人が産み出すソウルフルな音楽世界が、MTVを伴って世界に広がった末に、シングル「Say It Isn’t So」に到達した幸福な世界。二人の内的エネルギーの発露。
それを経て、1984年発表された新作は「Big Bam Boom」。(後のスクリティ・ポリティの作品名のよう)
この1984年特有の切迫感がにじむ時代状況下でありながらも、ホール&オーツ頂点の季節。

この作品には、ある極みまで来れたがゆえの余裕・遊びがある。
アルバムの音作りは、当時売れっ子のアーサー・ベーカー(上記「コンフュージョン」等12インチで活躍)と1982年ロキシーの「アヴァロン」を産み出したボブ・クリアマウンテン。
A面いきなり、それまであった彼らの音像から離れたハードさを持つ「ダンス・オン・ユア・ニーズ」で始まる。
野太いベーシックリズム、機械的ドラムの背景で、女性コーラスが寸断前後リピートしつつ鳴り、スクラッチな重なり合いをする。
そのまま2曲目「アウト・オブ・タッチ」(このアルバムから最初のシングルカット曲)へ地続きで入って行く。
■hall & oates ”method of modern love”1984■
A面3曲目は、2枚目のシングルカットとなった「メソッド・オブ・モダン・ラヴ」。
性急でアップテンポな1,2曲目から一転して、スローダウン。
月明かりの夜にふわふわと浮かぶような詞・メロディ・よく”泣く”ギターが合い間った姿は、実に美しい。

このアルバムでは、上の3曲とは別に、好きな曲がA面最後に収録されている。
聴き込むたびに鳥肌が立つような官能を覚える曲「Something Are Better Left Unsaid」。
日本語タイトルは「言わずにおいて」。

■hall & oates “something are better left unsaid” 1984 ■
アルバムの装丁としては、「ヒップホップを取り込んだホール&オーツ」という表層的言い回しがあったとしても、それはあくまで表層。
魂に訴えかけるソウルフルな音楽は揺らがない。
彼らの曲を聴いていると、いつも思うのは、イントロからノックアウト。。。という曲も多いが、後半になるほどヴォルテージが上がって行く曲があって、そこで深みが出るものがある。この曲は後者に属する。
彼ら独自のスタイルに引き込まれて、感情を揺さぶられる。
ふだん火を焚いてもなかなか燃えないこころだが、時代のはやりすたりによらず、今も自分のこころに日をともす彼らの音楽は有効である。