武家屋敷の周りを散策してきました
植物好きの私は今回も
木々や植物を見たくて出かけたのです

まずは武家屋敷通りの北端にある
江戸時代は武士の敷地
その後は旧角館中学校のあった場所からです
広~い敷地は緑がいっぱい

武家屋敷にはモミジやカエデ
種類が豊富に植えられているので
葉の下から垂れ下がる実は
色もさまざまです
このモミジは淡い紅色の実がいっぱいでした

郷土の日本画家 平福百穂は
アララギ派の歌人でもありました
その百穂に校歌の作詞を依頼された島木赤彦が
未完成のまま途中で亡くなり
その後、百穂に後を任された斉藤茂吉は
中村健吉や岡麓など
アララギ派の総力を結集して完成させたのです
上は茂吉より百穂に渡された原稿をそのまま写した碑です
修正を加えた朱色の文字もそのまま
原稿の最後に大きく朱色で
「大体余り 恥ずかしくなからんと 存じ候 」
と茂吉が書いています
自信のほどがうかがえますね


その平福百穂の碑
肖像は田口省吾氏が書いてます
田口省吾氏は田口菊汀の息子さん
田口菊汀は角館出身
孫が芥川賞の高井有一氏
下に平福百穂の歌二編が刻まれています
「うつろへる 川乃(の)ながれ越(を) 見る耳(に)さへ
年ふり尓(に)計(け)里(り) 國(くに)越(を)出し与(よ)里(り)」
『うつろえる 川の流れを 見るにさえ 年ふりにけり 国を出しより』
「ひ登(と)時耳(に) 芽吹き立ち匂ふ みちの久(く)能(の)
明る記(き)春耳(に) あひに計(け)留(る)加(か)毛(も)」
『ひと時に 芽吹き立ち匂う みちのくの 明るき春に あいにけるかも』

小田野家の「ガマズミ」が白い花を咲かせていました

可憐な花です

武家屋敷にはあちらこちらのお宅にある
「ツリバナ」
青い実をつけ始めました

江戸時代には藩の分校である
弘道書院が建っていた場所は
今は空き地になっています
そこに忘れな草がいっぱい

小田野家のシンボル
「クマザサ」です
恥かしながら私はクマザサを
生き物のクマという字を書いて
熊が好んで食べるからクマザサというのだと信じていました
案内人になり小田野家のクマザサに出会い
初めて「クマ」は歌舞伎の「クマドリ」から来ているものだと知りました
ご覧ください
若い葉っぱにはクマがありませんね
人間と同じで歳を取ってくるとクマができるんですね・・・・・
と案内の時に笑いを誘いながら説明したのも懐かしい












































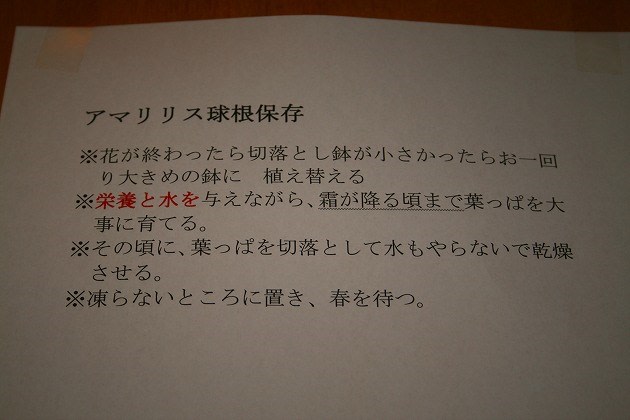
 良くなります
良くなります

















