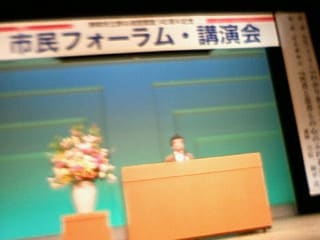あの国は、どうしてこのような国際世論を無視するかのような核実験を繰り返すのでしょうか。明らかに間違っています。
第一部が「わかりあえる医療のための広場」市民フォーラム。「医療用語」の認知度と理解度のギャップが患者と医療側のインフォームコンセントを左右するということからの実態と改善をめぐるシンポでした。
呼吸器科の千原医師が司会となって心臓外科の山崎医師、血液内科の岩井医師、内科の河野医師、岩井看護師他2名、地球温暖化防止センターの服部さん、患者支援図書室の関野さんらがパネリスト。
ゲストパネリストは、読売新聞用語委員会幹事の関根健一さん。例えば、ショックという言葉は患者側は94,4%は認知しているが正確な言葉の意味を理解しているのは43,4%。この現状をどう踏まえるか。
第二部は作家の立松和平さんの「患者と医師の関係」をどういう関係として捕らえていったらいいのか、を「自己犠牲」と「救い」という宗教的意味合いを媒介にしての講演。立松さんらしい展開でした。
島本光臣病院長の「今日の企画は良かったと思う。「地域で医療関係者を育ててほしい」という言葉がまだわかってもらえない現実がある。地域医療をしっかりと支えて生きたい」でしめくくられました。
呼吸器科の千原医師が司会となって心臓外科の山崎医師、血液内科の岩井医師、内科の河野医師、岩井看護師他2名、地球温暖化防止センターの服部さん、患者支援図書室の関野さんらがパネリスト。
ゲストパネリストは、読売新聞用語委員会幹事の関根健一さん。例えば、ショックという言葉は患者側は94,4%は認知しているが正確な言葉の意味を理解しているのは43,4%。この現状をどう踏まえるか。
第二部は作家の立松和平さんの「患者と医師の関係」をどういう関係として捕らえていったらいいのか、を「自己犠牲」と「救い」という宗教的意味合いを媒介にしての講演。立松さんらしい展開でした。
島本光臣病院長の「今日の企画は良かったと思う。「地域で医療関係者を育ててほしい」という言葉がまだわかってもらえない現実がある。地域医療をしっかりと支えて生きたい」でしめくくられました。