スカーレットの放送が始まって以来ずっと訪ねたいと思っていたところだ。まったくミーハーな話だが、このドラマの脚本を書いた水橋文美江がインタビューで、「このドラマには悪人はひとりも出てこない。」と語っていた。悪人がひとりもいないとはまるで桃源郷じゃないか!そこいったいどんなところなのだろうかとそんなに距離も離れていない信楽の町にがぜん興味が湧いてきた。
思い立ったのは去年の暮れ。しかし、名阪国道は雪の恐れもあるから、これは春になってからだろうと考えていたらこのコロナショックだ。さすがに県外ナンバーの車が駐車場に止まっていたら後ろ指をさされるだろうと我慢をしていたが、やっとそのチャンスが訪れた。
この梅雨時、今日も昼からは雨の予報だったので朝は思いっきり早く家を出た。まあ、例年、高野山に上るのも朝が早いが、人がいなくてひっそりとした観光地はこれはこれですごく魅力的なのである。
午前4時40分にガソリンを給油してそのまま阪和道に乗り込む。
京奈和道は橿原市内だけがつながっていないだけでそのまま名阪国道に乗る。しかし、奈良県人の車の運転は荒くたい。割り込みは当たり前でスピードも速い。名阪国道に入っても交通量は多くて道もけっこう荒れているし、加えて軽自動車ではアップダウンのきつい自動車専用道路は大変だということを思い知った。坂道でまったく加速しない。おまけにこんな交通事情だと半自動運転システムも役に立たないのだ。
僕の思惑では2時間10分くらいで現地到着と考えていたけれども2時間40分のスコアになった。
カーナビの案内もいい加減と言えばいい加減で、大内というインターチェンジから下りたのだが、その後は普段は誰も通らないのではなかろうかという山道が続いた。舗装はされているものの、両側からは草が飛び出ていて、上の方からも木の枝が垂れ下がってきている。

車高が2メートル近い僕の車は二、三度その枝をひっかけてしまった。これから狸の里を訪ねるのでこれはきっと化かされているなと思いながらなんとか幹線道路に出ることができた。ちなみに帰りはずっと2車線の道路を通って上野インターチェンジから帰ることができた。帰りによく見たら隣のインターチェンジだった。やっぱり化かされた・・。
今日の目的は街並みの散策もあるけれども、スカーレットのロケ地になったところを何か所か訪ねてみたいと考えている。事前に調べたのは、丸熊陶業のロケが行われた窯元と、最終回で喜美子さんが上っていった坂道だ。
信楽の中心街というのはそれほど大きくなく、外周道路は3kmと少ししかない。そのコースの最後あたりに目的の場所があるらしい。
信楽駅前の今時らしいマスクをした大狸を見て新宮神社を参拝。


そこから外周道路を歩く。最初のところは何もないところだが、川沿いの路肩を見てみるとワラビがやたらと生えている。ここは春に来るといい感じだ。ワラビはその後いたるところで見ることができた。

道を歩いていると、ちょっと脳みその暖かそうな男性が声をかけてきた。「観光ですか?」「そうなんです。」それだけの会話だが、睨まれるよりも気持ちがホッとする。
丸熊陶業のロケは山文という窯元でおこなわれたらしく、誰もいないが敷地の中に入ってみると、その時の写真が小さなパネルになって飾られていた。




もう少し奥にも嘉元があって、近づいてゆくと、庭の草むしりをしていたおばあさんが声をかけてくれた。
和歌山からきたことや、スカーレットのドラマにあこがれてやってきたことを話すと、観光マップを手渡してくれて、目の前の煙突もよくドラマに出ていたんですよと教えてくれた。

そして、丸熊陶業の登り窯は別の窯元にあるということも教えてくれた。
うちはギャラリーもやっているので10時過ぎに来てくれたら作品を見ることや買い物もできますよと教えてくれたがこれは事情があって実現しなかった。
再び外周道路に戻り喜美子さんが上っていった坂道を目指す。それはすぐに見つかった。目の前には卯山窯という窯元があるのだが、そこの奥さんらしき人が植木に水をやっていたので念のために聞いてみると、たしかにこの場所がそうであった。ちなみに武志君と真奈ちゃんが並んで歩いた坂もこの場所だ。



歩いてゆくと1軒すでに開店している陶器屋さんがあった。中をのぞいてぐい飲みの値段を聞いてみると釉薬のかかっていないものはけっこう高価だと言われた。値札が貼られていなかったので、ちなみにこれっていくらですかと聞いたら1万円です・・。ウッ、これではおみやげに買って帰れない・・。となると、ギャラリーを構えているようなお店だともっと値段が跳ね上がりそうでさっきのお店には寄らないでおこうと決めた。
そして登り窯のある宗陶苑を訪ねる。

ここのお店もすでに開店準備に入っているようで入り口が開いていた。若女将さんらしき人が招き入れてくれた。ここで恥をしのんで、1000円くらいで買えるぐい飲みってありますかと聞いたら、けっこうあるようだ。そして聞いてみるとほとんどは釉薬をかけずに焼いた信楽の土の色がそのまま出ているものだそうだ。まさしく緋色、スカーレットだ。
小ぶりなものは1個700円。これで十分。2個買って1540円しか払っていないのにお茶までふるまってくれたうえにいろいろな話を聞かせてくれた。
登り窯はもちろん、撮影で使われたタヌキの置物はほとんどがここの製品だということ、陶芸の森の近くの玉桂寺駅のそばには川原家と、タヌキの置物が置いてあった三差路があるということ。どちらも今もそのまま残っているらしい。(川原家は入り口の門だけで、家はセットだったそうだ。)
ちなみに、ここの登り窯は現役で年に2回は火を入れて製品を作っているそうだ。今は8月の火入れに向かって焼くための製品を窯に並べる直前で、窯の中に棚を組んでいるところだそうだ。

喜美子さんと照子さんが話をしていた通路にも薪も大量に積まれていて、薪だけであの巨大な登り窯の温度を維持するらしい。すごい。

僕もそこに行こうと駐車場まで戻ると、休館日と書いていた伝統産業会館というところの扉が開いていた。さっきの宗陶苑の若女将さんに、ここには新たに喜美子さんの穴窯が移築されて展示される予定だということを聞いていたので、事務の人に聞くと、受付の反対側に照明を落とされた状態で展示されていた。あの、吉野川さんのタヌキや目覚まし時計も置かれていたが、公開前なので写真撮影はNGとのこと・・。残念。
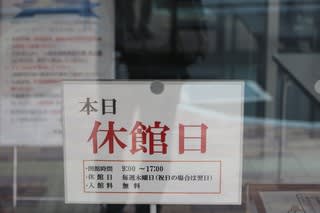
車に乗って移動。玉桂寺駅まで行ってみたがその場所がまったくわからない。そんなに道がたくさんあるわけではないのだがやっぱりわからない。それに、道は狭く、森の中を行くようなところばかりでその先に何があるのかわからない。吉野川さんが土を掘っていたっぽいところがあっただけだ。



そのかわり、巨大なタラノメの木の群落を見つけた。どうも盗られた形跡がない。この辺の人たちはタラノメは食べないのだろうか。市街地からは目と鼻の先なのに・・。

最後に陶芸の森へ。ここには神山清子の作品とともに、八郎さんが大賞をとった壺も展示されていた。


そろそろ雨が気になってきたので午前11時半に信楽を後にした。
帰りの幹線道路沿いの窯では煙突から火柱が立っていた。ここは観光地でもあるが、確かに産業と創作の場でもあるのだ。きちんと生きている町なのだ。

信楽で出会った人たちは確かに優しい人ばかりだった。そして、人だけでなく、山菜採りにとっても桃源郷のようであった。
そして僕のおみやげはふたつのぐい呑みとマグカップ。加えて、喜美子さんのように陶器の欠けらを拾ってきた。


多分、室町の物ではなく、ただの火鉢の欠けらだと思うけれども、僕の人生のお伴になってくれるだろうか。
買ってきたマグカップも喜美子さんの初めて作ったコーヒーカップのように、縁が欠けたものだ。B品として安く売られていた。


もうひとつ拾っていた素焼きの欠けらの端くれを細かくすり潰し、カシュー塗料と混ぜて即席のパテを作り割れ目に盛ってみた。ついでに漆の粘土で作られたぐい飲みの欠けたところも直してみた。
家に帰っても楽しみが続く信楽なのだ。


2020年5月25日探訪。
思い立ったのは去年の暮れ。しかし、名阪国道は雪の恐れもあるから、これは春になってからだろうと考えていたらこのコロナショックだ。さすがに県外ナンバーの車が駐車場に止まっていたら後ろ指をさされるだろうと我慢をしていたが、やっとそのチャンスが訪れた。
この梅雨時、今日も昼からは雨の予報だったので朝は思いっきり早く家を出た。まあ、例年、高野山に上るのも朝が早いが、人がいなくてひっそりとした観光地はこれはこれですごく魅力的なのである。
午前4時40分にガソリンを給油してそのまま阪和道に乗り込む。
京奈和道は橿原市内だけがつながっていないだけでそのまま名阪国道に乗る。しかし、奈良県人の車の運転は荒くたい。割り込みは当たり前でスピードも速い。名阪国道に入っても交通量は多くて道もけっこう荒れているし、加えて軽自動車ではアップダウンのきつい自動車専用道路は大変だということを思い知った。坂道でまったく加速しない。おまけにこんな交通事情だと半自動運転システムも役に立たないのだ。
僕の思惑では2時間10分くらいで現地到着と考えていたけれども2時間40分のスコアになった。
カーナビの案内もいい加減と言えばいい加減で、大内というインターチェンジから下りたのだが、その後は普段は誰も通らないのではなかろうかという山道が続いた。舗装はされているものの、両側からは草が飛び出ていて、上の方からも木の枝が垂れ下がってきている。

車高が2メートル近い僕の車は二、三度その枝をひっかけてしまった。これから狸の里を訪ねるのでこれはきっと化かされているなと思いながらなんとか幹線道路に出ることができた。ちなみに帰りはずっと2車線の道路を通って上野インターチェンジから帰ることができた。帰りによく見たら隣のインターチェンジだった。やっぱり化かされた・・。
今日の目的は街並みの散策もあるけれども、スカーレットのロケ地になったところを何か所か訪ねてみたいと考えている。事前に調べたのは、丸熊陶業のロケが行われた窯元と、最終回で喜美子さんが上っていった坂道だ。
信楽の中心街というのはそれほど大きくなく、外周道路は3kmと少ししかない。そのコースの最後あたりに目的の場所があるらしい。
信楽駅前の今時らしいマスクをした大狸を見て新宮神社を参拝。


そこから外周道路を歩く。最初のところは何もないところだが、川沿いの路肩を見てみるとワラビがやたらと生えている。ここは春に来るといい感じだ。ワラビはその後いたるところで見ることができた。

道を歩いていると、ちょっと脳みその暖かそうな男性が声をかけてきた。「観光ですか?」「そうなんです。」それだけの会話だが、睨まれるよりも気持ちがホッとする。
丸熊陶業のロケは山文という窯元でおこなわれたらしく、誰もいないが敷地の中に入ってみると、その時の写真が小さなパネルになって飾られていた。




もう少し奥にも嘉元があって、近づいてゆくと、庭の草むしりをしていたおばあさんが声をかけてくれた。
和歌山からきたことや、スカーレットのドラマにあこがれてやってきたことを話すと、観光マップを手渡してくれて、目の前の煙突もよくドラマに出ていたんですよと教えてくれた。

そして、丸熊陶業の登り窯は別の窯元にあるということも教えてくれた。
うちはギャラリーもやっているので10時過ぎに来てくれたら作品を見ることや買い物もできますよと教えてくれたがこれは事情があって実現しなかった。
再び外周道路に戻り喜美子さんが上っていった坂道を目指す。それはすぐに見つかった。目の前には卯山窯という窯元があるのだが、そこの奥さんらしき人が植木に水をやっていたので念のために聞いてみると、たしかにこの場所がそうであった。ちなみに武志君と真奈ちゃんが並んで歩いた坂もこの場所だ。



歩いてゆくと1軒すでに開店している陶器屋さんがあった。中をのぞいてぐい飲みの値段を聞いてみると釉薬のかかっていないものはけっこう高価だと言われた。値札が貼られていなかったので、ちなみにこれっていくらですかと聞いたら1万円です・・。ウッ、これではおみやげに買って帰れない・・。となると、ギャラリーを構えているようなお店だともっと値段が跳ね上がりそうでさっきのお店には寄らないでおこうと決めた。
そして登り窯のある宗陶苑を訪ねる。

ここのお店もすでに開店準備に入っているようで入り口が開いていた。若女将さんらしき人が招き入れてくれた。ここで恥をしのんで、1000円くらいで買えるぐい飲みってありますかと聞いたら、けっこうあるようだ。そして聞いてみるとほとんどは釉薬をかけずに焼いた信楽の土の色がそのまま出ているものだそうだ。まさしく緋色、スカーレットだ。
小ぶりなものは1個700円。これで十分。2個買って1540円しか払っていないのにお茶までふるまってくれたうえにいろいろな話を聞かせてくれた。
登り窯はもちろん、撮影で使われたタヌキの置物はほとんどがここの製品だということ、陶芸の森の近くの玉桂寺駅のそばには川原家と、タヌキの置物が置いてあった三差路があるということ。どちらも今もそのまま残っているらしい。(川原家は入り口の門だけで、家はセットだったそうだ。)
ちなみに、ここの登り窯は現役で年に2回は火を入れて製品を作っているそうだ。今は8月の火入れに向かって焼くための製品を窯に並べる直前で、窯の中に棚を組んでいるところだそうだ。

喜美子さんと照子さんが話をしていた通路にも薪も大量に積まれていて、薪だけであの巨大な登り窯の温度を維持するらしい。すごい。

僕もそこに行こうと駐車場まで戻ると、休館日と書いていた伝統産業会館というところの扉が開いていた。さっきの宗陶苑の若女将さんに、ここには新たに喜美子さんの穴窯が移築されて展示される予定だということを聞いていたので、事務の人に聞くと、受付の反対側に照明を落とされた状態で展示されていた。あの、吉野川さんのタヌキや目覚まし時計も置かれていたが、公開前なので写真撮影はNGとのこと・・。残念。
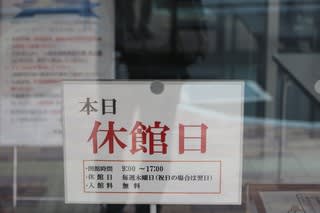
車に乗って移動。玉桂寺駅まで行ってみたがその場所がまったくわからない。そんなに道がたくさんあるわけではないのだがやっぱりわからない。それに、道は狭く、森の中を行くようなところばかりでその先に何があるのかわからない。吉野川さんが土を掘っていたっぽいところがあっただけだ。



そのかわり、巨大なタラノメの木の群落を見つけた。どうも盗られた形跡がない。この辺の人たちはタラノメは食べないのだろうか。市街地からは目と鼻の先なのに・・。

最後に陶芸の森へ。ここには神山清子の作品とともに、八郎さんが大賞をとった壺も展示されていた。


そろそろ雨が気になってきたので午前11時半に信楽を後にした。
帰りの幹線道路沿いの窯では煙突から火柱が立っていた。ここは観光地でもあるが、確かに産業と創作の場でもあるのだ。きちんと生きている町なのだ。

信楽で出会った人たちは確かに優しい人ばかりだった。そして、人だけでなく、山菜採りにとっても桃源郷のようであった。
そして僕のおみやげはふたつのぐい呑みとマグカップ。加えて、喜美子さんのように陶器の欠けらを拾ってきた。


多分、室町の物ではなく、ただの火鉢の欠けらだと思うけれども、僕の人生のお伴になってくれるだろうか。
買ってきたマグカップも喜美子さんの初めて作ったコーヒーカップのように、縁が欠けたものだ。B品として安く売られていた。


もうひとつ拾っていた素焼きの欠けらの端くれを細かくすり潰し、カシュー塗料と混ぜて即席のパテを作り割れ目に盛ってみた。ついでに漆の粘土で作られたぐい飲みの欠けたところも直してみた。
家に帰っても楽しみが続く信楽なのだ。


2020年5月25日探訪。















