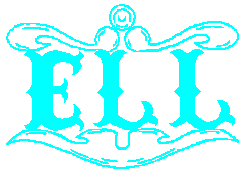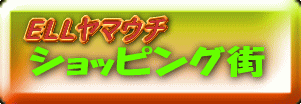日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
私が初めてもったデジカメは富士フイルムの30万画素のカメラでした。
そのカメラで商品写真を取り、HP用に加工し初めてのホームページをつくりました・・・が、
幾ら、WEB上での解像度・・・大体私の場合、20Kbyte程度・・・が低いとはいえ、
中には、如何しようもないくらいぼやけていた商品もありましたが、
それでも、お客様からのコメントで・・・
「このHPは軽くて見やすいです」などと云われることが嬉しく、更なる励みになりました。
もう、14~5年も前の話ですけど・・・ね。
今でも、HPやブログの場合は、一枚の写真は20Kbyte程度ですが、
Facebookなどでは、高解像度のそのままをスマホからアップすることも・・・
そのままでも圧縮してくれるなんて、随分と進化してきたものですよね。
進化といえば、日本で初めてコンピューターを作った会社ってご存知でしょうか?
実は私は、今朝の今朝まで知らなかったんですよ・・・
今朝は、このトリビアを紹介してみようと思います。
~以下、7月6日読売新聞朝刊より抜粋~
 日本で初めてコンピューターを作った企業がどこかご存知でしょうか。NECなど情報技術(IT)関連の企業が浮かびますが、実はカメラやフィルムが主力の富士フイルムです。
日本で初めてコンピューターを作った企業がどこかご存知でしょうか。NECなど情報技術(IT)関連の企業が浮かびますが、実はカメラやフィルムが主力の富士フイルムです。
カメラのレンズ設計には光の屈折率の算定に膨大な計算が必要で、数か月かかることもあったそうです。これを省力化しようと、レンズ技師の岡崎文次氏(1914~98年)の提案で49年に開発が始まりました。
東京大などが国家プロジェクトとしてコンピューター開発を進めていた中で、岡崎氏は設計から組み立てまでほぼ独力で取り組み、56年に完成させて「FUJIC」=写真、国立科学博物館提供=と名付けました。
幅4㍍、高さ2㍍で、人の平均2000倍の速さで計算することができました。後継機は開発されませんでしたが、約2年間、レンズ設計や気象庁などのデータ処理に活躍しました。
日進月歩の世界だけに、FUJICの計算速度は「スマートフォンの数万分の一程度」(情報処理学会)だそうです。しかし、ここから始まった日本のコンピューターの開発技術は今も、世界のトップレベルにあります。情報処理学会は業界の発展に貢献した「情報処理技術遺産」の第1弾にFUJIを選び、国立科学博物館(東京)に展示されています。
そのカメラで商品写真を取り、HP用に加工し初めてのホームページをつくりました・・・が、
幾ら、WEB上での解像度・・・大体私の場合、20Kbyte程度・・・が低いとはいえ、
中には、如何しようもないくらいぼやけていた商品もありましたが、
それでも、お客様からのコメントで・・・
「このHPは軽くて見やすいです」などと云われることが嬉しく、更なる励みになりました。
もう、14~5年も前の話ですけど・・・ね。
今でも、HPやブログの場合は、一枚の写真は20Kbyte程度ですが、
Facebookなどでは、高解像度のそのままをスマホからアップすることも・・・
そのままでも圧縮してくれるなんて、随分と進化してきたものですよね。
進化といえば、日本で初めてコンピューターを作った会社ってご存知でしょうか?
実は私は、今朝の今朝まで知らなかったんですよ・・・
今朝は、このトリビアを紹介してみようと思います。
~以下、7月6日読売新聞朝刊より抜粋~

カメラのレンズ設計には光の屈折率の算定に膨大な計算が必要で、数か月かかることもあったそうです。これを省力化しようと、レンズ技師の岡崎文次氏(1914~98年)の提案で49年に開発が始まりました。
Econo
トリビア
トリビア
日本初は富士フイルム
東京大などが国家プロジェクトとしてコンピューター開発を進めていた中で、岡崎氏は設計から組み立てまでほぼ独力で取り組み、56年に完成させて「FUJIC」=写真、国立科学博物館提供=と名付けました。
幅4㍍、高さ2㍍で、人の平均2000倍の速さで計算することができました。後継機は開発されませんでしたが、約2年間、レンズ設計や気象庁などのデータ処理に活躍しました。
日進月歩の世界だけに、FUJICの計算速度は「スマートフォンの数万分の一程度」(情報処理学会)だそうです。しかし、ここから始まった日本のコンピューターの開発技術は今も、世界のトップレベルにあります。情報処理学会は業界の発展に貢献した「情報処理技術遺産」の第1弾にFUJIを選び、国立科学博物館(東京)に展示されています。