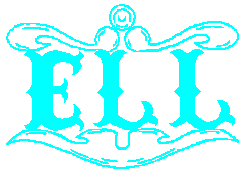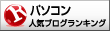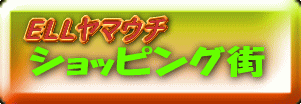日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
昨夕は、久しぶりに外食をしようと買い物がてら出掛けました・・・
かつて、数回利用したことのある店舗へ
いざ注文をしようとすると、
店員さんが「現在定食だけで、単品物は致しておりません」・・・と
しかし、席に案内されてしまってるので取り敢えず生ビールと天ぷら定食・・・
ビールは来たものの、先付もなく、天ぷらが来るまで・・・ただ、ただビールを・・・
早々に、食事を済ませ店を出たけど、3日遅れの結婚記念日を楽しむには物足りず・・・
別の店に入り、飲み直しをやりました。
なぜ、あのようなシステムに変更したんでしょうね・・・考えてみるに・・・
世の中不景気やから、定食だけやと食材の仕入れが決めやすい・・・ってこと?
もしそうなら、今までの客がさらに足が遠のいてしまうんじゃないのかなぁ~・・・
結論、私たちは二度と利用することは無いと思います。
家路へ向かう途中、お腹までおかしくなり小走り状態で帰宅しトイレへ・・・
ホンマに今年の記念日は、ケチがついてしまいました。
ところで、火災警報器の設置義務化から10年たったようで
そろそろ電池の寿命切れなどで点検が必要なようですよ。
我が家も作動確認をしてみなくては・・・
今朝は、この記事を転載してみようと思います。
~以下、11月6日読売新聞朝刊より抜粋~
「隣室の住民が気付かなければ危なかった」。東京消防庁の担当者が振り返るのは昨年10月の火災。東京都内の共同住宅1階の部屋でたばこの火が燃え広がり、天井を焼いた。警報器は電池切れで作動せず、気付いた隣人が119番。就寝中の住人男性は無事だった。

警報器は、2006年6月施行の改正消防法で新築住宅に設置が義務づけられた。11年6月以降は住宅全体に対象が拡大され、総務省消防庁に推計では、全国の設置率は81.2%(今年6月時点)に達している。
ただ、日本火災報知機工業会によると、警報器本体や電池の寿命は10年程度のものが多く、電池交換しても電子回路が劣化した古い警報器は火災を見逃す危険性がある。
同庁が今年6月、335の消防本部を通じ5万2497台の作動を確認したところ、約2%の897台で電池切れや故障が確認された。このため、同庁は来年度、全国の消防本部を通じて本格調査を実施する方針だ。
警報器の相談は、日本火災報知機工業会のフリーダイヤル(0120・565・911)。平日午前9時~午後5時。
かつて、数回利用したことのある店舗へ
いざ注文をしようとすると、
店員さんが「現在定食だけで、単品物は致しておりません」・・・と
しかし、席に案内されてしまってるので取り敢えず生ビールと天ぷら定食・・・
ビールは来たものの、先付もなく、天ぷらが来るまで・・・ただ、ただビールを・・・
早々に、食事を済ませ店を出たけど、3日遅れの結婚記念日を楽しむには物足りず・・・
別の店に入り、飲み直しをやりました。
なぜ、あのようなシステムに変更したんでしょうね・・・考えてみるに・・・
世の中不景気やから、定食だけやと食材の仕入れが決めやすい・・・ってこと?
もしそうなら、今までの客がさらに足が遠のいてしまうんじゃないのかなぁ~・・・
結論、私たちは二度と利用することは無いと思います。
家路へ向かう途中、お腹までおかしくなり小走り状態で帰宅しトイレへ・・・
ホンマに今年の記念日は、ケチがついてしまいました。
ところで、火災警報器の設置義務化から10年たったようで
そろそろ電池の寿命切れなどで点検が必要なようですよ。
我が家も作動確認をしてみなくては・・・
今朝は、この記事を転載してみようと思います。
~以下、11月6日読売新聞朝刊より抜粋~
火災警報器1100万台交換時期
住宅用義務化10年 電池切れの恐れ
住宅用火災警報器の設置が義務化されて10年が経ち、約1100万台が交換時期に差し掛かっていることが総務省消防庁の推計でわかった。電池切れなどで作動しなくなる恐れがあり、実際に作動しなかったケースも。同庁は「火災時の逃げ遅れにつながりかねない」と定期的な作動確認を呼びかけている。「隣室の住民が気付かなければ危なかった」。東京消防庁の担当者が振り返るのは昨年10月の火災。東京都内の共同住宅1階の部屋でたばこの火が燃え広がり、天井を焼いた。警報器は電池切れで作動せず、気付いた隣人が119番。就寝中の住人男性は無事だった。

警報器は、2006年6月施行の改正消防法で新築住宅に設置が義務づけられた。11年6月以降は住宅全体に対象が拡大され、総務省消防庁に推計では、全国の設置率は81.2%(今年6月時点)に達している。
ただ、日本火災報知機工業会によると、警報器本体や電池の寿命は10年程度のものが多く、電池交換しても電子回路が劣化した古い警報器は火災を見逃す危険性がある。
同庁が今年6月、335の消防本部を通じ5万2497台の作動を確認したところ、約2%の897台で電池切れや故障が確認された。このため、同庁は来年度、全国の消防本部を通じて本格調査を実施する方針だ。
警報器の相談は、日本火災報知機工業会のフリーダイヤル(0120・565・911)。平日午前9時~午後5時。