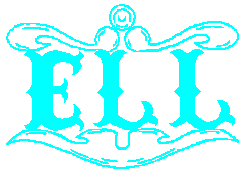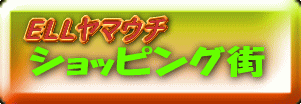日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
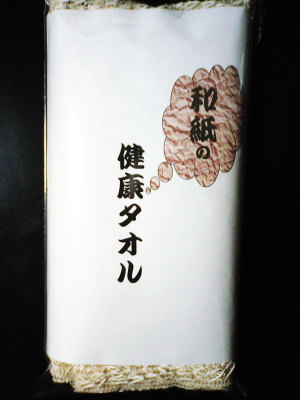 ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |
気持ちがネガティブになると何事にも臆するようになってしまう気がします・・・
だから、私はどんな状況下においても、出来得る限りポジティブに・・・
ポジティブにをモットーに現在までやってきたと自負しています。
且つて30歳の時、妻と子供二人を連れて京都へ舞い戻った時には、
アパートの権利金程度の手持ち資金しかなく、
先行きを考えた時には、不安ももちろんありました・・・
しかし、郷里での姉弟との確執による妻の心理状態・子供たちへの影響等々を考え合わせた時、
妻と二人して、一からやり直すための希望の方がどんなに大きかったことか・・・
勿論、周りの人達に大いに助けて頂いたご恩は忘れていません。
あの当時が乗り越えられたんだから・・・と常に念頭に置くようにしてるんですね。
周りを見渡してみると・・・やはり、色々な立場の人達がいます。
ネガティブに考えないで、出来得る限りポジティブに・・・と話すようにしてるんです・・・
いつの日か・・・必ず一筋の光がさす時が来るのを信じて前だけを見つめて頑張ってほしいですね。
今朝は、京大と自立相談支援機関の共同研究についての記事を転載してみようと思います。
~以下、2月22日読売新聞夕刊より抜粋~
こころ
福祉相談と
心理的ケア
心理的ケア
失業、貧困、引きこもりなどで、福祉の相談窓口を訪れる人の中には、心理面のケアが必要な人が少なくない――。そんな問題意識から、京都大学心の未来研究センターと千葉市の自立相談支援機関※が、生活困窮者の実態を調査し、その傾向を分析する共同研究に取り組んでいる。(高橋圭史)
※
自立相談支援機関 失業や病気などで生活に困る
人を生活保護を受ける手前で支える相談窓口。2015年4月に始まった生活困窮者自立支援制度の伴い、福祉事務所のある902自治体に設置されている。一人一人の状況に応じた支援プランを作る。
例えば、引きこもり。典型的なのは学生時代に不登校になり、そのまま中高年に至るケースだが、最近は、

貧困と心の問題 連動
不況で就職先が見つけられず、大学を卒業してから、こもり始める例もあるという。「複合的な要因が関わったおり、心理的ケアや就労支援、住宅支援などを含む包括的な対応が必要になっている」と広井さん。有効な支援策を考えるために、生活困窮者の重複する課題の傾向を分析しようと昨年4月から、千葉市の自立相談支援機関である「生活自立・仕事相談センター稲毛」と共同研究を始めた。
まだ研究途中だが、昨年4~6月に相談を受けた78人の抱える課題(複数回答)を集計すると、「経済的困窮」「住まい(家賃など)」「就職」「心の健康」「病気」「家族関係」などが多かった。約7割が、三つ以上の課題を抱えていた。
配偶者や恋人からの暴力(DV)なども含め、「家族関係」に問題を持つ20人のうち、18人は「心の健康」にも課題があった。「就職」問題を抱える26人でも、約半数の12人は「心の健康」にも課題があった。
集計した同センター長の菊池謙さん(精神保健福祉士)は「生活保護、就労支援などの公的福祉の対応は、法律・制度で守備範囲を限定してきた面がある。現実に相談に来る人にはコミュニケーション力や行動力が弱い人も多く、縦割り的な対応では済まないことが多い」と指摘する。
広井さんは「心理的なケアのようなことは、かつては家族や職場、地域の中で対応されていた。しかし、家族の多様化、都市化、雇用環境の悪化などの中で、その支えが弱まり、『心のケアの社会保障制度』が求められるようになっている。さらに研究を進め、効果的な支援策のあり方を提案したい」と反している。