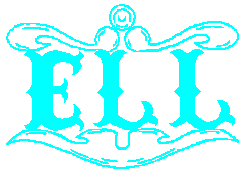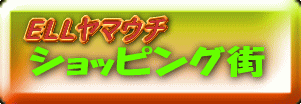日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
私はここ何年も読書というものをした記憶がありません・・・
新聞だけは、出来るだけ隅まで読む努力はしているのですが、
それでも、3分の1くらいしか読んでないんじゃないのかなぁ~・・・
どうしても興味のある記事くらいしか目を通してないと思います。
ツイッターが出始めた頃、すでにブログをやっていた関係で
ツイッターの140文字以内という限定された文字数がネックになりやりませんでした。
フェイスブックをやり始めた時には・・・
ただ文字を書いて写真を張り付けるだけということに物足りなさを感じましたね。
ブログだと多少の制約はあるにしても、1万文字くらい書けますし、
文字の装飾やレイアウトもできるわけで、私にとっては、そのことが楽しいわけです。
PCの小技などを忘れないためにもブログはやめられないですね。
話は少々変わりますが・・・
このSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の影響が
青少年の読解力に悪影響を及ぼしているとの指摘がよくありますね・・・
実際、私自身もLINEを使用する場合は、短い言葉しか使いません。
会話している感覚なので、用件だけで十分相手には通じるってことがあるんですよね。
このやりとりが当たり前となり、読解力まで影響してるんじゃないかと・・・
要するに、文章であれば前後の言葉から状況を把握し意味を理解していくのですが、
「行く?」と打てば「行く」だけで会話が成り立ってしまうLINEの怖さなんでしょうね。
読書をやらないんだったら、
せめて新聞の記事を読むことにより読解力をつける努力をした方がいいのかもですよね。
今朝は、読解力に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、2月1日読売新聞朝刊より抜粋~

東京都立高校3年の女子生徒(18)は通学の電車内でスマートフォンをチェックするのが日課だ。朝までに届いたLINEのメッセージに返信する。「友達には『了解』も『り』で済ます。それで通じるし、長い言葉は面倒くさい」。帰りの電車もスマホ。就寝前の午前1時からは、友達とその日の出来事などを2時間ほど報告し合う。1日の利用時間は約4時間。女子生徒は「スマホがなければ、もっと寝たり本を読んだりしてたかも」と笑う。
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)はスマホの普及に伴って若者らの間で急速に広まった。2008年に日本語版のサービスが始まった簡易投稿サイト「ツイッター」は140文字以内の「つぶやき」を書き込める。一方、11年に始まった4LINEでは仲間内で対話型のコミュニケーションが可能だ。いずれも瞬時に短いメッセージを発信できる利点があるが、長文のやりとりには適さない面がある。
昨年12月に公表された国際学力調査の結果では、日本の15歳の読解力は4位から8位に低下。文部科学省は原因の一つとして、スマホの普及に伴う長文を読む機会の減少を挙げた。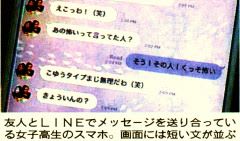
スマホの利用時間が増える一方、読書量は減少している。内閣府の15年度の調査では、平日にスマホで2時間以上ネットを利用する高校生の割合は前年度比3.5㌽増の66.8%。5時間以上使った割合も1.1㌽増えて12.5%に上った。
これに対し、全国学校図書館協議会(東京)によると、高校生の1か月の平均読書冊数は10年の1.9冊をピークに減少傾向が続き、16年は1.4冊となった。
ネット依存の専門医療を提供する久里浜医療センター(神奈川県)にはスマホのゲームにはまった若者の姿も目立ち、樋口進院長(62)は「勉強や読書の時間が取れず、学力が落ちる傾向がある」と指摘する。
認知心理学が専門の河原純一郎・北海道大特任准教授(46)の実験では、スマホがそばに置いてあるだけで、「メールが来ないか」などと気を取られ、注意力が低下することが確認された。また、脳科学者の川島隆太・東北大教授(57)がスマホを操作中の大学生約20人の脳の血流量を測定したところ、論理的な思考を行う大脳の前頭前野が「眠っているような、ボーッとした状態」になっていたという。
川島教授は「脳が発達する18歳ぐらいまではスマホの使用を制限し、しっかりした文章を読む環境を作るべきだ」と訴えている。
新聞だけは、出来るだけ隅まで読む努力はしているのですが、
それでも、3分の1くらいしか読んでないんじゃないのかなぁ~・・・
どうしても興味のある記事くらいしか目を通してないと思います。
ツイッターが出始めた頃、すでにブログをやっていた関係で
ツイッターの140文字以内という限定された文字数がネックになりやりませんでした。
フェイスブックをやり始めた時には・・・
ただ文字を書いて写真を張り付けるだけということに物足りなさを感じましたね。
ブログだと多少の制約はあるにしても、1万文字くらい書けますし、
文字の装飾やレイアウトもできるわけで、私にとっては、そのことが楽しいわけです。
PCの小技などを忘れないためにもブログはやめられないですね。
話は少々変わりますが・・・
このSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の影響が
青少年の読解力に悪影響を及ぼしているとの指摘がよくありますね・・・
実際、私自身もLINEを使用する場合は、短い言葉しか使いません。
会話している感覚なので、用件だけで十分相手には通じるってことがあるんですよね。
このやりとりが当たり前となり、読解力まで影響してるんじゃないかと・・・
要するに、文章であれば前後の言葉から状況を把握し意味を理解していくのですが、
「行く?」と打てば「行く」だけで会話が成り立ってしまうLINEの怖さなんでしょうね。
読書をやらないんだったら、
せめて新聞の記事を読むことにより読解力をつける努力をした方がいいのかもですよね。
今朝は、読解力に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、2月1日読売新聞朝刊より抜粋~

SNS没頭 長文読まず
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)はスマホの普及に伴って若者らの間で急速に広まった。2008年に日本語版のサービスが始まった簡易投稿サイト「ツイッター」は140文字以内の「つぶやき」を書き込める。一方、11年に始まった4LINEでは仲間内で対話型のコミュニケーションが可能だ。いずれも瞬時に短いメッセージを発信できる利点があるが、長文のやりとりには適さない面がある。
昨年12月に公表された国際学力調査の結果では、日本の15歳の読解力は4位から8位に低下。文部科学省は原因の一つとして、スマホの普及に伴う長文を読む機会の減少を挙げた。
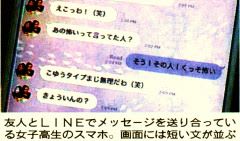
スマホの利用時間が増える一方、読書量は減少している。内閣府の15年度の調査では、平日にスマホで2時間以上ネットを利用する高校生の割合は前年度比3.5㌽増の66.8%。5時間以上使った割合も1.1㌽増えて12.5%に上った。
これに対し、全国学校図書館協議会(東京)によると、高校生の1か月の平均読書冊数は10年の1.9冊をピークに減少傾向が続き、16年は1.4冊となった。
ネット依存の専門医療を提供する久里浜医療センター(神奈川県)にはスマホのゲームにはまった若者の姿も目立ち、樋口進院長(62)は「勉強や読書の時間が取れず、学力が落ちる傾向がある」と指摘する。
認知心理学が専門の河原純一郎・北海道大特任准教授(46)の実験では、スマホがそばに置いてあるだけで、「メールが来ないか」などと気を取られ、注意力が低下することが確認された。また、脳科学者の川島隆太・東北大教授(57)がスマホを操作中の大学生約20人の脳の血流量を測定したところ、論理的な思考を行う大脳の前頭前野が「眠っているような、ボーッとした状態」になっていたという。
川島教授は「脳が発達する18歳ぐらいまではスマホの使用を制限し、しっかりした文章を読む環境を作るべきだ」と訴えている。