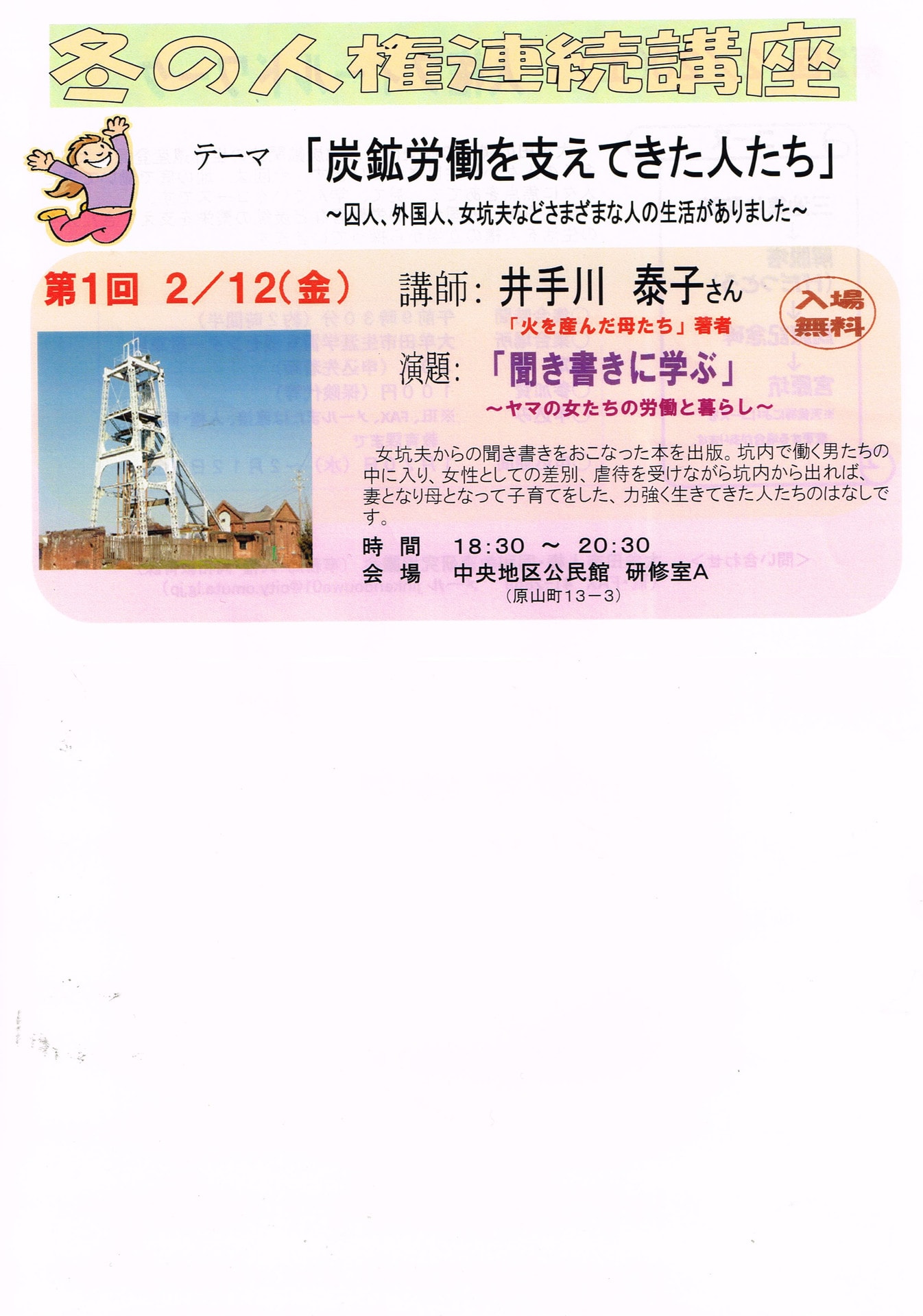冬の人権連続講座が開催されます。
連続講座のテーマは「炭鉱労働を支えてきた人たち」で副題に~囚人、外国人、女坑夫などさまざまな人の生活がありました~と紹介されています。
第1回講座は2月12日(金)18時半から20時半まで、中央地区公民館(原山町)研修室Aで行われます。
第1回の講師は井手川 泰子さんです。
講師の演題は「聞き書きに学ぶ~ヤマの女たちの労働と暮らし~」。
講師の井手川さんは「女坑夫からの聞き書きを行った本を出版」されている方です。
炭坑産業が大牟田からなくなってすでに長い月日が過ぎ去りました。
炭坑産業が生まれた明治時代の遺跡が世界遺産になり世界の宝として大事にされるようになりました。
炭坑産業を支えた当時の方々がどのような苦労をされ働いてこられたか~その歴史も、ともに語りつ継がれてゆくことが大事なことと思います。
この講座では「坑内で働く男たちの中に入り、女性としての差別、虐待を受けながら坑内から出れば、妻となり母となって子育てをした、力強く生きてきた人たちのはなし」が聞けるそうです。
炭鉱画で目にしたことのある~あの女坑夫たちの生の声が聞かれる~と期待します。
第2回は2月20日(土)で、人権フィールドワークとなっています。
問い合わせ先:大牟田市人権・同和教育研究協議会・事務局ー人権・同和教育課 電話ファックス0944-41-2869
(下:チラシより)
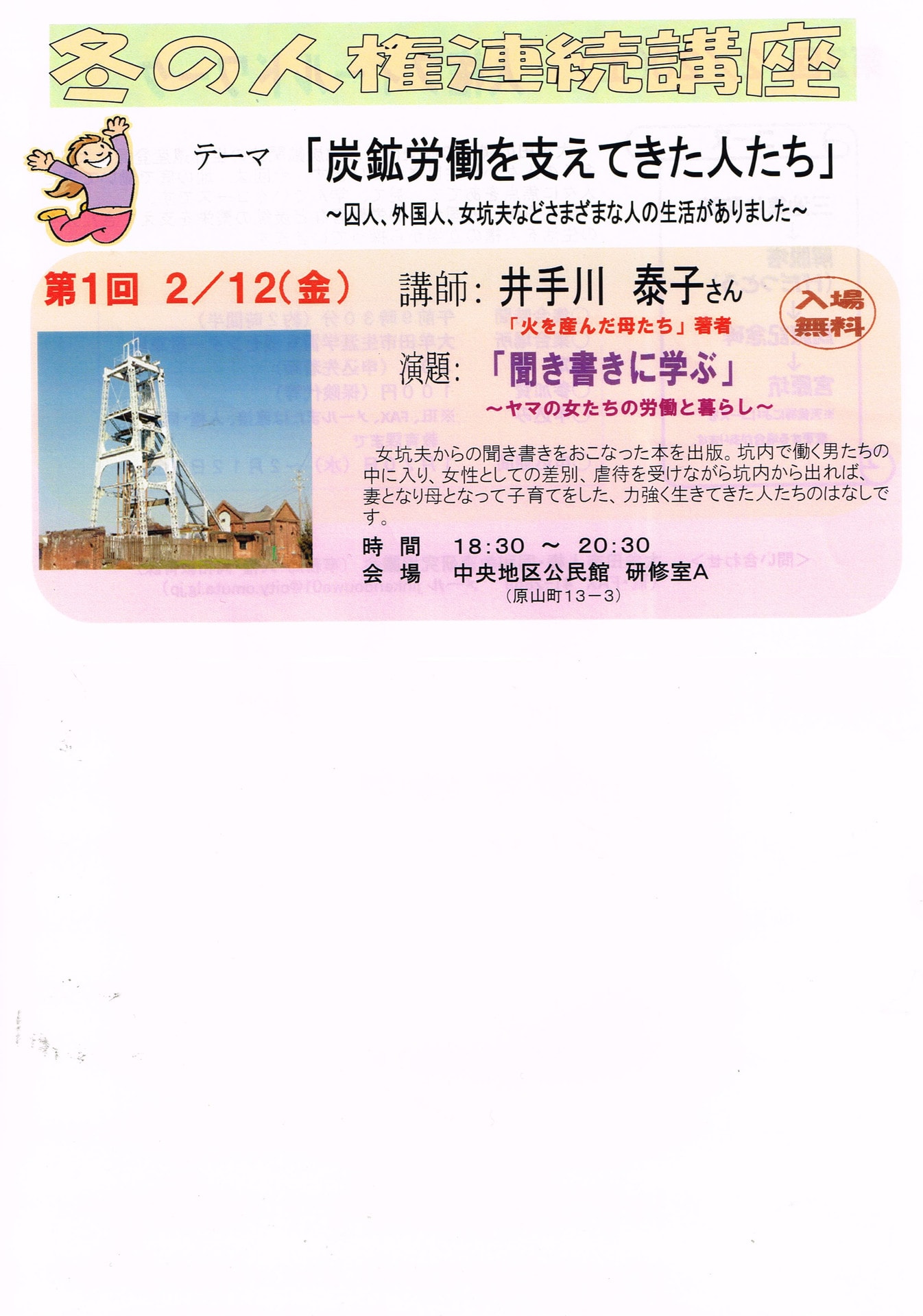
連続講座のテーマは「炭鉱労働を支えてきた人たち」で副題に~囚人、外国人、女坑夫などさまざまな人の生活がありました~と紹介されています。
第1回講座は2月12日(金)18時半から20時半まで、中央地区公民館(原山町)研修室Aで行われます。
第1回の講師は井手川 泰子さんです。
講師の演題は「聞き書きに学ぶ~ヤマの女たちの労働と暮らし~」。
講師の井手川さんは「女坑夫からの聞き書きを行った本を出版」されている方です。
炭坑産業が大牟田からなくなってすでに長い月日が過ぎ去りました。
炭坑産業が生まれた明治時代の遺跡が世界遺産になり世界の宝として大事にされるようになりました。
炭坑産業を支えた当時の方々がどのような苦労をされ働いてこられたか~その歴史も、ともに語りつ継がれてゆくことが大事なことと思います。
この講座では「坑内で働く男たちの中に入り、女性としての差別、虐待を受けながら坑内から出れば、妻となり母となって子育てをした、力強く生きてきた人たちのはなし」が聞けるそうです。
炭鉱画で目にしたことのある~あの女坑夫たちの生の声が聞かれる~と期待します。
第2回は2月20日(土)で、人権フィールドワークとなっています。

問い合わせ先:大牟田市人権・同和教育研究協議会・事務局ー人権・同和教育課 電話ファックス0944-41-2869
(下:チラシより)