与党もどうかしている。「検証」だろう。歴史を検証して何がわるいのだろう。科学でいえば「検算」「実験」だ。何もおかしくないと思う。
歴史に関して,決まったことには何も言わない・言わせないというのは,そもそも「学問的に」オカシイと思っている。学問は「批判的精神」に基づくものだから。
そういう目で見てみると,高校生向けの歴史教科書はいざしらず,参考書もまったく「面白くない」。
著者自身の考えを展開したっていい。そして「入試対策としての事実はこう,しかし,解釈は異なっている」ぐらいの説明をする。これが僕の望む姿。
かといって,自画自賛ばかりではいけない。
要はバランス。「いい・わるい」でなく,事実がどうだったか,「ときどきの世界観を元に」検証するなら意味ありと思う。
歴史認識というと,右よりも左よりもすぐに「戦争」のことばかり。チョット待て,戦争以外にも日本の転換点は多いぞ。
たとえば,プラザ合意。あそこからバブル景気が始まったと解釈されている。しかし,それは,30年後のいまの解釈ではどうなのだろう。
そういう,僕は「根本を揺るがすようなこと」は起きたほうがむしろよいと思う。なぜなら,それは「考える」から。自分で考えないと答はないから。
東京裁判にしても戦犯にしても,言葉がひとり歩きしている。「戦犯」とはそもそもなにか,昭和20年に敗北した日本が受け入れた「降伏」とはなにか,そういう「意味」を考える事こそ「歴史教育」「実学」だ。
そういう意味で,数学や物理は解釈が揺れないので精神的にはラク。でも,何十年経過しても同じ問題が入試に出るのだから,「出題の意味」を受験生も考えないと。「重要問題」は新しい命題でなく,伝統ある命題なのだと。
原爆,広島,長崎,いろいろ考える事の多い季節である。










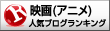


 ほどの水郷だったが。
ほどの水郷だったが。
 」と思うしかない,そう感じていた午前中の釣行。
」と思うしかない,そう感じていた午前中の釣行。 水郷には5時には到着していたのだが...。
水郷には5時には到着していたのだが...。

 が立ち,偏光グラスがたびたび曇ったほどである
が立ち,偏光グラスがたびたび曇ったほどである 。そんな場所に行くなよって話だが,実績というものは怖い
。そんな場所に行くなよって話だが,実績というものは怖い 。
。

 でまともにルアーが投げられない。かといってバイブには反応しない。思い切って,ネコリグシンカーを一番重いものにして,さらに
でまともにルアーが投げられない。かといってバイブには反応しない。思い切って,ネコリグシンカーを一番重いものにして,さらに

 。
。

 。これでなんとかレポートが書ける,とへびん・ビッグフィッシュサービスに連絡
。これでなんとかレポートが書ける,とへびん・ビッグフィッシュサービスに連絡 すると,「アサイチの水路で釣っていますが,
すると,「アサイチの水路で釣っていますが, 」
」 」などと暴言を吐いたが,すっとばしてコンビニに行ってきたらしい。八郎ではコンビニが非常に少ないので,僕も箱ティッシュを確認しておこう。八郎初ピノ...,暑いのヤダナア(笑)。
」などと暴言を吐いたが,すっとばしてコンビニに行ってきたらしい。八郎ではコンビニが非常に少ないので,僕も箱ティッシュを確認しておこう。八郎初ピノ...,暑いのヤダナア(笑)。 。そしてその水門には....
。そしてその水門には.... 。何もいうまい
。何もいうまい 。
。 。いや,「カンカン」とルアーをこづく魚が居るがわからない。
。いや,「カンカン」とルアーをこづく魚が居るがわからない。

 。もしかして,この水路付近で見かける魚もハスかな。次回からD-ZONE・FRYは必須。いや,毎回必須なのに投げていなかった。真夏の定番を忘れていたね
。もしかして,この水路付近で見かける魚もハスかな。次回からD-ZONE・FRYは必須。いや,毎回必須なのに投げていなかった。真夏の定番を忘れていたね 。
。

 。在庫はこれ1個しかないので,あと2個ぐらい補充しよう。重さを変えて,根こそぎ八郎でもやってみるのだ。
。在庫はこれ1個しかないので,あと2個ぐらい補充しよう。重さを変えて,根こそぎ八郎でもやってみるのだ。 。
。
 。デラクーは重量があるのでバレやすいのかもしれない。
。デラクーは重量があるのでバレやすいのかもしれない。 。取手の花火
。取手の花火 大会があったりしたが,スムーズに帰還。湘南方面のような渋滞がないからやっぱり水郷は通える方面だ。
大会があったりしたが,スムーズに帰還。湘南方面のような渋滞がないからやっぱり水郷は通える方面だ。







