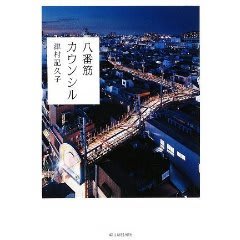
正直言うとちょっと乗り切れなかった。つまらないというわけではない。彼女にとっては切実な問題が描かれてあるのだろうが、読み手にそれが伝わりきらない。独りよがりすれすれのところで成立しているって感じだ。それは彼女の作家としての技術が拙いということではない。読者におもねるような書き方はしないからだ。そういう意味では潔い。
この町で育った3人の男女が主人公だ。彼らは一度はここから出て行こうとしたにも関わらず、再びここで暮らすことになる。商店街は昔ながらの人間関係が残り、それがうっとうしいはずなのだが、彼らはそんなものも含めて受け入れる。ここで育ち、ここで暮らした。15歳の時間とその15年後が交錯する。それらは交互に描かれていくのだが、現在と過去であるにもかかわらず、この両者は小説の中で等価なものとして描かれる。2つの時間は別々の小説のようだ。
主人公は同じだし、同じ場所で同じ人間関係の中の2つの時間であるにも関わらず、である。巨大ショッピングモール建設を巡る商店街カウンシル(青年団のことらしい)の面々の戦々恐々なさまが描かれるが、これはそんなお話を見せようというわけではない。だいたいお話自体は別に面白いものではない。主人公3人の描き分けすらあまり明確ではない。際立ったドラマもないし、それぞれの話は地味すぎてこんなエピソードでいつまで続くのか、心配するほどだ。行方不明だった父親との再会や、事故によって汚名を着せられこの町を追われた友人が再びここに舞い戻ってきて、ショッピングモール建設の推進を仕切る話とか、派手な展開を期待できるエピソードはないわけではないが、そこからは話を進めない。
失われいく古い商店街、そこで暮らす人々の姿を通して、かってあった地域の絆が残る場所で、今も暮らそうとする中途半端な大人たち(もう30歳だし、子供とは言えないから)の見捨てられたような日々を描く。なんだかへんに懐かしい。自分も昔、商店街の中で住んでいたからか。子どもの頃、大正区にある泉尾商店街の中で暮らした。あの雑多な場所での少年時代は今でも鮮明に記憶に残っている。
そんな個人的なことが影響しているというわけではないが、ただこの小説の主人公たちの潔くないさまはなんだか心に沁みるのだ。なんでもないただの日常がこの古い商店街の人間関係を背景に描かれる。ただゆっくり読み進めるだけだ。読み終わるとそれだけだ。距離感は拭い去れない。だが、決して嫌な気分ではない。不思議な懐かしさが残る。
この町で育った3人の男女が主人公だ。彼らは一度はここから出て行こうとしたにも関わらず、再びここで暮らすことになる。商店街は昔ながらの人間関係が残り、それがうっとうしいはずなのだが、彼らはそんなものも含めて受け入れる。ここで育ち、ここで暮らした。15歳の時間とその15年後が交錯する。それらは交互に描かれていくのだが、現在と過去であるにもかかわらず、この両者は小説の中で等価なものとして描かれる。2つの時間は別々の小説のようだ。
主人公は同じだし、同じ場所で同じ人間関係の中の2つの時間であるにも関わらず、である。巨大ショッピングモール建設を巡る商店街カウンシル(青年団のことらしい)の面々の戦々恐々なさまが描かれるが、これはそんなお話を見せようというわけではない。だいたいお話自体は別に面白いものではない。主人公3人の描き分けすらあまり明確ではない。際立ったドラマもないし、それぞれの話は地味すぎてこんなエピソードでいつまで続くのか、心配するほどだ。行方不明だった父親との再会や、事故によって汚名を着せられこの町を追われた友人が再びここに舞い戻ってきて、ショッピングモール建設の推進を仕切る話とか、派手な展開を期待できるエピソードはないわけではないが、そこからは話を進めない。
失われいく古い商店街、そこで暮らす人々の姿を通して、かってあった地域の絆が残る場所で、今も暮らそうとする中途半端な大人たち(もう30歳だし、子供とは言えないから)の見捨てられたような日々を描く。なんだかへんに懐かしい。自分も昔、商店街の中で住んでいたからか。子どもの頃、大正区にある泉尾商店街の中で暮らした。あの雑多な場所での少年時代は今でも鮮明に記憶に残っている。
そんな個人的なことが影響しているというわけではないが、ただこの小説の主人公たちの潔くないさまはなんだか心に沁みるのだ。なんでもないただの日常がこの古い商店街の人間関係を背景に描かれる。ただゆっくり読み進めるだけだ。読み終わるとそれだけだ。距離感は拭い去れない。だが、決して嫌な気分ではない。不思議な懐かしさが残る。

























