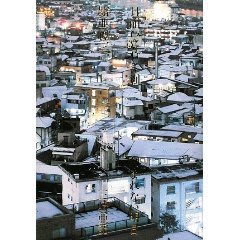
これは『失われた町』の続編である。三崎亜記はよほどこの設定が気に入ったらしい。彼は現実の世界を舞台にしない。見た目はよく似てるけど彼が書く世界は、いつもなんだか微妙にねじれている。ここに描かれる町は、世界から消えた町を含む。ぽっかりと穴が開いたように、ある部分が失われた。ありえないことが、ここでは起きた。だれもが、そんなことを現実とは思いたくはない。だが、現実にそれは起きたのだ。仕方ないことだ。
だから、もう誰もそのことには触れない。(それでいいのか、と言われると、だめでしょ、としか言いようがないのだが、でも、この世界ではそういうことで済ましているようだ)でも、人々の心の中には、今も確実にそのことが残っている。当事者を身内に持つものなら当然のことだろう。あれから10年、何事もなかったかのように、時間は穏やかに過ぎていく。世界は平穏無事だ。
あの事件の生き残りの女性が主人公だ。彼女はあの時3095人と一緒に消えるはずだった。なのに、彼女だけがあの町にいたのに消えなかった。消えた町では今もあの時間のまま彼らが生きている。ここにはないどこかで、止まった時間の中で。だが、そこに行く術はない。
彼女と何人かの人々のドラマが短編連作のスタイルで語られる。主人公はエピソードごとに変わるから、彼女だけが主人公であるわけではない。ただ彼女はこの小説の中心にいるから、主人公と断定しただけだ。『となり町戦争』からずっと、同じようなテイストのお話を連打している。この拘りはすごい。時々あまりにSFチックになり過ぎて失敗することもあるが、この寂しさは好きだ。
最後のエピソードを読みながらあまりの幸福感に泣きそうになった。消えてしまった町が、完全に消えようとするその瞬間がなぜこんなにも愛おしいのか。記憶の中であの町は想い出として残る。いつか、そうしなくてはならなかった。いつまでもなかったことにしていられるわけではない。忘れたフリとか、それはないだろう。だから、彼らはその後の人生を生きる。そのためには実に12年間という歳月が必要だった。祝祭的空間にあるその町に戻ってきた男は、彼女のもとへと歩みを進める。感動的なラストだ。
だから、もう誰もそのことには触れない。(それでいいのか、と言われると、だめでしょ、としか言いようがないのだが、でも、この世界ではそういうことで済ましているようだ)でも、人々の心の中には、今も確実にそのことが残っている。当事者を身内に持つものなら当然のことだろう。あれから10年、何事もなかったかのように、時間は穏やかに過ぎていく。世界は平穏無事だ。
あの事件の生き残りの女性が主人公だ。彼女はあの時3095人と一緒に消えるはずだった。なのに、彼女だけがあの町にいたのに消えなかった。消えた町では今もあの時間のまま彼らが生きている。ここにはないどこかで、止まった時間の中で。だが、そこに行く術はない。
彼女と何人かの人々のドラマが短編連作のスタイルで語られる。主人公はエピソードごとに変わるから、彼女だけが主人公であるわけではない。ただ彼女はこの小説の中心にいるから、主人公と断定しただけだ。『となり町戦争』からずっと、同じようなテイストのお話を連打している。この拘りはすごい。時々あまりにSFチックになり過ぎて失敗することもあるが、この寂しさは好きだ。
最後のエピソードを読みながらあまりの幸福感に泣きそうになった。消えてしまった町が、完全に消えようとするその瞬間がなぜこんなにも愛おしいのか。記憶の中であの町は想い出として残る。いつか、そうしなくてはならなかった。いつまでもなかったことにしていられるわけではない。忘れたフリとか、それはないだろう。だから、彼らはその後の人生を生きる。そのためには実に12年間という歳月が必要だった。祝祭的空間にあるその町に戻ってきた男は、彼女のもとへと歩みを進める。感動的なラストだ。

























