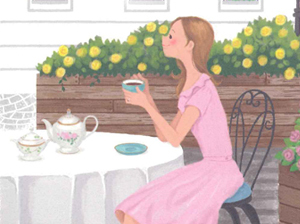6月の診療部便り
6月の診療部便り
皆様こんにちは!
5月半ばより早くも蒸し暑い日が増えてきましたね。
今年の夏は例年よりも平均気温が高くなるであろうと言われております。
熱中症対策など体調管理にお気を付け下さいね。
4月より人工授精と体外受精が保険適用となりました。
費用の負担が軽減されることで治療が受けやすくなられたかと思います。
より多くの方々のご妊娠に繋がっていくことを願っております。
しかし、保険適用ではデメリットもございます。
今回は保険適用の体外受精について、そのデメリットに注目してお話させて頂きます。
保険適用の体外受精では採卵の場合も移植の場合も、実施できる超音波検査や血液検査の回数に制限があります。
また、使用できる薬剤の種類が限定されていたり、採卵で卵を育てる際の注射の量や回数にも制限がかけられています。
これらの影響がより大きいのが採卵です。
注射が限られることにより、採卵周期に卵胞が育たず採卵がキャンセルる場合も出たり、
採れる卵子の数が少なくなる可能性も出て参ります。
特に、多嚢胞性卵巣の方はその可能性が高くなります。
多嚢胞性卵巣は十分に注射をすることで多数の卵胞が育ちやすい特徴があります。
特徴を生かし、受精卵が多く凍結できれば、一回の採卵で第二子や第三子の妊娠も可能となります。
卵巣の反応性や体質はお一人お一人異なり、必要な注射の量・回数もお一人お一人異なるので、
保険内の治療よりも、自費の治療の方がより適している方もおられます。
体外受精を希望される場合、患者様の体質や過去のデータを踏まえ最適な治療方針をご提案させて頂きます。
そのうえで、ご夫婦でよく相談し保険適用の体外受精か自費の体外受精かを選択されて下さい。
保険適用に伴っては、不明瞭な点もあり様々な疑問を抱かれている患者様も多いかと存じます。
当院では適宜、厚生労働省に確認を取りながら診療を行っておりますので、
何か気になることがあればご相談下さい!