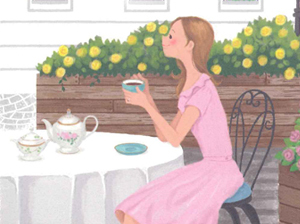gooニュースで面白い記事を見つけました。
「昭和の大経営者」松下幸之助さんの「部下の叱り方」です。
しかも今の若者が望むような”甘い叱り方”ではなく”厳しい叱り方”です。
「叱」という漢字は、「口を使って、相手を鋭い刃のように切る」ことを表しているそうです。
「七」という漢字は、十文字という意味だそうですから、
「叱る」とは、相手を十文字に口で切り刻むことといえるそうです。
本来は、厳しいものなのですね。
そのgooニュースの文章の一部を掲載させて頂きます。
「松下からの厳しい叱り」
経営を担当するようになって、時折、厳しく叱られた。
尋常でない叱り方で、頭のなかが真っ白になることもあったが、
「叱る」ということは、語源からして、そういうことだから、
尋常でないのが当たり前なのかもしれない。
同じように、松下幸之助に叱られた先輩は、多分、数知れず、だろう。
私と同じように、茫然自失した人も多いのは間違いない。
~略~
昭和53(1978)年11月のある日、外は、肌寒さを感じる一日であった。
雑談の折に、直接、どのように叱るのか、
叱り方のコツでも聞こうと思い、聞いてみたことがあった。
「えっ? わしの叱り方がうまい? みんな、そう言っておるんか。
そんなことはないで。
わしが叱るときか?
わしが部下を叱るときには、いろいろ考えて叱るということはないな。
とにかく、叱らんといかんから叱るわけだから、
後のことを考えたり、
この時はこういう叱り方をしようとか、そんなことを考えて叱るということはないな。
そんな不純な叱り方はせんよ。
私心なく、一生懸命叱る。
策をもって叱るというようなことはせん。
これがその部下のためにも、会社のためにもなると思うから、命がけで叱る。
もちろん、叱りながら、その部下に対して、感謝の気持ちはあるわけや。
感謝しながら、命がけで、叱るということやね。
けどな、叱るということは、その部下に期待しとるからやということもある。
まあ、成長が期待できん者まで、叱っても意味ないもんな。
けどな、叱った後、言葉が過ぎたかな、と思う時もあるし、
ああいう言い方、叱り方でよかったのかな、と思い考えることもあるし、
本当にわかってくれたんやろうかと案じたりするな。
いろいろな思いが心のなかを駆け巡るわけや。それどころか、夜、寝れんこともたびたびある。
4、5日、ずっと残ることもある。
叱る方はいいですねとか、言いたいことが言えていいですねと思う人もおるだろうけどね。
叱った後は、いつもつらく悲しいもんやで。わしだけかもしれんがね。
~略~
けど、とにかく、叱るときに、策をもって叱ることはしない」
というようなことを説明してくれた。松下幸之助らしい話だと思いながら聞いていた。
少し、間をおいて、「けどな」と、松下が話を続けた。
「叱られた後が大事」
「けどな。叱られる部下を見ておると、
叱られるのがうまい人と、下手な人とがおるね、わしの経験として。
いろいろ言い訳をする者は論外として、
叱って、『わかりました』ということでその場は終わるとしても、
そのあとが、大事であるわけや。
叱られた者は叱られたことで、精一杯かもしれんが、
今も言ったけどな、叱ったほうもそれ以上に思い悩んでおる場合もあるわけや。
いわば、抜いた刀を、どう鞘に納めようかと。
そんなときに、その部下が、すぐにやってきて、
『先ほどのことはよくわかりました。これからは十分気を付けます。すみませんでした』と言うと、
こっちも思い悩んでいるところだから、
ああ、あの叱り方でよかったな、わかってくれたんやな、ということになるわね。
叱ったほうも、内心ホッとして、やあ、わかればそれでいい、これからも頑張るように、ということになる。
刀がそこで納められる。
叱ったほうも、一区切りついたという気分になると同時に、なかなかいい部下だなと思う。
また、かえって、そういう部下が可愛くなる。
人情やな、それが。
もっとも、わからんのにわかりましたと言ってくるのはあかんけどな。
うん、そりゃ、すぐわかるで。
まあ、叱られ上手は、叱ったほうに、いやな余韻を残さん工夫をする人やな」
~略~
いや~~とても面白いお話です。
叱られた後の部下の態度、私もよく見て判断しています。
私も人事採用・人事教育をしているので、心に響くお話でした。
最近は現場のチーフ達が新人さん教育をしてくれるようになり、
私も随分と楽になりましたが、、、
誰も叱りたくて叱る事はしませんよね。
ここで注意喚起しなくてはいけない時は、叱らざるを得ませんね。
それが医療の為であり、いらして下さる患者様の為でもあります。
今年もあと半月となります。
より良い2014年でありますよう、
残された2014年の一日一日を大切に過ごしていきたいですね。
ーby事務長ー

 とくおかレディースクリニック
とくおかレディースクリニック

 励ましメッセージ、まことに有難うございました
励ましメッセージ、まことに有難うございました


 とくおかレディースクリニック
とくおかレディースクリニック


















 12月の受付便り
12月の受付便り とくおかLC受付・医療事務スタッフより
とくおかLC受付・医療事務スタッフより
 12月の看護部・検査部便り その2
12月の看護部・検査部便り その2 とくおかLC看護部・検査部スタッフより
とくおかLC看護部・検査部スタッフより