今日はほぼ1日中雨となり、首都圏の最高気温は真夏
日になった一昨日より10℃くらいも下がり、涼しい1日で
した。
その一昨日、暑い中訪ねた東京・東村山市での企画展
の模様です。
========================
2008年8月15日(日)

第2次世界大戦が終わって63年の日、東京・東村山市
の「東村山ふるさと歴史館」で開催中の企画展「陸軍少年
通信兵学校」の観覧に、職場の先輩、Hさんなどと行った。


なぜこの企画展に出かけたか。それは、かつて東村山
市にあった陸軍少年通信兵学校の施設が、第2次大戦
後転用され、誘ってもらったHさんの初期の職場であった
というのが一つ。
次に、新潟県にあった村松少年通信兵学校の卒業生で、
やはり職場の先輩であり四国遍路の先輩でもあるSさん
から、1期先輩が戦場に赴く途中、東シナ海で散ったこと
を記した鎮魂の書を、最近いただいたこと。
もうひとつは、少年通信兵が習得したのと同じモールス
通信の仕事を、私も初めての職場で5年間したことがある
ということから。
陸軍少年通信兵学校は、東村山市富士見町、現在の
第一中や明治学院高校周辺の広大な地域を占めていた。

第2次大戦当時の通信は、主にモールス通信で行われ
たが、通信要員の育成は、「頭の軟らかい純真な少年の
頃から適正なものを選んで教育するのが効果的」というこ
とから、徴兵制度より若い15~16歳の少年を選抜して
行った。
入学希望者は全国から集まり、昭和18年(1943)の
11期生は、定員700人のところ10,000人の応募があ
ったという。
会場には、無線機や受話器、電鍵など、多くの通信機
器が展示されていた。

その中には、Sさんが使った受話器もあった。


通信兵学校の校舎や生徒、訓練中の様子など貴重な
写真も多い。
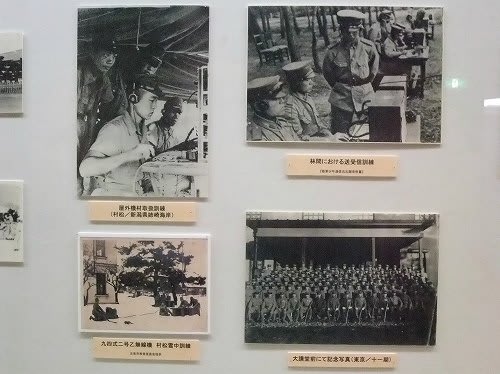
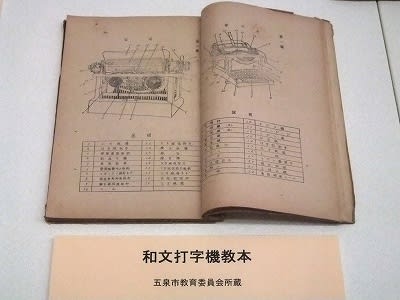
モールス通信を受信して記録する和文タイプライターは、
「和文打字機」と呼ばれ、その教本や、訓練の写真もある。
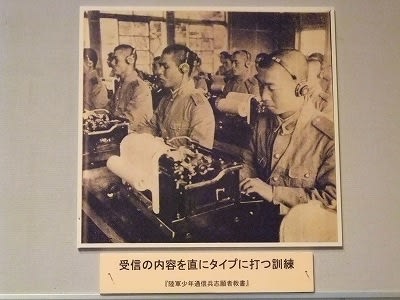
私も最初の職場で、この和文と欧文のタイプライター
の改良したものを使用したが、受信するモールス音は、
このようなレシーバーからでなく、音響機という装置で
聴取した。
蛇足ながら、5年間使ったモールス記号は忘れること
は無く、ン十年過ぎた今でもよく覚えている。
例えば「サイタマ(SAITAMA)」は、和文と英文(欧
文)では以下のようになる。
【和文】 ―・―・― ・― ―・ ―・・―
【英文】 ・・・ ・― ・・ ― ・― ― ― ・―
あわせていえば、現在はデジタルの時代で、地上TV
放送も3年後にはデジタルTVだけになるが、デジタル
通信のさきがけが、このモールス通信なのである。
会場では、東京国立美術館フィルムセンター所蔵の映
画「武蔵野に鍛ふ 陸軍少年通信兵学校の記録」の抜
粋映像も上映されていた。

展示や映像を見ると、厳しい通信訓練や戦闘訓練を経
て戦場に赴き、乏しい資材や食料の中、敵機の来襲を避
けながら通信を確保するため苦労した様子がよく分かり、
改めて平和の尊さをかみしめた終戦記念日であった
この企画展は9月7日(日)まで開催中。
開館時刻は9:30~17:00、月曜休館、入場無料
観覧を終え、東村山駅近くで昼食後、少年通信兵学校
があった現場を訪ねることにした。

西武国分寺線で一つ国分寺寄りの小川駅で下車し、西
へ10分足らずで通信兵学校の正門前に着く。
Hさんが通勤した半世紀以上前は、小川駅から職場まで
の道の両側は林だったとのこと。商店街や住宅の続くその
変わりように驚いていた。
正門の手前を流れる野火止用水の橋の、石のらんかん
は、当時のままらしい。

ここが、少年通信兵学校の正門を入ったあたり。

左手は現在、明治学院高校の正門になっている。
野火止用水に沿って北東に進み、敷地の東端付近まで
行ったら、古い建物が見えた。

そばに近づくと横長に長い平屋の建物。通信兵学校の
材料庫だったものと思われ、現在は使っていないようで
朽ちかけているが、貴重な近代化遺産といえよう。

敷地の東端を北に進み、Hさんのもうひとつの乗降駅
だったという西武多摩湖線の八坂駅に向かった。
歩いた距離はわずかだが、猛暑日の午後で、終戦当日
をしのばせる、厳しい日差しだった。
日になった一昨日より10℃くらいも下がり、涼しい1日で
した。
その一昨日、暑い中訪ねた東京・東村山市での企画展
の模様です。
========================
2008年8月15日(日)
第2次世界大戦が終わって63年の日、東京・東村山市
の「東村山ふるさと歴史館」で開催中の企画展「陸軍少年
通信兵学校」の観覧に、職場の先輩、Hさんなどと行った。


なぜこの企画展に出かけたか。それは、かつて東村山
市にあった陸軍少年通信兵学校の施設が、第2次大戦
後転用され、誘ってもらったHさんの初期の職場であった
というのが一つ。
次に、新潟県にあった村松少年通信兵学校の卒業生で、
やはり職場の先輩であり四国遍路の先輩でもあるSさん
から、1期先輩が戦場に赴く途中、東シナ海で散ったこと
を記した鎮魂の書を、最近いただいたこと。
もうひとつは、少年通信兵が習得したのと同じモールス
通信の仕事を、私も初めての職場で5年間したことがある
ということから。
陸軍少年通信兵学校は、東村山市富士見町、現在の
第一中や明治学院高校周辺の広大な地域を占めていた。

第2次大戦当時の通信は、主にモールス通信で行われ
たが、通信要員の育成は、「頭の軟らかい純真な少年の
頃から適正なものを選んで教育するのが効果的」というこ
とから、徴兵制度より若い15~16歳の少年を選抜して
行った。
入学希望者は全国から集まり、昭和18年(1943)の
11期生は、定員700人のところ10,000人の応募があ
ったという。
会場には、無線機や受話器、電鍵など、多くの通信機
器が展示されていた。

その中には、Sさんが使った受話器もあった。


通信兵学校の校舎や生徒、訓練中の様子など貴重な
写真も多い。
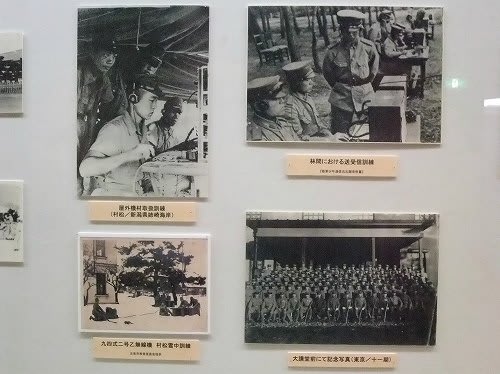
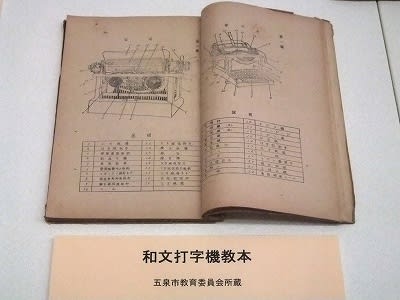
モールス通信を受信して記録する和文タイプライターは、
「和文打字機」と呼ばれ、その教本や、訓練の写真もある。
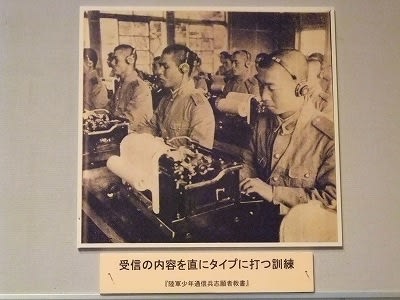
私も最初の職場で、この和文と欧文のタイプライター
の改良したものを使用したが、受信するモールス音は、
このようなレシーバーからでなく、音響機という装置で
聴取した。
蛇足ながら、5年間使ったモールス記号は忘れること
は無く、ン十年過ぎた今でもよく覚えている。
例えば「サイタマ(SAITAMA)」は、和文と英文(欧
文)では以下のようになる。
【和文】 ―・―・― ・― ―・ ―・・―
【英文】 ・・・ ・― ・・ ― ・― ― ― ・―
あわせていえば、現在はデジタルの時代で、地上TV
放送も3年後にはデジタルTVだけになるが、デジタル
通信のさきがけが、このモールス通信なのである。
会場では、東京国立美術館フィルムセンター所蔵の映
画「武蔵野に鍛ふ 陸軍少年通信兵学校の記録」の抜
粋映像も上映されていた。

展示や映像を見ると、厳しい通信訓練や戦闘訓練を経
て戦場に赴き、乏しい資材や食料の中、敵機の来襲を避
けながら通信を確保するため苦労した様子がよく分かり、
改めて平和の尊さをかみしめた終戦記念日であった
この企画展は9月7日(日)まで開催中。
開館時刻は9:30~17:00、月曜休館、入場無料
観覧を終え、東村山駅近くで昼食後、少年通信兵学校
があった現場を訪ねることにした。
西武国分寺線で一つ国分寺寄りの小川駅で下車し、西
へ10分足らずで通信兵学校の正門前に着く。
Hさんが通勤した半世紀以上前は、小川駅から職場まで
の道の両側は林だったとのこと。商店街や住宅の続くその
変わりように驚いていた。
正門の手前を流れる野火止用水の橋の、石のらんかん
は、当時のままらしい。

ここが、少年通信兵学校の正門を入ったあたり。

左手は現在、明治学院高校の正門になっている。
野火止用水に沿って北東に進み、敷地の東端付近まで
行ったら、古い建物が見えた。

そばに近づくと横長に長い平屋の建物。通信兵学校の
材料庫だったものと思われ、現在は使っていないようで
朽ちかけているが、貴重な近代化遺産といえよう。

敷地の東端を北に進み、Hさんのもうひとつの乗降駅
だったという西武多摩湖線の八坂駅に向かった。
歩いた距離はわずかだが、猛暑日の午後で、終戦当日
をしのばせる、厳しい日差しだった。















