2009年5月17日(日)

今日は、JR武蔵野線周辺を歩く、「カタツムリ歩行」の第184回例会
に参加しました。 集合は、西武池袋線ひばりが丘駅です。
遅れて参加の I さんを待ち、10時25分ころ出発しました。
まず向かったのは、駅の北側、昔ながらの細く曲がりくねった商店街
を抜けて間もないところにあった、埼玉県最南端の地。

何年か前に私も、やまさんなどと一緒に確認したところで、上の地図の
緑のピンの位置です。
駅寄りに少し戻って東に向かうと、しゃれた感じのレストランがありました。

看板には、店名の上に「新日本料理」と書かれています。
西東京市立栄小近くの畑では、露地栽培のトマトが実をつけていま
した。

さらに進んだ先の、広葉樹林の一角に育ったタケノコ。

栄町一丁目に入って西武線の線路近くには、古くからの農家らしい
屋敷があり、そのかたわらに「保谷市保存樹木」と記されたケヤキの
古木が立っています。保谷(ほうや)市は合併前の市名で、現在は
旧田無(たなし)市と合併して西東京市です。

西東京市内の電柱に貼ってある町名・番地などの表示板には、地図が
付いていました。

周辺の番地も分かり、家探しなどには便利ですが、北を上にした同じ
ものばかりなので、場所によっては方位を考えて判断しなくてはならず、
その道の向きにしたがった地図ならば、なお分かり易いのにと、親切な
ようで残念な表示です。
近くの踏切を渡って、線路の南の住吉町四丁目へ。五差路の交差点
は「又六地蔵」となっていて、交差点際に「又六石仏群」と記された小さ
いお堂がありました。

中には5体の石仏が並んでいます。元禄10年(1697)造立の青面
金剛から明治30年(1897)の地蔵尊など、当時の上保谷村の又六
講中が造立したもののようです。

交差点の少し東から、南に向かう旧道沿いに畑があり、見たことのない
大きな葉が茂っていて、花のつぼみも付いていました。花は食用になるよう
です。

帰宅後、事務局のDさんから「アイティチョーク(別名チョウセンアザミ)」
とのメールをもらいました。確かにアザミを大きくしたような葉でした。
南に進むと、間もなくゴールの尉殿(じょうどの)神社。珍しい名の神社で、
私ははじめて聞く名前です。11時50分ごろ到着しました。

創建は永正2年(1505)と伝えられ、当時の上保谷村に無くてはなら
ない生活用水を保護する水の神「ジョードノ」を祭ったことにはじまる社と
のこと。
ちなみに、境内にある記念碑を見ると、「保谷」姓の氏子の方が現在も
たくさんお住まいのようです。

南に延びる参道は100mくらいあり、大きなケヤキやイチョウが並んで
います。

境内の、大きなツツジが見ごろでした。

昼食後のミーティング。雨と強風の予報が出ていたためか、参加者はいつ
もより少ない11人。 でも、雨は降りませんでした。

その中で、今回で累計150回参加の I さんに、事務局から記念品が
おくられました。 おめでとうございます。

184回の例会中150回参加ですから、参加率は8割を超え、常連中
の常連の I さんです。これからも、ますますのご参加を…。
ほかに、定年を迎えられた後、お一人で、かねてから念願のネパール
の首都カトマンドゥを何度も訪れ、ほかの人にもネパールを訪ねて欲しい
と、パソコンを習得した上で、『なぜかネパール』というオールカラーの冊
子をパソコンを駆使して制作し、自費出版された(別の)I さんの話なども
伺い、13時過ぎに散会となりました。
今日は、JR武蔵野線周辺を歩く、「カタツムリ歩行」の第184回例会
に参加しました。 集合は、西武池袋線ひばりが丘駅です。
遅れて参加の I さんを待ち、10時25分ころ出発しました。
まず向かったのは、駅の北側、昔ながらの細く曲がりくねった商店街
を抜けて間もないところにあった、埼玉県最南端の地。

何年か前に私も、やまさんなどと一緒に確認したところで、上の地図の
緑のピンの位置です。
駅寄りに少し戻って東に向かうと、しゃれた感じのレストランがありました。

看板には、店名の上に「新日本料理」と書かれています。
西東京市立栄小近くの畑では、露地栽培のトマトが実をつけていま
した。

さらに進んだ先の、広葉樹林の一角に育ったタケノコ。

栄町一丁目に入って西武線の線路近くには、古くからの農家らしい
屋敷があり、そのかたわらに「保谷市保存樹木」と記されたケヤキの
古木が立っています。保谷(ほうや)市は合併前の市名で、現在は
旧田無(たなし)市と合併して西東京市です。

西東京市内の電柱に貼ってある町名・番地などの表示板には、地図が
付いていました。

周辺の番地も分かり、家探しなどには便利ですが、北を上にした同じ
ものばかりなので、場所によっては方位を考えて判断しなくてはならず、
その道の向きにしたがった地図ならば、なお分かり易いのにと、親切な
ようで残念な表示です。
近くの踏切を渡って、線路の南の住吉町四丁目へ。五差路の交差点
は「又六地蔵」となっていて、交差点際に「又六石仏群」と記された小さ
いお堂がありました。

中には5体の石仏が並んでいます。元禄10年(1697)造立の青面
金剛から明治30年(1897)の地蔵尊など、当時の上保谷村の又六
講中が造立したもののようです。

交差点の少し東から、南に向かう旧道沿いに畑があり、見たことのない
大きな葉が茂っていて、花のつぼみも付いていました。花は食用になるよう
です。

帰宅後、事務局のDさんから「アイティチョーク(別名チョウセンアザミ)」
とのメールをもらいました。確かにアザミを大きくしたような葉でした。
南に進むと、間もなくゴールの尉殿(じょうどの)神社。珍しい名の神社で、
私ははじめて聞く名前です。11時50分ごろ到着しました。

創建は永正2年(1505)と伝えられ、当時の上保谷村に無くてはなら
ない生活用水を保護する水の神「ジョードノ」を祭ったことにはじまる社と
のこと。
ちなみに、境内にある記念碑を見ると、「保谷」姓の氏子の方が現在も
たくさんお住まいのようです。

南に延びる参道は100mくらいあり、大きなケヤキやイチョウが並んで
います。

境内の、大きなツツジが見ごろでした。

昼食後のミーティング。雨と強風の予報が出ていたためか、参加者はいつ
もより少ない11人。 でも、雨は降りませんでした。

その中で、今回で累計150回参加の I さんに、事務局から記念品が
おくられました。 おめでとうございます。

184回の例会中150回参加ですから、参加率は8割を超え、常連中
の常連の I さんです。これからも、ますますのご参加を…。
ほかに、定年を迎えられた後、お一人で、かねてから念願のネパール
の首都カトマンドゥを何度も訪れ、ほかの人にもネパールを訪ねて欲しい
と、パソコンを習得した上で、『なぜかネパール』というオールカラーの冊
子をパソコンを駆使して制作し、自費出版された(別の)I さんの話なども
伺い、13時過ぎに散会となりました。










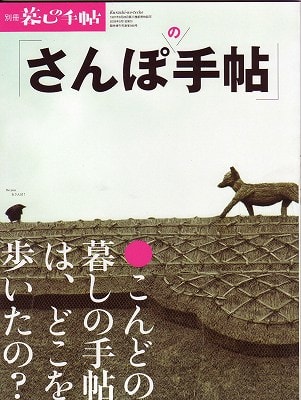







 。
。 。
。























































 。
。 



















