坂村真民の言葉(3) 声
|
坂村真民について (坂村真民記念館 プロフィールから抜粋) |
『声』
生きていることは
すばらしいぞ
そういっている
石がある
木がある
川辺に立つと
水も
そういって
流れていく
〈生きていることは すばらしいぞ〉と私に語りかける。
自然の中で黙って生きている、「石」であり「木」の声が私に語りかけてくる。
〈生きていることは すばらしいぞ〉と。
さらに耳をすませば、流れていく水さえも〈すばらしいぞ〉と囁きかけてくる。
牧村真民(しんみん)さんに語りかけてくるのは、
自然に宿る精霊の声なのかもしれない。
午前零時に起床して夜明けに重信川のほとりで地球に祈りを捧げる生活を送る
真民さんには、森羅万象に宿っていると言われる精霊たちの、
いのちの声が聞こえるのかもしれない。
真民さんの言葉を反芻しながら、今を生きる真民さんがたどり着いた
妥協を許さない孤高の精神修養のことを思った。
そういえば、十数年前に御世話になっていた若い気功師が言っていた。
週五日、患者さんと向き合い気功の施術を行うと、心身ともに疲労して
くる。休診日の日には人気のない森に入り、大樹にしがみついて、
大樹から「気」もらってくると、心身が癒されると。
若い気功師はこれを、「大樹と語る」と言っていた。
もう一人、こちらは高齢の気功師で、ジーパンにTシャツというラフな服装
で施術にあたる。
前者の若い気功師が50分5,000円の施術料に対して、後者は5分で5,000円。
どちらも、人気の気功師だが、前者は撫でるように、もむように施術す
る。対して後者は、患者の体に手をかざすだけで触れもしない。
しかも手をかざしながら世間話をする。あるとき私は、高齢の施術師に言
った。「先生、私は車で一時間以上かけて此処にきています。5分ではなく
もう少し長く施術(やって)いただけますか」と。先生いわく「私の施術は5分
間で十分で、それ以上は必要なく、時間をかけても効果は同じなのです」
その先生が、最近診療をやめた。
年を重ねるにしたがって、体内から発する「気」の量が薄くなり、患者が
望む効果が希薄になって来たのが、原因という。
気功もまた、特定の人間に備わった特殊な能力なのだろう。
森羅万象、生きとし生けるものすべては、留まることを知らず、
流れていく。
「方丈記」の鴨長明は、川面を流れる泡沫を人の世のさだめと考え〈行く河の流れは絶えずし
て……ひさしくとどまりたる例なし〉と無常観を表し、
「平家物語」では、琵琶の音にのせて諸行無常の響き奏で、どんなに権勢をふるい得意の絶頂にあ
ってもそれは一瞬のことで〈ただ春の夢のごとし……ひとへに風の前の塵におなじ〉と、
人生の儚さを謳いあげる。
だからこそ、真民さんは今の一瞬を精一杯生きろと教えている。
凡人には難しい生き方かもしれないが……。
ブックデーター
「坂村真民 一日一言 人生の詩、一念の言葉」
致知出版社 2006(平成18)年12月刊 第一刷
(読書案内№181) (2021.10.01記)












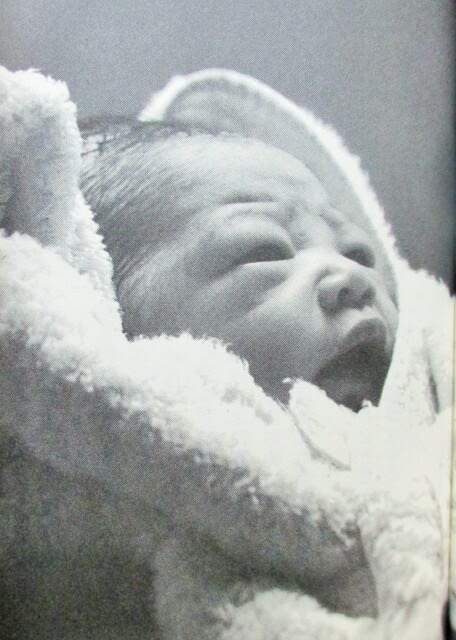
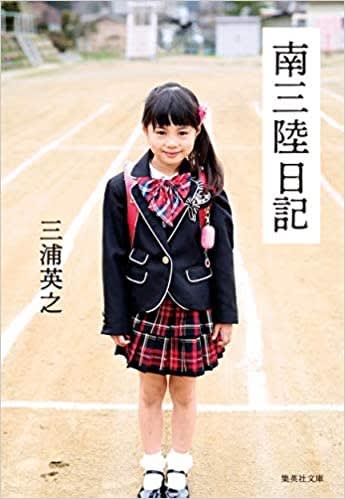


 (本文に添えられた写真)
(本文に添えられた写真)
 (図2 防災対策庁舎三階の屋上に津波が襲う)
(図2 防災対策庁舎三階の屋上に津波が襲う) (雨あがりのペイブメント・撮影)
(雨あがりのペイブメント・撮影)
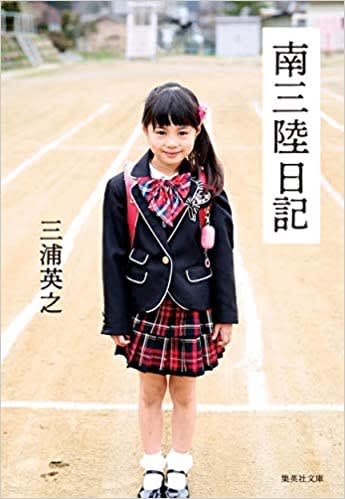 集英社文庫 2019.2 1刷 2019.3 2刷
集英社文庫 2019.2 1刷 2019.3 2刷 (南三陸町)
(南三陸町)



