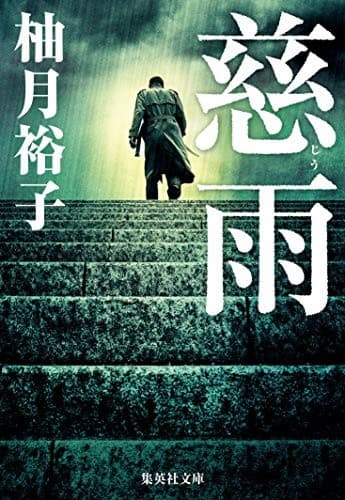読書案内「最期の言葉の村へ」
③ 誰にも止めることはできない
(前回②からの続き)
だが、……
|
(ランプの中の)縄の切れ端を灯心にして火をつけた。私の灯油が共給する弱い黄色のチラチラする明かりが、夜の闇を照らした。私がガンプにいないときは、商売に意欲的な村人が儲けるため町で買ってガンプに持ち帰って売った。電池式の安い中国製LEDランタンのスイッチを入れる者もいた。そういうランタンの光は青く冷たくてギラギラしている。電池の消耗が早いため、ランタンは数日しか持たない。そして熱帯雨林で電池は入手しにくい。(引用) |
最後に奪われるものは
白い人たちが訪れるたびに、ガンプの村は豊かになり、人々は白い人たちを歓迎した。
熱帯雨林の中の植物を採って食べ、獲物を捕らえ、さばいて食べる。
すべての行為は自分たちのために…である。
簡単な布、あるいは植物で編んだ物を腰の周りに巻き付けるだけの簡易なもの、
そんなものさえ必要としない部族もいる。白い人が入ってくれば、腰の巻布は短パンに代り、
やがて、それらは富の象徴として定着していく。
著者が訪れたとき、彼らは泥で汚れ、よれよれになりぼろぼろの短パンを身に着けていた。
それは、貧しさゆえにという理由からではなく、
元来衣服に対する感覚が私たちとは異なっていて、
白い人が持ってきた便利な物程度の意味しか持っていないのだ。
銃を持った白い人と一緒に暴力も入ってくる。
物と物の交換を経て、最後に彼らが交換するのは、人とお金なのだ。
「人狩り」(という表現は著者は使用していない)が頻繁に行われる。
白い人が熱帯雨林の村々を訪れ、短期契約労働者として男たちが他所に集められ、
村々から消えていく。
プランテーションで働く労働力としてガンプ村の人々も「狩られ」ていく。
|
プランテーションとは |
数年後、契約労働を終えた男たちは帰ってくる。
西洋由来の土産を持って、たとえば点かなくなった懐中電灯の電池であったり、
鍋や釜、工場生産の布などである。
そして、最大の土産は公用語として使われている新しい言語トク・ピシンであった。
白い人達が訪れるたびに持ってきた物をガンプ村の人々は歓迎した。
新しいものが入ってくるつどに村は変化し、それに伴って何かを失っていった。
新しい物、特にトク・ピシン語を話すことは、
彼ら契約労働者としてプランテーションで働いた者たちにとっては、
最高のステイタスシンボルになったのに違いない。
トク・ビシン語はまさに彼らにとって、
新しい社会へと繋がる扉を開ける貴重な鍵だったに違いない。
古いタヤップ語は、おそらく未発達の言語なのだろう。全くの想像だが、
「美しい」という言葉には多くの意味があり、
例えば、愛らしい、可愛い、愛しい、このましい、
きれい、いさぎよい、さっぱりしているなど、広辞苑には多くの例が出ている。
古代社会においてはこの「美しい」という言葉一つで表現していました。
言語が発達し成熟してくると、言葉の意味が単純化し、
たくさんの修飾語などでより的確な表現をするようになります。
ステイタスシンボルのトク・ビシン語は表現力豊かであるが、
老人や女子供たちが話すタヤップ語は陳腐で時代遅れと若者たちは思う。
日本語が時代の変遷の中で変遷してきたように、ガンプの村にも時代の波は
「文明」という新しい風をもたらしたのだ。
もう誰にも止めることはできないであろう。
|
かってガンプに固有だっ物の大部分はタヤッブ語が衰え始めるよりずっと前に消滅していた。情け容赦のない巨大なプルトーザーのごとく、20世紀はガンプのーそしてパプアニーユギニアのほどんとの地域のー人々が信じていたもの、作り上げていたものをすべて破壊してしまった。(引用) |
トク・ビシンが侵入するはるか前に文化の崩壊が始まった。白い人が悪いのではない。
白い人が運んできた文明が悪いのではい。
全ては、淘汰という原理に従った結果なのかもしれないと私は思った。
この本の全容を紹介するには、あと何枚の用紙を用意したらいいのだろう。
言語が淘汰されていく過程を大まかに紹介できたと思いますが、
最後にとても辛い現実を紹介して終わりとします。
ガンプの村に現れた集団 殺戮と恐怖
ガンプ村を訪れたのは、「白い人」ばかりではなかった。
1942年、太平洋戦争のさなかガンプ村に訪れた集団があった。
ガンプの村人はその集団のために家を建ててやり、塩と交換にサンゴヤシを提供した。
訪れた集団は最初友好的で、村人にも歓迎された。
|
だがやがて兵隊は、マラリアをはじめとした熱帯性の病気にかかるようになり、、 |
狂暴化し、多くのガンプの人々を死に追いやり、
タヤップ語を話す人々を減少させ、トク・ビシン語の普及に拍車をかけた。
その軍隊は日本軍であった。
そればかりでなく、戦後キリスト教の伝道師たちは、トク・ビシン語で普及を始め、
村人はトク・ビシンによる祈りを唱え、賛美歌を歌い、ミサに聞き入った。
さらに、前述したように、
契約労働者として村を出た人々によるトク・ビシンの普及も大きく影響したようだ。
最後に
消滅危機言語は、タヤップ語ばかりでなく、根未開の地で暮らす人々の部族や地域に
今なお数多く存在している。しかも、50年経ち、100年も経てばそのほとんどの言語は
その存在を失くしていくだろうと著者は論を閉じている。
文明化そのものは、悪いことではないが、それに伴い先祖から受け継いだ文化が失われ、
消滅していき、誰にもそれを止めることはできないという現実を突きつけられて、
私は唖然とした。
(おわり)
(読書紹介№170) (2021.2.3記)












 (原書房 2020.1.25刊 第一刷)
(原書房 2020.1.25刊 第一刷)




 (堀除積雪之図)
(堀除積雪之図)