読書案内「南三陸日記」④ 遺体捜索
「やるなら、今しかないんだ……」
|
前書き |
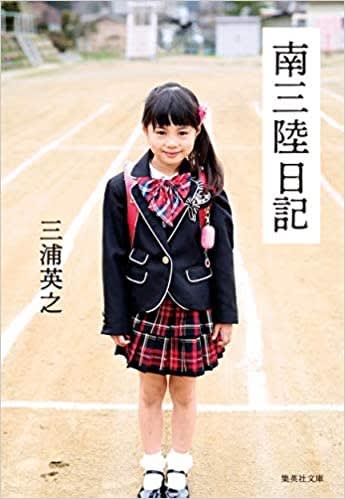 (集英社文庫 2019年2月 第1刷) 著者:朝日新聞記者・三浦英之
(集英社文庫 2019年2月 第1刷) 著者:朝日新聞記者・三浦英之
日記に記された内容は、2011年春から2012年春までの、
震災翌日から現地に入った記者の肌で感じた震災ルポルタージュである。
震災を経て生きる人々の姿を真摯とらえた眼差しが優しい。
震災翌日に現地入りした著者は次のように心の内を吐露しています。
|
最初の数日はまともに記事が書けなかった。 |
著者のこの気持ちはシリーズ②(過去ログ・5月6日)の中で紹介したように「 誰のために記事を書くのか。
その命題を忘れないよう」という気持ちに反映されている。
本書の冒頭には、津波が襲った直後の惨状を見つめる記者としての目がある。
|
リボンを結んだ小さな頭が泥の中に顔をうずめている。 |
震災関係の本の中には、遺体の惨状についての報告をときどき見かける。
想像を絶するような現実に遭遇し、災害の非情さに圧倒される。
木に引っ掛かった遺体、損傷が激しく目をそむけてしまうような遺体等々。
|
機動隊員はね、(遺体が)オヤジやオフクロだと思ってやっていますよ。 |
海で見つかった遺体の写真は、着衣はなく、肉体は白いローソクのようにつるんとしていて、
男女の区別さえつきそうにない。県警幹部のの言葉は、著者に語りかける言葉と同時に、
自分に言い聞かせる言葉でもあったのだろう。
 (本文に添えられた写真)
(本文に添えられた写真)
(南三陸日記・遺体捜索 撮影・西畑志朗氏)
悲しみと、鼻をつく瓦礫や油の匂いが異臭となって体全体に染みついてくる。
「出来るだけ早く遺体を発見する」という使命感を持たなければ、続けられる作業ではない。
県警機動隊員や自衛隊員などプロが覚悟をもって活動しても、
過酷な作業に違いない。
地方公務員の中にも、遺体に関する作業の業務命令で従事する人たちは、
嘔吐と発熱の中歯を食いしばるようにして過酷な現実を堪えたと聞いて言います。
一日一日を地を這うような苦しみの中、やはり強い覚悟がなければ続かない作業だ。
「海が時化(しけ)るたびに連日遺体が打ち上げられてくる」。
遺体捜索の現場は、精神的にも、肉体的にも過酷だ。
異臭の中を飛び交う大量のハエは、捜索員の士気を減退させ、体力の消耗を加速させる
|
あちこちで煙が巻き上がっていた。警察の機動隊員たちは打ち寄せられた流木を燃やし、 |
日が経てば遺体の損傷は一層進んでしまう。
人間の尊厳の為にも、遺族の為にも誰かが従事しなければならない過酷な作業だ。
海岸に流れつく遺体は時間の経過とともに、減少する。同様に瓦礫に飲み込まれた遺体も減少する。
後は、海底に沈んだ遺体だ。
「海底を網でさらうかどうかー」だ。
反対意見もある。
|
いくら亡くなっているとはいえ、身内が網に掛けられて引き上げられることを、 |
逡巡する機動隊員。
夏が迫ってくれば、遺体の損傷は激しくなる。
「なにも遮るもののない海岸で、機動隊員を長時間働かせることは不可能だ」
責任者として部下への配慮は当然のことだ。
配慮や優しさがあれば、部下は過酷な作業にも従事する強さを維持することができるのだ。
「遺体捜索」の章は次の3行を記して終わる。
|
「やるなら、今しかないんだ……」 |
日記の具体的な日付がないので、何時の頃のルポルタージュなのか不明だが、
記載内容からして、震災間もない頃と思われる。
海底の遺体捜索に漁網を使用したという報道は、耳にしたことはないが、
潜水夫を導入した報道を耳にしたことはある。
文面から推測するに、
漁網(底引き網のようなもの)を導入しての「遺体捜索」に踏み切ったように思える。
このことが報道されなかったとすれば、
社会的な規範の維持と遺族への配慮があったからなのだろう。
2020年秋、私は10メートルもかさ上げされた防潮堤の上を走る道路に立った。
震災からもうすぐ10年を迎える。
かさ上げされた道路の下には、かって民家が点在し、松林が海岸線を走っていたはずだ。
瓦礫は取り除かれ、新しい道路や海岸線の工事で走り回るダンプを除けば、
静かな三陸の海が、あの日のことを忘れたように優しい風を送ってくる。
山を削り、造成された高台に民家は移住した。
海岸線は遠く、南三陸町に昔日の面影を残す景色はない。
復旧・復興のスローガンに裏打ちされ、新しい町ができた。
できつつある……。
津波の来たあの日、町は失われたけれど、
祖父や父や母から受け継いだ
三陸に住む人々の穏やかな笑顔がふる里の象徴として、
大切な心の遺産として残っていくことを願いながら、
海岸線を走る道路に戻った。
(つづく)
(2021.6.5記) (読書案内№175)
















