
(つづき)
「流通経由右折」の貼り紙。
「507は都橋」「←南・西→」などと同様、運転手さんに向けての注意喚起である。


ここは福岡市東区の「浜田」バス停。


「73番」と「78番」はこの先の交差点を右折して流通センターへ、「77番」は流通センターには行かず直進する。

ただし「73番」「78番」は、この交差点を曲がってすぐのところにある「流通センター西」のバス停には停車しない。

JR九州バスのバス停名は「筑前浜田」。
鉄道の駅名(山陰本線「浜田」駅)との重複を避ける意図があったのだろうと思われる。


同様に、この先には「筑前土井」や「筑前蒲田」といったバス停もあり。



反対側。
ひとつ先は「松島一丁目」。
「松島一丁目」の次は、西鉄が「原田」で、JRは「箱崎原田」。
全く別の場所にある「原田」駅は「筑前」に所在することから、これとは区別する意味で、「筑前」ではなく「箱崎」が付いた感じだろうか(“はらだ”と“はるだ”で読みに違いはありますが)。
鉄道のことはあまり詳しくないので、的外れなことを書いているかもしれません。
(つづく)
「流通経由右折」の貼り紙。
「507は都橋」「←南・西→」などと同様、運転手さんに向けての注意喚起である。


ここは福岡市東区の「浜田」バス停。


「73番」と「78番」はこの先の交差点を右折して流通センターへ、「77番」は流通センターには行かず直進する。

ただし「73番」「78番」は、この交差点を曲がってすぐのところにある「流通センター西」のバス停には停車しない。

JR九州バスのバス停名は「筑前浜田」。
鉄道の駅名(山陰本線「浜田」駅)との重複を避ける意図があったのだろうと思われる。


同様に、この先には「筑前土井」や「筑前蒲田」といったバス停もあり。



反対側。
ひとつ先は「松島一丁目」。
「松島一丁目」の次は、西鉄が「原田」で、JRは「箱崎原田」。
全く別の場所にある「原田」駅は「筑前」に所在することから、これとは区別する意味で、「筑前」ではなく「箱崎」が付いた感じだろうか(“はらだ”と“はるだ”で読みに違いはありますが)。
鉄道のことはあまり詳しくないので、的外れなことを書いているかもしれません。
(つづく)
















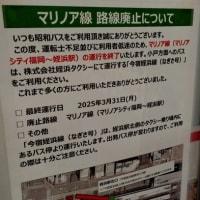















































JRは、国鉄時代から、同じ名称となる「駅名」をさまざまな接頭語をつけて識別できるようにしています。それも全国規模で。もっともわずかな例外はありますが(「福島」のように)。
そこで、バス停であっても、全国を見渡して同じ名称となる鉄道またはバスの「駅」があれば接頭語をつけるのだと、私は解釈しています。
でも、今ふと気づいたのですが、それならば、「筑前土井」は、どこの「土井」駅と区別するためのものなのでしょう?
鉄道の「土井」駅はすぐに目の前にあり、「筑前」と付けたところで区別になっていないではないか、と。
鉄道を「土井」駅、バスを「筑前土井」駅とすることで名称の上では区別されるからそれでよし、としたのか、それとも、鉄道は鉄道、バスはバスで、別々に名称の重複を避けるようにしているのか、…
もしも後者なら、全国のJRバスの「駅名」に、「浜田」、「蒲田」、「土井」があるはず、ということになります。「浜田」については、島根県の「浜田」は確かに国鉄時代からの国鉄バスの拠点ですが。
たしかに、JRにとってはバス停も「駅」という扱いのようですね。
>でも、今ふと気づいたのですが、それならば、「筑前土井」は、どこの「土井」駅と区別するためのものなのでしょう?
>鉄道の「土井」駅はすぐに目の前にあり、「筑前」と付けたところで区別になっていないではないか、と。
>鉄道を「土井」駅、バスを「筑前土井」駅とすることで名称の上では区別されるからそれでよし、としたのか、それとも、鉄道は鉄道、バスはバスで、別々に名称の重複を避けるようにしているのか、…
>もしも後者なら、全国のJRバスの「駅名」に、「浜田」、「蒲田」、「土井」があるはず、ということになります。「浜田」については、島根県の「浜田」は確かに国鉄時代からの国鉄バスの拠点ですが。
全国のJRバスのバス停のことはわからないのですが、香椎線の土井駅と、JR九州バスの筑前土井バス停は、やや離れて位置することから、別の「駅」だという認識なのかな?と思っていました。