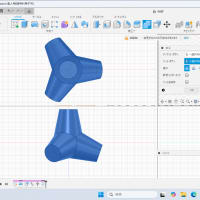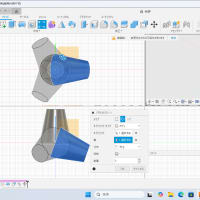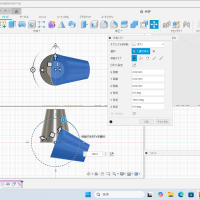○死んだら全て終わり。
生存は結果であり、結果である以上そこには目的も意味も存在する必要性はない。
文系大衆観念的には存在の意義や価値というものがあらゆる生物には予め存在しているものであるという錯覚が存在するようであるが、生存や存在自体には目的も意味も存在する必要性はない。起こったことの全てに意味をこじつける必要性はないのである。
生死に関わることであれば、あたかも絶対的な優先重大事項であると「思う。」であろうが、生存というのは常に暫定であり永遠ではない。ヒトにとって本能感情的には重大な生存価であっても、人間存在としての価値において生存というのは絶対的な価値にはなりえない。
目先の個人的本能が優先すれば、社会全体における持続可能性や安全性は意識の上から排除されがちな傾向がヒトにはある。しかし、社会全体の持続可能性や安全性が確保されない社会に自己が生き続ける合理的根拠など存在しないのである。
ドーパミンの持つ常習性が作り出す本能的な自己保存行動選択である気分的「安心。」というものは、本能的には最大優先事項として扱われるものである。しかし、これは本能に由来する仕組みによって作り出される価値観であって、本質的には自己自身の論理的選択によって決定されているものではない。
自己保存とは利己である。都合の良い時だけ「人は一人では生きてゆけない。」などと論じておきながら、一方では「死んだら全て終わり。」とする文系大衆観念には論理整合性が欠落している。
自己個人が死ぬとしても、社会自体は全く「終わり。」でも何でもない。個人の主観的価値観だけに依る「全て終わり。」という論証には、本質的な合理性が存在しないのである。
論理整合性のない文系大衆観念を相手にして論ずることは徒労である。その場限りの感情だけによって言い逃れや取り繕いをされていては何ら論理的検証も出来なければ、当然原因究明も対策も言及することが出来ないからである。
ヒトの全ては必ず死ぬ。死ぬのであれば社会持続可能性や安全性といったものが不要であろう。だが、それは今すぐ死ぬ者においての論理に過ぎず、社会持続可能性や安全性が確保されない社会に生き続ける合理的根拠も存在しないのである。「死んだら全て終わり。」という主張は、個人の生死に関わる事柄においては本能的価値観を優先しておきながら、一方では「一人では生きてゆけない。」と社会における自己存在を求める文系大衆観念特有のご都合主義によるものである。
生きてゆく過程においては社会への依存を主張しておきながら、死ぬ段階においては「全て終わり。」などと社会の存在を無視するのは、社会的な「甘え。」に過ぎない。
個人が社会という多数他人への依存が不可欠である以上、個人もまた他人に対しての被依存性を持たなければならない。これは権利と義務であって、権利だけを主張するというのは本能主体の動物的「ヒト。」の主張であり、人間性が欠落している。
社会公平性というものを社会に求めるのであれば、個人が他者に対しても公平であろうとすべきである。他者に対して不公平な者が社会(多数他人)に対して公平性を求めるというのは身勝手な主張である。
社会持続可能性や安全性を求めるというのは、自分が死んだ後の社会についてへの配慮、意識の広さによるものである。「死んだら全て終わり。」などという話には、個人の生存という本能主体の無意識的価値観に基づく意識狭窄性によって導き出された主張に過ぎない。
ヒトの多くは本能的欲求を持ち出されると簡単に思考が停止してしまう傾向がある。ゴルフのパターだの将棋の勝ち負けといった世間的評価成功といった欲望に直結する話を持ち出すと、簡単に本質的知能というものについての論理検証性が失われてしまうのも、その一例である。
既に起こったことに対して、事後正当化のための屁理屈をこじつけたがる性質がヒトにはある。養老孟司が「私は30年間も安月給で大学勤めをした。だから、そこには意味があったんだ、そう思わなきゃやってられないじゃありませんか。」などという単なる個人的感情を多数の文系大衆観念者達と共有することによって、あたかも論理的証明であるかの如く撹乱することが可能であり、こうした文系大衆観念の共有こそが洗脳ペテンの根源である。
文系大衆観念というものは、論理的な根拠証明を放棄し、個人的心情の多数共有による気分的安心によって作り出されるものである。
起こったことの全てが偶然に由来するものであるとしても、これから起こりうることの全てを無視して寝ていて良いという論拠には全くならない。むしろ、既に自分の脳に組み込まれた無意識的本能による危険性を認識することが重要なのであり、何が偶然で何が必然であるかを区別認識することこそが科学的認識というものの価値である。
「起こったことの全ては偶然であると称して寝ていても構わない。」と言われて、あらゆる事象に意味だの目的をこじつけることに意識誘導されているから、いつまで経ってもバカが治らず同じ過ちを繰り返し続けることに陥るのである。
自己が現時点において存在すること自体に意味だの目的があるわけではない。個人の生存や存在というものは、個人が主体的に意味や目的を見つけるものであって、自己以外から予め準備提供されるようなものではない。
自己存在の意味というものを予め「誰か。」に準備提供されるはずだという観念は、本能的社会形成習性によって作り出されるものであり。「誰か。」という他者に対する盲目的依存性、「甘え。」によるものである。
「ヒトは何処から来て、何処へ行くのか。」という問いがあるが。「何処へ行くのか。」という目的は「何処から来た。」のかという結果とは無関係である。ヒトという種の生物が、虐殺だの強姦の結果として生存していたとしても、虐殺や強姦が正当化できるわけではないからだ。
「ヒトは今までこうだった。」ことを大量に抽出枚挙しても、「ヒトとは永遠にこうである。」ことの論証にはならない。
ヒトは初期的には動物であるから、本能的無意識行動バイアスによって意識の9割以上を構造原理的に占めている。従って本質的な意識としての論理的思考は1割にも満たず、行動バイアスとしての機能を構造原理的に持っていない。
バイアスとは「程度。」問題である。行動バイアスというのは気分的な程度問題に過ぎず、構造的に合理性を持たない。構造的に合理性判断が困難であることを断片的に枚挙しても、合理性判断をしなくて良い論証にはならないのである。
文系大衆観念上では、ヒトという種の生物の傾向性を枚挙することで気分的に安心することで満足したり怖がるだけで、論理的思考を全くしたがらない。ヒトという種の生物の、どのような傾向性を枚挙しても、傾向性自体は結果以上の何物でもなく。気分的にどんなに安心満足しようが怖がろうが、意識的に選択される目的とは無関係なのである。
「ヒトとはこういうものである。」ことをどんなに大量に抽出枚挙しても、意識的目的選択可能性の反証には全くならない。
結果の大量抽出枚挙によって、あたかも意識的目的選択不可能性であるかのように錯覚するから文系大衆観念というのは論理的思考が全く出来ないのである。
ヒト、或は自己というものの傾向性が如何なるものであろうとも、自律的に論理的行動選択をしなくて良い理由には全くならない。ところが文系大衆観念によるアプリオリな思い込み上では、本能習性という傾向の多数抽出さえしておけば、本能習性のままに無意識に流されておいても良いものであると勝手に錯覚する性質がある。
「だって、そういうものだから。」とか「だって、みんなそうだから。」といった結果の多数抽出さえしておけば、気分的に安心し満足し、目的行動の論理検証性を放棄をするのは子供じみた言い逃れに過ぎない。
目的行動の論理検証、「考え。」というものは、気分的にしたいとかしたくないといった「思い。」で放棄して良いようなものではない。しかし、そもそも自己存在の動機自体が世間からの評価報酬である者の場合、自発的な目的行動の論理検証をしたがらないものであり、結果的に自律的な社会安全性や持続可能性には意識が働かないものなのである。
自己存在の動機自体を自己内部に持たず、目先の世間からの評価に依存している以上。あらゆる「考え。」もまた他者から問題を提供され、その問題についての解答以外には意識は働かない。与えられた問題への解答による他者からの評価報酬しか意識が働かないからである。こうした状態こそが無意識的な条件反射であり、チンパンジーの瞬間記憶能力テストでの成績評価と構造原理的に全く同じものなのである。
マイケル:サンデルの講義で頭が良くならないのは、サンデルが提供した問題の内部でしか考えが働かないという構造原理的な意識誘導が存在するからであり。むしろサンデルらの講義特有の「よく出来ました。」的な誉め言葉によって気分的に満足したことを、あたかも「自分の頭が良くなった。」と勝手に錯覚しているだけなのである。
ヒトの多くは気分的に良くなると、頭が良くなったと錯覚する性質がある。限定的な問題内部についての検証をしたことによって、あたかもあらゆる物事への検証性が獲得できたような気分に陥り、むしろ自らの無思考性を意識から外すことによって気分的に満足するのである。
問題を提供されなくても追求する自発性、評価報酬に依存しない徹底性というものは、本質的自発性によってのみ促されるものであり。他人から提供された問題内部でしか考えが及ばない自発性の欠落によって、あらゆる文系大衆観念というものは論理検証されることなく放置無視されてきたのである。
文系大衆観念というものは、すなはち自発性の欠落によって作り出されたものであり。本能的シーケンスによってアプリオリに陥る普遍的ヒトの習性の結果である。
「権威に服従しない社会は崩壊する。」と、大衆の多くは観念的に納得するであろう。しかし、これは論理的根拠には全くならず、単なる気分的な安心満足によって思考放棄している錯覚であることを、多くのヒトは認識できない。
権威というものは論理的、科学的に証明されたものではない。権威性とは多数によって認証されただけの文系観念上における服従安心対象に過ぎない。
権威に盲目的に服従しておけば気分的に安心であろう。ヒトとは封建的ヒエラルキー社会を形成しておけば気分的に安心するように本能的仕組みがあるからだ。
権威者が、「ヒトという種の生物には、他者との平和共存の傾向性がある。」と述べれば、あたかもヒトという種の生物は常に本能的無意識に平和共存に至る選択が可能であると錯覚し。多くのヒトは気分的に満足して自律的論理検証を放棄することが出来る。
ヒトには他者との平和共存の傾向性も確かに存在するであろう。しかし、本能というのは特定の「誰か。」が目的意識に基づいて選択したようなものではなく、あくまでも結果以上の意味が存在せず、ヒトには残虐性や無責任性といったものも明らかに存在するのである。
本能による行動選択によって、どのような結果をもたらすのかをある程度予測することは可能である。実際権威者と見なした相手に盲目的に服従しておけば残虐で無責任な行動に至ることも立証されている。
断片的安全性だけを頼りに本能の持つ危険性を無視するというのは、単なる気分的満足に過ぎず、極めて無意識的であり合理性が欠落している。
何が安全で、何が危険であるのかを認識区別し、選択するのは意識であって本能ではない。生物本能は個人の目先の生存に適することはあっても、人間として、社会安全性や持続可能性に適するようには構造原理的に出来ていないからである。
意識的にあらゆる全ての事柄を区別認識することはできないが、何が可能で何が不可能であるかを区別認識するのもまた意識である。認識不能な事柄における選択については科学的認識というものは役に立たないが、本能的行動バイアスの全てが常に安全である保障はなく、むしろ科学的に認識可能な安全性を無視して保障のない本能を優先させてしまう傾向があることが問題なのである。
酒を呑まずに自動車を運転したからといって重大事故に至らない保障があるわけではない。しかし、酒によって脳が麻痺した状態の方が重大事故に至る可能性が高いことに異論はなかろう。
科学的証明というものは、この世の全ての安全性を担保できるような万能なものではない。しかし、安全性を高めることには寄与できるとしても、損ねることにはならない。
科学が万能でないからといって、本能由来の観念の正当性を証明したことにはならないのである。
偶発的に本能的行動バイアスが上手く作用したことがあるとしても、常に本能的行動バイアスが上手く作用することの論証にはならないのだが。本能的行動バイアスによって上手く作用した経験程、あたかも既に自分の中に組み込まれた本能的な行動バイアスが特別に優位であるかのような錯覚を促すために、ヒトの多くは本能的行動バイアスを優先してしまうのである。
ギャンブルや投資で多額の損失を補えるという根拠のない錯覚も、このようにして暴走するのである。
将棋やレーシングカーの操縦などにおける無意識的能力の高さというものは、あくまで日々の鍛練習熟によって得られるものであり、決して先天的に組み込まれた能力などではない。
ところが、ヒトの多くは概ね上手く作用した結果だけに基づいて、自分の無意識的行動バイアスの全ては常に安全であると簡単に安心し、錯覚する傾向がある。
概ね上手く作用した結果の多数枚挙によって、あたかも絶対的に上手く作用すると錯覚するのである。
概ね自分にとって利己的に上手く作用した結果が多い場合、自分というものが予め先天的に意味を持つものであると錯覚するのである。
自分の行動選択が、概ね自分にとって有利に働いたことによって気分的に安心して無意識本能任せにしておくことが出来るようになるのである。
こうした無意識による「馴れ。」というものこそが、ドーパミンの持つ常習性によって作り出された行動学習の正体である。
多くの場合騙されたことがない者の場合、論理的根拠もなく「自分は絶対騙されることはない。」と勝手に思い込むことによって、自己存在が他人とは異なる特別なものであると錯覚し、「自分だけは大丈夫。」であると気分的に安心するのである。
東大の学長が論じたように、「全てを疑え。」というのが正しい判断を導く。だが、多くのヒトは今まで信じ込んできたものを疑い、検証することを怖れ。盲目的に信じ込み続けることの気分的安心「甘え。」を放棄することが困難である。
盲目的に多数や権威を信頼することに依存してきた者にとって、その依存を断ち切ることに対して精神的恐慌をきたすため、何が何でも多数や権威性への盲信を捨てることが出来なくなってしまうのである。
文系大衆観念的には、「甘え。」を断ち切るためには精神論的な努力辛抱根性によって、無理矢理我慢し、堪えることによって達成出来ると勝手に勘違いする。
精神論的な忍耐というものには、個人の許容量というものがあり。努力辛抱根性的な忍耐我慢によって全てがどうにかなるようなものではない。煙草の依存症治療同様に、無意識下に行動学習された条件反射的価値観というものを矯正するためには、地道で小さな努力の積み重ねによる「慣れ。」が肝要である。一朝一夕にどうにかなるようなものであると「思う。」ことこそ、短絡的な文系大衆観念というものである。
世間という多数他人や、それによって認証された権威に対する盲目的服従迎合というものは、長い期間に渡る刷り込み行動学習によって作り出されたものである。依存症というのは無意識下に安心快楽として刷り込まれてしまったものであり、急激に依存症を治すことは原理的にも不可能である。依存症の類というものは、ある程度の時間期間に渡る、地道な「慣れ。」によって矯正するべきものであって、短絡的に忍耐我慢によって治るようなものではない。
ドーパミンが持つ常習性による「慣れ(馴れ)。」というものは、その性質に無為無策に流されるのではなく。積極的に意識的目的のために利用する道具として扱うべきなのである。
社会性、或は社交性といったものを持たないことを。多くの大衆文系観念者達は人間性の欠如と勝手に錯覚する。しかし本能的な社会形成習性というものは「ヒト。」としての本能の程度問題に過ぎず、何ら社会安全性や持続可能性に影響を及ぼすものではない。むしろ社交性、或はコミュニケーション能力と称して多数権威に盲目的服従迎合をしてしまうことの方が人間性の欠落を招くことの方が圧倒的に多いことを、多くのヒトは認識したがらない。
文系の観念上では、社交的でない生物的コミュニケーション能力の低い者に対する観念的恐怖心によって、あたかも生物的コミュニケーション能力が低いことこそが人間性の欠落であるかのような錯覚を抱きがちである。しかし、この観念には論理的合理性は全く存在せず、単なる本能的恐怖心によるヒステリックな拒絶反応に過ぎない。
社交性がないことというのは、社交性に固執する者にとっては耐えがたい精神的に恐慌をきたすような地獄であると勝手に錯覚しがちであるが。社交性のない者にとっては社交性がないことは普通で自然なことであって、何ら精神的恐慌などきたすことはなく。むしろ精神的恐慌をきたすと勝手に錯覚していること自体が社交性に対する依存症の現れであり、勝手な主観的思い込みに過ぎない。
文系大衆観念上における「社会性。」というものは、単なる外見上の気分的安心感を論じているだけであり。何ら論理的人間性や安全性の論証にはなっておらず。本質的な「人間としての社会性。」の論証とは無関係な観念に過ぎない。
生物本能的な社会形成習性が希薄で観念的安心感をもたらさない者に対しての異常なまでの拒絶反応こそが、非人間的排除差別というものの根源である。そこに気付かず漫然と排除差別をし続けておいて「社会性。」もすったくれもあったものではない。
自分の価値観の、一体何が論理的根拠を持たない実証不能の文系大衆観念であるかすら自律的に検証できずに、人間とは何かを論ずる資格はない。それは単なる「ヒト。」という種の大型類人猿に過ぎないからである。
たとえどんなに学力学歴が高くても、年収が多くても、書いた本の販売部数が多くてもである。
Ende;
生存は結果であり、結果である以上そこには目的も意味も存在する必要性はない。
文系大衆観念的には存在の意義や価値というものがあらゆる生物には予め存在しているものであるという錯覚が存在するようであるが、生存や存在自体には目的も意味も存在する必要性はない。起こったことの全てに意味をこじつける必要性はないのである。
生死に関わることであれば、あたかも絶対的な優先重大事項であると「思う。」であろうが、生存というのは常に暫定であり永遠ではない。ヒトにとって本能感情的には重大な生存価であっても、人間存在としての価値において生存というのは絶対的な価値にはなりえない。
目先の個人的本能が優先すれば、社会全体における持続可能性や安全性は意識の上から排除されがちな傾向がヒトにはある。しかし、社会全体の持続可能性や安全性が確保されない社会に自己が生き続ける合理的根拠など存在しないのである。
ドーパミンの持つ常習性が作り出す本能的な自己保存行動選択である気分的「安心。」というものは、本能的には最大優先事項として扱われるものである。しかし、これは本能に由来する仕組みによって作り出される価値観であって、本質的には自己自身の論理的選択によって決定されているものではない。
自己保存とは利己である。都合の良い時だけ「人は一人では生きてゆけない。」などと論じておきながら、一方では「死んだら全て終わり。」とする文系大衆観念には論理整合性が欠落している。
自己個人が死ぬとしても、社会自体は全く「終わり。」でも何でもない。個人の主観的価値観だけに依る「全て終わり。」という論証には、本質的な合理性が存在しないのである。
論理整合性のない文系大衆観念を相手にして論ずることは徒労である。その場限りの感情だけによって言い逃れや取り繕いをされていては何ら論理的検証も出来なければ、当然原因究明も対策も言及することが出来ないからである。
ヒトの全ては必ず死ぬ。死ぬのであれば社会持続可能性や安全性といったものが不要であろう。だが、それは今すぐ死ぬ者においての論理に過ぎず、社会持続可能性や安全性が確保されない社会に生き続ける合理的根拠も存在しないのである。「死んだら全て終わり。」という主張は、個人の生死に関わる事柄においては本能的価値観を優先しておきながら、一方では「一人では生きてゆけない。」と社会における自己存在を求める文系大衆観念特有のご都合主義によるものである。
生きてゆく過程においては社会への依存を主張しておきながら、死ぬ段階においては「全て終わり。」などと社会の存在を無視するのは、社会的な「甘え。」に過ぎない。
個人が社会という多数他人への依存が不可欠である以上、個人もまた他人に対しての被依存性を持たなければならない。これは権利と義務であって、権利だけを主張するというのは本能主体の動物的「ヒト。」の主張であり、人間性が欠落している。
社会公平性というものを社会に求めるのであれば、個人が他者に対しても公平であろうとすべきである。他者に対して不公平な者が社会(多数他人)に対して公平性を求めるというのは身勝手な主張である。
社会持続可能性や安全性を求めるというのは、自分が死んだ後の社会についてへの配慮、意識の広さによるものである。「死んだら全て終わり。」などという話には、個人の生存という本能主体の無意識的価値観に基づく意識狭窄性によって導き出された主張に過ぎない。
ヒトの多くは本能的欲求を持ち出されると簡単に思考が停止してしまう傾向がある。ゴルフのパターだの将棋の勝ち負けといった世間的評価成功といった欲望に直結する話を持ち出すと、簡単に本質的知能というものについての論理検証性が失われてしまうのも、その一例である。
既に起こったことに対して、事後正当化のための屁理屈をこじつけたがる性質がヒトにはある。養老孟司が「私は30年間も安月給で大学勤めをした。だから、そこには意味があったんだ、そう思わなきゃやってられないじゃありませんか。」などという単なる個人的感情を多数の文系大衆観念者達と共有することによって、あたかも論理的証明であるかの如く撹乱することが可能であり、こうした文系大衆観念の共有こそが洗脳ペテンの根源である。
文系大衆観念というものは、論理的な根拠証明を放棄し、個人的心情の多数共有による気分的安心によって作り出されるものである。
起こったことの全てが偶然に由来するものであるとしても、これから起こりうることの全てを無視して寝ていて良いという論拠には全くならない。むしろ、既に自分の脳に組み込まれた無意識的本能による危険性を認識することが重要なのであり、何が偶然で何が必然であるかを区別認識することこそが科学的認識というものの価値である。
「起こったことの全ては偶然であると称して寝ていても構わない。」と言われて、あらゆる事象に意味だの目的をこじつけることに意識誘導されているから、いつまで経ってもバカが治らず同じ過ちを繰り返し続けることに陥るのである。
自己が現時点において存在すること自体に意味だの目的があるわけではない。個人の生存や存在というものは、個人が主体的に意味や目的を見つけるものであって、自己以外から予め準備提供されるようなものではない。
自己存在の意味というものを予め「誰か。」に準備提供されるはずだという観念は、本能的社会形成習性によって作り出されるものであり。「誰か。」という他者に対する盲目的依存性、「甘え。」によるものである。
「ヒトは何処から来て、何処へ行くのか。」という問いがあるが。「何処へ行くのか。」という目的は「何処から来た。」のかという結果とは無関係である。ヒトという種の生物が、虐殺だの強姦の結果として生存していたとしても、虐殺や強姦が正当化できるわけではないからだ。
「ヒトは今までこうだった。」ことを大量に抽出枚挙しても、「ヒトとは永遠にこうである。」ことの論証にはならない。
ヒトは初期的には動物であるから、本能的無意識行動バイアスによって意識の9割以上を構造原理的に占めている。従って本質的な意識としての論理的思考は1割にも満たず、行動バイアスとしての機能を構造原理的に持っていない。
バイアスとは「程度。」問題である。行動バイアスというのは気分的な程度問題に過ぎず、構造的に合理性を持たない。構造的に合理性判断が困難であることを断片的に枚挙しても、合理性判断をしなくて良い論証にはならないのである。
文系大衆観念上では、ヒトという種の生物の傾向性を枚挙することで気分的に安心することで満足したり怖がるだけで、論理的思考を全くしたがらない。ヒトという種の生物の、どのような傾向性を枚挙しても、傾向性自体は結果以上の何物でもなく。気分的にどんなに安心満足しようが怖がろうが、意識的に選択される目的とは無関係なのである。
「ヒトとはこういうものである。」ことをどんなに大量に抽出枚挙しても、意識的目的選択可能性の反証には全くならない。
結果の大量抽出枚挙によって、あたかも意識的目的選択不可能性であるかのように錯覚するから文系大衆観念というのは論理的思考が全く出来ないのである。
ヒト、或は自己というものの傾向性が如何なるものであろうとも、自律的に論理的行動選択をしなくて良い理由には全くならない。ところが文系大衆観念によるアプリオリな思い込み上では、本能習性という傾向の多数抽出さえしておけば、本能習性のままに無意識に流されておいても良いものであると勝手に錯覚する性質がある。
「だって、そういうものだから。」とか「だって、みんなそうだから。」といった結果の多数抽出さえしておけば、気分的に安心し満足し、目的行動の論理検証性を放棄をするのは子供じみた言い逃れに過ぎない。
目的行動の論理検証、「考え。」というものは、気分的にしたいとかしたくないといった「思い。」で放棄して良いようなものではない。しかし、そもそも自己存在の動機自体が世間からの評価報酬である者の場合、自発的な目的行動の論理検証をしたがらないものであり、結果的に自律的な社会安全性や持続可能性には意識が働かないものなのである。
自己存在の動機自体を自己内部に持たず、目先の世間からの評価に依存している以上。あらゆる「考え。」もまた他者から問題を提供され、その問題についての解答以外には意識は働かない。与えられた問題への解答による他者からの評価報酬しか意識が働かないからである。こうした状態こそが無意識的な条件反射であり、チンパンジーの瞬間記憶能力テストでの成績評価と構造原理的に全く同じものなのである。
マイケル:サンデルの講義で頭が良くならないのは、サンデルが提供した問題の内部でしか考えが働かないという構造原理的な意識誘導が存在するからであり。むしろサンデルらの講義特有の「よく出来ました。」的な誉め言葉によって気分的に満足したことを、あたかも「自分の頭が良くなった。」と勝手に錯覚しているだけなのである。
ヒトの多くは気分的に良くなると、頭が良くなったと錯覚する性質がある。限定的な問題内部についての検証をしたことによって、あたかもあらゆる物事への検証性が獲得できたような気分に陥り、むしろ自らの無思考性を意識から外すことによって気分的に満足するのである。
問題を提供されなくても追求する自発性、評価報酬に依存しない徹底性というものは、本質的自発性によってのみ促されるものであり。他人から提供された問題内部でしか考えが及ばない自発性の欠落によって、あらゆる文系大衆観念というものは論理検証されることなく放置無視されてきたのである。
文系大衆観念というものは、すなはち自発性の欠落によって作り出されたものであり。本能的シーケンスによってアプリオリに陥る普遍的ヒトの習性の結果である。
「権威に服従しない社会は崩壊する。」と、大衆の多くは観念的に納得するであろう。しかし、これは論理的根拠には全くならず、単なる気分的な安心満足によって思考放棄している錯覚であることを、多くのヒトは認識できない。
権威というものは論理的、科学的に証明されたものではない。権威性とは多数によって認証されただけの文系観念上における服従安心対象に過ぎない。
権威に盲目的に服従しておけば気分的に安心であろう。ヒトとは封建的ヒエラルキー社会を形成しておけば気分的に安心するように本能的仕組みがあるからだ。
権威者が、「ヒトという種の生物には、他者との平和共存の傾向性がある。」と述べれば、あたかもヒトという種の生物は常に本能的無意識に平和共存に至る選択が可能であると錯覚し。多くのヒトは気分的に満足して自律的論理検証を放棄することが出来る。
ヒトには他者との平和共存の傾向性も確かに存在するであろう。しかし、本能というのは特定の「誰か。」が目的意識に基づいて選択したようなものではなく、あくまでも結果以上の意味が存在せず、ヒトには残虐性や無責任性といったものも明らかに存在するのである。
本能による行動選択によって、どのような結果をもたらすのかをある程度予測することは可能である。実際権威者と見なした相手に盲目的に服従しておけば残虐で無責任な行動に至ることも立証されている。
断片的安全性だけを頼りに本能の持つ危険性を無視するというのは、単なる気分的満足に過ぎず、極めて無意識的であり合理性が欠落している。
何が安全で、何が危険であるのかを認識区別し、選択するのは意識であって本能ではない。生物本能は個人の目先の生存に適することはあっても、人間として、社会安全性や持続可能性に適するようには構造原理的に出来ていないからである。
意識的にあらゆる全ての事柄を区別認識することはできないが、何が可能で何が不可能であるかを区別認識するのもまた意識である。認識不能な事柄における選択については科学的認識というものは役に立たないが、本能的行動バイアスの全てが常に安全である保障はなく、むしろ科学的に認識可能な安全性を無視して保障のない本能を優先させてしまう傾向があることが問題なのである。
酒を呑まずに自動車を運転したからといって重大事故に至らない保障があるわけではない。しかし、酒によって脳が麻痺した状態の方が重大事故に至る可能性が高いことに異論はなかろう。
科学的証明というものは、この世の全ての安全性を担保できるような万能なものではない。しかし、安全性を高めることには寄与できるとしても、損ねることにはならない。
科学が万能でないからといって、本能由来の観念の正当性を証明したことにはならないのである。
偶発的に本能的行動バイアスが上手く作用したことがあるとしても、常に本能的行動バイアスが上手く作用することの論証にはならないのだが。本能的行動バイアスによって上手く作用した経験程、あたかも既に自分の中に組み込まれた本能的な行動バイアスが特別に優位であるかのような錯覚を促すために、ヒトの多くは本能的行動バイアスを優先してしまうのである。
ギャンブルや投資で多額の損失を補えるという根拠のない錯覚も、このようにして暴走するのである。
将棋やレーシングカーの操縦などにおける無意識的能力の高さというものは、あくまで日々の鍛練習熟によって得られるものであり、決して先天的に組み込まれた能力などではない。
ところが、ヒトの多くは概ね上手く作用した結果だけに基づいて、自分の無意識的行動バイアスの全ては常に安全であると簡単に安心し、錯覚する傾向がある。
概ね上手く作用した結果の多数枚挙によって、あたかも絶対的に上手く作用すると錯覚するのである。
概ね自分にとって利己的に上手く作用した結果が多い場合、自分というものが予め先天的に意味を持つものであると錯覚するのである。
自分の行動選択が、概ね自分にとって有利に働いたことによって気分的に安心して無意識本能任せにしておくことが出来るようになるのである。
こうした無意識による「馴れ。」というものこそが、ドーパミンの持つ常習性によって作り出された行動学習の正体である。
多くの場合騙されたことがない者の場合、論理的根拠もなく「自分は絶対騙されることはない。」と勝手に思い込むことによって、自己存在が他人とは異なる特別なものであると錯覚し、「自分だけは大丈夫。」であると気分的に安心するのである。
東大の学長が論じたように、「全てを疑え。」というのが正しい判断を導く。だが、多くのヒトは今まで信じ込んできたものを疑い、検証することを怖れ。盲目的に信じ込み続けることの気分的安心「甘え。」を放棄することが困難である。
盲目的に多数や権威を信頼することに依存してきた者にとって、その依存を断ち切ることに対して精神的恐慌をきたすため、何が何でも多数や権威性への盲信を捨てることが出来なくなってしまうのである。
文系大衆観念的には、「甘え。」を断ち切るためには精神論的な努力辛抱根性によって、無理矢理我慢し、堪えることによって達成出来ると勝手に勘違いする。
精神論的な忍耐というものには、個人の許容量というものがあり。努力辛抱根性的な忍耐我慢によって全てがどうにかなるようなものではない。煙草の依存症治療同様に、無意識下に行動学習された条件反射的価値観というものを矯正するためには、地道で小さな努力の積み重ねによる「慣れ。」が肝要である。一朝一夕にどうにかなるようなものであると「思う。」ことこそ、短絡的な文系大衆観念というものである。
世間という多数他人や、それによって認証された権威に対する盲目的服従迎合というものは、長い期間に渡る刷り込み行動学習によって作り出されたものである。依存症というのは無意識下に安心快楽として刷り込まれてしまったものであり、急激に依存症を治すことは原理的にも不可能である。依存症の類というものは、ある程度の時間期間に渡る、地道な「慣れ。」によって矯正するべきものであって、短絡的に忍耐我慢によって治るようなものではない。
ドーパミンが持つ常習性による「慣れ(馴れ)。」というものは、その性質に無為無策に流されるのではなく。積極的に意識的目的のために利用する道具として扱うべきなのである。
社会性、或は社交性といったものを持たないことを。多くの大衆文系観念者達は人間性の欠如と勝手に錯覚する。しかし本能的な社会形成習性というものは「ヒト。」としての本能の程度問題に過ぎず、何ら社会安全性や持続可能性に影響を及ぼすものではない。むしろ社交性、或はコミュニケーション能力と称して多数権威に盲目的服従迎合をしてしまうことの方が人間性の欠落を招くことの方が圧倒的に多いことを、多くのヒトは認識したがらない。
文系の観念上では、社交的でない生物的コミュニケーション能力の低い者に対する観念的恐怖心によって、あたかも生物的コミュニケーション能力が低いことこそが人間性の欠落であるかのような錯覚を抱きがちである。しかし、この観念には論理的合理性は全く存在せず、単なる本能的恐怖心によるヒステリックな拒絶反応に過ぎない。
社交性がないことというのは、社交性に固執する者にとっては耐えがたい精神的に恐慌をきたすような地獄であると勝手に錯覚しがちであるが。社交性のない者にとっては社交性がないことは普通で自然なことであって、何ら精神的恐慌などきたすことはなく。むしろ精神的恐慌をきたすと勝手に錯覚していること自体が社交性に対する依存症の現れであり、勝手な主観的思い込みに過ぎない。
文系大衆観念上における「社会性。」というものは、単なる外見上の気分的安心感を論じているだけであり。何ら論理的人間性や安全性の論証にはなっておらず。本質的な「人間としての社会性。」の論証とは無関係な観念に過ぎない。
生物本能的な社会形成習性が希薄で観念的安心感をもたらさない者に対しての異常なまでの拒絶反応こそが、非人間的排除差別というものの根源である。そこに気付かず漫然と排除差別をし続けておいて「社会性。」もすったくれもあったものではない。
自分の価値観の、一体何が論理的根拠を持たない実証不能の文系大衆観念であるかすら自律的に検証できずに、人間とは何かを論ずる資格はない。それは単なる「ヒト。」という種の大型類人猿に過ぎないからである。
たとえどんなに学力学歴が高くても、年収が多くても、書いた本の販売部数が多くてもである。
Ende;