秋田が舞台の映像作品が、もうすぐいくつかテレビで放送される。
●サザエさんオープニング
フジテレビ系のアニメ「サザエさん」のオープニングで、秋田県の風景が描かれている。
4月から6月までが「春バージョン」で、7月から9月までは「夏バージョン」になるとのことだったので、次回7月6日放送から新しくなるはず。
どんな風景が描かれるか。続きはこちら。
●こころ旅
視聴者から寄せられた手紙にしたためられた「こころの風景」を火野正平が自転車で訪ねる、NHK BSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」。
現在は「2014年春の旅」として、3月31日から7月25日まで14週(本放送日基準・お休みの週は除く)かけて愛知県から日本海側ヘ出て北上し北海道へ至る行程を放送中。新潟県と北海道は2週かけて、新潟では佐渡ヶ島にも渡った。
今日6月30日から7月4日までは秋田県が、翌週7日から11日までは青森県が取り上げられる。(先週は休みで、秋田から北海道まで一気にラストスパート)
両県とも昨年10月以来で、秋田県は3度目、青森県は4度目の旅となるはず。
放送は、月曜は手紙の“ボツネタ”や火曜以降のさわりをダイジェストで紹介する「月曜朝版」。
本編は火曜から金曜で、朝に14分間の「朝版」、夜に29分の「とうちゃこ版」が放送される。(とうちゃこ版はその週の土日に再放送あり)
朝版は目的地前で終わってしまうし、とうちゃこ版でも最初から放送されるので、とうちゃこ版だけ見れば済むけれど、別編集なので朝版だけのシーンもあるらしい。
放送の前の週までにロケを済ませているので、正平さんたちは少なくとも秋田県の旅は終えていることになる。
正平さんが秋田県内のどこを訪れるのかは、放送を見るまで分からないものばかりと思っていたら、番組表(NHK公式やテレビの電子番組表など)では、市町村名が既に明らかになっていた。
それによれば、火曜から順に 由利本荘市、秋田市、三種町、小坂町 とのこと。
ちなみに2011年春の旅では、にかほ市、湯沢市、男鹿市、大館市、昨秋は八郎潟町、男鹿市、横手市、湯沢市が目的地だった。
秋田市が初めて目的地となるわけだが、こころ旅のパターンからして、どんな場所が選ばれたのか見当も付かない。
大森山や仁別のような山だったら坂で正平さんがはあはあ大変そう。あるいは海や川か、はたまた街中や郊外の何でもないような場所になるか…
【30日追記】月曜朝版では、高所恐怖症(特に橋を怖がる)の正平さんが、雄物川に架かる雄物新橋を怖がりながら新屋(栗田町)側から勝平側へ渡るシーンが放送された。7号線(南バイパス)方面から坂を下って左折して新橋に入ったようだ。
ということは、秋田市中央部~北部が目的地の可能性が高い。
どんな道中になるかも含めて、別記事にするつもりです。
●昔の角館
さらに、昔の角館の風景が7月12日に放送されるはず。
BSジャパンで土曜の夜に寅さん(男はつらいよ)シリーズを順に放送しているが、その38作、1987年8月公開の「男はつらいよ知床旅情【5日訂正】知床慕情」で、角館もロケ地の1つだったようだ。マドンナは竹下景子。
【7月12日追記】角館は冒頭(主題歌の前)のシーンの舞台だったようだ。
ほかに寅さんシリーズでは、1985年夏の35作「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾」で、平田満の実家という設定で、鹿角市が舞台になっていた。国鉄末期の陸中花輪駅(現・鹿角花輪駅)、鹿角の街中の「松風」という造酒屋、スキー場(夏なので雪はない)が映っていた。【7月6日追記】スキー場は「水晶山スキー場」とのこと。
寅さんで秋田でロケが行われたのは、おそらくこの2作だけのようだ。
26年に渡って48作品作られた映画にしては、あまり多くない気がする。ちなみに青森県も同じくらいだが、1971年正月の7作「男はつらいよ 奮闘編」では、弘前から鰺ヶ沢にかけての五能線や弘南バスが登場する。
数えたわけでなく感覚的には、寅さんが行く先は、北海道と九州など西日本が多いような気がする。
同じ山田洋次監督の「釣りバカ日誌」では、2004年の「釣りバカ日誌15 ハマちゃんに明日はない!?」で秋田県内各地が舞台になった。
以下はついでに、NHKの2つの連続ドラマの舞台。ドラマの舞台になった土地では観光客が増加するという。
●大河ドラマ
日曜夜の大河ドラマ。基本的に史実に基づく歴史ものだから、どうしても舞台に地域的な偏りは大きいと思われる。ロケをするにしても、必ずしもその現地で行うとは限らない。なお、ネット上には過去の舞台の一覧表のような資料は見当たらなかった。
秋田は、1993年の「炎立つ(ほむらたつ)」で後三年の役が描かれたので、それが該当。ロケが行われたかは不明。
青森は、弘前周辺が舞台の1986年の「いのち」。橋田壽賀子脚本、三田佳子主演。戦後が舞台で、歴史上の人物でない人が主人公という異色の大河ドラマだったが、人気はあったらしい。
ラグノオささきのお菓子「いのち」や、主人公の名前やドラマの内容からリンゴの品種「未希ライフ」が命名されるなど、青森では今にも影響を残している。
僕は青森が舞台なのは分かっていて何となく見た記憶はあるが、細かなストーリーや舞台は覚えていない。
●朝ドラ
NHKの朝の連続テレビ小説は、これまでにすべての都道府県が舞台になった。
完全なフィクションだから舞台は自由に設定できるし、昨年の「あまちゃん」の大ヒットもあって、誘致に乗り出す所もあるようだ。
先に青森を見ると、1971年(年度通して)の「繭子ひとり」。
原作は八戸出身の三浦哲郎(中学校の教科書にも載っていた「盆土産」の作者)、山口果林主演。宮城、広島、石川などとともに、八戸市と三戸町が舞台になったそうだ。
あとは、当時はけっこう話題になって、別枠で続編にもなった2000年度前半の「私の青空」。内館牧子作、田畑智子主演。
下北半島の大間町が舞台で、「大間のマグロ」が有名になったのもこのドラマが一役買っているか?
Wikipediaによれば青森はこの程度らしく、意外に少ない。津軽地方は一度も舞台になっていないことになる。
では秋田。
1976年度前半の「雲のじゅうたん」は角館町。田向正健作、浅茅陽子主演。
1981年度前半の「まんさくの花」が横手市。高橋正圀作、中村明美主演。
僕はどちらも記憶にないが、当時を知る人には「雲のじゅうたん」が今も強く印象付けられているようで、「まんさくの花」はそういえばあったっけ? 程度の人も少なくないようだ。
ちなみに、横手市増田町の日の丸醸造がドラマにちなんで「まんさくの花」という日本酒を製造している。
Wikipediaでは、以上2作品だけが秋田が舞台の朝ドラとされている。
昨年だったか、秋田県議会で、「『あまちゃん』のように朝ドラを秋田に誘致してはどうか」という質疑がされたようだ。
それを伝える新聞記事でも、「過去に秋田が舞台となったのは『雲の~』と『まんさく~』の2作のみ」といった記述があった。(議会中での直接の質疑応答ではなく、記者が調べたか、新聞社が県に問い合わせたかのような書き方だったはず)
ところが、少なくとももう1作、秋田が舞台になっていて、僕は覚えている。
※全編通しての舞台ではなく、部分的にロケが行われた形なので、そういう意味では上記2作とは異なるのかもしれない。
1992年度後半の「ひらり」である。
脚本は後に「私の青空」など多数のドラマを手掛ける、秋田市出身の内館牧子。その名が広く知られた初期の作品ではないだろうか。(内館さんは魁にエッセイを執筆するなど、今も秋田と縁が深い。上記の議会の「2作品のみ」の時、問題にならないかと気をもんだが、気付かれなかったのかスルーしてくれたのか)
主人公・藪沢ひらりを演じたのは石田ひかり。朝ドラの主演は、無名の新人が選ばれる時と、既に活躍中の若手が選ばれる時があるが、この時は後者。
主題歌は当時としては珍しく歌詞付きで、ドリームズ・カム・トゥルーの「晴れたらいいね」。ドリカム12枚目のシングルであり、代表曲の1つとしていいだろう。
舞台は(放送当時としての)現代で、内館さんらしく相撲がテーマ。
だから主要な舞台は両国なのだけど、その名も「寒風山(かんぷうざん)」という四股名の秋田出身の新人力士がいて、その関係でひらりたちが秋田を訪れるシーンがあって、秋田ロケが行われた。
Wikipediaによれば、寒風山はひらりのいとこの加賀谷久男という人物だそう。(秋田らしい姓だ)
秋田市の広小路のお堀沿いの歩道をひらりたちが歩き、それをお堀越し(中土橋から)に撮影したシーンがあり、後ろを市営バスが走っていたのを覚えている。男鹿の寒風山のシーンもあったか。
あと相撲部屋が「梅若部屋」だったのは、秋田民謡の大御所「浅野梅若」にちなんだものだろうか。
鍵本景子、渡辺いっけい、花沢徳衛、石倉三郎が出ていたのは覚えていて、いずれも僕はこのドラマで初めて知った。寒風山役は小林稔侍の長男・小林健。
他にも、両親役が伊武雅刀、伊東ゆかり、梅若部屋の親方が伊東四朗、語りは倍賞千恵子。さらに三遊亭楽太郎(現・圓楽)も出演していたようだが、ほとんど記憶にない。(当時は高校生で毎日見ていてわけではないけれど)
そう言えば、その時の新聞報道では、伊東四朗夫人が五城目出身だと書かれていた(たぶん)のを思い出した。ちなみに「私の青空」にも伊東四朗が出演している。
※「ひらり」は2022年から2023年にかけて再放送され、ほぼ全編を見ることができた。詳細はこの記事など。
最近は「フィルムコミッション」として各地でロケーションの誘致やお世話が行われているが、秋田県は角館以外ではどこかやっているだろうか。(大曲にもあるようだが、公式ホームページでは実績が2013年2月で止まっている)
秋田県が韓国ドラマのロケを誘致して、最初はそれなりに経済効果があったようだが、2度目は失敗した経験もある。考え方も好みも違う海外の人に日本の映像を見せて、そこに行こうと思わせるのは、相当難しいと思う。
秋田ならではの風景や雪景色など、国内向けにも魅力的な撮影地は少なくないはずだし、まずは国内向けの誘致をしたほうがいいのではないだろうか。
【2017年7月1日追記】2017年6月には、秋田県知事と秋田市長らが東京のNHKを訪れ、秋田が舞台のドラマを作るよう要望をした。秋田出身のモデルにできそうな人物のリストも渡したとか。
●サザエさんオープニング
フジテレビ系のアニメ「サザエさん」のオープニングで、秋田県の風景が描かれている。
4月から6月までが「春バージョン」で、7月から9月までは「夏バージョン」になるとのことだったので、次回7月6日放送から新しくなるはず。
どんな風景が描かれるか。続きはこちら。
●こころ旅
視聴者から寄せられた手紙にしたためられた「こころの風景」を火野正平が自転車で訪ねる、NHK BSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」。
現在は「2014年春の旅」として、3月31日から7月25日まで14週(本放送日基準・お休みの週は除く)かけて愛知県から日本海側ヘ出て北上し北海道へ至る行程を放送中。新潟県と北海道は2週かけて、新潟では佐渡ヶ島にも渡った。
今日6月30日から7月4日までは秋田県が、翌週7日から11日までは青森県が取り上げられる。(先週は休みで、秋田から北海道まで一気にラストスパート)
両県とも昨年10月以来で、秋田県は3度目、青森県は4度目の旅となるはず。
放送は、月曜は手紙の“ボツネタ”や火曜以降のさわりをダイジェストで紹介する「月曜朝版」。
本編は火曜から金曜で、朝に14分間の「朝版」、夜に29分の「とうちゃこ版」が放送される。(とうちゃこ版はその週の土日に再放送あり)
朝版は目的地前で終わってしまうし、とうちゃこ版でも最初から放送されるので、とうちゃこ版だけ見れば済むけれど、別編集なので朝版だけのシーンもあるらしい。
放送の前の週までにロケを済ませているので、正平さんたちは少なくとも秋田県の旅は終えていることになる。
正平さんが秋田県内のどこを訪れるのかは、放送を見るまで分からないものばかりと思っていたら、番組表(NHK公式やテレビの電子番組表など)では、市町村名が既に明らかになっていた。
それによれば、火曜から順に 由利本荘市、秋田市、三種町、小坂町 とのこと。
ちなみに2011年春の旅では、にかほ市、湯沢市、男鹿市、大館市、昨秋は八郎潟町、男鹿市、横手市、湯沢市が目的地だった。
ところで、当ブログのようなgooブログの無料版ではアクセス解析ができないのだが、ちょうど先週、無料版利用者でもおためし版としてアクセス解析を利用できた。(と言ってもしょぼい解析で、アクセス解析だけを目当てに有料版にするくらいなら、他のブログサービスに乗り換えたほうがいい)
それによれば、毎日のページ別閲覧数では、トップページに次いで昨秋のこころ旅の記事(上記リンク先)が見られていた(毎日50~100ページビュー)。それに、「こころ旅 本荘」といった検索キーワードでたどり着いたアクセスが若干あった。ロケ隊に遭遇した人が検索したのだろうか。
それによれば、毎日のページ別閲覧数では、トップページに次いで昨秋のこころ旅の記事(上記リンク先)が見られていた(毎日50~100ページビュー)。それに、「こころ旅 本荘」といった検索キーワードでたどり着いたアクセスが若干あった。ロケ隊に遭遇した人が検索したのだろうか。
秋田市が初めて目的地となるわけだが、こころ旅のパターンからして、どんな場所が選ばれたのか見当も付かない。
大森山や仁別のような山だったら坂で正平さんがはあはあ大変そう。あるいは海や川か、はたまた街中や郊外の何でもないような場所になるか…
【30日追記】月曜朝版では、高所恐怖症(特に橋を怖がる)の正平さんが、雄物川に架かる雄物新橋を怖がりながら新屋(栗田町)側から勝平側へ渡るシーンが放送された。7号線(南バイパス)方面から坂を下って左折して新橋に入ったようだ。
ということは、秋田市中央部~北部が目的地の可能性が高い。
どんな道中になるかも含めて、別記事にするつもりです。
●昔の角館
さらに、昔の角館の風景が7月12日に放送されるはず。
BSジャパンで土曜の夜に寅さん(男はつらいよ)シリーズを順に放送しているが、その38作、1987年8月公開の「男はつらいよ
【7月12日追記】角館は冒頭(主題歌の前)のシーンの舞台だったようだ。
ほかに寅さんシリーズでは、1985年夏の35作「男はつらいよ 寅次郎恋愛塾」で、平田満の実家という設定で、鹿角市が舞台になっていた。国鉄末期の陸中花輪駅(現・鹿角花輪駅)、鹿角の街中の「松風」という造酒屋、スキー場(夏なので雪はない)が映っていた。【7月6日追記】スキー場は「水晶山スキー場」とのこと。
寅さんで秋田でロケが行われたのは、おそらくこの2作だけのようだ。
26年に渡って48作品作られた映画にしては、あまり多くない気がする。ちなみに青森県も同じくらいだが、1971年正月の7作「男はつらいよ 奮闘編」では、弘前から鰺ヶ沢にかけての五能線や弘南バスが登場する。
数えたわけでなく感覚的には、寅さんが行く先は、北海道と九州など西日本が多いような気がする。
同じ山田洋次監督の「釣りバカ日誌」では、2004年の「釣りバカ日誌15 ハマちゃんに明日はない!?」で秋田県内各地が舞台になった。
以下はついでに、NHKの2つの連続ドラマの舞台。ドラマの舞台になった土地では観光客が増加するという。
●大河ドラマ
日曜夜の大河ドラマ。基本的に史実に基づく歴史ものだから、どうしても舞台に地域的な偏りは大きいと思われる。ロケをするにしても、必ずしもその現地で行うとは限らない。なお、ネット上には過去の舞台の一覧表のような資料は見当たらなかった。
秋田は、1993年の「炎立つ(ほむらたつ)」で後三年の役が描かれたので、それが該当。ロケが行われたかは不明。
青森は、弘前周辺が舞台の1986年の「いのち」。橋田壽賀子脚本、三田佳子主演。戦後が舞台で、歴史上の人物でない人が主人公という異色の大河ドラマだったが、人気はあったらしい。
ラグノオささきのお菓子「いのち」や、主人公の名前やドラマの内容からリンゴの品種「未希ライフ」が命名されるなど、青森では今にも影響を残している。
僕は青森が舞台なのは分かっていて何となく見た記憶はあるが、細かなストーリーや舞台は覚えていない。
●朝ドラ
NHKの朝の連続テレビ小説は、これまでにすべての都道府県が舞台になった。
完全なフィクションだから舞台は自由に設定できるし、昨年の「あまちゃん」の大ヒットもあって、誘致に乗り出す所もあるようだ。
先に青森を見ると、1971年(年度通して)の「繭子ひとり」。
原作は八戸出身の三浦哲郎(中学校の教科書にも載っていた「盆土産」の作者)、山口果林主演。宮城、広島、石川などとともに、八戸市と三戸町が舞台になったそうだ。
あとは、当時はけっこう話題になって、別枠で続編にもなった2000年度前半の「私の青空」。内館牧子作、田畑智子主演。
下北半島の大間町が舞台で、「大間のマグロ」が有名になったのもこのドラマが一役買っているか?
Wikipediaによれば青森はこの程度らしく、意外に少ない。津軽地方は一度も舞台になっていないことになる。
では秋田。
1976年度前半の「雲のじゅうたん」は角館町。田向正健作、浅茅陽子主演。
1981年度前半の「まんさくの花」が横手市。高橋正圀作、中村明美主演。
僕はどちらも記憶にないが、当時を知る人には「雲のじゅうたん」が今も強く印象付けられているようで、「まんさくの花」はそういえばあったっけ? 程度の人も少なくないようだ。
ちなみに、横手市増田町の日の丸醸造がドラマにちなんで「まんさくの花」という日本酒を製造している。
Wikipediaでは、以上2作品だけが秋田が舞台の朝ドラとされている。
昨年だったか、秋田県議会で、「『あまちゃん』のように朝ドラを秋田に誘致してはどうか」という質疑がされたようだ。
それを伝える新聞記事でも、「過去に秋田が舞台となったのは『雲の~』と『まんさく~』の2作のみ」といった記述があった。(議会中での直接の質疑応答ではなく、記者が調べたか、新聞社が県に問い合わせたかのような書き方だったはず)
ところが、少なくとももう1作、秋田が舞台になっていて、僕は覚えている。
※全編通しての舞台ではなく、部分的にロケが行われた形なので、そういう意味では上記2作とは異なるのかもしれない。
1992年度後半の「ひらり」である。
脚本は後に「私の青空」など多数のドラマを手掛ける、秋田市出身の内館牧子。その名が広く知られた初期の作品ではないだろうか。(内館さんは魁にエッセイを執筆するなど、今も秋田と縁が深い。上記の議会の「2作品のみ」の時、問題にならないかと気をもんだが、気付かれなかったのかスルーしてくれたのか)
主人公・藪沢ひらりを演じたのは石田ひかり。朝ドラの主演は、無名の新人が選ばれる時と、既に活躍中の若手が選ばれる時があるが、この時は後者。
主題歌は当時としては珍しく歌詞付きで、ドリームズ・カム・トゥルーの「晴れたらいいね」。ドリカム12枚目のシングルであり、代表曲の1つとしていいだろう。
舞台は(放送当時としての)現代で、内館さんらしく相撲がテーマ。
だから主要な舞台は両国なのだけど、その名も「寒風山(かんぷうざん)」という四股名の秋田出身の新人力士がいて、その関係でひらりたちが秋田を訪れるシーンがあって、秋田ロケが行われた。
Wikipediaによれば、寒風山はひらりのいとこの加賀谷久男という人物だそう。(秋田らしい姓だ)
秋田市の広小路のお堀沿いの歩道をひらりたちが歩き、それをお堀越し(中土橋から)に撮影したシーンがあり、後ろを市営バスが走っていたのを覚えている。男鹿の寒風山のシーンもあったか。
あと相撲部屋が「梅若部屋」だったのは、秋田民謡の大御所「浅野梅若」にちなんだものだろうか。
鍵本景子、渡辺いっけい、花沢徳衛、石倉三郎が出ていたのは覚えていて、いずれも僕はこのドラマで初めて知った。寒風山役は小林稔侍の長男・小林健。
他にも、両親役が伊武雅刀、伊東ゆかり、梅若部屋の親方が伊東四朗、語りは倍賞千恵子。さらに三遊亭楽太郎(現・圓楽)も出演していたようだが、ほとんど記憶にない。(当時は高校生で毎日見ていてわけではないけれど)
そう言えば、その時の新聞報道では、伊東四朗夫人が五城目出身だと書かれていた(たぶん)のを思い出した。ちなみに「私の青空」にも伊東四朗が出演している。
※「ひらり」は2022年から2023年にかけて再放送され、ほぼ全編を見ることができた。詳細はこの記事など。
最近は「フィルムコミッション」として各地でロケーションの誘致やお世話が行われているが、秋田県は角館以外ではどこかやっているだろうか。(大曲にもあるようだが、公式ホームページでは実績が2013年2月で止まっている)
秋田県が韓国ドラマのロケを誘致して、最初はそれなりに経済効果があったようだが、2度目は失敗した経験もある。考え方も好みも違う海外の人に日本の映像を見せて、そこに行こうと思わせるのは、相当難しいと思う。
秋田ならではの風景や雪景色など、国内向けにも魅力的な撮影地は少なくないはずだし、まずは国内向けの誘致をしたほうがいいのではないだろうか。
【2017年7月1日追記】2017年6月には、秋田県知事と秋田市長らが東京のNHKを訪れ、秋田が舞台のドラマを作るよう要望をした。秋田出身のモデルにできそうな人物のリストも渡したとか。










 (再掲)緑の色合いが他と微妙に違う気がする
(再掲)緑の色合いが他と微妙に違う気がする 行き先表示の方向幕には、「入道崎」「男鹿温泉」など男鹿ローカル路線のものが残っている
行き先表示の方向幕には、「入道崎」「男鹿温泉」など男鹿ローカル路線のものが残っている (再掲)いすゞガーラ10-51
(再掲)いすゞガーラ10-51 前にも後ろにも、でかい「H」エンブレムが輝く
前にも後ろにも、でかい「H」エンブレムが輝く (再掲)ロフトの看板の下がエレベーター
(再掲)ロフトの看板の下がエレベーター 市営バス最後の車両138号車の感熱紙式整理券。昔のトメさん当時は青と赤のインクだった
市営バス最後の車両138号車の感熱紙式整理券。昔のトメさん当時は青と赤のインクだった 2011年に撮影した「7305」のダイヤモンドカット側
2011年に撮影した「7305」のダイヤモンドカット側
 セブンプレミアム 北海道バニラ 1000ml 409円
セブンプレミアム 北海道バニラ 1000ml 409円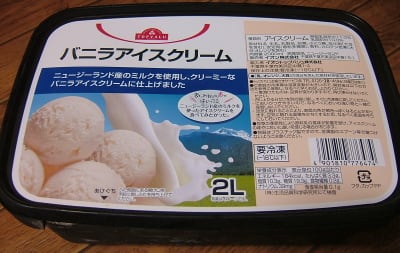 トップバリュ バニラアイスクリーム 2L 598円(1L 398円もあり)
トップバリュ バニラアイスクリーム 2L 598円(1L 398円もあり) 「アイスクリーム」
「アイスクリーム」
 グランルーフペデストリアンデッキからバスターミナルを見下ろす
グランルーフペデストリアンデッキからバスターミナルを見下ろす 八重洲南口バス乗り場
八重洲南口バス乗り場 さんさんぬまづ・東京号(どこにも「さんさんぬまづ」とは表示がない)
さんさんぬまづ・東京号(どこにも「さんさんぬまづ」とは表示がない) すっかり暗くなった
すっかり暗くなった 三島駅にて
三島駅にて (再掲)ニホンタンポポ。花の下の緑色の膨らんだ部分が総苞。セイヨウタンポポではここが反り返るなので、識別のポイントとなる
(再掲)ニホンタンポポ。花の下の緑色の膨らんだ部分が総苞。セイヨウタンポポではここが反り返るなので、識別のポイントとなる 「火災出動」だけ
「火災出動」だけ 「ベルが鳴り、消防車が出動しました。」つまり「ベル鳴動警戒事案」
「ベルが鳴り、消防車が出動しました。」つまり「ベル鳴動警戒事案」 帯広駅改札口
帯広駅改札口 札幌方面の発車標
札幌方面の発車標 い・ろ・は・す ハスカップ
い・ろ・は・す ハスカップ ジョージアミルクコーヒー/キリンガラナ
ジョージアミルクコーヒー/キリンガラナ トップバリュ ガラナ/FIRE北海道限定ミルクテイスト
トップバリュ ガラナ/FIRE北海道限定ミルクテイスト 北海道日高 ヨーグルッペ
北海道日高 ヨーグルッペ 月寒あんぱん
月寒あんぱん

 特製幕の内 北海道旅弁当 1000円
特製幕の内 北海道旅弁当 1000円 「北海道内各地の食材を存分に生かした献立を作り上げました。」
「北海道内各地の食材を存分に生かした献立を作り上げました。」 「地理院地図」より。左上が秋田駅、赤丸がそのため池
「地理院地図」より。左上が秋田駅、赤丸がそのため池 天気が悪いですが
天気が悪いですが 今はどうなっている?(ストリートビューで見ると、今も空き地は少なくないみたい)
今はどうなっている?(ストリートビューで見ると、今も空き地は少なくないみたい) 目的の池が見下ろせる
目的の池が見下ろせる 池のほとりに下りることはできない
池のほとりに下りることはできない 池が現れる
池が現れる 奥行きがある。東西方向は300メートルほどあると思われる
奥行きがある。東西方向は300メートルほどあると思われる 桜台から撮影
桜台から撮影 昭文社エアリアマップより
昭文社エアリアマップより 電柱広告(現在は桜四丁目になっている場所のはずだから、現存しないかもしれない)
電柱広告(現在は桜四丁目になっている場所のはずだから、現存しないかもしれない) 「きけん」です
「きけん」です キハ261系。正面のマークは「Super Tokachi」の「ST」
キハ261系。正面のマークは「Super Tokachi」の「ST」 これは指定席ですが
これは指定席ですが


 キハ283系によるスーパーとかち。キハ261より細身で正面がLED
キハ283系によるスーパーとかち。キハ261より細身で正面がLED 785系電車による「すずらん」
785系電車による「すずらん」 LEDは後にフルカラーに交換されている
LEDは後にフルカラーに交換されている 東室蘭から先は普通列車となって支線に入り、室蘭が終点
東室蘭から先は普通列車となって支線に入り、室蘭が終点 落ち着いた雰囲気
落ち着いた雰囲気 東室蘭駅東口。実際には“南南東口”といった位置
東室蘭駅東口。実際には“南南東口”といった位置 赤いのは「わたれーる」という東西自由通路(南南東-北北西自由通路?)
赤いのは「わたれーる」という東西自由通路(南南東-北北西自由通路?) キハ283系のデザインは、カメラを縦に構えたくなってしまうらしい
キハ283系のデザインは、カメラを縦に構えたくなってしまうらしい 夕暮れの大沼公園
夕暮れの大沼公園 キハ283系は側面のLEDが贅沢
キハ283系は側面のLEDが贅沢 正面のマークは「+」「メ」「*」で北斗七星
正面のマークは「+」「メ」「*」で北斗七星 上の建物は御隅櫓(復元)
上の建物は御隅櫓(復元) 4月末
4月末 千秋トンネルの上でもある
千秋トンネルの上でもある 山の上のほうにニセアカシアが広がっている
山の上のほうにニセアカシアが広がっている こちらも真っ白
こちらも真っ白 近くで見ると、それほど白くない
近くで見ると、それほど白くない ずいぶん高い木も
ずいぶん高い木も 大学の職員住宅「糠塚宿舎(旧称・糠塚官舎)」付近の丘
大学の職員住宅「糠塚宿舎(旧称・糠塚官舎)」付近の丘

 バス停のポールが曲がってるよ(次が終点なので、ここから乗る人はいない)
バス停のポールが曲がってるよ(次が終点なので、ここから乗る人はいない) 今が盛りのニセアカシア
今が盛りのニセアカシア 「秋田県に初めて誕生! はるやま秋田土崎店/秋田山手台店」
「秋田県に初めて誕生! はるやま秋田土崎店/秋田山手台店」




