JR貨物を発端に、鉄道各社の検査不正が明らかになっている。自動車業界などでもそうで、今まで明るみに出なかっただけなのかもしれない。
2024年9月19日には、315km/hで併結走行中の東北新幹線E5系「はやぶさ」とE6系「こまち」の連結が外れるという、前代未聞の事象が発生した。報道では「JR東日本では初めて」などと控えめだが、少なくとも新幹線では日本初だろう(連結して走る新幹線はJR東日本しかないし)。
日本の鉄道車両は、連結が外れると直ちに停車する仕組みになるのは知っていたが、JR東日本の連結する新幹線では、前方の編成(今回ははやぶさ)は弱く、後方の編成(同こまち)では強くブレーキが作動し、追突を避ける仕組み(※)になっているというのは、知らなかった。今回はそれが正常に作動して、300メートルの間隔をおいて停車でき、大事故には至らなかった。
※報道では「非常ブレーキ」などとひとくくりの表現だが、9月26日付のJR東日本のニュースリリースでは、前方編成は「非常ブレーキ動作」のみ、後方編成では「非常・緊急ブレーキ動作」としていて、かかるブレーキの種類が異なるようだ。
鉄道において、非常時には、最大(最強)のブレーキをかけるのが原則だと思っていたので、あえて弱くかけるというのも意表を突かれた。
新幹線と在来線では、緊急時のブレーキの種類も異なるようで、よく分からないが、前方編成には運転士が乗っているわけで、状況に応じてブレーキを調節(さらに強くかける)ことができるからかもしれない。そうだとしても素人目には、下り坂などで発生した時は、追突するケースがないとは言えないようにも、思えてしまう。
また、原因が分からないうちに、併結での運転を再開したのには、少々不安になった。
9月26日には調査結果が明らかにされた。E6系の製造段階で発生した金属片が連結器内に残っていて、それによって回路が短絡して、連結が解除されたため。E6系だけ、製造から約10年経って、なんてことがあるとは。
26日には、JR東日本本社で本件の記者会見が行われ、全国ニュースでも、秋田県のローカルニュースでも報道された。
NHK秋田放送局では、それに加えて、同日に行われた、JR東日本秋田支社長の定例記者会見での発言も伝えていた。おわび程度で、あまり内容はなかったけれど。その会見場の風景が本題。
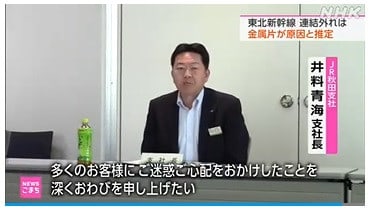 NHK NEWS WEB「東北新幹線 車両の連結部分外れは金属片が原因か」より
NHK NEWS WEB「東北新幹線 車両の連結部分外れは金属片が原因か」より
秋田駅そばの、秋田支社内が会場かと思われる。長机の中央に支社長が座り、やけに広い間隔をおいて両隣にも人がいる。
そして、映像で確認できる限り、支社長とその右隣の人には、同じペットボトルの緑茶が置かれている。
スポーツ選手なんかの記者会見では、スポンサー企業の商品がこれ見よがしに何本も置かれていることがあるけれど、企業の記者会見では置いていないことが多いような… 今回の本社の記者会見では(社長は出席せず)、何もなかった。しかし、過去のJR東日本の社長会見の写真を検索してみると、置く場合があったから、社長や支社長会見ではそういう通例になっているのでしょう。
今回は、ラベルの向きがテキトーなことから判断して、メーカーから提供されたものなどではなく、秋田支社が用意したであろう、その緑茶のブランドは、
 伊藤園「お~いお茶」600ml
伊藤園「お~いお茶」600ml
シェアは知らないが、日本のペットボトル入り緑茶の代名詞ではある。マイナーな安物を置いたりすれば、東日本旅客鉄道株式会社のメンツにも関わるかもしれないし(だったら湯呑み茶碗なり水差しなりを使えばいいということにもなるけれど)。
あと、600mlだと、机上で良くも悪くも目立つし、量が多すぎると思う。
もっとふさわしい商品があるではないか。
 (再掲)「日本の茶事」※2024年2月27日に「朝の茶事」からリニューアル
(再掲)「日本の茶事」※2024年2月27日に「朝の茶事」からリニューアル
JR東日本クロスステーションのオリジナル商品「acure」と伊藤園のダブルブランドで、基本的にJR東日本の駅周辺でしか購入できない緑茶「日本の茶事」があるのに。
さらに、同社のコンビニ・NewDaysには、「EKI na CAFE 緑茶」というのもある。こちらは低価格で、販売者は伊藤園。
さらにさらに、忘れてはいけないのがacureの「From AQUA 白神山地の天然水」。秋田県山本郡藤里町で採水され、同町の株式会社藤里開発公社が販売者。
ただし、「From AQUA 谷川連峰の天然水」とエリアを分けているらしいので、首都圏などでは売っていないかもしれない。また、秋田支社管内では、同じ採水地・販売者でFrom AQUAを名乗らない「白神山地の天然水」が売られていたことがあった。
秋田支社長の会見の場に、お~いお茶でなく、こうした商品を置けば、自社グループや地元(藤里町)の宣伝になり、売り上げ、企業イメージ、地域受けの向上につながるのに。しかも、秋田駅に行けばすぐに手に入る(支社内にも自販機があるのでは?)のに。むしろ、お~いお茶を、どういう経緯でどこで買ってきたのか気になる。
何より、上記、過去の本社社長の記者会見の場にあったのは、From AQUAの小さいボトル。しかも、ラベルが正面を向くように置かれていた。【30日補足・つまり本社では、飲み物以外の役割も持たせてボトルを置いているのに対し、秋田支社では「単なる飲み物」としてしか認識せずに置いていることになろう。】
「会見の席上に飲み物を出す」ことだけは本社から支社に通達されていて、「どんな飲み物をどんなふうに出す」かは伝わっていなかったのだろうか。だとしても、JR東日本の社員ならば、思いつかないものだろうか。もうちょっと愛社精神みたいなのがあってもいいのではないでしょうか。
【2025年1月28日追記・NHK秋田放送局の映像から、2025年1月23日の秋田支社の記者会見】
2024年9月と同じと思しき部屋と机で、支社の「モビリティ・サービスユニットリーダー」なる人と支社長が左右に並んで着席。モビリティ・サービスユニットリーダーの前にはノートパソコンはあるが、飲み物はなし。支社長の前には今回もお~いお茶が置かれていた。
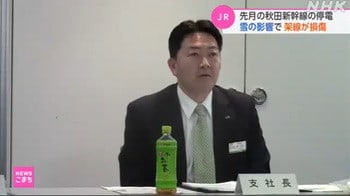 NHKでは前回より大映しになった。しかもラベル正面をこちらに向けて
NHKでは前回より大映しになった。しかもラベル正面をこちらに向けて
【2025年2月22日追記・東北本部長の記者会見】
2025年2月20日の東北本部長(旧・仙台支社長)の記者会見が、NHK秋田で放送された。机上に飲み物は置かれていなかった。
【2025年3月27日追記】
2025年3月26日にも、秋田支社長らが発言する場があった。NHKは報道しなかったが、秋田魁新報は写真なしで「26日の定例会見」と表記。秋田放送は映像があったが、記者会見とは表現しなかった(どういう場なのか伝えず)。会議机がコの字型に配置され、20人ほどが着席。そのほぼ全席に、相変わらずお~いお茶。
2024年9月19日には、315km/hで併結走行中の東北新幹線E5系「はやぶさ」とE6系「こまち」の連結が外れるという、前代未聞の事象が発生した。報道では「JR東日本では初めて」などと控えめだが、少なくとも新幹線では日本初だろう(連結して走る新幹線はJR東日本しかないし)。
日本の鉄道車両は、連結が外れると直ちに停車する仕組みになるのは知っていたが、JR東日本の連結する新幹線では、前方の編成(今回ははやぶさ)は弱く、後方の編成(同こまち)では強くブレーキが作動し、追突を避ける仕組み(※)になっているというのは、知らなかった。今回はそれが正常に作動して、300メートルの間隔をおいて停車でき、大事故には至らなかった。
※報道では「非常ブレーキ」などとひとくくりの表現だが、9月26日付のJR東日本のニュースリリースでは、前方編成は「非常ブレーキ動作」のみ、後方編成では「非常・緊急ブレーキ動作」としていて、かかるブレーキの種類が異なるようだ。
鉄道において、非常時には、最大(最強)のブレーキをかけるのが原則だと思っていたので、あえて弱くかけるというのも意表を突かれた。
新幹線と在来線では、緊急時のブレーキの種類も異なるようで、よく分からないが、前方編成には運転士が乗っているわけで、状況に応じてブレーキを調節(さらに強くかける)ことができるからかもしれない。そうだとしても素人目には、下り坂などで発生した時は、追突するケースがないとは言えないようにも、思えてしまう。
また、原因が分からないうちに、併結での運転を再開したのには、少々不安になった。
9月26日には調査結果が明らかにされた。E6系の製造段階で発生した金属片が連結器内に残っていて、それによって回路が短絡して、連結が解除されたため。E6系だけ、製造から約10年経って、なんてことがあるとは。
26日には、JR東日本本社で本件の記者会見が行われ、全国ニュースでも、秋田県のローカルニュースでも報道された。
NHK秋田放送局では、それに加えて、同日に行われた、JR東日本秋田支社長の定例記者会見での発言も伝えていた。おわび程度で、あまり内容はなかったけれど。その会見場の風景が本題。
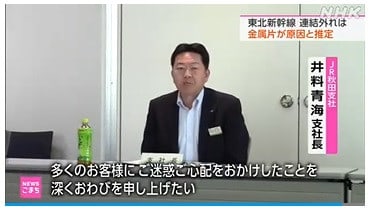 NHK NEWS WEB「東北新幹線 車両の連結部分外れは金属片が原因か」より
NHK NEWS WEB「東北新幹線 車両の連結部分外れは金属片が原因か」より秋田駅そばの、秋田支社内が会場かと思われる。長机の中央に支社長が座り、やけに広い間隔をおいて両隣にも人がいる。
そして、映像で確認できる限り、支社長とその右隣の人には、同じペットボトルの緑茶が置かれている。
スポーツ選手なんかの記者会見では、スポンサー企業の商品がこれ見よがしに何本も置かれていることがあるけれど、企業の記者会見では置いていないことが多いような… 今回の本社の記者会見では(社長は出席せず)、何もなかった。しかし、過去のJR東日本の社長会見の写真を検索してみると、置く場合があったから、社長や支社長会見ではそういう通例になっているのでしょう。
今回は、ラベルの向きがテキトーなことから判断して、メーカーから提供されたものなどではなく、秋田支社が用意したであろう、その緑茶のブランドは、
 伊藤園「お~いお茶」600ml
伊藤園「お~いお茶」600mlシェアは知らないが、日本のペットボトル入り緑茶の代名詞ではある。マイナーな安物を置いたりすれば、東日本旅客鉄道株式会社のメンツにも関わるかもしれないし(だったら湯呑み茶碗なり水差しなりを使えばいいということにもなるけれど)。
あと、600mlだと、机上で良くも悪くも目立つし、量が多すぎると思う。
もっとふさわしい商品があるではないか。
 (再掲)「日本の茶事」※2024年2月27日に「朝の茶事」からリニューアル
(再掲)「日本の茶事」※2024年2月27日に「朝の茶事」からリニューアルJR東日本クロスステーションのオリジナル商品「acure」と伊藤園のダブルブランドで、基本的にJR東日本の駅周辺でしか購入できない緑茶「日本の茶事」があるのに。
さらに、同社のコンビニ・NewDaysには、「EKI na CAFE 緑茶」というのもある。こちらは低価格で、販売者は伊藤園。
さらにさらに、忘れてはいけないのがacureの「From AQUA 白神山地の天然水」。秋田県山本郡藤里町で採水され、同町の株式会社藤里開発公社が販売者。
ただし、「From AQUA 谷川連峰の天然水」とエリアを分けているらしいので、首都圏などでは売っていないかもしれない。また、秋田支社管内では、同じ採水地・販売者でFrom AQUAを名乗らない「白神山地の天然水」が売られていたことがあった。
秋田支社長の会見の場に、お~いお茶でなく、こうした商品を置けば、自社グループや地元(藤里町)の宣伝になり、売り上げ、企業イメージ、地域受けの向上につながるのに。しかも、秋田駅に行けばすぐに手に入る(支社内にも自販機があるのでは?)のに。むしろ、お~いお茶を、どういう経緯でどこで買ってきたのか気になる。
何より、上記、過去の本社社長の記者会見の場にあったのは、From AQUAの小さいボトル。しかも、ラベルが正面を向くように置かれていた。【30日補足・つまり本社では、飲み物以外の役割も持たせてボトルを置いているのに対し、秋田支社では「単なる飲み物」としてしか認識せずに置いていることになろう。】
「会見の席上に飲み物を出す」ことだけは本社から支社に通達されていて、「どんな飲み物をどんなふうに出す」かは伝わっていなかったのだろうか。だとしても、JR東日本の社員ならば、思いつかないものだろうか。もうちょっと愛社精神みたいなのがあってもいいのではないでしょうか。
【2025年1月28日追記・NHK秋田放送局の映像から、2025年1月23日の秋田支社の記者会見】
2024年9月と同じと思しき部屋と机で、支社の「モビリティ・サービスユニットリーダー」なる人と支社長が左右に並んで着席。モビリティ・サービスユニットリーダーの前にはノートパソコンはあるが、飲み物はなし。支社長の前には今回もお~いお茶が置かれていた。
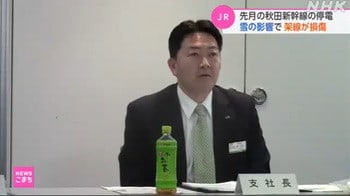 NHKでは前回より大映しになった。しかもラベル正面をこちらに向けて
NHKでは前回より大映しになった。しかもラベル正面をこちらに向けて【2025年2月22日追記・東北本部長の記者会見】
2025年2月20日の東北本部長(旧・仙台支社長)の記者会見が、NHK秋田で放送された。机上に飲み物は置かれていなかった。
【2025年3月27日追記】
2025年3月26日にも、秋田支社長らが発言する場があった。NHKは報道しなかったが、秋田魁新報は写真なしで「26日の定例会見」と表記。秋田放送は映像があったが、記者会見とは表現しなかった(どういう場なのか伝えず)。会議机がコの字型に配置され、20人ほどが着席。そのほぼ全席に、相変わらずお~いお茶。










 追分→大久保 下り列車後部から(潟上市昭和大久保付近)
追分→大久保 下り列車後部から(潟上市昭和大久保付近) 羽後飯塚付近
羽後飯塚付近 奥は男鹿半島
奥は男鹿半島 この車両のせい
この車両のせい GV-E400-18 秋田側(奥羽本線下り後部)
GV-E400-18 秋田側(奥羽本線下り後部)
 ◆運転情報◆
◆運転情報◆ (再掲)ほぼ同一の保戸野千代田町街区公園
(再掲)ほぼ同一の保戸野千代田町街区公園 昔ながらの蛇口ではあるのだけど
昔ながらの蛇口ではあるのだけど 何か違う?
何か違う? ここが違う
ここが違う
 保戸野八丁街区公園の水飲み側は青。構造上、凍結防止にできないのか
保戸野八丁街区公園の水飲み側は青。構造上、凍結防止にできないのか たけや お月見うさぎ 半額で税込み106円
たけや お月見うさぎ 半額で税込み106円 手で丸めているのか、いびつな形
手で丸めているのか、いびつな形 食べ応えあり
食べ応えあり 持ち帰る途中で盛大にひっくり返ってしまいました【18日追記・でも崩壊はせずタフ】
持ち帰る途中で盛大にひっくり返ってしまいました【18日追記・でも崩壊はせずタフ】
 (再掲)2019年版
(再掲)2019年版 泉上の町街区公園
泉上の町街区公園 泉銀の町街区公園
泉銀の町街区公園
 2010年度施工 保戸野街区公園(保戸野八丁。戦前の政治家・町田忠治生誕地跡、元市長公舎隣)
2010年度施工 保戸野街区公園(保戸野八丁。戦前の政治家・町田忠治生誕地跡、元市長公舎隣) 2018年度施工 保戸野八丁街区公園(
2018年度施工 保戸野八丁街区公園( 見たことないタイプ
見たことないタイプ 南から
南から 北から
北から 前者の横断歩道
前者の横断歩道 後者の横断歩道
後者の横断歩道
 左手前角が交番、右折で泉外旭川駅
左手前角が交番、右折で泉外旭川駅
 仮囲いが設置されていた
仮囲いが設置されていた
 北・泉いちょう通り側から、交差点方向
北・泉いちょう通り側から、交差点方向 囲いのすき間から、店舗玄関
囲いのすき間から、店舗玄関



