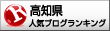会員の丸井一郎です。
会員の丸井一郎です。食べる日々(8)
前回から、欧州(事例は主として中欧)の
基本的な飲食生態を具体的に紹介している。
その導入として、
飲食生態の非均質性(階層性)、及び制度によって
保証され管理される保存食の優勢
という二つの要因を揚げ、
まずは飲食への制度の関わりと
保存食の優勢をパンを例にして紹介した。
自治都市(自由都市や帝国都市とも言う)のギルドで
上席に位置する製パン業者が
責任と独占権をもって市民の糧を供給する。
分かち合うべきパン一つの重量は5Kgにもなる。
今回は歴史的背景をも含めて、もう少し詳細に、
「生きる糧」である基本食品の特徴を見ていく。
実はパンを(貴族・僧侶など特権階層は別として)
自由都市民以外の庶民・農民が
常食するようになるのは
18~19世紀頃からで、
それ以前は粗挽きの粉を使った
膨らまない「おやき」のような物、
または獣脂(主に豚)で炒りつけた
粗挽きの穀物(大麦など)に
水を注いで煮立てる粥が日常的だった。
教会税・年貢などの取り立て、
製粉設備(水車、風車、馬力の挽き臼など)やパン焼き窯を
領主・自治都市が独占していたことなどが背景にある。
麦を粉にするのはタダでない、
窯を使うのもタダでない。
村々に自前の共同パン焼き釜が普及するのは、
近代化(植民地獲得)の歴史と平行する。
飲食の階層による差異が重要な要因となる。
簡単に言うと、
社会的な階層(階級、身分など)によって、
当事者達には「当たり前」の飲食物、飲食行動が互いに相違する。
現代では通用しない歴史的な固定観念には、
パンの序列があって、フランスの場合、
小麦だけの白いパンが最上位で、
混入するフスマの色が濃くなるほど地位が下がった。
小麦ではなくライ麦など他の麦類、
さらには豆やクルミなど麦以外の材料の混入物の順に評価が下がる。
以下同文で、何を日常的に食べるかが、
何者であるかに対応することになる。
で、「何を食べるか言ってみろ、あんたが誰だか言ってやろう」という
ブリヤ・サバラン(18~19世紀の食味研究者)の言葉の背景が分かる。
ちなみに、クルミやどんぐり類の混入が嫌われたのは、
豚の餌とするからだとされる。
夏の間森に放した豚は木の実や小動物を食べて、
おいしくなって帰ってくる(これは後でまた)。
中欧では環境条件からライ麦の利用も一般的であるが、
白いパンへの評価はもちろん高かった。
「田舎パン」 15~20 Kg フランス・オーヴェルニュ
サン・ネクテールの市場で

Helmut Reichelt撮影 (2023.5.27)
https://www.flickr.com/photos/24973309@N04/52965513467/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/24973309@N04/52965513467/in/photostream/
※ この記事は、NPO法人土といのち『土といのち通信』2024年6月号より転載しました。