

<大銀杏、霜月の空を飾る>
けやき通りの入り口にある大銀杏 今がさかり。
交差点の端っこに生えている樹は雄木なのかついぞ
実がなっているのを見たことがない。
ご承知の通り銀杏は雌雄両木がないと実を結ばない
銀杏通りまで行けば実のなっている樹は沢山あるが
ここの樹はひとりぼっち。
それでも枝を目一杯広げて存在感がある。


<大銀杏、霜月の空を飾る>
けやき通りの入り口にある大銀杏 今がさかり。
交差点の端っこに生えている樹は雄木なのかついぞ
実がなっているのを見たことがない。
ご承知の通り銀杏は雌雄両木がないと実を結ばない
銀杏通りまで行けば実のなっている樹は沢山あるが
ここの樹はひとりぼっち。
それでも枝を目一杯広げて存在感がある。



<つくばね空木>
冬の装いになったつくばね空木 種になっても絵に
なるたたずまい 名前のもとになった「はねつき」
の尾羽根のような種 ピンクの色もいい。
別名 アベリア

<秋明菊>
秋明菊は正しくは「菊」ではない キンポウゲ科
イチリンソウ属である。見てくれが菊によく似ている
のでそう呼ばれている。別名 貴船菊、加賀菊とも
呼ばれ、京都貴船地方で良く栽培されていることから
貴船菊の方が通りが良い。 花姿はいかにも優し気で
見た者の心をなごませる花である。



<柿の紅葉>
柿の紅葉が今年はひときわ赤く美しい。
柿の実も熟して落柿まではゆかないとしても真っ赤に
熟れ見事なものだ その赤い実が目立たない程の紅葉
なのである。もみじの赤も素晴らしいけれどおおきな
葉がかなりの迫力で頭上にせまってくるのは圧巻で
ある。

 木星
木星
<十三夜月と木星>
25日は十三夜月 満月の二日前の月である。
厳しい寒さを迎えた空はところどころ雲が有るものの
きれいに澄み渡っている。そして木星と月が接近する
夜でもある。 18:00すぎほぼ中天近くの月の右下に
光る星を見つけた 木星である。肉眼でみると両者の
間はかなり近くに見える。


<けやき紅葉>
今年も近くのけやき並木が紅葉している。約1km程
のこのけやき並木は枚方八景になっているほど有名で
行き交う人の目を楽しませている。車の通行もさほど
でもなく、排気ガスに侵されないので鮮やかな紅葉を
見せてくれているのではないかと思う。


< 野紺菊 2 >
野紺菊も峠を越えた 微妙な花びらのグラデーション
が薄紫の色に変わって来ている。 昨日今日の温かい
気温でなく真冬の寒さになるんだそうな 冬の苦手な
私には辛抱我慢の4カ月が始まる。

< 紫苑 >
22日は快晴 文字通り雲一つない深い青空が広がって
とても気持ちがいい。特養の庭の花壇の紫苑も見上る
ほどに育っていっぱい花をつけている その花の色が
青空に溶けいるようだ。


<上弦の月/月面X>
11/20は上弦の月 いわゆる半月である 地球から見て
太陽と月が九十度に位置した時で日没時月は頂天になり
半分に見える。
この上弦の月の時月面Xが観測できる クレーターの縁と
山脈が重なり合って偶然この形になったものでXの字型
が有名である。



<南京ハゼ>
南京ハゼの紅葉 例年のごとく見事なものだ。
しかし、例年と若干ちがういつもなら全ての南京ハゼ
は真っ赤に燃えているはず 今年は少しおくれている
まばらに緑色が散見される。
このまま散らないで欲しい 短い秋はほんとに駆け足
だった。


<花水木紅葉>
昨日は厳しい寒さだった。何でも12月中頃の冷え込み
だったそうな ウォーク途中にある特養の庭の花水木
もいい色合いに紅葉してきた。赤く色づいた葉っぱの
間につやつやとした実がちょこんと見え隠れしている
しかし、小鳥には口に合わないのかついばんでいる姿
は見かけない。
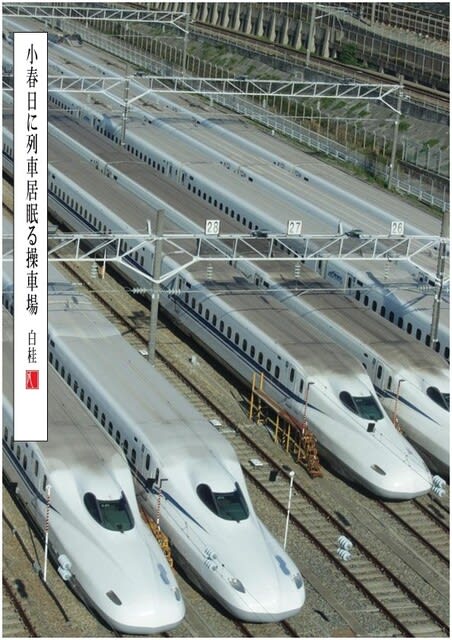
<新幹線>
我が家から万博記念公園までは京阪香里園から門真市
まで京阪電車、そして門真市から万博記念公園までは
モノレールに乗る。ちなみに門真市駅はナショナルの
正門前。そこから約20分で着く 高架になったモノ
レールに乗るのが大好きだ。 第一、見晴らしが良い
途中の摂津駅手前で新幹線の摂津操車場の上をとおる
ドアにへばりついて新幹線の列車群をカメラに収める。


<えのころ草>
えのころ草も実りの時 小さな粟のような穂が重たげに
揺れる。 これから周りが枯れてくるとスズメやハトの
貴重なえさになる なんといっても道端に溢れるほどに
実がみのっているのだから。そして実がなくなった穂先
が寒風にさらされているのも、これはこれで又いい。

<いたどり>
春の代表的な山野草「いたどり」は筍状の若芽が有名
であるが、晩秋から初冬にかけて粟つぶのような花を
咲かす。 花は小さくても群れて多量に咲くので遠く
からでも目立つ 結ぶ実は小判型をした薄っぺらい
ものでそのまま立ち枯れをしてしまう。

<三日月>
11月15日は三日月である。新月より三日目の月のことで
文字通り「みっかつき」イメージ的には三日月はもう少
し太った月を想像するが正しくはそうではない。
あまりに細いので17:30の月の入りまで30分ほどの観測
時間しかなく日没後の夕空で確認できたのは15分ほど。