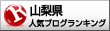市川三郷町内には道祖神がたくさんあります。
何回かに分けて、それらをご紹介します。
道祖神というのは、いわゆる道ばたの神様で、古くは村々のあちらこちらに建てられ、外からの厄災が入ってくるのを防ぐと信じられていました。
今では子孫繁盛や交通安全の神様としても信仰されています。
道祖神の形はいろいろあるようですが、町内にある道祖神の多くは双体道祖神といって、一対の男女の形をしているもので、今回ご紹介するものはすべて双体道祖神です。
まずは、「落合の道祖神」。
このあたりは昔、芦川と笛吹川、鳴沢川が合流したことから起きた地名で、正式には「おちあい」と呼ぶのでしょうが、町民は「おちゃあ」と呼んでいます。
落合の道祖神は、地蔵尊のかたわらにひっそりと祀られています。

落合の地蔵尊・道祖神のある場所は、本通りと新道と呼ばれる南線通りの間の古い細い道です。
町の整備事業で整備されたため、ご覧のような真新しい石碑が立てられています。

次は、同じ道を少し上ったところにある「春日町の道祖神」。
やはり単独ではなく秋葉様(防火の神様ですね)の社(やしろ)の隣に祀られています。

表面がほとんど擦り切れてしまったような道祖神で、作られた年代はわかっていません。
道祖神と秋葉社は、今でこそ同じ場所にありますが、ずうっと以前は別々の場所に祀られていたのかもしれません。

最後は、「出口の道祖神」と呼ばれる五丁目にある道祖神。
本通りの北側、通称「中北の通り」と呼ばれる道の十字路にあります。

「出口の道祖神」は、文化五年(1808年)に作られたことがわかっているそうです[※]。
14日は小正月。
道祖神の前には、繭玉が飾られていました。

※「甲州・市川のまちづくり読本」より
何回かに分けて、それらをご紹介します。
道祖神というのは、いわゆる道ばたの神様で、古くは村々のあちらこちらに建てられ、外からの厄災が入ってくるのを防ぐと信じられていました。
今では子孫繁盛や交通安全の神様としても信仰されています。
道祖神の形はいろいろあるようですが、町内にある道祖神の多くは双体道祖神といって、一対の男女の形をしているもので、今回ご紹介するものはすべて双体道祖神です。
まずは、「落合の道祖神」。
このあたりは昔、芦川と笛吹川、鳴沢川が合流したことから起きた地名で、正式には「おちあい」と呼ぶのでしょうが、町民は「おちゃあ」と呼んでいます。
落合の道祖神は、地蔵尊のかたわらにひっそりと祀られています。

落合の地蔵尊・道祖神のある場所は、本通りと新道と呼ばれる南線通りの間の古い細い道です。
町の整備事業で整備されたため、ご覧のような真新しい石碑が立てられています。

次は、同じ道を少し上ったところにある「春日町の道祖神」。
やはり単独ではなく秋葉様(防火の神様ですね)の社(やしろ)の隣に祀られています。

表面がほとんど擦り切れてしまったような道祖神で、作られた年代はわかっていません。
道祖神と秋葉社は、今でこそ同じ場所にありますが、ずうっと以前は別々の場所に祀られていたのかもしれません。

最後は、「出口の道祖神」と呼ばれる五丁目にある道祖神。
本通りの北側、通称「中北の通り」と呼ばれる道の十字路にあります。

「出口の道祖神」は、文化五年(1808年)に作られたことがわかっているそうです[※]。
14日は小正月。
道祖神の前には、繭玉が飾られていました。

※「甲州・市川のまちづくり読本」より