時は6月半ば。ダンナが「今度麻溝で
SC相模原VSカマタマーレ讃岐の試合があるんだよね~」と。
え?「かまたま~れ?」それってもしや
釜たまっ!さぬきうどんの定番メニューの釜揚げ玉子うどんの事??と。
まさかな~?と思ったんだけど、本当にカマタマーレの由来は釜タマうどんから命名されてました。
私等夫婦は香川県出身、相模原市在住なのです。そりゃあもう行くしかあるまい~~。
まずはチケット入手です。
ええ。そっから~。
私、サッカーのテレビ観戦はした事あっても、スタジアムへは…。
あ。
あったな…。
2002年FIFAワールドカップの時、朝日新聞のチケットが当たって、横浜スタジアムへ行ったんだった。それ以来のサッカー観戦。もちろんチケットの売り場も知らない。
なもので、まずはWEBサイト検索。したらば、相模大野の不動産屋で前売り券を取り扱ってたのでゲットしました。
SC相模原のホーム、麻溝公園競技場のチケットは、A席(メインスタンド)…当日券1500円を前売り券1200円) B席(バックスタンド)…当日券1000円を前売り券700円と大変お得です。
ちなみに、B席を購入しました。
ってな事で、
2013年6月23日(日曜)13:00キックオフに合わせ、我が家を12時に出発しました。
ええ。今回は水道みちをウォーキングで目的地の相模原麻溝公園競技場を目指します。
ところがところがっ!!
楽勝のハズが、スタジアムに到着したら、スタジアムの外でキックオフの笛の音が聞こえてしまった~~。
や。到着前までは、SC相模原とカマタマーレ讃岐のどっちを応援するか悩んでいたのに、スタジアムに入ってみれば、B席のSC相模原は大にぎわいだったのです。こりゃいかん!と。そこそこ空いてる席は…。
空いてる席=カマタマーレサポーターの後ろの席でした。
何気にハードルが高い場所です。だ・大丈夫かしら?私、カマタマーレの選手の名前の一人も知らないのに…。
ともかく、ゲームに集中です。
カマタマーレは、前半から積極的にゴールを目指します。
でも、見ててすぐわかった!
カマタマーレの弱点は決定力のあるFWがいない。ボールをゴールへ押し込む力ある選手がいないんです。
ではSC相模原は…。
なんともまとまりのないチーム。チームワークが機能してないっ。それでもゴールを目指してるのですが、カマタマーレの守備はピカいちです。守備が堅い堅いっ。
そんなこんなで前半0-0のまま終了です。
あとね。カマタマーレのサポーターのすぐ後ろの席に座ったのは大正解でしたっ!
ノリのいいリズム&気持ちよくしかも昂揚する応援歌の数々っ。太鼓のリズム。サポーターの男性の声で『闘え~男達~』と。こう…うわっ!!私も踊りてぇ~~っ!!と。いつの間にやらサポーターに合わせてカマタマーレを応援してました。
さて、ハーフタイムを使い、バックスタンドを右往左往してみる。

バックスタンドは、メインスタンドと違い屋根がありません。6月下旬に炎天下の午後の観戦ってどうなの??と心配もしていたのですが、当日は梅雨空。雨が落ちてこないのが不思議な程。ともあれ、日焼けの恐怖からは開放されました。まあ、日焼け止めクリームはバッチリ塗っているけどね。

B席です。ダンナは前日に「どうせ客なんか1000人もいないんだから、席は空き放題だよっ」と言ってましたが、実際B席は観客が多かった!後半に発表になった観客数は、
2581人でした。ダンナの予想よりは大分多かったね。つーか、ほとんど安いB席の客ですねっ。


さてカマタマーレのサポーターの着てるカマタマーレ讃岐のユニホームに貼付けてあるスポンサー名が気になります。
どうも年によりスポンサーが変わってるのか、サポーターのユニホームについてるスポンサー名が色々です。
視認出来た所によると…。
穴吹工務店・Ks"デンキ・うどん県
ん?
うどん県ってソレ、香川県のPR名だよね?PR名がスポンサー????
なんて謎な香川県…。
悩んでるうちに後半が始まってしまった~~。
後半はコートの左右チェンジです。カマタマーレが狙うゴールが近くなりました。これでカマタマーレが攻めまくってくれれば…。
カマタマーレの監督は選手起用がアグレッシブ!
交代をどんどん進めていきます。噂では、カマタマーレの選手達は前半から100%で戦い、後半エネルギー切れをしてしまうチームだとか。後半にエネルギー切れを起こすのを選手交代で補うという戦法かな?
んじゃあ、SC相模原の監督はどうするのかな?
あれ??
SC相模原は動かない…。
いいのか、それで??
つーか、カマタマーレはゴールを目指して頑張るので、コートはほぼ右半分で展開してます。そんなこんなでSC相模原の守備に負担がかかったのか、イエローカード2枚退場となる選手が。
その直後、カマタマーレの野口選手が遂にゴールっ!!

もう0-0で分けるのか??って程ゴールが遠かったから、ゴールの瞬間大喜びしちゃったわ~。よかった!カマタマーレサポーターのすぐ後ろの席で。悪め建ちは免れたっ。
カマタマーレは1点を守りそのまま試合終了。

選手がサポーターの前に来て手を振ってくれました。や。手を叩いてたらシャッターチャンス外してしまった。
ちなみにこの試合は
JFL前半戦最終節。
試合前の順位表はカマタマーレ讃岐は全18チーム中首位。SC相模原は第五位という成績。
なにげに応援しがいのある試合だったわ~。後半戦もサッカー観戦したいな。最終節のゼルビア町田戦、まだ試合会場決まってないんだよね。もしこれが麻溝競技場で闘うなら観戦したい。でなければ、長野バルセイロ戦~~。それまでにSC相模原が上位で踏ん張ってたらまたチケットを買おうっ!
カマタマーレの試合は…。もしかしたら、来年はカマタマーレはJ2に上がってるかもしれん…。
さて。試合前は脇目もふらずスタジアムに駆け込んだので、売店とか全くチェック出来ませんでした。
何があるのかしら??

ハッ!!こ・これはっ!!
 はやぶさ2「星の王子様に会いに行きませんか?」関連キャンペーン
はやぶさ2「星の王子様に会いに行きませんか?」関連キャンペーンですねっ。
私、既にミリオンキャンペーンに登録済みですっ。小惑星1999JU3に打ち込むターゲットマーカーに自分の名前を登録済みです。うっ。今年はJAXA相模原の特別公開へ行けませんでした~。夏コミ合わせの原稿締切と、公開日程がかぶってしまったのが敗因です。
他に朝日新聞の


こんなんありましたっ。
でもここの背景になってる選手、試合に殆ど出てなかったんだよね~。

スタジアムの壁です。市の花アジサイが咲いてました。ちと見頃過ぎてますね。
さて帰る前に、
相模原公園の花菖蒲の咲き具合を確認します。

既に今シーズンは見頃を過ぎてますね。
麻溝公園では。

ラベンダーが咲いてます。でも、ミツバチどこへ行った??なんか、ごっついハチが幅効かせてます。

麻溝公園は、アジサイが有名。

上の画像の道が水道みち。
帰り道は、行きとは別の散歩みちで我が家へ戻ります。

道なりにアジサイを観賞しつつ帰宅です。
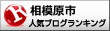 神奈川県相模原市 ブログランキングへ
神奈川県相模原市 ブログランキングへ







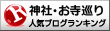 神社・お寺巡り ブログランキングへ
神社・お寺巡り ブログランキングへ
























 市立崇善公民館です。
市立崇善公民館です。




















 こんなんありましたっ。
こんなんありましたっ。 スタジアムの壁です。市の花アジサイが咲いてました。ちと見頃過ぎてますね。
スタジアムの壁です。市の花アジサイが咲いてました。ちと見頃過ぎてますね。
 ラベンダーが咲いてます。でも、ミツバチどこへ行った??なんか、ごっついハチが幅効かせてます。
ラベンダーが咲いてます。でも、ミツバチどこへ行った??なんか、ごっついハチが幅効かせてます。 麻溝公園は、アジサイが有名。
麻溝公園は、アジサイが有名。







 十三仏像
十三仏像 参道のアジサイ。奥に見えているのが本堂。
参道のアジサイ。奥に見えているのが本堂。 本堂脇に、北条のミツウロコの灯籠発見。って事は…。
本堂脇に、北条のミツウロコの灯籠発見。って事は…。








 時刻は14時40分。ぼちぼちおやつタイムです。
時刻は14時40分。ぼちぼちおやつタイムです。 既に撮影枚数が200枚超えちゃったぜ。もういつ電池が終了となってもおかしくないな。つーか、なぜに200枚も撮影出来てるのか?やっぱこまめにカメラ撮影終了ボタンを押してるのが正解なのか?それとも撮影出来てない…。や。今、確認する気力がない。更には確認に使う電池がもったいない。
既に撮影枚数が200枚超えちゃったぜ。もういつ電池が終了となってもおかしくないな。つーか、なぜに200枚も撮影出来てるのか?やっぱこまめにカメラ撮影終了ボタンを押してるのが正解なのか?それとも撮影出来てない…。や。今、確認する気力がない。更には確認に使う電池がもったいない。



 脱力顔出し看板が迎えてくれました。はうっ
脱力顔出し看板が迎えてくれました。はうっ ~~~更に体力削られる…
~~~更に体力削られる… 。
。












 イチョウの木です。
イチョウの木です。
 参道ですね。
参道ですね。








 旧孔子廟
旧孔子廟 鐘楼の鐘。
鐘楼の鐘。

 裏から~。門の外に階段が。
裏から~。門の外に階段が。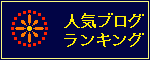




 桜井門
桜井門











