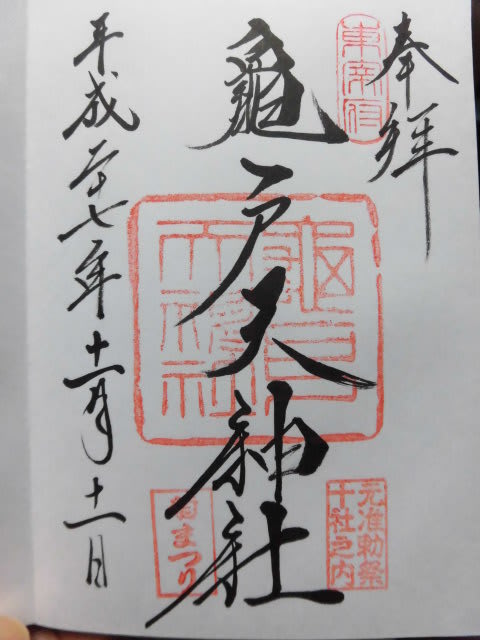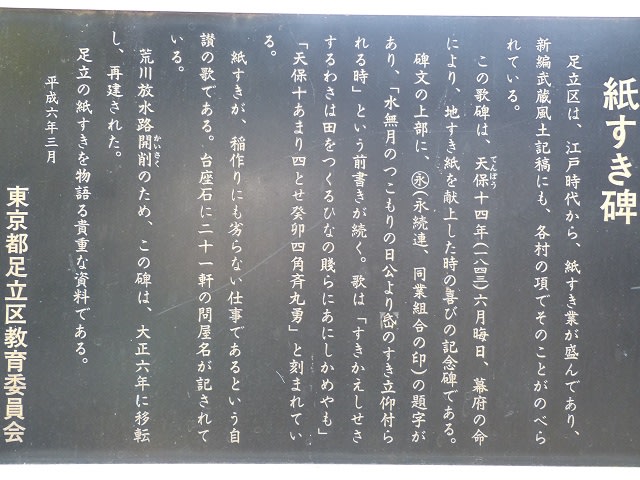長らく千住亀戸歩きの情報が続いておりましたがそれも一段落。その間に撮影した「カンムリカイツブリ」の捕食が偶然撮影できましたので報告します。
晴天を見つけて、行きつけのため池に出かけてみました。前回証拠写真の「カンムリカイツブリ」が堰堤側で餌を探しておりました。ご存じの通り一旦潜水すると、数分間は浮き上がらずまた泳ぎが得意で離れたところに浮上します。地形と河川水方向を見ていればある程度その浮上地点は想定が付きますが、それでもなかなかいい角度や距離には来てくれません。
それでこだわる人は、三脚を抱えて堰堤をドタドタ走り回ることになります。いい絵ではありませんね。
さて今回は、偶然待ち構えたところで大きな魚を咥えて浮上してきました。連写しましたから、駒落としの映像のように、全部を連続で見ていただければいいのですが、それでは枚数が多すぎます。端折って並べますのでご覧ください

ここで気が付いたのです。




なるほど。このくらいの魚を食べることが出来るのですから、この池に冬の間居つくのは納得です。
晴天を見つけて、行きつけのため池に出かけてみました。前回証拠写真の「カンムリカイツブリ」が堰堤側で餌を探しておりました。ご存じの通り一旦潜水すると、数分間は浮き上がらずまた泳ぎが得意で離れたところに浮上します。地形と河川水方向を見ていればある程度その浮上地点は想定が付きますが、それでもなかなかいい角度や距離には来てくれません。
それでこだわる人は、三脚を抱えて堰堤をドタドタ走り回ることになります。いい絵ではありませんね。
さて今回は、偶然待ち構えたところで大きな魚を咥えて浮上してきました。連写しましたから、駒落としの映像のように、全部を連続で見ていただければいいのですが、それでは枚数が多すぎます。端折って並べますのでご覧ください

ここで気が付いたのです。




なるほど。このくらいの魚を食べることが出来るのですから、この池に冬の間居つくのは納得です。