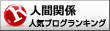講演「戦時下における日本の教会と国家」 原誠さん(同志社大学神学部教授)
「2・11信教の自由を守る日」の集会(関西地方教会連合社会委員会主催)が当大阪教会で行われました。21教会・伝道所等より63名の参加がありました。
大阪教会から12名が参加されました。集会は「戦時下における日本の教会と国家」と題し同志社大学神学部教授で牧師の原誠さんよりご講演がありました。原さんより始めに「自分は6代目クリスチャンで、曾祖母は日本で最初にバプテスマをその父から受け、曾祖母の父は日本で最初のバプテスト教会の牧師であった」との自己紹介がありました。又、御自身の父親も牧師でいらっしゃったのですが、戦時下において国策に流されていった父の姿を知って、問題意識を覚えるようになったそうであります。講演では、明治期から戦時下に至るまでの日本が戦争に向かう歴史をひもときながら、それに教会や各教派は如何に関わっていったのかを整理しながら淡々と話されたのですが、2つのことが心に留まりました。
一つは、「明治以降、日本のプロテスタント教会の歴史は130年余、15年戦争はその中間地点にあたる。この15年戦争は明治以降の日本のプロテスタント教会がもっていたブルジョア意識の体質が変わらず、あぶりだされたに過ぎなかった」ということです。二つ目は、「戦時体制が整えられていく中、国家神道の下で国家統制が敷かれていく中で、キリスト教界は一つに統合したが、それは一方で各教派のアイデンティティー (それによって立つ信仰のこだわり)を薄めてしまい、国策に足をすくわれ戦争に追従する道を拓いた」という事です。つまりそれが「国家の枠を超えられなかった日本のプロテスタント教会」の実態というのです。そして最後に、「バプテスト教会ならバプテストとしての、メソジスト教会ならメソジストとしてのアイデンティティー(それによって立つもの)があるが、時代状況の中で如何なるものからも侵されることがない、奪われることがないために、それぞれの教派というものが継承され、存在している」ということを教えて戴きました。
改めて、「わたし」がバプテストであるとはどういうことなのか、「わたし」がバプテスト教会に属するとはどういうことなのか問われました。今日の時代にあってそのことを明確にし、再構築していくことは、かつての戦時下の道をくり返さないために如何に大切であるかを知らされました。(俊)
「2・11信教の自由を守る日」の集会(関西地方教会連合社会委員会主催)が当大阪教会で行われました。21教会・伝道所等より63名の参加がありました。
大阪教会から12名が参加されました。集会は「戦時下における日本の教会と国家」と題し同志社大学神学部教授で牧師の原誠さんよりご講演がありました。原さんより始めに「自分は6代目クリスチャンで、曾祖母は日本で最初にバプテスマをその父から受け、曾祖母の父は日本で最初のバプテスト教会の牧師であった」との自己紹介がありました。又、御自身の父親も牧師でいらっしゃったのですが、戦時下において国策に流されていった父の姿を知って、問題意識を覚えるようになったそうであります。講演では、明治期から戦時下に至るまでの日本が戦争に向かう歴史をひもときながら、それに教会や各教派は如何に関わっていったのかを整理しながら淡々と話されたのですが、2つのことが心に留まりました。
一つは、「明治以降、日本のプロテスタント教会の歴史は130年余、15年戦争はその中間地点にあたる。この15年戦争は明治以降の日本のプロテスタント教会がもっていたブルジョア意識の体質が変わらず、あぶりだされたに過ぎなかった」ということです。二つ目は、「戦時体制が整えられていく中、国家神道の下で国家統制が敷かれていく中で、キリスト教界は一つに統合したが、それは一方で各教派のアイデンティティー (それによって立つ信仰のこだわり)を薄めてしまい、国策に足をすくわれ戦争に追従する道を拓いた」という事です。つまりそれが「国家の枠を超えられなかった日本のプロテスタント教会」の実態というのです。そして最後に、「バプテスト教会ならバプテストとしての、メソジスト教会ならメソジストとしてのアイデンティティー(それによって立つもの)があるが、時代状況の中で如何なるものからも侵されることがない、奪われることがないために、それぞれの教派というものが継承され、存在している」ということを教えて戴きました。
改めて、「わたし」がバプテストであるとはどういうことなのか、「わたし」がバプテスト教会に属するとはどういうことなのか問われました。今日の時代にあってそのことを明確にし、再構築していくことは、かつての戦時下の道をくり返さないために如何に大切であるかを知らされました。(俊)