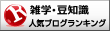主日礼拝宣教 詩編139編1~24節
今日の詩編139編は、詩編の中でも大変印象深い賛歌の一つではないでしょうか。それは、この詩人が全知全能の偉大な神さまと、あたかも向い合って会話するように「あなた」と呼びかけているところにあると思います。神さまは自分の日常的な、身近な存在である。そのような信頼と確信をもって賛美しているところに、わたしたちは信仰者の真の平安を見ることができます。人としての弱さの中で、訴えるように祈り求める詩人のその姿。そこにわたしたち自身の信仰の想いを重ねる時、わたしたちもまた偉大な神さまに向かって「あなた」と呼びかけることができる幸いを覚えるでしょう。この詩人は常に「わたし」という存在を知っておられる主なる神を認識しています。何とこの短い詩の中には、訳されていない原語も含めますと「わたし」という言葉が実に29回も繰り返されているんですね。その「わたし」というところに、皆さん個人個人のお名前を入れて読んでみてください。どうでしょう・・・まあ、それだけ神さまとの信頼関係を持って、或いはまた築こうとして、一対一で向き合っている、そういうこの詩人の心と信仰。それがわたしたちの胸を打つのだと思います。それでは1節から丁寧に見ていきましょう。
①「全知の神」まず1節~6節で詩人はすべてのことを知っておられる神さまを賛美しています。どのようにかと申しますと、1節「主よ、あなたはわたしを究め、わたしを知っておられる」。そのように、わたしのすべて、私自身が知り得ないような事までも知りつくしておられる、と讃えているのです。「わたしは何処から来たのか」「どういった存在なのか」。これは人間の根源的問題です。しかし、それは人間が自分の頭で考えても、なかなか答えは得られません。よく何かの時に自己紹介をやりますが、大方の人は「わたしはこれこれ、このような者です」とはなかなか答えられないしでしょう。また他己紹介といのもありますね。他人が「この人はこのような人です」と紹介するのですが、言いにくいし、また言われた本人も心外であったりと、なかなかその人の本質を言い当てることなどできはしません。けれど、この詩人は「わたしを造られた神がわたしを究め、わたしを知ってくださる」。そういうのです。自分はいったいどこから来たのか、一体何者で、どういった存在なのか。その答えは神が一切を誤りなく知っておられる。そういうのです。そこにわたしの存在の確かさ、意義がある。それを詩人は知っているのです。宗教改革者の一人であったジャン・カルヴァンは「神を知ることこそが、すなわち、わたしを知ることである」と、著書の中で記していますが。「自分が何者であるか知りたい、わたしは何者なのか」と言う答えが、全能者なるお方の前には確かにあると言っているのです。そういう安心感、平安がこの詩人のように信仰者には与えられているのです。わたしを創造された神は、わたしに関心があり、わたしを究め、知り尽くしていてくださる。わたしは神の御前に確かに存在している。主である神を信じるもののアイデンティティーはまさにこのところにあるといえるでしょう。
続いて、2-4節「座るのも立つのも知り、遠くからわたしの計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、わたしの道にことごとく通じておられる。わたしの舌がまだひと言も語らぬさきに、主よ、あなたはすべてを知っておられる」。神はわたしの行動、動作を全て知っておられるだけでなく、わたしの心の中の思いその全てを知っておられます。「一言も言わなくても、すべてわかっていてくれる」。それは大変慰められる事であります。しかしまた同時に恐るべき事でもあるでしょう。隠れた罪の思いさえ全能者なる神さまにすべて知られているからです。
5-6節「前からも後ろからもわたしを囲み、御手をわたしの上に置いてくださる。その驚くべき知識はわたしを越え、あまりにも高くて到達できない」。四六時中、休むこともなく神さまがわたしのことをご覧になっていらっしゃる。そんな事を聞いたら、それはとても堅苦しくて、窮屈なことのように感じるかもしれません。日ごろ様々な人間関係の中で忙しく動き回り、人に気を遣いながら生活をしている人にとっては、誰にも知られないところでたった一人になってくつろぎたい、そう思うのは当然でしょう。人間はどんなに気を遣わない相手であっても、一時も離れず一緒にいたのでは、気の休まる暇もありません。自分をあるがままに理解し、受け入れ、裏も表もなく接してくれるような相手がと願っても、現実にはまず難しいでしょう。なぜなら人間はどんなに頑張ってみても自己中心的考えから完全に自由になることはおよそ不可能なことだからです。人はたやすく人を誤解し、人は人のすべてを受け入れ切れないからです。しかし、この詩人はそのような「人の思い」ではなく、全てを知っておられる全知全能の神さまが、「あらゆる方向からわたしを囲ってくださり、御手をわたしにおいていてくださる」と、信頼をもって賛美するのです。
誰かに自分のことを一部分だけ知られるということは、それが良いことであっても悪いことであっても、気を遣ってしまいます。自分が実際以上に大きなもののように見られたのでは、いつも背伸びしていなければならなくなってしまいます。逆に実際より小さい者と見下されてしまえば、それもまた心中穏やかではありません。しかし、神の御前では「自分は自分であるとおりに見られ、知られている」のです。何よりも神さまはわたしを造って下さったお方であるので、どんな部分も隠さず知られているのは平安であり嬉しい限りのことです。ただわたしどもは罪多き存在でありますから、だからこそ主イエスさまの御救いが必要であり、その福音によってこそ、この魂の平安があるわけですが。このように主は人の一切を見通しておられるお方であられ、いつも御前に立ち返って生きる者を守り導いていてくださる、驚くべき叡智に満ちたお方なのです。
②「遍在の神」さらに詩人は主を賛美します。今日の礼拝の招詞の言葉ですが。7-10節「どこに行けば、あなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば、御顔を避けることができよう。天に登ろうとも、あなたはそこにいまし 陰府に身を横たえようとも 見よ、あなたはそこにいます。曙の翼を駆って海のかなたに行き着こうとも、あなたはそこにもいまし、御手をもってわたしを導き、右の御手をもってわたしをとらえてくださる」。詩人は神が霊的なお方であることを知っています。神が霊であるなら、神は場所に縛られることはありません。神は霊なるお方、偏在の神はどの場所にも、どの時間にも、どの空間にもおられるお方です。この詩人は「どこに逃れれば、御顔を避けることができよう」と問い、この遍在の神さまのもとから逃れようと試みますが、神の力の及ばぬ世界はありません。又、神の目の届かない所もありません。どこにも隠れることはできない。それが不可能であることを知らされたのです。この詩の主人公とされるダビデ王は人の妻に横恋慕して、その夫を戦の最前線に送り死なせてしまうと言う、恐ろしい罪を犯してしました。しかし神さまはそれを全て知っておられ預言者をお遣わしになってその恐ろしい罪を指摘なさるのですね。その時彼は「ああ神は全てをご存知であった、自分は何と恐ろしいことをしてしまったのか」と大変後悔するのです。どこに行けばあなたの霊から離れることが出来よう。どこに逃れれば、御顔を避けることが出来よう。神のもとから逃れようとする詩人の試みはこうして失敗します。しかし、そのことは彼にとって幸いなことでした。わたしが天に登ろうとも、海のかなたに行き着こうとも、どこに行ってもわたしをご存知の神を知ることとなったからです。それはまた、どこまでも共にいてくださる神であられると言うことを悟ることとなったからです。神に立ち返る者にとっては決してわずらわしいことではなく、むしろ大いなる慰め、平安であることを知ったからです。神がおられない場所はどこにもない。いつどこにいてもそこに主が共におられるのです。 11節「闇の中でも主はわたしを見ておられる。夜も光がわたしを照らし出す」。闇、夜は人間を孤独にします。けれどこの闇、夜はただそう言った時間帯を言っているのではなくて、人生の闇、死の闇、陰府の闇、絶望の闇を指しているのですね。しかし、主なる神は闇の中でもわたしを見ておられる。暗い暗い夜も主の光がわたしを照らし出すと言うのです。12節「闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も、光も、変わるところがない」。闇も神の御前では闇ではなくなる。命と光の神の御前にいるわたしには、たとえ暗闇に思えるような時でさえ、真昼と同じように主の光を見るものとされる、というんですね。わたしたちも日々その人生の歩みにおいて、神さまのそのようなみ光の中を生きる者とされたいものです。
③「全能の神の業」詩人はさらに主を賛美します。13-15節「あなたは、わたしの内臓を造り、母の胎内にわたしを組み立ててくださった。わたしはあなたに感謝をささげる。わたしは恐ろしい力によって、驚くべきものに造り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、わたしの魂はよく知っている。秘められたところでわたしは造られ、深い地の底で織りなされた。あなたには、わたしの骨も隠されてはいない」。わたしの命の誕生に際し、神さまが如何なる愛を注ぎ、深い知恵と緻密な業によって、わたしを創造されたか。その驚くべき神の御業に、詩人は驚きをもって主を賛美します。 16節「胎児であったわたしをあなたの目は見ておられた。わたしの日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も造られないうちから」。わたしどもは自分のことは自分が一番よく知っていると思っています。けれども、わたしどもは自分が誕生した時のことなど知りません。誕生前に母の胎内にいた時のことなど知りはしません。しかし、私どもを創造された神は、わたしの誕生前、胎児の時、誕生の時、すべてを知り、見ておられた。何ともミステリアス、神秘的なことであります。この詩人は、わたしという人間の始めから、その全ての日々が神の書に書き記されているといいます。そして、その御前にある一日一日が「あなたの御計らいは、わたしにとっていかに貴いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても、砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、わたしはなお、あなたの中にいる」。そう賛美するのです。わたしたち一人ひとりの命の創造、そして人生の歩みに、どんなに深い神さまの御計らいがあったことでしょうか。その神の御計らいは、砂粒よりも多く、数え尽くすことは出来ません。神の御計らいを極め尽くすことは出来ません。「わたしはなお、あなたの中にいる」と、詩人が賛美していますように、まさに神の御手の中でわたしたちも又、どこまでも神さまと共におり、そのご計画を持って守られ、生かされているのです。
④「神の審きと導きを訴え求める祈り」さて、この詩編139編の詩人は、ここまで神の全知、神の遍在、神の全能を、賛美のうたをもって表してきました。ところが突然、最後に審きの祈りがなされており、いささか読み手としては驚かされます。一説によりますと、この139編は元々、「どうか神よ、逆らう者を滅ぼしてください。わたしを離れよ、流血を謀る者。と、ここにあるような神の審きを嘆き訴える祈りから始まり、展開されていったものではないかとも言われています。この詩人の目の前には神に逆らう者たちがおり、それが詩人を苦しめ、神を悲しませていたのです。神が造られた世界に何故、神に逆らう者が存在し、不条理な現実が存在するのか、という問題、問は現代もあります。詩人自らもいわれのない罪を背負わされ、さらに流血を諮る者がおり、神の名を騙り町々を虚しくしていた現実があった。そういう中で詩人は、「逆らう者を打ち滅ぼしてください」と祈らざるを得ませんでした。彼は神に報復を求めて祈ります。罪を憎み、罪から遠ざかることは、何処までも聖なる神に対する真実な畏れに相応しい礼拝する者の態度でありました。詩人はこの潔白な態度から、神に敵する者の裁きを訴えたのです。彼は、神の聖なる御名を汚して流血を謀る者を憎み、このように祈ったのです。ただその一方で、この詩人は1-17節で読みましたように、自分の限界と不確かさを知っていました。神こそ全知全能なるお方であるとわきまえていたのです。自分もまた過ちを犯す不完全な人間であるに過ぎない。この詩人は神のまえにあって謙遜に生きる道を心得ていました。こうして至った祈りが、23-24節の「神よ、わたしを究め わたしの心を知ってください。わたしを試し、悩みを知ってください。ご覧ください わたしの内に迷いの道があるかどうかを。どうか、わたしを とこしえの道に導いてください」との、祈りであったのです。このどこまでも共にいてくださる主なるお方に救いの確信を抱きつつ、賛美の歌をもって今週もこの礼拝から、それぞれの場へ遣わされてまいりましょう。「人の一歩一歩を究め、御旨にかなう道を備えてくださる主」(詩編37:23)にあって。