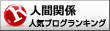エレミヤ31章27節~34節
聖書の旧約と新約というのは約束の約であり、神と人間の間に交される契約のことであります。信仰はこの契約を基としているのです。エレミヤ書のこの箇所は、バビロニアに攻め込まれ、すでに壊滅的状況にあったユダとエルサレムの人々に対して、主が「見よ、新しい契約を結ぶ時が来る」と約束なさるところであります。新しい契約というのですから、古い契約があった訳で、それこそ主がシナイ山でモーセに授けた律法であります。
この契約は、イスラエルの民がかつて出エジプトへと導かれた主に忠実に従うなら祝福をもたらすが、これに反して不信であるならばのろいを受けることになるという条件つきのものでした。イスラエルの民は、その神との契約を軽んじ、エレミヤの再三にわたる神に立ち帰って悔い改めて生きなさいとの警告にも拘わらず、神の律法に背き、罪を犯し続けました。そして遂に審判の時を迎え、バビロニアによってユダの国は崩壊します。
バビロニアに捕囚として連行されたユダの人々は、異国の地にあってさまざまのことを思い巡らしたことでしょう。「なぜこんなことになってしまったのか。エレミヤがあんなこと、こんなことを言っていた。自分たちは真実な預言に耳を傾けることが出来なかった、、、」。そこで彼ら自らが、このような事態を招いたのだということを今更ながらに思い知らされたことでしょう。何もかも失ってようやくそのことに気づいた、いや気づかされたのです。そしてその暗闇の中で放たれるともし火のようなエレミヤの預言の言葉を、彼らは受けとり握り締め、それを「希望の約束」としていったのではないでしょうか。主は石の板にではなく、「わたしの律法を彼らの胸の中に授け、心に記す」(今も肝に銘じると言われますが、心はリバムという原語から来ている「肝」:レバーのことです)。そしてそのことをして、「わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる」「わたしは彼らの悪を赦し、再び彼らの罪に心を留めることはない」と言われるのです。
これこそ、主が古い契約を破棄なさった新しい契約(神の約束)の宣言です。
聖書の旧約と新約というのは約束の約であり、神と人間の間に交される契約のことであります。信仰はこの契約を基としているのです。エレミヤ書のこの箇所は、バビロニアに攻め込まれ、すでに壊滅的状況にあったユダとエルサレムの人々に対して、主が「見よ、新しい契約を結ぶ時が来る」と約束なさるところであります。新しい契約というのですから、古い契約があった訳で、それこそ主がシナイ山でモーセに授けた律法であります。
この契約は、イスラエルの民がかつて出エジプトへと導かれた主に忠実に従うなら祝福をもたらすが、これに反して不信であるならばのろいを受けることになるという条件つきのものでした。イスラエルの民は、その神との契約を軽んじ、エレミヤの再三にわたる神に立ち帰って悔い改めて生きなさいとの警告にも拘わらず、神の律法に背き、罪を犯し続けました。そして遂に審判の時を迎え、バビロニアによってユダの国は崩壊します。
バビロニアに捕囚として連行されたユダの人々は、異国の地にあってさまざまのことを思い巡らしたことでしょう。「なぜこんなことになってしまったのか。エレミヤがあんなこと、こんなことを言っていた。自分たちは真実な預言に耳を傾けることが出来なかった、、、」。そこで彼ら自らが、このような事態を招いたのだということを今更ながらに思い知らされたことでしょう。何もかも失ってようやくそのことに気づいた、いや気づかされたのです。そしてその暗闇の中で放たれるともし火のようなエレミヤの預言の言葉を、彼らは受けとり握り締め、それを「希望の約束」としていったのではないでしょうか。主は石の板にではなく、「わたしの律法を彼らの胸の中に授け、心に記す」(今も肝に銘じると言われますが、心はリバムという原語から来ている「肝」:レバーのことです)。そしてそのことをして、「わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる」「わたしは彼らの悪を赦し、再び彼らの罪に心を留めることはない」と言われるのです。
これこそ、主が古い契約を破棄なさった新しい契約(神の約束)の宣言です。