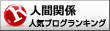受難週礼拝宣教 ルカ23章32~43節
本日の箇所はイエスさまが十字架に磔にされる場面であります。
そこにはユダヤの民衆、ユダヤの議員、ローマの兵士、そしてイエスさまと同じように十字架に磔にされた2人の犯罪人と、様々な登場人物が記されています。
今日は特に、十字架上でのイエスさまのお言葉とこの二人の犯罪人たちに焦点を当てつつ、「主イエスの十字架と私の十字架」と題して御言葉から聞いていきたいと思います。
①「主イエスのとりなし」
本日のところで、まず何と言っても印象深いのは、イエスさまが十字架に磔にされながらも「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」と言われた、という事です。
ここでイエスさまが、「彼ら」と言っているのは、罪の無いイエスさまを十字架に磔にしていった人々のことであります。祭司たちや律法学者、ファリサイ派の人々は、イエスさまの言葉と行いを理解できず、憎しみと妬みが殺意にまで及びます。又、ユダヤの議員たちは、神の時をわきまえ知ることができませんでした。さらにユダヤの民衆は、イエスさまのエルサレム入城をホサナ、ホサナと喜び迎えましたが、僅か数日で「イエスを十字架につけろ」と大声で叫ぶのです。さらにローマの権力によってイエスさまは鞭打たれ、屈辱を受け、十字架につけられました。ですからそこにはユダヤ人とローマ人の両者が関わっていたんですね。イエスさまはそのような自分を十字架に引き渡し、殺害しようとする者のために、父の神に赦しを乞い、とりなされるのです。追いつめられ死の恐怖を前にされたイエスさまのこのお言葉にはただ驚くばかりであります。
かつてイエスさまは、「一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回。『悔改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやりなさい」(ルカ17:4)とおっしゃいました。さらに、「あなたがたは敵を愛しなさい」(ルカ6:35)と語られました。
それは、まさにこの最期の最期までイエスさまご自身、敵対する人びとを赦し、執り成されたのです。これが神の愛です。イエスさまがその身をもって示された愛は、赦しと、敵でさえ「神の愛に立ち返って生きるように」と執りなす祈りであります。イエスさまは彼らが罪から解放され、立ち返って命を得ることを願われたのです。今も変ることなく、ともすれば救いようもない罪深い者のために、十字架の主がとりなしてくださるということは、私どもにとってもどんなに大きな救いと希望であることでしょう。
同時に、そのとりなしは、主に赦され従う私たちに与えられた手本であり、招きであります。
②主イエスの十字架
さて、この十字架上でのイエスさまのとりなしの言葉は、同様に十字架に磔にされていた二人の犯罪人にももちろん聞こえていたでしょう。
しかし犯罪人の一人は、「お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ」とイエスをののしった、というのです。イエスさまとりなしの言葉は彼の心に届きません。心を閉ざしイエスさまを「ののしり続けた」(原意)のです。彼はユダヤの議員たちやローマの兵士たちと同じように、イエスさまに向かって「自分を救ってみろ」といい、さらに「我々を救ってみろ」と言うのです。
十字架刑はもともとローマ帝国の処刑方法です。彼はユダヤ人であったようですので、ローマ帝国に対して何らかの政治犯か活動家であったのかも知れません。ローマ帝国の支配の下でユダヤ民衆はいつか救世主(メシア)が現れて、政治的な指導力や軍事力を発揮し、ユダヤの民を解放に導くと、期待していたと考えられます。それがもしかしたら、「あのイエスという男かもしれない」。そんな期待が十字架に磔になった弱々しいまるで敗北者のその姿によって崩れ去った。それが「自分を救ってみろ。我々を救ってみろ」と、ののしりの言葉になったのでしょう。
しかし、かりにイエスさまがそのような世の王としてローマ帝国を滅ぼしユダヤを解放なさったとしても、それは一時のものに過ぎません。世には争いが絶えず、その強大なローマの帝国さえもやがて滅亡の時が訪れました。世の権力や支配は必ず終わりが来ます。しかし、イエスさまはそういう形とは異なる「天の国」(神さまがご支配される国)を人々に伝え、お示しになられたのです。それはまさに、イエスさまが罪人の一人となって、神の裁きを受けることによって、すべての人の罪の贖いを果たされる道であったのです。世から見るなら十字架のイエスさまはまさに敗北者のように見えますが、そうではないのです。イエスさまが罪ある私たちを赦し、贖うには、こういう形でしか救い得なかったのであります。D・ボンフェッファーはその著書「主のよき力に守られて:一日一章」(p.170)の中で次のように言っています。「神はこの世において無力で弱い。しかし神はまさにそのようにして、しかもそのようにしてのみ僕たちのもとにおり、また僕たちを助けるのである。」
ところで、マルコやマタイの福音書では、その犯罪人の2人ともイエスをののしったと記されておりますが。このルカ福音書では、もう一人の犯罪人がイエスさまのとりなしの祈りを聞いて、相方の犯罪人に「お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は、自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない」と言ってたしなめたと記されています。
彼ももしかしたら始めの犯罪人と一緒にイエスさまをののしっていたのかもしれません。ところが彼は十字架上で、父の神に自分たちのことをとりなされる主イエスの姿を目の当たりにしたのです。彼はもう一人をたしなめ、「お前は神をも恐れないのか」と言いますが。そのイエスさまのお姿ととりなしの言葉に、神を畏れ敬う心を取り戻すのです。十字架刑という極限の状況で、彼はイエスさまの中に神の救いを見出すのですね。
彼はここで何と、「イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを思い出してください」と言うのであります。イエスさまはその言葉に対して次のようにおっしゃいます。「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる(未来形:だろう)」。
この最期の場面を読んである方は、「この犯罪人はこのイエスさまの、『今日わたしと一緒に楽園にいる』との約束を戴いて、亡くなってしまうのですね」とおっしゃいました。そのとおりです。彼は十字架から下りて助かるというのではなく、その十字架の上で苦しみながら地上の生涯を終えるのです。けれど彼は、「今日、あなたはわたしと一緒に楽園にいるだろう」というイエスさまの約束、これは罪のゆるしの宣言ですね。その確かな希望を戴いて召されていくのです。楽園というのは、あのアダムとエバ、人間が神と近く共に生きたエデンの園を彷彿とさせます。神の救い、主イエスが一緒にいてくださる。いることになる。それが彼にとっての、又、主に救われた私たちにとっての楽園、パラダイスなのです。
③私の十字架
最後に、今日の宣教題を「主イエスの十字架と私の十字架」とつけました。
主イエスの十字架を挟んで左右に二人の犯罪人の十字架がありました。今から2000年も前のできごとです。けれども今日の箇所から示されますことは、それが「私の十字架」でもある、ということです。犯罪人の一人は十字架上でイエスを最期までののしり続けました。一方の犯罪人は十字架のイエスとの出会いを通して、主の御赦しと救いを得るのです。私はこの二人の犯罪人が十字架につけれられたように、罪に滅ぶ外ないような者であります。そのような者のために、罪の無い主イエスが十字架にかかり貴い犠牲を払い、私の罪の裁きを受けてくださったのです。これこそまさに、ルカ福音書からこれまで放蕩息子のたとえ、徴税人のザアカイ等の物語を読んできましたように、「人の子は、失われた者を捜して救うために来たのである」との福音なのです。
滅びの十字架を共に担って下さった主イエスの犠牲とその痛み。それは神の愛であります。その深い大きな御救いを生涯忘れることがないように、日々主を賛美し、仕えつつ、主がもたらされた福音を伝え、証しする者とされてまいりましょう。やがて完全なかたちで訪れる神の国を待ち望み、希望をもって歩んでまいりましょう。
本日の箇所はイエスさまが十字架に磔にされる場面であります。
そこにはユダヤの民衆、ユダヤの議員、ローマの兵士、そしてイエスさまと同じように十字架に磔にされた2人の犯罪人と、様々な登場人物が記されています。
今日は特に、十字架上でのイエスさまのお言葉とこの二人の犯罪人たちに焦点を当てつつ、「主イエスの十字架と私の十字架」と題して御言葉から聞いていきたいと思います。
①「主イエスのとりなし」
本日のところで、まず何と言っても印象深いのは、イエスさまが十字架に磔にされながらも「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」と言われた、という事です。
ここでイエスさまが、「彼ら」と言っているのは、罪の無いイエスさまを十字架に磔にしていった人々のことであります。祭司たちや律法学者、ファリサイ派の人々は、イエスさまの言葉と行いを理解できず、憎しみと妬みが殺意にまで及びます。又、ユダヤの議員たちは、神の時をわきまえ知ることができませんでした。さらにユダヤの民衆は、イエスさまのエルサレム入城をホサナ、ホサナと喜び迎えましたが、僅か数日で「イエスを十字架につけろ」と大声で叫ぶのです。さらにローマの権力によってイエスさまは鞭打たれ、屈辱を受け、十字架につけられました。ですからそこにはユダヤ人とローマ人の両者が関わっていたんですね。イエスさまはそのような自分を十字架に引き渡し、殺害しようとする者のために、父の神に赦しを乞い、とりなされるのです。追いつめられ死の恐怖を前にされたイエスさまのこのお言葉にはただ驚くばかりであります。
かつてイエスさまは、「一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回。『悔改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやりなさい」(ルカ17:4)とおっしゃいました。さらに、「あなたがたは敵を愛しなさい」(ルカ6:35)と語られました。
それは、まさにこの最期の最期までイエスさまご自身、敵対する人びとを赦し、執り成されたのです。これが神の愛です。イエスさまがその身をもって示された愛は、赦しと、敵でさえ「神の愛に立ち返って生きるように」と執りなす祈りであります。イエスさまは彼らが罪から解放され、立ち返って命を得ることを願われたのです。今も変ることなく、ともすれば救いようもない罪深い者のために、十字架の主がとりなしてくださるということは、私どもにとってもどんなに大きな救いと希望であることでしょう。
同時に、そのとりなしは、主に赦され従う私たちに与えられた手本であり、招きであります。
②主イエスの十字架
さて、この十字架上でのイエスさまのとりなしの言葉は、同様に十字架に磔にされていた二人の犯罪人にももちろん聞こえていたでしょう。
しかし犯罪人の一人は、「お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ」とイエスをののしった、というのです。イエスさまとりなしの言葉は彼の心に届きません。心を閉ざしイエスさまを「ののしり続けた」(原意)のです。彼はユダヤの議員たちやローマの兵士たちと同じように、イエスさまに向かって「自分を救ってみろ」といい、さらに「我々を救ってみろ」と言うのです。
十字架刑はもともとローマ帝国の処刑方法です。彼はユダヤ人であったようですので、ローマ帝国に対して何らかの政治犯か活動家であったのかも知れません。ローマ帝国の支配の下でユダヤ民衆はいつか救世主(メシア)が現れて、政治的な指導力や軍事力を発揮し、ユダヤの民を解放に導くと、期待していたと考えられます。それがもしかしたら、「あのイエスという男かもしれない」。そんな期待が十字架に磔になった弱々しいまるで敗北者のその姿によって崩れ去った。それが「自分を救ってみろ。我々を救ってみろ」と、ののしりの言葉になったのでしょう。
しかし、かりにイエスさまがそのような世の王としてローマ帝国を滅ぼしユダヤを解放なさったとしても、それは一時のものに過ぎません。世には争いが絶えず、その強大なローマの帝国さえもやがて滅亡の時が訪れました。世の権力や支配は必ず終わりが来ます。しかし、イエスさまはそういう形とは異なる「天の国」(神さまがご支配される国)を人々に伝え、お示しになられたのです。それはまさに、イエスさまが罪人の一人となって、神の裁きを受けることによって、すべての人の罪の贖いを果たされる道であったのです。世から見るなら十字架のイエスさまはまさに敗北者のように見えますが、そうではないのです。イエスさまが罪ある私たちを赦し、贖うには、こういう形でしか救い得なかったのであります。D・ボンフェッファーはその著書「主のよき力に守られて:一日一章」(p.170)の中で次のように言っています。「神はこの世において無力で弱い。しかし神はまさにそのようにして、しかもそのようにしてのみ僕たちのもとにおり、また僕たちを助けるのである。」
ところで、マルコやマタイの福音書では、その犯罪人の2人ともイエスをののしったと記されておりますが。このルカ福音書では、もう一人の犯罪人がイエスさまのとりなしの祈りを聞いて、相方の犯罪人に「お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は、自分のやったことの報いを受けているのだから、当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない」と言ってたしなめたと記されています。
彼ももしかしたら始めの犯罪人と一緒にイエスさまをののしっていたのかもしれません。ところが彼は十字架上で、父の神に自分たちのことをとりなされる主イエスの姿を目の当たりにしたのです。彼はもう一人をたしなめ、「お前は神をも恐れないのか」と言いますが。そのイエスさまのお姿ととりなしの言葉に、神を畏れ敬う心を取り戻すのです。十字架刑という極限の状況で、彼はイエスさまの中に神の救いを見出すのですね。
彼はここで何と、「イエスよ、あなたの御国においでになるときには、わたしを思い出してください」と言うのであります。イエスさまはその言葉に対して次のようにおっしゃいます。「はっきり言っておくが、あなたは今日わたしと一緒に楽園にいる(未来形:だろう)」。
この最期の場面を読んである方は、「この犯罪人はこのイエスさまの、『今日わたしと一緒に楽園にいる』との約束を戴いて、亡くなってしまうのですね」とおっしゃいました。そのとおりです。彼は十字架から下りて助かるというのではなく、その十字架の上で苦しみながら地上の生涯を終えるのです。けれど彼は、「今日、あなたはわたしと一緒に楽園にいるだろう」というイエスさまの約束、これは罪のゆるしの宣言ですね。その確かな希望を戴いて召されていくのです。楽園というのは、あのアダムとエバ、人間が神と近く共に生きたエデンの園を彷彿とさせます。神の救い、主イエスが一緒にいてくださる。いることになる。それが彼にとっての、又、主に救われた私たちにとっての楽園、パラダイスなのです。
③私の十字架
最後に、今日の宣教題を「主イエスの十字架と私の十字架」とつけました。
主イエスの十字架を挟んで左右に二人の犯罪人の十字架がありました。今から2000年も前のできごとです。けれども今日の箇所から示されますことは、それが「私の十字架」でもある、ということです。犯罪人の一人は十字架上でイエスを最期までののしり続けました。一方の犯罪人は十字架のイエスとの出会いを通して、主の御赦しと救いを得るのです。私はこの二人の犯罪人が十字架につけれられたように、罪に滅ぶ外ないような者であります。そのような者のために、罪の無い主イエスが十字架にかかり貴い犠牲を払い、私の罪の裁きを受けてくださったのです。これこそまさに、ルカ福音書からこれまで放蕩息子のたとえ、徴税人のザアカイ等の物語を読んできましたように、「人の子は、失われた者を捜して救うために来たのである」との福音なのです。
滅びの十字架を共に担って下さった主イエスの犠牲とその痛み。それは神の愛であります。その深い大きな御救いを生涯忘れることがないように、日々主を賛美し、仕えつつ、主がもたらされた福音を伝え、証しする者とされてまいりましょう。やがて完全なかたちで訪れる神の国を待ち望み、希望をもって歩んでまいりましょう。