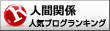主日礼拝宣教 ローマ11章1節~32節
今日はローマの信徒への手紙11章1~32節より「神の救いのまなざし」と題し、御言葉に聞いていきたいと思います。
この11章には3つの小見出しがつけられています。
1-10節は「イスラエルの残りの者」。今日のテキストである11―24節は「異邦人の救い」。さらに、25-36節は「イスラエルの再興」です。
そしてその全体は「神の秘められた御計画」として、すべての人が救いに与るという
神の壮大な御計画がここに示されているのです。その完成の日に至るまで「神は、憐れみを絶やそうとなさらない」というメッセージが語られています。
先ほど礼拝の招詞としてガラテヤ3章28節以降の言葉が読まれました。もう一度27節からお読みします。
「キリストに結ばれたあなたがたは皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなたがたはキリストにあって一つだからです。あなたがたは、もしキリストのものだとするなら、とりもなおさず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です」。
「イスラエルの残りの者」
イスラエル、ユダヤ人について旧約聖書では、神の愛によって選ばれた民であるとされています。しかし、それは何かこの世的にイスラエルに優れたものがあったからとか、力があったから選ばれたということではなく、申命記7・7-8にこう記されています。「主が心引かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに」と、ただ神の恵みの選びによるものであったのです。
そもそもそのような神の愛が選びの根拠であったのです。この「神の愛」とは「憐れみ」とも訳せます。それは「腸がちぎれるほどの思いをする」という意味です。
神は、ちっぽけで貧弱で神に呼ばわる外ない民を、まさに断腸の思いで憐れまれた。
それがイスラエルを宝の民として選ばれた理由なのです。それは又、キリストにある割私たち一人ひとりも同様ではないでしょうか。
ですから、イスラエルの民は何一つ誇り得るものをもっていなかった。誇るべきはただ恵みの神のみであり、その神に依り頼んで生きるほか無い。それがイスラエルの存在なのであります。
その神の恵みの信仰は、アブラハム、イサク、ヤコブという父祖たちの信仰を土台にイスラエルの民の中にあって継承されてきたものです。
しかし、旧約の歴史においてイスラエルの民はその神の恵みの選びに与ったにもかかわらず、神に背き、異教の神々にひれ伏し、罪を繰り返しその神の恵みを台なしにすることが繰り返されたのです。聖書のお言葉によるなら、神はねたむほどに、その民を愛しておられるがゆえに、彼らが立返るために下された審きは時にすさまじいものでした。
そのことを受けてパウロは、11章1節で「神は御自分の民(ユダヤの民)を退けられたのであろうか」と問います。又11節でも「ユダヤ人がつまずいたとは、倒れてしまったということなのか」と疑問を投げかけるのですが。すぐに「決してそうではない」と断言します。悔い改め神に立返って生きる道を選んだ「イスラエルの残りの者」。
この残りの者とは旧約時代に神に忠実に生きたイスラエルの人々、ユダヤ人たちのことを指しますが。同時にパウロは自分自身のようにイエス・キリストと出会い、救われたユダヤ人たちのことであったのです。いずれにしろ、神の恵みの選びは旧約聖書以来絶たれることがなかったし、今もそうだと言うのです。
イスラエルの民の歴史は不思議です。幾度も国を奪われ民も散らされ、もはや民族として存続し得ないような状況にありながら国を再建し、どこに住んでも何千年という歴史を神の民として生きてきた人たちを見るにつけ、イスラエルの民、ユダヤの人びとへの神の選びは、未だ変わっていないというパウロの言葉は非常に説得力があるなと思います。
いつの時代も、神を愛し、信仰をもって主の恵みに留まり続ける人たちがいます。それはたとえ木が切り倒されるような状況に遭遇しようとも、新たな若枝を芽吹かせる切り株のような人びとです。それこそパウロの言う「恵みによって選ばれた者」です。
私たちキリストの救いに生きる一人ひとりも、新約聖書にあるとおり、だれでも聖霊によらなければイエスを救い主だということは出来ないのです。それこそ一方的神の恵みであると言えましょう。
「異邦人の救い」
さて、パウロがイスラエルの民、ユダヤの人々について述べている事について読んでまいりましたが。次に本日の11~24節の個所であります「異邦人の救い」について読んでいきたいと思います。
はじめに申しましたように、この救いは神の恵みによってイスラエルの民にまず与えられたものであることに変わりございません。
しかしながら、11節「彼ら(ユダヤ人たち)の罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になった」。まあ独特な言い方ですが。決定的神の救いであるイエス・キリストを不信仰であったユダヤ人が十字架につけ、そのことによって全世界の人々に救いがもたらされるようになった、ということを言っているのでしょう。
使徒言行録13章44-46節にはこういう記述があります。
次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうと集まって来た。しかし、ユダヤ人はこの群集を見てひどくねたみ、口汚くののしって、パウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った「神の言葉は、まずあなたたちに語られるはずでした。だがあなたがたはそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに価しない者にしている。見なさい、わたしは異邦人の方へ行く。主はわたしたちにこう命じておられるからです。これはイザヤ書42章6節、49章6節を箇所からの引用として『わたしは、あなたを異邦人の光と定めた、あなたが、地の果てにまでも救いをもたらすために』」
この「あなた」とは勿論主イエス・キリストのことです。
異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして、永遠の命を得るように定められた人たちは皆、信仰に入った、と記録されています。
まさに異邦人への伝道の皮切りのところですが。このようにして、ユダヤ人たちが拒んだ主のみ救いが全世界に広げられていくようになったということです。こうしてパウロ自身がまずその異邦人伝道のパイオニアとなっていくわけです。
しかし、だからといってパウロのユダヤ人同胞への愛というのは決して無くなったというのではありません。10章1節に「彼ら(ユダヤ同胞)が救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています」と述べられているとおりです。
本日の11章25節以降読みますと、パウロはこの全世界に福音が告げ知らされ、主のみ救いが伝えられていくという異邦人への伝道は、究極的にユダヤ人・イスラエルの人々が主の救いに与っていくことにつながるという祈りと確信のうちになされていったのですね。
ところで、この手紙が書き送られた当時のローマの教会の構成は、大半が異邦人クリスチャンで一部がユダヤ人クリスチャンであったようです。ローマの教会の開拓時は少数のユダヤ人クリスチャンたちが中心的働きを担っていましたが。次第に異邦人のクリスチャンたちが多くを占め、その中心メンバーとなっていく中で、異邦人クリスチャンたちの声や力が教会において強くなり、逆にユダヤ人クリスチャンたちの立場は狭くなり、居場所がなくなるということが実際起こったようであります。それだけではありません。ローマの教会で異邦人クリスチャンがユダヤ人クリスチャンを、先に申しあげたようなことから見下し、自分たちこそ神に選ばれた者であると、おごり高ぶる者たちがいたようですね。まあ、そんなことがあるだろうかとお思いになるかも知れませんが。
この世界の歴史においてキリスト教でありながらユダヤ人を迫害するという蛮行が実際行なわれてきた事実を思う時、人間は罪深い者だなあと思います。
そこでパウロは、異邦人のクリスチャンを戒めて、18節「折り取られた枝に対して誇ってはならない」ということです。
つまり、ユダヤ人に対して誇ったり、見下してはならないという警告であります。
そもそも異邦人クリスチャンは、本来根であり幹であるイスラエルに与えられた恵みに接ぎ木されるかたちで福音に与っているということであります。
何も根が無いところから生えてきたわけじゃない。接ぎ木というのは、強く、水や養分を吸い上げる力が備わった木の枝を切って、そこに別の弱い品種をくっつけることで、それにゆたかに花や実を結ばせる方法です。そのようにして、異邦人クリスチャンは神の祝福に与る者とされた。ですから、ユダヤの人々に対して何も誇ることはできないのです。
異邦人クリスチャンの救いの根幹は、イスラエルに与えられた神の恵み。アブラハム、イサク、ヤコブの父祖たちから継承されてきた信仰であり、ただ神のあわれみによって神の民とされたことにおいて同様なのです。
ただ神のヘセド・憐れみの愛。キリストの十字架による救いの業により神の民とされたことを感謝します。パウロの言葉を借りますなら、「誇る者は主を誇れ」「十字架のキリストを誇れ」ですね。
私たちは神に対して何ができたか、何をしたから救われたのではありません。逆に罪からの解放と救いを必要とする者だからこそ、恵みをいただいている。何よりもそのことを感謝し、喜ぶ者でありたいですね。
20節「ユダヤ人は、不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています」。この不信仰とは、神の恵みに背を向け、究極のみ救いであるメシア、主イエス・キリストを受け入れなかったことであります。一方、信仰によって立っているとは、異邦人でありながらも、ただ救い主イエス・キリストにより頼んでいるあなた方、ということです。
そのうえで、信仰によって立っている異邦人クリスチャンのあなたがたに対して、パウロは20節「思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい」と進言します。
私たちは「救いのみ恵み」を台なしにすることがないようにしなければなりません。
21節「神は、自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、恐らくあなたがたも容赦されないでしょう」。
折り取られた枝に表されるユダヤの民の二の舞を私たち異邦人キリスト者が踏むことのないために、この教訓をしっかり心に留めていなければなりません。
同時に、一度折り取られたれ枝であっても、神の恵みといつくしみに真に立ち返るなら、神は再びその枝を接ぎ木してくださる。そういう御業を自由になさることがおできになるということであります。神にできないことは何もありません。
「神の救いのまなざし」
最後に、本日の箇所は「異邦人の救い」が語られていましたが、25節以降で今度は「
イスラエルの再興」という見出しで、全世界に向けられた神の救いの御計画について述べられています。
キリストの救いを信じることで救われる。それは行いによる義を厳守するユダヤの民にとってはあり得ないことであり、ねたみを起こさせるものです。
あのルカ15章の放蕩息子のたとえ話が思い起こされますね。
父の財産を使い果たして放蕩三昧をして帰って来た弟息子を父は叱りつけるどころか、喜び、受入れ、最上のもてなしをして迎えます。
兄息子はこんな待遇を私には一度もしてくれなかったと弟を非難し、そんな父親を強く
責めるのです。けれど、父は兄にこう諭すんですね。「子よ、お前はいつも一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ」。父は弟と兄に憐れみを絶やすことはなかった。
このたとえは、父の神と息子の和解だけでなく、父の神の憐れみのもとにある兄と弟の和解への招きがとして語られているのですね。罪のゆえにゆるしと和解に与った弟。又そのはじめから父の神のもとにあるがゆえに、神の寛大な救いの計画を受入れることができない兄。
本日のローマ11章は始めに申しましたように「神はユダヤ人も異邦人も、すなわち全世界とご自身とが和解して、すべての人が救いに与る完成」のために、憐れみと恵みの御業を成し遂げようとしておられます。
この神の御計画に思いを馳せ、ただ主の憐れみによって御救に与っている者にふさわしく、感謝と畏れつつ、主の和解の福音を携えて、今週もこの礼拝からそれぞれの証の場へと遣わされてまいりましょう。
今日はローマの信徒への手紙11章1~32節より「神の救いのまなざし」と題し、御言葉に聞いていきたいと思います。
この11章には3つの小見出しがつけられています。
1-10節は「イスラエルの残りの者」。今日のテキストである11―24節は「異邦人の救い」。さらに、25-36節は「イスラエルの再興」です。
そしてその全体は「神の秘められた御計画」として、すべての人が救いに与るという
神の壮大な御計画がここに示されているのです。その完成の日に至るまで「神は、憐れみを絶やそうとなさらない」というメッセージが語られています。
先ほど礼拝の招詞としてガラテヤ3章28節以降の言葉が読まれました。もう一度27節からお読みします。
「キリストに結ばれたあなたがたは皆、キリストを着ているからです。そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなたがたはキリストにあって一つだからです。あなたがたは、もしキリストのものだとするなら、とりもなおさず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です」。
「イスラエルの残りの者」
イスラエル、ユダヤ人について旧約聖書では、神の愛によって選ばれた民であるとされています。しかし、それは何かこの世的にイスラエルに優れたものがあったからとか、力があったから選ばれたということではなく、申命記7・7-8にこう記されています。「主が心引かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに」と、ただ神の恵みの選びによるものであったのです。
そもそもそのような神の愛が選びの根拠であったのです。この「神の愛」とは「憐れみ」とも訳せます。それは「腸がちぎれるほどの思いをする」という意味です。
神は、ちっぽけで貧弱で神に呼ばわる外ない民を、まさに断腸の思いで憐れまれた。
それがイスラエルを宝の民として選ばれた理由なのです。それは又、キリストにある割私たち一人ひとりも同様ではないでしょうか。
ですから、イスラエルの民は何一つ誇り得るものをもっていなかった。誇るべきはただ恵みの神のみであり、その神に依り頼んで生きるほか無い。それがイスラエルの存在なのであります。
その神の恵みの信仰は、アブラハム、イサク、ヤコブという父祖たちの信仰を土台にイスラエルの民の中にあって継承されてきたものです。
しかし、旧約の歴史においてイスラエルの民はその神の恵みの選びに与ったにもかかわらず、神に背き、異教の神々にひれ伏し、罪を繰り返しその神の恵みを台なしにすることが繰り返されたのです。聖書のお言葉によるなら、神はねたむほどに、その民を愛しておられるがゆえに、彼らが立返るために下された審きは時にすさまじいものでした。
そのことを受けてパウロは、11章1節で「神は御自分の民(ユダヤの民)を退けられたのであろうか」と問います。又11節でも「ユダヤ人がつまずいたとは、倒れてしまったということなのか」と疑問を投げかけるのですが。すぐに「決してそうではない」と断言します。悔い改め神に立返って生きる道を選んだ「イスラエルの残りの者」。
この残りの者とは旧約時代に神に忠実に生きたイスラエルの人々、ユダヤ人たちのことを指しますが。同時にパウロは自分自身のようにイエス・キリストと出会い、救われたユダヤ人たちのことであったのです。いずれにしろ、神の恵みの選びは旧約聖書以来絶たれることがなかったし、今もそうだと言うのです。
イスラエルの民の歴史は不思議です。幾度も国を奪われ民も散らされ、もはや民族として存続し得ないような状況にありながら国を再建し、どこに住んでも何千年という歴史を神の民として生きてきた人たちを見るにつけ、イスラエルの民、ユダヤの人びとへの神の選びは、未だ変わっていないというパウロの言葉は非常に説得力があるなと思います。
いつの時代も、神を愛し、信仰をもって主の恵みに留まり続ける人たちがいます。それはたとえ木が切り倒されるような状況に遭遇しようとも、新たな若枝を芽吹かせる切り株のような人びとです。それこそパウロの言う「恵みによって選ばれた者」です。
私たちキリストの救いに生きる一人ひとりも、新約聖書にあるとおり、だれでも聖霊によらなければイエスを救い主だということは出来ないのです。それこそ一方的神の恵みであると言えましょう。
「異邦人の救い」
さて、パウロがイスラエルの民、ユダヤの人々について述べている事について読んでまいりましたが。次に本日の11~24節の個所であります「異邦人の救い」について読んでいきたいと思います。
はじめに申しましたように、この救いは神の恵みによってイスラエルの民にまず与えられたものであることに変わりございません。
しかしながら、11節「彼ら(ユダヤ人たち)の罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になった」。まあ独特な言い方ですが。決定的神の救いであるイエス・キリストを不信仰であったユダヤ人が十字架につけ、そのことによって全世界の人々に救いがもたらされるようになった、ということを言っているのでしょう。
使徒言行録13章44-46節にはこういう記述があります。
次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうと集まって来た。しかし、ユダヤ人はこの群集を見てひどくねたみ、口汚くののしって、パウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った「神の言葉は、まずあなたたちに語られるはずでした。だがあなたがたはそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに価しない者にしている。見なさい、わたしは異邦人の方へ行く。主はわたしたちにこう命じておられるからです。これはイザヤ書42章6節、49章6節を箇所からの引用として『わたしは、あなたを異邦人の光と定めた、あなたが、地の果てにまでも救いをもたらすために』」
この「あなた」とは勿論主イエス・キリストのことです。
異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして、永遠の命を得るように定められた人たちは皆、信仰に入った、と記録されています。
まさに異邦人への伝道の皮切りのところですが。このようにして、ユダヤ人たちが拒んだ主のみ救いが全世界に広げられていくようになったということです。こうしてパウロ自身がまずその異邦人伝道のパイオニアとなっていくわけです。
しかし、だからといってパウロのユダヤ人同胞への愛というのは決して無くなったというのではありません。10章1節に「彼ら(ユダヤ同胞)が救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています」と述べられているとおりです。
本日の11章25節以降読みますと、パウロはこの全世界に福音が告げ知らされ、主のみ救いが伝えられていくという異邦人への伝道は、究極的にユダヤ人・イスラエルの人々が主の救いに与っていくことにつながるという祈りと確信のうちになされていったのですね。
ところで、この手紙が書き送られた当時のローマの教会の構成は、大半が異邦人クリスチャンで一部がユダヤ人クリスチャンであったようです。ローマの教会の開拓時は少数のユダヤ人クリスチャンたちが中心的働きを担っていましたが。次第に異邦人のクリスチャンたちが多くを占め、その中心メンバーとなっていく中で、異邦人クリスチャンたちの声や力が教会において強くなり、逆にユダヤ人クリスチャンたちの立場は狭くなり、居場所がなくなるということが実際起こったようであります。それだけではありません。ローマの教会で異邦人クリスチャンがユダヤ人クリスチャンを、先に申しあげたようなことから見下し、自分たちこそ神に選ばれた者であると、おごり高ぶる者たちがいたようですね。まあ、そんなことがあるだろうかとお思いになるかも知れませんが。
この世界の歴史においてキリスト教でありながらユダヤ人を迫害するという蛮行が実際行なわれてきた事実を思う時、人間は罪深い者だなあと思います。
そこでパウロは、異邦人のクリスチャンを戒めて、18節「折り取られた枝に対して誇ってはならない」ということです。
つまり、ユダヤ人に対して誇ったり、見下してはならないという警告であります。
そもそも異邦人クリスチャンは、本来根であり幹であるイスラエルに与えられた恵みに接ぎ木されるかたちで福音に与っているということであります。
何も根が無いところから生えてきたわけじゃない。接ぎ木というのは、強く、水や養分を吸い上げる力が備わった木の枝を切って、そこに別の弱い品種をくっつけることで、それにゆたかに花や実を結ばせる方法です。そのようにして、異邦人クリスチャンは神の祝福に与る者とされた。ですから、ユダヤの人々に対して何も誇ることはできないのです。
異邦人クリスチャンの救いの根幹は、イスラエルに与えられた神の恵み。アブラハム、イサク、ヤコブの父祖たちから継承されてきた信仰であり、ただ神のあわれみによって神の民とされたことにおいて同様なのです。
ただ神のヘセド・憐れみの愛。キリストの十字架による救いの業により神の民とされたことを感謝します。パウロの言葉を借りますなら、「誇る者は主を誇れ」「十字架のキリストを誇れ」ですね。
私たちは神に対して何ができたか、何をしたから救われたのではありません。逆に罪からの解放と救いを必要とする者だからこそ、恵みをいただいている。何よりもそのことを感謝し、喜ぶ者でありたいですね。
20節「ユダヤ人は、不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています」。この不信仰とは、神の恵みに背を向け、究極のみ救いであるメシア、主イエス・キリストを受け入れなかったことであります。一方、信仰によって立っているとは、異邦人でありながらも、ただ救い主イエス・キリストにより頼んでいるあなた方、ということです。
そのうえで、信仰によって立っている異邦人クリスチャンのあなたがたに対して、パウロは20節「思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい」と進言します。
私たちは「救いのみ恵み」を台なしにすることがないようにしなければなりません。
21節「神は、自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、恐らくあなたがたも容赦されないでしょう」。
折り取られた枝に表されるユダヤの民の二の舞を私たち異邦人キリスト者が踏むことのないために、この教訓をしっかり心に留めていなければなりません。
同時に、一度折り取られたれ枝であっても、神の恵みといつくしみに真に立ち返るなら、神は再びその枝を接ぎ木してくださる。そういう御業を自由になさることがおできになるということであります。神にできないことは何もありません。
「神の救いのまなざし」
最後に、本日の箇所は「異邦人の救い」が語られていましたが、25節以降で今度は「
イスラエルの再興」という見出しで、全世界に向けられた神の救いの御計画について述べられています。
キリストの救いを信じることで救われる。それは行いによる義を厳守するユダヤの民にとってはあり得ないことであり、ねたみを起こさせるものです。
あのルカ15章の放蕩息子のたとえ話が思い起こされますね。
父の財産を使い果たして放蕩三昧をして帰って来た弟息子を父は叱りつけるどころか、喜び、受入れ、最上のもてなしをして迎えます。
兄息子はこんな待遇を私には一度もしてくれなかったと弟を非難し、そんな父親を強く
責めるのです。けれど、父は兄にこう諭すんですね。「子よ、お前はいつも一緒にいる。わたしのものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ」。父は弟と兄に憐れみを絶やすことはなかった。
このたとえは、父の神と息子の和解だけでなく、父の神の憐れみのもとにある兄と弟の和解への招きがとして語られているのですね。罪のゆえにゆるしと和解に与った弟。又そのはじめから父の神のもとにあるがゆえに、神の寛大な救いの計画を受入れることができない兄。
本日のローマ11章は始めに申しましたように「神はユダヤ人も異邦人も、すなわち全世界とご自身とが和解して、すべての人が救いに与る完成」のために、憐れみと恵みの御業を成し遂げようとしておられます。
この神の御計画に思いを馳せ、ただ主の憐れみによって御救に与っている者にふさわしく、感謝と畏れつつ、主の和解の福音を携えて、今週もこの礼拝からそれぞれの証の場へと遣わされてまいりましょう。