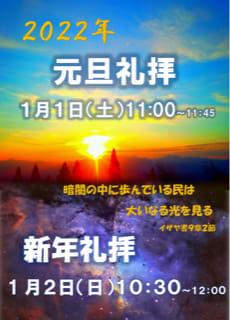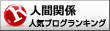歳晩礼拝宣教 ヨハネ福音書1章29-34節
今日は2021年最後の主日礼拝として主の守りと導きを感謝しつつ、お捧げしています。
本日はヨハネ福音書1章29-34節より、「世の罪を取り除く神の小羊」と題し、御言葉に聞いていきます。
今日の前の所には、主イエスにバプテスマを施した洗礼者ヨハネの証言が記されております。そこでは、ヨハネがエルサレムのユダヤ人たちに遣わされたファリサイ派の人たちに、「あなたは、どなたですか」と尋ねられると、ヨハネは「わたしはメシア(救い主)ではない」と否定します。更に、彼らはヨハネに「あなたは、エリヤですか」「あの預言者(モーセのような)なのですか」と尋ねると、ヨハネは「そうではない」とこれも否定します。そこで彼らは、「それでは一体、あなたは自分を何だと言うのですか」と尋ねると、ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて答えます。
「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。『主の道をまっすぐにせよ』と」。「主の道をまっすぐにする」とは、社会と世にあって生きる者が、神の前で自らを正して生きる、といってよいでしょう。
それを聞いて彼らはヨハネに「あなたはメシアでも、エリヤでも、またあの預言者でもないのに、なぜ、バプテスマを授けるのですか」と尋ねると、ヨハネは「わたしは水でバプテスマを授けるが、あなたがたの中には、あなたがたの知らない方がおられる。その人はわたしの後から来られる方で、わたしはその履物のひもを解く資格もない」と答えるのです。
このように、ヨハネは「主の道をまっすぐにせよ」と荒れ野で呼ばわる「声」だと、自らの使命がそのお方を指し示す声に過ぎないことを告げ、「あなたがたの知らないメシアが、わたしの後から来る」と証言します。
その翌日のことです。ヨハネは、まさにそのメシアである主イエスが自分の方へ来られるのを見て、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊」と認めました。新約聖書ではヨハネ黙示録はじめ14回小羊という言葉が用いられていますが、それはいずれも「主イエス」を指しております。
主イエスがおいでになる以前の、つまり旧約聖書の出エジプト記12章で、囚われのエジプト脱出の夜、イスラエルの家々を守ったのは、綴られたとおり「ほふられた小羊の血をその家の鴨居に塗った」ことによって、死の使いがその家々を過越し、彼らは災いを免れたのです。イスラエルの人々を世の力と滅びから解放したのはその「小羊の血」でした。
洗礼者のヨハネは、祭司ザカリヤとその妻エリサベトの間に生まれ、恐らく毎日神殿で人々の罪をあがなうための、引いてこられて屠られる牛や羊とその祭儀によって、神のゆるしを得た人々の様子を見て育ったのでありましょう。
洗礼者のヨハネはこの主イエスこそ、そのような祭儀、つまり儀式に遙かに勝って、世のすべての人に解放と救いをもたらすために来られた「神の小羊」であると証言したのであります。しかしヨハネ自身はまだ知らなかったでしょう。一体どのようなかたちでその救いが実現されるかを。
旧約聖書において、罪に滅びるほかなかった民の救いのため自らをささげる「苦難の僕」を描いたイザヤ書53章には、多くの者の罪を背負ってほふり場に引かれていく「小羊」が描写されています。その12節に「多くの人の過ちを担い/背いた者のために執り成しをしたのは/この人であった」とございます。そのお姿こそ正に、受難の道を歩んでくださったキリストそのものであります。人が何度犠牲の燔祭をささげようとも、人もこの世界も滅びに向かうほかない罪深いものであります。神の義と慈しみが世に示され、真実な悔い改めがすべての人にもたらされるために、神はその御独り子を世に遣わされる以外なかったのです。この主イエスが「神の小羊」として私たち人間の罪を自ら負い、肉を裂き、血を流し、死をもって、完全な贖罪、罪からの解放と救いをもたらしてくださった。いや今も十字架につけられ給いしままなるお姿としてもたらしてくださっているということであります。
洗礼者のヨハネは、「自分の方へイエスが来られるの見た」と29節にございますが。今日の礼拝の招詞として読まれましたイザヤ書62章11節の御言葉をもう一度お読みします。「見よ、主は地の果てにまで布告される。娘シオンに言え。見よ、あなたの救いが進んで来る。見よ、主にかち得られたものは御もとに従い/主の働きの実りは御前に進む。」この「あなたの救いが進んで来る」。その生ける言なるキリストを彼は確かに見たのであります。
洗礼者ヨハネの証言は続きます。32節「わたしは、霊が鳩のように天から降って、この方の上にとどまるのを見た。わたしはこの方を知らなかった。しかし、水でバプテスマを授けるためにわたしをお遣わしになった方が、霊が降って、ある人にとどまるのを見たら、その人が、聖霊によってバプテスマを授ける人である」とわたしに言われた。
主イエスが洗礼者ヨハネから水のバプテスマをお受けになる記述は他のマタイ、マルコ、ルカの福音書にもございます。それだけ重要であるということですね。
神の子である主イエスが、洗礼者ヨハネから水のバプテスマを受ける必要がなぜあるのか、という素朴な疑問を持たれる方もおられるでしょう。それはまず主イエス御自身が私たちと同じ人となられ、如何に神の前に生きるべきかを自ら示してくださったということです。先に申しましたように水のバプテスマは、神の御前に悔い改め、清めに与る中で、身を正して生きていく人の側の表明といえるでしょう。けれども主イエスはその水のバプテスマと同時に聖霊をお受けになられます。それは主イエスが聖霊によって世の人々にバプテスマを授けるお方であるということを表しています。そのことを洗礼者ヨハネ自身が知ることになるのです。(33節)
「人はだれでも水と霊によらなければ決して神の国を見ることはできない」(ヨハネ3章)と主イエスはおっしゃいました。罪の赦しと聖霊のバプテスマをお授けになる主は、神の小羊として私たち人間の罪を贖いとるために十字架の苦難と死を自ら負って神の栄光を顕わされたのです。
ヨハネ福音書には「栄光」という言葉がよく出てまいりますが。先週の箇所にも「わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた」とありました。それは世に言うところの繁栄や栄誉ではありません。
その栄光とはキリストの受難と死を通してすべての人に神の御救いがもたらされたことが「栄光」なのであります。
最後に、本日の箇所で洗礼者ヨハネが二度「わたしはこの方を知らなかった」(31節、33節)と繰り返していることについて、お話しをしたいと思います。
洗礼者のヨハネはイエスより半年先に生まれます。母マリアとエリサベトは親類であり、互いに胎に子を宿していた時も顔も会わせて互いに祝福を祈りました。その後もきっとヨハネとイエスは何らかの家族的な交流があったと想像されます。
ところがこのところで、ヨハネは「わたしはこの方を知らなかった」と繰り返して述べるのです。不思議に思いますが、それは人間的な付き合いによってヨハネはイエスのことをよく知っていたということはあると思うのですが。ここで言うところの知る、とはそういう次元のものではないのです。
ヨハネが本当にイエスさまがどういうお方であるのかということを実感したのは、まさにイエスさまが水でバプテスマを受けると同時に、天から鳩のように聖霊が降り、イエスさまの上にとどまるのを見たからであります。そこに圧倒的な神の臨在をヨハネ自身が体験したからであります。だからヨハネは「わたしはそれを見た。だから、この方こそ神の子であると証しした」(34節)のであります。
私は小学4年生の頃に、学校の友達に誘われて教会学校に通うようになりました。その時代の取り巻く環境から自分の心は結構すさみ、荒れ、どこか自分の居場所を探し求めていました。教会学校に毎週のように出席するようになり、中学生になると少年少女会に入り、同級の友だけでなく高校生のお兄さんやお姉さんたちとも交流する機会があり、教会のこと、信仰のこと、学校や友達のことなど語り合えたことが徐々に私のこころの居場となっていきました。そして私は高校1年のイースターの日に主イエスを信じて生きる信仰告白をし、バプテスマ(洗礼)を受けたのです。
しかし、その後の青年期、さらに社会人になってからも人間関係や仕事の問題で悩むこともありました。が、不思議なんですがその時々に聖霊の導きとしかいうことのできない必要な助けと支えを戴いて、42年目の信仰生活、またこれも神さまの恵み以外何ものでもありませんが、牧師として31年目を迎えております。それは実に高校1年の時に私なりのわかった分だけのありのままの自分を神さまにゆだねて生きる決心をして、バプテスマの恵みに与ったこの出発点があったからだと思うのです。
もし主と出会ってなかったら、、、。キリストの御名のもとにバプテスマに与ることなく古い自分のまま生き続けていたなら、、、、。私の人生は暗闇の中にさまよい光を見出すことなく滅びに向っていたかも知れないでしょう。
けれども、ゆたかな聖霊の働きと主イエスにある兄弟姉妹の交わりと証しを通して、神が共におられることを私は経験してきたのです。だから私も又34節にありますように「この方こそ神の子であると証ししている」のです。新しい年もお一人お一人に与えられた救いの恵み、その人生に中で経験する神のお導きと御業が証しされていきますよう、祝福をお祈りします。今年もこうして主に守られて皆様と共に歳晩の礼拝をささげることができました幸いを主に感謝し、主を賛美します。
「私たちの間に宿られたキリスト」ヨハネ福音書1章1-5,14
「メリ―クリスマス」、救いの御子イエス・キリストのご降誕おめでとうございます。
クリスマスは毎年12月のこの時期に世界中でお祝いされるようになっています。呼び名をホーリーディ聖なる日として宗教を超えての祝日となっているようです。今日はそのクリスマスの本来の意味をヨハネ1章14節「言は肉となってわたしたちの間に宿られた。」という御言葉を軸に、聖書から聞きとっていきたいと思います。
1章1節の冒頭には、「初めに言があった」と記してありますが。これは有名な天地創造」の記事である創世記1章の「初めに、神は天地を創造された」という記述から始まる御言葉を想起させます。今日のヨハネ1章3節に「万物は言によって成った。成ったもので言によらずになったものは何一つなかった」とあります。そのように神さまの創造の御業は、神ご自身が「光あれ」と宣言された御言葉によって始められ、世にあるすべてのものが造られたことを聖書は伝えるのです。
以前詩人の谷川俊太郎さんがある高校の生徒たちを対象に授業をなさったときの情景が新聞のコラムに掲載されていたのに目が留まりました。谷川さんが「言葉って、どこから出て来ると思う?」と生徒たちに問いかけます。「頭の中」かな、「心」かな、と首をひねる生徒たち。それ対して谷川さんは、「人は生まれてきたときには言葉を持っていない。周りの大人が使う言葉を学び、まねて、自分の言葉にしていく。実は言葉って、自分の外にあるものなんだ」とそう答えます。 私はそのやり取りに、なるほどなあ、と思いました。人は言葉を受け、それを蓄えて、自分の言葉となっていく。自分の外にある言葉と出会い、それに触れることを通して自分の内側が変えられ、自分が形成されていくものなのですね。まさに、人は自分の外にある言葉と出会い、それよって形づくられ、人間という存在となっていくのでしょう。聖書は神の言がすべての「命の源」であることを私たちに指し示し、そのいのちの言葉によって日々新たにされ、新しい人として生きるよう、私たちを招いているのです。
さて、1節に漢字の葉がついていない「言」が何度も繰り返して出てきます。この「言」とは原語でロゴスですが、英語訳の聖書では大文字で記されています。神御自身を表わすセオスと同様、大文字の表記となっているのです。
ですから「言」、ロゴスとは神と同格のものであることを示しているということであります。
創世記で「神が光あれ」と宣言すると、その「とおりになった」とありますが。その後に続く水、すべての創造の御業は、ロゴスなる「言」が発せられると、すべて実態をもった出来事となるのです。それは時満ちて新約という新しい時代の幕が開かれるまさにその時、ヨハネ1章14節に記されているとおり、「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」という出来事として世に現れるのです。
おわかりのとおり、その「言」とは2節の初めから神と共におられたイエス・キリストを表します。神は御独り子、イエス・キリストをこの世界に生きる私たちの間にお遣わし下さったのであります。 それは、私たち世に生きる者が、生ける神の言であられるキリストによって、12節「神の子」とされ、「神の子」(12節)とされ、神によって「生まれる」(13節)、すななわち、新しい命に生きる者とされるためであります。
その生ける神の言であられるキリストは、14節「言は肉となってわたしたちの間に宿られた」と伝えます。
この「宿る」という言葉には、テント(幕屋)を張るという意味があります。旧約聖書の出エジプトの時代、イスラエルの民はシナイの荒れ野の道を辿ることになります。その旅の途上、彼らは「テントを張って」神を礼拝したのです。それが聖所と呼ばれるものでした。彼らは荒れ野を行く先々で、神が自分たちのうちに住んでくださることを、テントを張って共に生活するなかで確認しつつ、荒れ野の旅を続けたのです。
イエス・キリストは私たち人間と同じ肉の体をとってこの世界に来てくださいました。そして、その生涯を通して苦しむ者、悩む者、世の権力に打ちひしがれて小さくされた者、弱っている者や病人、また罪人や汚れているとレッテルを貼られたような人たちを招き、交わりや食事を共にされました。こうして主イエスは喜びも悲しみも共に分かち合われました。
それはまさに、あのイザヤが預言した「暗闇に住む民は、大いなる光を見、死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた」という神の国の到来であります。
そして神の義と愛が全世界に現わされるあの十字架の受難と死に至っては、人の罪を自ら負い、底知れぬ暗闇のどん底にまで下り、ご自身を与え尽くされるキリストとなられたのです。キリストは父の神のもとを離れ。私たちの間に宿られたのです。
先日、私も関わっております大阪キリスト教連合会の研修会、「聖書とコロナウイルス流行」と題し、神戸改革派神学校校長である吉田隆先生のご講演をお聞きしました。その模様はユーチューブでもご覧になることができます。
その中で私が特に心に残りました先生の言葉を少しだけご紹介したと思います。
「この1年半のコロナ危機の中で私たちは大きく2つのチャレンジを受けている。1つは外的なチャレンジ、教会が集まれなくなった。教会はエクレシア:集会という意味。それが集まれなくなったのに果たして教会といえるのかはありますが。それでもインターネットの普及で外的チャレンジには工夫して乗り越えられるかも知れない。けれども、それよりももっと深刻な問題は、私たちの内側に起こってきた内的なチャレンジということです。このコロナ危機の中で、教会も「命を守る」、特に弱さの中にあるお年寄りの命を守る、そういう思いから教会の集まりを制限することになったと思いますが。外出を自粛するということによって、実際にはお年寄りの方々の肉体的な衰えが進んでしまう。あるいは認知症が進んでしまうことが起こっています。毎週、教会の集まりによって健康を維持できた方々が出かけないことによって、衰えてしまう。また、この1年半の間に、家にいることで精神的疾患が進んだ方、心の病が深刻となってしまった方もおられます。ご存じのように自死なさる方の数も急増しております。ソーシャルデスタンスということが未だに言われますけれど、それを訳すと「社会的な距離をとりましょう」ということで、おかしなことです。距離をとらなければならないのは物理的距離であって、社会的距離は本来とってはいけないんだと思います。そう考えますと、私たちは「命を守る」ためにといって一体何を守っているんでしょうか?私たちは何の命を大切だと思っているのでしょうか?」
これは大変深い問いかけであります。私ごとで恐縮ですが、私の母は一昨年の9月に亡くなりました。特養で容体が悪くなり救急搬送され病院に入院するも、コロナ禍で家族でも面会ができず、看取ることもできませんでした。私のように最期のお別れさえできない方々もきっと多くおられることだと思います。
先ほど、14節の「言は肉となって、私たちの間に宿られた」、その言葉の深さをおぼえました。生ける言であられるキリストは、実にすべての創造主なる父の神のもとを「離れ」、神と人との途絶えた関係性を回復するために世に来きて下さったのです。それだけではありません、キリストは「私たちの間に宿られた」。それは人と人を隔て、分断と孤立を生じさせる隔ての壁を打ち破って、人と人とのいのちの交わりが回復するために、キリストはお出で下さり、今も私たちの間にお住まい下さっている。これがクリスマスの大いなる恵みなのであります。
14節「わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた」。
それは何か華々しい功績や働きの中に栄光を見たというのではなく、私たち人間の罪と弱さのただ中に跳びこまれ、どこまでも共におられるそのお方の中に、確かな神の栄光を見るのであります。
昨今の世界、国内においてもいたましい事件や災害が後を絶ちませんが。このクリスマスが、全世界で暗闇の中に輝く光を見出す新しい歩みの始まりとなっていきますことを祈りつつ、共にいましたもうキリストにあって、このクリスマスから歩み出してまいりましょう。
祈ります。
慈愛にとみ給う主なる神さま、今日このように救い主、イエス・キリストの御降誕を祝うクリスマスの礼拝に招いてくださり、ありがとうございます。「言は肉となって私たちの間に宿られた」。そのあなたの御言葉によって、私たちはあなたのゆたかな慈愛と恵みを今日新たにいたしました。特にコロナ下にあって、今も距離をとることさえできずに、日夜勤務されておられる医療従事者の方々や諸処の施設で勤務なさっておられる方々のうえに、あなたのお支えと顧みがございますようお願いいたします。また、病床の友や、このところに集まりたくても集まることができなかった友のうえにも、あなたの恵みと祝福とを与えてください。主イエスの御名によって祈ります。アーメン。
礼拝宣教 ミカ書5章1-4節a アドベントⅢ
今年のアドベントは特に「神の平和」を覚える時として導かれていますが。
12月8日は真珠湾攻撃による太平洋戦争開戦の日でしたが。その指揮に当たった山本五十六氏の個人的手記がこのほど明らかにされました。その手記によれば当初は米英との講和の道を求めていたようですが、結局は最高司令部の指示に従わざるを得ず、あのトラ、トラ、トラの真珠湾の奇襲攻撃から太平洋戦争の泥沼になだれこんでいったということであります。敗戦後多くの先達の苦労と勤労努力、その功績によって私たちの国は復興を遂げ、幸いなことには過去の過ちを繰り返すことなく戦争を遠ざけてきました。その一方で近年グローバル化が進むにつれ、世界的規模で持つ者と持たない者の格差、貧富の差、その拡がりは日本も例外ではありません。世界も日本も経済的戦争と言われるような現況下、これは果たして平和といえるのかと考えさせられます。それはミカ書の時代と重なって来るように思えます。神への畏れとその掟と戒めが蔑ろにされていったところから滅びを招いていったイスラエルの民の歴史。そのところから、今を生きる私たちに向けて語られている神の言葉に聞いていくことは大事です。
ミカは南ユダの王ヨタム、アハズ、ヒゼキヤという3代の王が統治した時代に立てられた預言者でありました。サウル、ダビデ、ソロモンと続いたイスラエルの統一王国は、神に対する罪ゆえに南と北に分裂し、南北それぞれに王が立てられ、紀元前8世紀あたりまでは北も南もそれぞれに繁栄していたのですが、やがて北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、南ユダも常にアッシリアの脅威にさらされるという混迷の中におかれていたのです。
そういった大国の脅威に常にさらされる中、エルサレムの都市部では王や指導者たちの間で贈収賄の不正と汚職が繰り返され、民の間においては繁栄を願うための偶像礼拝が広がっていました。
それはエルサレムの神殿も例外ではありませんでした。宗教的指導者らはそれを阻止するどころか、利権と保身に走り、自らをまつりあげる者さえいました。さらに、交易や商業によって金を得て豊かになった裕福な者らは貧しい者たちを搾取していました。ミカはそうした時代の中で神の言葉を人々に語ったのです。
ミカは、ユダのエルサレムの都からずっと南西部の外れにあるモレシュトという農村に生れ育ち、貧しい農夫であったとも言われています。それだけに彼自らもそうですが、貧しい同胞の痛みや苦しみを身をもって知っていた人物であったのではないでしょうか。
ミカ書の1~3章において彼が語っているように、彼は神を忘れ、神の戒めを棄て、神を畏れない王や民に対して、神の警告に聞き従わない者にふりかかる災い審判を語り続けるのです。
このミカの預言に耳を傾けることがなかった南ユダの王や民は、4章の終わりにありますように、アッシリアに包囲されてあえぎ苦しみ、王は蔑まれ、その面目は失墜することになっていきます。
そのようにミカはユダの民に悔い改めを迫る一方で、今日の5章1節では「エフラタのベツレヘムよ/お前はユダの部族の中でいと小さき者。お前の中から、わたしのために/イスラエルを治める者が出る」と希望を語ります。世の力と勢力に押し流され、なすすべなく苦悩にあえぐことになる民に、ミカは安らかな憩いを与えてくださる新しい王、メシアが現れる期待を表明するのです。
このベツレヘムとは、不正と腐敗がはびこっていた大都市エルサレムとは対照的にごく小さな田舎町であります。けれども、そこはかつてイスラエルの偉大な王ダビデがお生まれになった町でありました。ミカより先に預言者として活動していたイザヤは、「ダビデの父エッサイの株からひとつの芽が萌えいで/その根からひとつの若枝が育つ」(イザヤ11:1)と、新しい平和の王、メシアの到来を預言しました。
ミカはさらにその平和の王が、いと小さき、取るに足りないベツレヘムの町、ユダのエフラタの部族のいと小さき者のうちから現れると、預言します。
実にここに、神御自身がそのご計画と目的を成し遂げるために、しいたげられ、苦しみあえぐようなる小さき者、取るに足りない者を選ばれたという「神の選び」が示されているのです。
そもそも神がイスラエルの民を選ばれ、あなたたちはわたしの「宝の民」だとされたことについて、申命記7章7節以降には、「主が心引かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった(新共同訳改訂版「少なかった」)。ただ、あなたに対する愛のゆえに」と書かれています。いわゆる世にいう選民思想というと、他より優れている、秀でているから選ばれるとなりますが。聖書の神の選びはそれとはまったく異なります。それは唯神さまの深い憐れみ、慈悲としかいうことが出来ないものなのであります。旧約聖書に登場する勇者ギデオンは、神に相対して「自分たちの一族はマナセの中で一番貧弱なものです。それにわたしは家族の中でいちばん年下の者です」と告白しました(士師記6:15)。又、サウル王は、神に相対して「わたしはイスラエルで最も小さい部族べニアミンの者ですし、そのべニアミンでも最小の一族です」と告白しています(サムエル記上9:21)。さらにダビデ王も又、8人の息子の一番末っ子でありましたが、神は王としてそのダビデを敢えて選ばれました(サムエル記上16:11-12)。
以上のように、神のご計画とその選びは、世の基準によるようなものではありません。
聖書は明らかに、小さき者であるがゆえに、自ら身を引きそうになるような者をあえて引き立てられるのです。それが「神さまの選び」であることを明らかにします。
それはまた私たちに対しても、自分が世にあってどんなに小さい存在か、役に立たないような者かと思う時、不安や恐れ、あるいは怒りを覚える事があるでしょう。気が重くなったりコンプレックスを感じたりすることもあるかも知れません。
コリント二、12章に、弱さを覚え涙する使徒パウロに、主は次のようにお語りになりました。「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ」。ここに神さまの祝福のお約束があります。
今日のこのミカ書においてミカは、苦しみにあえぎ、先行の見えないような状況に陥る小さきユダの民に向けて、いと小さき者のうちに神の御計画を遂行する新しい王、メシアが立てられるという預言を民に取り継いでいくのです。
2節にはこう記されています。「まことに、主は彼らを捨ておかれる。産婦が子を産むときまで。そのとき、彼の兄弟の残りの者は/イスラエルの子らのもとに帰る」。
ユダの人びとにとってアッシリア、バビロニアによるエルサレムの陥落とその捕囚の時代は、どれほど重苦しい時であったことでしょうか。彼らにとってそれは「神に捨ておかれた」ような苦難の時代でした。しかしそれは、産婦が子を生む産みの苦しみであり、時が来たら「残れる者はイスラエルの子らのもとに帰る」、まさに希望の約束であったのです。
旧約聖書のエズラ記2章によりますと、バビロニアの捕囚から帰還したユダの民の総数は42,360人であったと記されています。それは捕囚とされたユダの人々の数からすればほんの僅かな少数の人たちでした。その人たちは、預言者たちの言葉をずっと心に留め、捕囚という苦難を経ても、なお主の命の言葉に望みをおき、その教えを胸に約束の地エルサレムへと戻ったのでしょう。まさに彼らは「残りの者」であったのです。そして遂にエルサレムの神殿は再建され、神への信仰が復興されていきますけれども。ユダとその民を取り巻く情勢は非常に厳しく、その後のユダの民の歴史は幾度も周辺の大国に翻弄され続ける苦難の歩みが続くのであります。しかしそういう中で、このミカによって示された新しい王、メシアの出現の預言は、如何なる時もユダヤの民を支え、励まし続けたのではないでしょうか。 このミカの時代から700年余の年月を経て、ユダの地、それはまさに小さなベツレへムの町にその新しい王、救い主が遂にお出でくださったのです。立派なエルサレムの宮殿にではなく、みすぼらしい家畜小屋の飼い葉桶の中に寝かせてある、いと小さき乳飲み子の姿をとって。
この新しい王、救い主・メシアについて、ミカは3節以降でこう語ります。「彼は立って、群れを養う/主の力、神である主の御名の威厳をもって。彼らは安らかに住まう。今や、彼は大いなる者となり/その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそ、まさしく平和である」。
小さき者のうちから興される新しい王、メシアは勇ましい軍馬にまたがったいくさびとではなく、群れを養う牧者にたとえられます。一匹一匹を心にかけて養い世話をする羊飼い。また敵から守る王のような羊飼い。弱く、小さくされた者のうちに共に住まわれ、その苦しみや痛みを御自身のものとして感受なさるお方。「彼こそ、まさしく平和である」とミカは預言したのです。
私たちは何をして「平和」と言うのでしょうか。戦争のない社会。確かにそうでありましょう。しかし世に小さくされた人、神に依り頼むほかない一人ひとりが神とその養いによって平安に与っていくとき、そこに実に神の国の平和が訪れるのです。今日も神さまはこの群れを養う羊飼いのように、誰もが平和の主のふところにとびこんで憩い、平安を得るようにと、招き続けておられます。
本日は「小さき者のうちに」と題し、御言葉に聞いてきました。主が招き給う「神の選び」について、今一度その深い慈愛と恵みを思いめぐらしてみましょう。 「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選んだ」(ヨハネ15:15)と招き入れ、ご自身の栄光を顕す器、証し人として立てておられる主を賛美します。
次週はいよいよ主の御降誕を祝うクリスマス礼拝です。小さき者のうちに始まった主の救いの出来事が今や世界の出来事にまで拡がっています。確かに世には様々な苦難、また私たちの日々においても様々な問題は尽きませんが、小さき者のうちから現れてくださった平和の王、救い主の勝利がすべての世界と分かち合われていきますよう、希望をもって祈り歩む者とされてまいりましょう。
礼拝宣教 ミカ書4章1~4節 アドベントⅡ・世界バプテスト祈祷週間最終日
本日はミカ書4章より「終末の約束」と題し、御言葉に聞いていきたいと思います。「終末」というと、皆さんどういうことを思い浮かべるしょうか。
まあ巷でいわれる「終末」、それは人類が滅びに向かう世紀末、世界の終わり、人類の滅亡の時をイメージされている方も多いのではないでしょうか。確かに、国内外において近年著しく地震、災害、事件、疫病、加えて平和が脅かされている国々の状況が深刻化してきており、終末は近いと感じる方も少なくはないと思いますが。
ユダヤ教の「終末観」によると、それは長く続いてきた「悪の時代が終わる時」であるとされています。ユダヤ教の終末とその完成は「地上の悪」が絶頂に達するとき、神・ヤハウェがメシアを地上界へ派遣し、サタン(悪)の勢力を滅ぼし、神・ヤハウェが最終的な勝利を収める、メシアを王とする「新イスラエル王国」が実現されるものとされています。
一方、キリスト教では、旧約聖書に預言されたメシアはすでに来られ、天に昇られましたが、目には見えませんが今も共におられると信じています。罪の力に滅ぶ外ない世界と人類がメシアなるキリストの贖い、その救いの業によって新たにされている。そこに終末はすでに来ているのです。それは遠い未来のことではなく、キリストが到来されたその時からすでに始まっているのです。 ユダヤ教でもキリスト教でも終末は神の主権による完成の時であることに変わりありません。が、その完成の日が近づきますと妊婦が子を産むときの産みの苦しみのような苦難があることを旧約、新約両聖書に記されており、そこには確かな信仰の道を歩み通していくことの重要性が語られているわけであります。キリスト者にとりましては終末のときを生きながら、未だ訪れていない主の来臨(再臨)を待ち望みつつ歩みを続けているのです。
聖書には終末の最後の審判ということが書かれています。その審判はメシアなるキリストによって罪贖われ、愛と救いの恵みに与って生きる者にとりましては希望です。それは羊である私たちが羊飼いである神を知り、羊飼いが羊を見分けるように、神ご自身が私たちを知っておられるからです。又、キリストに罪贖われた者は、神が滅びの罪を裁かれるまったき義と聖なるお方であることを知っています。神以外に完全にきよいものはありません。すべての人の救いを願われる聖なるお方に信頼して歩む者にとって、終末はまさに希望の約束なのです。
では、今日のミカ書から「終末の約束」のメッセージを聞いていましょう。
1―2節「終わりの日に/主の神殿の山は、山々の頭として堅く立ち/どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かい/多くの国々が来て言う。『主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう』」。
このように、その日が来るとユダの民だけでなく様々な国の人たちが主を礼拝するために世界中から「主の山」「神の家」に集うという預言であります。
ご存じの通り、イエス・キリストの降誕、地上での公生涯、その死と復活と聖霊降臨のときから現在に至ります2千年間、聖地エルサレムには世界中から巡礼に訪れる人たちの流れが尽きることはありません。さらには「主の山」「神の家」が聖地エルサレムという物理的場所に限定されるのではなく、今や世界中のイエスを主、救い主キリストと信じる共同体が「主の山」「神の家」とされているのです。それは、キリストのお約束が実現し、聖霊なる神さまが世界の国々のどこにあっても主を求める人の間に分け隔てなく臨まれるのです。今日もこうして私たちも又「主の山」「神の家」に共に集い、「世界の王なる主」を世界中の同心の友と共に礼拝しているのであります。なんと素晴らしい恵みでしょうか。
2節にはさらに「『主は道を示される。わたしたちはその道を歩もう』とございます。
「主の道」とは「主の教え」と「御言葉」です。続く2節に「主の教えはシオンから/御言葉はエルサレムから出る」とありますように、主の山、神の家に集い、神を礼拝する人びとは、その「主の教え」と「御言葉」を聞き、それを行いながら歩んでいくようにと、諭しているのです。
それは具体的には十戒に代表される神の律法でありますが。それらは「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神を愛せよ」。又「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」との戒めに集約されます。
申命記8章のところには「人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉よって生きる」と記されていますが。人が人として生き、命を得るためにこそ、主は教えと御言葉を与えてくださるのです。また、キリストは「わたしは道であり、真理であり、命である」と言われました。私たちは、生ける御言葉であるキリストが、そのご生涯の歩みを通して現わされた「主の道」を、キリストに倣い、歩み通してまいりたいと願うものです。「主の山」「神の家」に集うものが「主の道を歩む」その時、魂の喜びと平安に与ることができるのです。
さて、4節には本日の宣教題である「終末の約束」が実現したその世界観について次のようなビジョンが語られています。
「主は多くの民の争い裁き/はるか遠くまでも、強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし/槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず/もはや戦うことを学ばない」。
1章の初めでミカは北イスラエルのサマリアと南ユダのエルサレムについて幻を見せられます。彼は同じく南ユダで活動した預言者イザヤより少し後になってから預言者の活動をいたします。イザヤは王に直接合って神から預かった言葉を訴えることができたように、ある程度地位のある人でありました。 一方のミカは民衆の一人として、南ユダの繁栄の陰に隠された重大な悪を告発し、訴え続けた預言者です。国の指導者たちは都市や国家の繁栄は計りますが、それは貧しい人たち、弱い立場の人たちの犠牲のうえに成り立っていたのです。政治家、宗教的な指導者の多くは腐敗し、自分たちの利権や地位を保全することばかりを考え奔走していました。
そういった有様をミカはよく見、身近に知っていたのです。神に聞き頼もうとはせず、大国との同盟を結び、国益を図ろうとおもねるような外交に走って行ったことが、遂に禍を招くこととなります。ユダの地とエルサレムは破壊され、略奪と民の捕囚という悲惨な結末を迎えます。
今日のミカの預言はもはや避けることのできないそうした絶望的状況を前に、それでもやがては「終末の時」、すなわち、先に申しました「神の業よる平和の実現」のときが必ず来る、という希望のメッセージなのです。
ここには、武器と農具の描写がでてまいりますが。戦時中は日本でも武器を作るために鍋などの金属が徴収されたと聞いていますが。それは生活のいわば人が生きるために必要な道具が、人を殺傷するための武器となって使われることのおぞましさであります。それがここでは、その戦争の道具、殺戮の武器となった剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とすると神自らがそのよう仰せになるのです。鋤と鎌といえば、庶民が農作物を生産していくための道具です。そこに人々の日常の暮らしと生活が取り戻されていくのであります。
ペシャワール会の中村哲医師が銃撃によって亡くなられてからこの12月4日で、2年となりました。中村医師は「水がないから食料がない、貧しいから争いが絶えず、患者が絶えないのだ」と、水の必要性を痛感なさって井戸を掘り続け始め、それがやがて一大灌漑用水となっていくのです。緑が茂った土地を見たとき、その住民がTVのインタビューで、「争いがないのでもう武器を手にしなくてよい」と語っていたのを以前見ましたが。まさに「武器が鍬や鎌」といった人が生きるための道具に打ち直されたように思ったものです。
中村医師は銃弾に倒れ、さらにアフガニスタンではクーデターが勃発しタリバン政権が統治するようになりました。灌漑用水はいったいどうなるのかと思いましたが。一昨日ニュースが飛び込んできました。タリバンの指導者の一人が会見し、中村医師のその働きに驚きと感謝を表し、この事業はアフガニスタンにとって必要な事業だと話していました。
預言者ミカが見たこの「終末の約束」は、今日の時代の中においても平和のビジョンとして高く掲げられています。ニューヨークの国連本部の入り口の所にこの「彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない」との御言葉が刻まれているのもそういった意味からでしょう。
確かに世界に目を向けますと、終末の完成、平和の実現の日とはかけ離れたような現実であります。が、であるがこそ、このミカが預かった御言葉に聞き従い、その来るべき日に向け、わたしたちも又、主の道を歩み続けるものとされていきたいと願うものです。
神はこのミカの時代から700年余の時を経、御子、イエス・キリストを全世界、全人類のメシア、救い主としてこの地上に遣わしてくださいました。 このお方によって世の権力、武力によらず、命の言葉、真理の御言葉を持って救いの業は実現し、神が真に望まれる平和の道が拓かれたのであります。
今日はこの後、主の晩餐が持たれます。エフェソ2章に次のような御言葉があります。 「あなたがたは、以前は遠く離れていたが、今や、キリスト・イエスにおいて、キリストの血によって近い者となったのです。実に、キリストはわたしたちの平和であります」。アーメン。主イエス・キリストの十字架に厳粛なる神の義、いつくしみ深い神の愛がすべての世界と人々に顕わされました。この救いの業をとおして神との和解、さらに人と人、国と国、全被造世界との和解という究極の「平和への道」が拓かれているのであります。
「多くの国々が来て言う。『主の山に登り、ヤコブの家に行こう。主は私たちに道を示される。わたしたちはその道を行こう』」。
この平和のキリストのご降誕を待ち望んでいくアドベントの時。私たちもその御声に聞き、平和の主、キリストの示される道を歩んでいく者とされてまいりましょう。