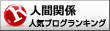礼拝宣教 Ⅰコリント8章1-13節
コリントは当時ギリシャの中心地として栄えていましたが、ギリシャ神話にありますように、まあ神々を崇めるため数々の偶像が町中の至るところにあり、多くの人がその偶像に供え物をするような風土でした。
コリント教会の信徒たちはそのような中で、自分たちの信仰を守っていました。
私の前任地の篠栗キリスト教会が建っています福岡県糟屋郡篠栗町は、九州の新四国霊場として町中に88か所の札所があり、春秋のシーズンになりますと九州各地から白装束を身にまとい杖をもったお遍路さんたちで賑わいます。篠栗町にはキリスト教会が篠栗教会ただ一つでありましたので、お遍路さんが88か所の札所を回り終った後に、ぜひともキリストの十字架を掲げる篠栗キリスト教会にて、唯一の神、万物の創造主、まことの救い主と出会って頂きたいという祈りをもって、福音宣教に励んでおりました。篠栗町にはこの天王寺と同様神社仏閣が多くありました。さらに、大きな涅槃像が建立され、いろんな地蔵もいたるところにありました。
そういうものを純粋な気持ちお参りなさる方々に対して、私は偶像を拝んでいると人々に対して裁くようなことはいたしませんでした。なぜなら、その方々の中には不治の病や難題を抱えておられるご家族のために、自分がお遍路さんになって巡礼されているという方がおられ、亡くなられた故人の魂が安らかであるようにとの切に願いながら札所を回っておられることを知ったからです。しかしだからといって、全天全地を創造し給う神さまが人が作った動かない石像や木像に宿るわけはありません。
かつて使徒パウロはギリシャ(アテネ)での伝道旅行の時(使徒17章22節以降)に、アテネの人々に次のように語りかけました。
「アテネの皆さん、あらゆる点においてあなたがたが信仰のあつい方であることを、わたしは認めます。道を歩きながら、あなたがたが拝むいろいろなものを見ていると、『知られざる神に』と刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それで、あなたがたが知らずに拝んでいるもの、それをわたしはお知らせしましょう。世界とその中の万物とを造られた神が、その方です。この神は天地の主ですから、手で造った神殿などにはお住みになりません。」
いくら科学や物理学が発展し進化しても、それらの研究が進めば進むほどすべてを構成している存在と意思を無視することができない、という思い至った学者は少なくありません。生ける神こそが、この世界と万物を創り、治めておられます。
又、偶像は何も仏像や仏壇、地蔵や観音に限りません。偶像を作り出すのは人であり、人の欲望や執着心、囚われた心が偶像を作り出していくのです。お金や財産、名誉や地位、権力。仕事、家庭ですら神よりも絶対的なものに成り代って崇拝対象となるのも、偶像を拝むことにほかなりません。
こうした世のものを絶対化し最優先するとき、神の御心に反する生き方に向かっていきます。それは他者や社会に対してもそうです。戦争や環境の悪化もその一つの事象であります。
聖書に戻りますが。当時コリントの町にはそのような偶像が多く立ち並び、祀られ、その参道が市場と化していました。お宮参りの観光地のように、露店が出て様々なものが売られ賑わっていたのでしょう。
コリントの市場で売られている物のなかには、ユダヤ人が律法で禁じられていた動物の肉や、ここで問題となった偶像に供えられてから卸された肉類なども並んでいたのでしょう。
律法に厳格なユダヤ人たちは、そういう肉などを一々詮索して、買い物をしたのです。
私も随分前にガリラヤとエルサレムに聖地旅行した折、ユダヤの方々が食事に関してのきまりを細かに守っておられる様子を伺い知りました。たとえば、かの地にはチーズ入りハンバーガーが売られておりませんでした。仔牛の肉をその母の乳で煮てはならないとの律法の書・レビ記の戒めを固く守られていたからだそうです。
先ほど読みましたコリントの教会には、ギリシャ人、ローマ人のほかユダヤ人のキリスト教徒もおりました。彼らの中には、「偶像に供えられたものは汚れているから、そういった食べ物を口にすべきかどうか」と悩み苦しんでいた人たちがいたのです。彼らが人の家に招かれて食事をする時も、偶像に供えられたものかを確認し、どう対処したらよいか迷っていました。ある人たちは食べても大丈夫だと言うし、別の人たちは絶対食べないと言うのです。彼らの日常生活はいつも悩ましいものでした。
この「偶像に供えられた肉について」、パウロ自らの考えを持っていました。それは今日読みました先に書かれています10章25節のところで次のように述べています。
「市場で売っているものは、良心の問題としていちいち詮索せず、何でも食べなさい。」
その根拠については、本日の8章4-6節で「世の中に偶像の神などはなく、また、唯一の神以外いかなる神もいないことを、わたしたちは知っています・・・・たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても、わたしたちにとっては、唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神から出、わたしたちはこの神に帰って行くのです。また、唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、わたしたちはこの主によって存在しているのです」と述べます。これがパウロの基本的なスタンスでありました。
ですから、それがたとえ偶像に供えられた肉であったとしても、イエス・キリストの御名によって神に感謝して頂く。「地とそこに満ちているものは、主のものだからです。」(10章26節)
ところでコリントの教会の一部の人たちは、こうした偶像の肉について「「我々は、知識を持っている」と誇り、良心が責められる人の前で平然と飲み食いしていました。
そのことに危機感をもったパウロは、7節のところで、「しかし、この知識がだれにでもあるわけではありません。ある人たちは、今までの偶像になじんできた習慣にとらわれて、肉を食べる際に、それが偶像に供えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるのです」と説明します。
この「汚される」と言うのは、懸念や疑い、惑う心が出ることによって、良いはずのものが損なわれてしまうという事です。
さらにパウロは9節で、「あなたがたのこの自由な態度が、(良心の)弱い人々を罪に誘うようなことにならないように、気をつけなさい。知識を持っているあなたが偶像の神殿で食事の席に着いているのを、だれかが見ると、その人は弱い(良心が弱い)のに、その良心が強められて、偶像に供えられたものを食べるようにならないだろうか。そうなると、あなたの知識によって、弱い(良心の)人が滅びてしまいます」と述べます。
心に確信が持てない人たち、ここでは「弱い人たち」と表現されていますが。その人たちは確信が持てないまま知識を持つ人の言葉のまま偶像に供えられた肉を食べ、後で後悔し、自分を責める人や信仰そのものにつまづく人がいたのです。
弱い良心の人が、あなたの知識と自由な態度によって滅びてします。これは衝撃的なことです。
1節で「知識は人を高ぶらせるが、愛は造り上げる」とありますように、たとえ信仰の知識を持っていても、すべての人に向けられた神の愛を知るのでなければ、人を傷つけ罪を犯すことになるというのです。
私どもの教会のほんのすぐ側に建っております宗教施設がありますが。私が着任する前から年に一度、そこの信徒さんが「お裾わけです」と赤飯をもっていらっしゃっていました。私どもの教会からもイースターにはイースターエッグをお届けしていたことから、こうした交流が始まったようですが。
しかし、私たちの教会の中で、その頂き物をどのように扱い、対応したらよいのか、という話になったことがありました。コリントの信徒たちと同様、「食べても問題ない」「いや食べるのは問題だ」という様々な意見がでました。教会で食べると、良心に呵責や抵抗を感じる方がいるのなら、それはどうだろうか。食べても大丈夫という方に持ち帰ってもらえばどうだろうか。みんなでいろいろと話し合われました。結果的には、感謝の気持ちで頂いたうえで、教会の通車場に勤務されている方にお渡しし、受け取っていただきました。
各々これが正しいと思うことはあっても、共に祈りつつ、最善を見出そうと努めることができたこと。又、主にあって良心が責められる思いをされている方とも思いを通わせてあゆむことができたのは、幸いでした。
パウロはローマの信徒たちに向けても、「何を食べてもよい」と主張する人たちに向け、「信仰の弱い人」を受け入れなさい!と強く勧告します。そして「その考えを批判してはなりません。信仰的な考えで野菜しか食べない人を軽蔑することが決してあってはならない」(ローマ14章)と述べます。
その一方で、「信仰的な考えで野菜しか食べない人は、食べる人を裁いてはなりません」とも述べます。
その人たちも、何を食べてもよいと信じていた人を裁くようなことがあった。自分が野菜しか食べないとしても、自由に肉を食べる人を裁く権利はないのです。「食べる人は主のために食べる。食べない人も主のために食べない。」その人その人それぞれの主との関係性、そのあり方で神に感謝を表す。そのことが何よりも尊いのです。
私たちは小さい時から、親から言われること、あるいは先生と言われるような人から「そうあるべき」「そうすべき」との指摘を、考えるいとまもなくただ受け入れて育ってきたという経験を持つ方は多いのではないでしょうか。幼少期から、大きくなって皆と同じようにとか。常識的にということが教えら育ってきた。社会生活をしていく上でのルール、決まりごとを大切にし、学習し、知識をもつことによって、考える力、判断する力が培われていったわけですけれども。その一方でそれらの染みついた知識によって、「こうあるべき」「こうあって普通、あたりまえ、当然」といった固定観念に縛られ、それを人に押しつけたり、逆にそのように生きることが出来ない自分を傷つけることも起こっていくのです。
以前、私がアンガーマネージメントの基礎講座を受ける機会があった折、講師の方から、「わたしたちのうちには怒りの根があり、『自分はこうあるべきだ』というものが、わたしたちを怒らせるものの正体だと」教えていただいたのですが。「自分はこうあるべきだ」ということを、私は意識、無意識のうちに自分とは異なる人にも同様にあてはめていないだろうか。だとするなら、わたしたちはいつも怒りの感情に支配され続けている、とそのことをまず知らされたのです。普段から自分の怒りがどこから来ているのか。怒りと向き合うということについて学ぶことができました。
イエスさまも時に、心の憤りや怒りを表すことがありました。宮清めの折に貧しい者たちが蔑ろに扱われていたことを怒られたのです。ここでは、何に対して怒られたかということが大事です。
又、律法を学んだことで高慢になった人が、律法を守ることの困難な人を裁いて、罪人と決めつけていることを非常に残念に思われました。「知識は人を高ぶらせるが、愛は造り上げる。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は、知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし、神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。」(1b-3)
イエスさまは律法とは、「神を愛すること。そして自分を愛するように隣人を愛すること」にそのすべてがあると、仰せになりました。また、「自分にしてもらいたいと思うことは何でも人にしなさい。これこそ律法と預言者である」(マタイ7章12節)と仰せになられました。
今週も今日のみ言葉を思いめぐらし、聖霊に導かれつつ、それぞれの場に遣わされてまいりましょう。