さきほど、こんなツイートをした。
(今はツイートじゃなく「Xにポストした」と言うべきか)
教員や医師、看護師、介護士など
「人助け系」の職業の労働環境は、
油断すると地獄の鬼もびっくりの阿鼻地獄👹になる。
この原因は「良心に付け込まれる」からだ。
医師や看護師であれば、
「苦しんでいる患者を見捨てて帰るのか?」
とでも言えば「カツアゲ」は完了である。
しかしここには、もっと厄介な問題が潜んでいて、
このシチュエーションで本当に
「生徒や患者を見捨てて帰れる人」は、
はっきり言ってこの仕事に向いていない、
という面も持っているところだ。
つまり優秀な人だけが潰されていく。
政府やマスコミ、有識者は、
この問題にもっと踏み込んで欲しいと思う。










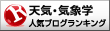


























これは教師や医師だけでなく、サービス業全般に当てはまることだと思います。
元々は本来その業務はやるべきことではなかったが、余裕があるときにサービス精神旺盛な従業員が始めた、あるいはすでに業務上必要な結果は満たしているのにより高い結果を目指した従業員がいたことから始まります。
それを見た管理職や顧客、地域住民が本来ボランティアだったサービスやより高い業務水準を当たり前と思うようになり、最終的には要求しだします。
その結果、本来やらなくてよかったものが強制化していくのだと思います。これが重なったり、時代の変化で業務量だけは増えていくのだと思います。
良心に付け込まれるのはこのような業務量の増大だけではありません。
記事にあるように「確かに直接の給与は出ないが顧客を見捨てるのか」というのもその一つです。同様に「自分の能力不足で時間がかかっているのに残業代を請求したり定時帰宅をするのはバツが悪い」というのもあるでしょう。
経営者・管理職側は「価格そのままで業務量を減らすと顧客や地域との関係性が悪くなる」という心配をしているのでしょう。とはいえ経営者はそればかり考えていたり、管理職は一般従業員からの昇進のためマネジメントスキルがうまくできておらず一人当たりの業務を減らすことができない。
「(ビジネスライクにやりたいなら)この仕事は向いていない」と管理職や先輩がよく言うことですが、自分が昔受けた仕打ちを押し付けているのだと思います。「苦しい思いは後輩にはさせないようにしよう」とはなかなかいかないようです。
ただ、日本の場合以下のような問題が出てくる可能性が高いので、改善が必要です。
・雇用問題:この手のコースは正社員はほぼない。多くは派遣・パート・アルバイトで、給与も時給制・ボーナスなしとなり、雇用の不安定・低収入に(どこかで見たが、この手のコースは年収300万が限界だとか)。
→同一労働同一賃金、福利厚生の同一化の徹底。建前でなく実質的な業務で判断。下に合わせるのでなく上に合わせる方で。
→現在の正社員・非正規のような分断された身分でなく、これらを複合させた制度に。非正規でもキャリアとみなされるようにする。
・情報共有問題:日本の職場は妬みと業務の押し付けで成り立っているため、「ろくに仕事しない奴には何も教えてやんない」と思われ、従業員間で情報格差が生じる可能性がある。そこで、必要な情報は常に文書化し(もちろんそのための要員も必須)、情報格差が生じないようにする。
・経営者と管理職:「働き方改革」=「いかに労働者が怠けるか」という感覚
・労働者(社畜):「働き方改革」=「働きたくない人の言い訳」「大量リストラの前兆」という意識
を取り去ることが必須です。
>ボランティアが業務に... への返信
そうですね。
本来は労働者の「温情」であったものを
おバカな経営者・使用者は「当たり前」と考えるようになり、
「温情をかけてくれて当たり前だろ」という態度になるのでしょう。
このようにかけばおかしさが浮き彫りになるのですが、
現実に起こっている現象の中では気づきにくいのが
また怖いところでもあります。
>まったり働きたい従業員のために... への返信
メンバーシップ型労働はもう限界でしょうね。
性善説に基づいたモデルですし、日本人の進化が
そこまで追いついていないということです。
学校でも、ある程度以上の学年は
レベル別に授業を行うことが多いですし、
仕事でもそうするべきでしょう。
徹底した同一労働同一労働が望まれます。
「電話対応一本で優3000円、良2000円、可1000円」くらいに
細かくジョブを分ける必要があるかもしれません。
>まずは…... への返信
「楽をするのは悪」という考えが諸悪の根源ですね。
「少しでも楽をしよう」という考えがなければ、
工夫、技術の進歩はありえません。
「苦労するのは美徳」であれば、たとえば
南米と北米の間に運河を掘るとなったときにも、
パナマ運河のようなものができるのではなく、
アメリカ大陸の一番横幅が太い所を掘る、
などという愚行に走りかねません……。