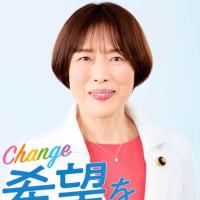Ⅰ: 10連休の実相
10連休とフランスの長期休暇バカンスの違い。
日本人が自ら休む権利を獲得したら、きっとこの国の世の中も余裕ある世の中になるだろう。労働3権は、戦後直後に先人が弾圧と闘いながら、二度と戦時中の翼賛政治社会を再現しないために闘い勝ち取った成果。いま基本的人権の労働権のありようはどうなっているか・・・
「掛け声だけの働き方改革」
誰のための10連休?貧富の差が拡大する中で中小企業や若い子育て家族は保育を頼み、保育所は政府の臨時開園で苦闘。貧しい者はより貧しく、富める者はより金持ちに。労組の最大のナショナルセンターである連合には、日本の弱者の声は聞こえない。政府は弱者を無視し怨念が沈殿してゆく。まともな労働権の主張すら口に出して言えないとしたら、弱者の怨念は、突然想像だにしない形態となって噴出することもないとは言えないだろう。鬱積する庶民の不満に、政府や大資本・大企業は真剣に向きあうべきだ。
Ⅱ:天皇ご夫妻と天皇制
美智子皇后が「国際児童図書年」での講演を、今は亡き出版人にして作家、思想家である小宮山量平氏から教えていただいた。
戦時中に弾圧された児童文学の編集者たち(ここでは山本有三氏らをさす)を間接的に支持するお言葉を知ってから、私は注目してきた。美智子妃を通じて天皇も変わってきた。ご夫妻を支持する。
だが、天皇ご退位の発表後から、世の中は神話と戦前の天皇制時代に急激に激変した。三種の神器、天照大神、神武天皇、まるでこれが昭和天皇の「人間宣言」を1945年直後に聴いた日本国民にとって70年も経ってからの公の出来事だろうか。あまりに皇室の「簡素に」「質素に」と言う声をかき消すようなスケジュールと 内容でことは進んでゆく。安倍晋三政府がおこなっていることは、【戦前並みの天皇制復活】作業でしかない。
きけ
わだつみの
こえを!!
Ⅲ: 差別とハンセン病、さらに・・
群馬交響楽団を今井正監督が戦後まもなく『ここに泉あり』で映画化した。群響は、学校など県内各地を演奏して回った。音楽をきく機会のない様々な場所も慰問し、県内のハンセン病施設も演奏に訪れた。
松本清張の小説『砂の器』の映画化で、野村芳太郎監督は加藤剛・加藤嘉両氏を親子役に充てた。多彩な俳優陣と東京交響楽団が映画のクライマックスで演奏する交響曲「宿命」とは、観客を感動させた。
戦前に、ハンセン病に罹患して、隔離施設に入り苦悶した青年北条民雄。彼の手紙と要望を真摯に受け止め、支え続け、小説『いのちの初夜』を世にだすために尽力したのは、既に「雪国」などで文壇に位置を確立していた若き日の川端康成だった。
ハンセン病患者への差別と迫害。日本だけでなく、外国にも差別とや偏見はある。
それを克服する営みが、世界人権宣言に至る人々の闘いとして、世界人権宣言や国際人権規約として世界の歴史に刻まれた。安倍政権の日本は、国連の人権部会や委員の勧告すら受け入れていない。
疾病に対する偏見も、ハンセン病にとどまらず、結核、肝炎、エイズとさらされてきた。
さらに現代にも続くうえに、疾病以外の領域にも差別や迫害はある。
故人となられた作家に井上光晴がいる。彼は小説『地の群れ』で、被爆者住民と被差別住民の反目と争いを描きだした。日本社会の実像が問われている。