都内の中学受験開始まで残り、50日。そろそろ受験生の親御さんたちは願書、受験料振り込みなどで奔走する時期。なんと筆者もその一人です。下記の塾を経営している後藤氏によれば、受験成功の秘訣は『「偏差値だけで学校を格付けしないこと」、学校を選ぶ際には、あれもこれもと求めすぎないことも大切です。』12月下旬の最終模擬試験の結果だけに捉われるのではなく、偏差値、進学実績、通学距離、学費、クラブ活動、敷地の広さなどを総合的に考慮し、判断する冷静さが必要です。9年前にも味わいましたが、子供の人生の重要な時期に過ごす学校を決める、落ち着かない時期です。
以下抜粋コピー
中学受験まであと50日。受験生の保護者にとって今一番の悩みの種は、受験校を決めることではないでしょうか?
「わが子には、どの学校が一番向いているのか?」「どの学校なら合格の可能性が高いのか?」。悩みは尽きません。少しでも“いい学校”に合格してほしいけれど、『チャレンジ』には“リスク”も伴います。
「合格可能性」は、テストの成績や授業中の様子からある程度、理にかなった判断をすることもできますが、ひとりひとりの教え子にとって「どの学校が一番向いているのか」「一番ふさわしい学校がどこなのか」は、30年以上この仕事を続けてきた私自身でも「よくわからない」というのが本音です。
なぜならば、入学後の中学・高校の6年間は、子どもがもっとも成長し、変化する時期です。その期間に学校生活を通じてどんな友だちや先輩、先生方と出会うかによって、成長の方向は大きく変わってくるからです。
“偏差値の高い学校”ばかりが成功への道ではない
私が常日頃、保護者の方々にアドバイスしているのは、「偏差値で学校を格付けしないこと」、そして「偏差値の高い学校に進学するのが『よい受験』だと決めつけないこと」の二つです。
保護者の中には、「偏差値の高い学校には、優秀な生徒が集まる。優秀な生徒の集まる学校に入学させれば、わが子が鍛えられ、『いい大学』にも合格できる」と考える方が多くいらっしゃいます。それは決して間違った考え方ではないでしょう。しかし、成功への道のりは「鍛えられて伸びる」ばかりではありません。
小学4年の時点で、かけ算の九九ができないレベルの「学力」だった女の子がいました。その子のご両親は「高校受験も難しいだろう」と判断して、「偏差値の低い」中高一貫校に入学させます。そこで彼女は、「周囲に、自分よりさらに勉強のできない子がいる」ことに気付きました。同時に、「このままじゃ……」と思って猛勉強を始めます。最終的には、その学校をトップで卒業し、今では幼い頃からの憧れだった職業に就いて活躍しています。まさに「鶏口となるも牛後となるなかれ」を地で行くような話です。
なにが幸いするか、それとも禍(わざわい)の元になるか。それは、神のみぞ知るところなのかもしれません。
学校に多くを求めすぎないで
もう一つ、保護者のみなさんにお願いしたいことは、「学校に多くを求めすぎない」ということです。
たとえば「わが子を医師にしたい」と思う保護者は、「医学部への進学実績が高い学校」の受験を勧めるかもしれません。確かにカリキュラムや選択講座の有無、受験指導のノウハウの蓄積に関しては、学校ごとに差があります。そして共通の志を持つ仲間がいれば、モチベーションが上がるということもあります。
しかし実際には、医学部への進学実績の高い学校に通ったからといって、予備校等に通わず医学部に合格できた教え子はほんのわずかです。医学部のない女子大の付属校に進学しながら、一念発起して、慶応大学の医学部に進学した教え子だっているのです。
進学実績だけではありません。「硬式野球部の強い学校に進ませたい」「海外留学に力を入れていて、国際人として活躍できる素養が身につく学校は?」「家から近くて、グラウンドの広い学校はどこ?」などなど、「わが子のために」という保護者の気持ちは痛いほどわかります。
しかし、親がせっかく苦労して探した“硬式野球部の強い学校”に進学した子どもが、テニス部に入部してしまった、というケースもあります。“国際人として活躍できる素養”といっても、たかだか3週間程度の短期留学で身につくかどうかは疑問です。JR山手線の内側で“広いグラウンド”を求めること自体が「ないものねだり」です。
学校を選ぶ際には、あれもこれもと求めすぎないことも大切です。
中高6年間の学校生活で身につけるべきこと
私は、中高の6年間というのは「集団生活の中で守るべきルールと基礎学力をしっかりと身につけさせる期間」「それらをベースに人間として成長させ、自立させていく期間」だと思います。もっと端的にいえば、「これからの自分の人生をいかに生きていくのかを考えさせ、学ばせ、そのための力を身につけさせる期間」ということです。
6年という長い時間ですから、部活動でいい汗を流し、文化祭や海外留学などのイベントを楽しみ、広いグラウンドで思いっきり走り回ってほしいと思いますが、6年後には、その場所から大学や社会へと「巣立って」いかなければなりません。
いつまでも学校の先生や両親が「与えてくれる」のを待つばかりではなく、手に入れたいものを「自分から選び、求め、手に入れる」ことを学んでいかなければ、自分の人生における「成長と自立」をなし遂げることはできません。その力を身につけることが、6年間で最も大事なことだといえます。
ですから、中学受験に臨むに当たって心得ておいてほしいのは、「偏差値の高い学校」を目指すことではなく、子ども自身に「これから何を学びたいのか」「何のために学ぶのか」「どんな人生を送っていきたいのか」「自分の夢は何なのか」をじっくり考えさせることです。そして学校選びを通して、子どもの人生について親子で本気になって考える最初の機会が、「中学受験」なのです。
「チャレンジ」がかけがえのない財産になることも
「偏差値にとらわれるな」とはいっても、「志望校の“偏差値”を安易に下げて、無理のない受験を勧めます」ということではありません。
中学受験は、子どもたちにとって人生で最初の“大きなチャレンジ”ですから、「当たって砕けろ!」くらいの気概を持って、「夢の実現に向けての挑戦を」というのが、私たちの基本的なスタンスです。
この年代の子どもたちは、遊びたい気持ち、怠けたい気持ち、勉強以外への様々な興味関心もあります。ですが、それを克服し、教師や両親のアドバイスに真剣に耳を傾け、志望校合格に向かって、少しでも自分の意思で歩み続けてほしいのです。
その「チャレンジ」の結果が成功であっても失敗であっても、その事実を真摯(しんし)に受け止めることができれば、その後の人生にとって、かけがえのない財産になります。
「生きるということ」を考える
少しでも偏差値の高い学校に合格する。「いい大学」に進学する。医師や弁護士になる。一流企業に就職する。自分の憧れの職業に就くことはとても大きな目標であり、「夢」でしょうが、それは「自分の人生をどう生きるのか」のほんの一部でしかありません。
もっと大切なのは、「医師になって何をするのか」「弁護士になって何がしたいのか」「一流企業で出世して、何を手に入れたいのか」を自分自身で考えることなのです。それが、「どう生きたいのか」「何のために生きるのか」という問いへの答えにつながります。
「自分と、自分の家族のため」「社会(他者)のため」。それは決して二律背反の答えではありません。もし私が「何のため?」と問われたならば、迷うことなく「両方」と答えます。
「中学受験」が人生で最も大切なことを考える最初のきっかけとなるのなら、それに勝るものはありません。受験の成否はちっぽけなもので、長い人生のなかのほんのささやかなエピソ
悩みのない親なんていない
世の中には、子どもに対する悩みがまったくない親なんて一人もいません。
「どの学校を目指せばよいかわからない」。いやそれ以前に、「何をやっても成績が伸びない」「何度、説教しても勉強しない」「親に反抗する」……。
そして子ども自身も、「なんでこんなに勉強しなくちゃいけないの?」「どうせ合格できるわけないよ」「どうして、パパもママもすぐに怒るんだよ」と、悩み苦しんでいるはずです。
わが子を愛するからこそ、厳しいことを言ってしまう親たち。親に認めてほしいからこそ、反抗的な態度をとってしまう子どもたち。
この構図は、中学受験をするしないにかかわらず、いつかどこかで必ず直面する親子関係のジレンマです。しかし、「反抗期」そのものが、「自分の足で歩きたい」という自立心のあらわれなのですから、むしろ、それは「成長と自立に向けてのチャンス」でもあるのです。
親としてできること
私たち大人、つまり親と教師にできることは、基本的にはどんな状況でも「応援」し続けることです。そして、子どもたちの「成長」を長い目で見守る覚悟をすることです。それしかできません。
お父さん、お母さんが「自分がどんなふうに生きてきたのか」「どんな失敗や挫折を経験し、どんな出会いやきっかけがあって立ち直れたのか」を語ってあげることは、子どもに人生で大切な何かに気付く「きっかけ」を与えられるかもしれません。
自分の人生を振り返りながら、「わが子に、どう生きてほしいのか」を語りかければ、子どもにふさわしい学校選択のヒントが得られる可能性もあります。











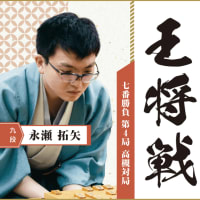















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます