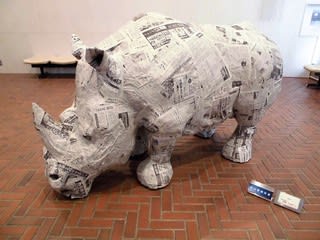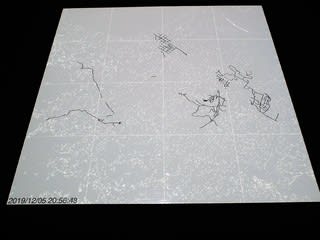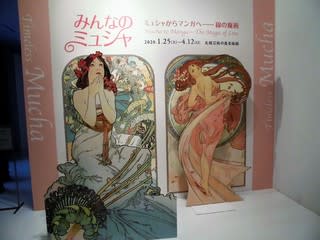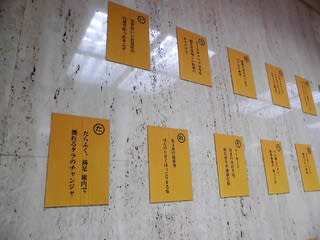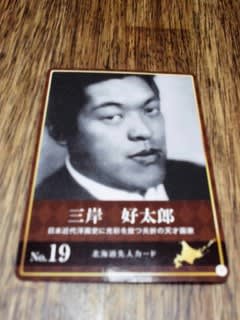■東京国立博物館「特別展 人、神、自然 ザ・アール・サーニ・コレクションの名品が語る古代世界」。カタール王族のコレクション展とのことだが、これが思いのほか素晴らしい展覧会であった。必見である(2/9で終了だが)。
「ラメセス2世像」:胸部のみの石像だが、かなり大きい。身長4mはあるな。
「王像頭部」:今度は赤碧玉の朱色を生かした小さな頭部像。細工が細かい。
「男性像頭部」:メソポタミア新シュメール期(紀元前2050年頃)のものだが、現代アート的なものを感じる。
「女性像頭部」:後頭部が長くひょろっとしている異形の像だが、それでも美しいことには間違いない。エジプト新王国時代、アマルナ文化のもの。
「ブレスレット」:エジプト第3中間期、第21王朝時代のもの。赤、青、金の配色で、今つけても全く不思議ではないデザイン。
「杯」:そこに女性の顔のレリーフがあり、それを彫るには相当大変だったと思われる。
「杯」:模様のあるメノウをそのまま杯の形にしたもの。
「飾り板」:中央アジアバクトリア・マルギアナ複合(←それ何?)のものだが、まあ、「カニ星人」と呼ぶしか無いような姿が刻まれている。
「仮面」:マヤ文明の仮面だが、ジョジョの奇妙な冒険の「スタンド」はこれを参考にしているのでは?
「女性像「スターゲイザー」」:アナトリア半島西部のもので、紀元前3300年~2500年くらいのもの。抽象彫刻というか、宇宙人が来ていたんだなというか。
「仏立像」:中央アジア後グプタ文化のもの。光背はもともと植物を表していたのかもしれない。
「アイベックス」:古代南アラビア文化の石像。本来より立派な角をしており、何かの象徴だったか。
「杯」:アケメネス朝ペルシアのもの。豹の顔をしたガラス製の杯で、貴重なものだろう。
「飾り板」:虎が描かれているのだが、その縞模様にラピスラズリやカーネソアン他の貴重な石が使われているもの。
「留め金」:ヘレニズム文化の驚くべき細かい彫金。

先が急がれるので、ここで本館に戻り、駆け足で展示室をまわる。
室生寺「釈迦如来坐像」「十一面観音菩薩立像」:本館の仏像彫刻コーナーは撮影不可のものが多くなってきた。いずれも撮影不可にして、国宝。
熊野速玉大社「橘蒔絵手箱及び内容品」:足利義満が奉納したもので、内容品がほぼ残っており、当時の化粧を知る上でも非常に貴重なのだとか。国宝。
京都・金地院「渓陰小築図」:今回の国宝室にはちょっと地味なこれが展示されていた。

この後、平成館の展示もサーッとみて、何とか東博は終了。最近、法隆寺宝物館に全く行けないのだが、とにかくちょっと見て回るだけで時間と体力を消耗する、恐ろしい東博マジックである。
続いて、恐る恐る東京都美術館へ。
■東京都美術館「ハマスホイとデンマーク絵画」。幸いなことに、待ち行列などはまったくなく、まあまあ快適に見ることができた。
ヴィルヘルム・マーストラン「フレゼレゲ・ラフェンベア(旧姓ヘーイロプ)の肖像」:デンマーク絵画はストレートな写実絵画が中心だ。結婚した女性の場合、必ず旧姓も記されているようだった。そういうルールなのかな。
クレステン・クプゲ「フレズレクスボー城の棟-湖と街、森を望む風景」:透明感のある広い景色は、北海道、さらには帯広を思わせる。
ダンクヴァト・ドライア「ブランスー島のドルメン」:ドルメンとは巨石記念物で、1830年代以降のデンマーク絵画によく登場するとのこと。
オスカル・ビュルク「遭難信号」:遭難の知らせがあったのだろう。不安顔で外を見る女性。漁師の生活は国が変わっても同じである。
オスカル・ビュルク「スケーインの海に漕ぎ出すボート」:ともすれば温和で平穏なものばかりに思えるデンマーク絵画だが、これは海の男の力強さを描いた作品。2017年に国立西洋美術館で「スケーエン:デンマークの芸術家村」という小展覧会が開かれたが、ここでは表記がスケーインに変わっている。外国語のカタカナ表記は難しいものだ。
ヴィゴ・ヨハンスン「台所の片隅、花を生ける画家の妻」:女性はこちらを向かずに花を活けている。親密派(アンティミスム)という感じだ。
ヨハン・ローゼ「夜の波止場、ホールン」:水のひんやりとした感じがする、北欧の夜の風景。2002年に北海道立近代美術館で開催された「スカンジナビア風景画展」(←これが良い展覧会だった)を思い起こさせるね。
ユーリウス・ポウルスン「夕暮れ」:スーパーリアル作品の一種にピントの合わない部分をあえて作る技法があるが、画面すべてにピントが合っていない不思議な作品。
ヴィゴ・ヨハンスン「きよしこの夜」:室内で明かりのついたクリスマスツリーの周りを輪になって女性と子供が囲んでいる作品。男性は登場しないものなのか。
ラウリツ・アナスン・レング「遅めの朝食、新聞を読む画家の妻」:若い頃は貧しい生活をしていたが、20歳年下の妻を迎え、明るい朝食風景を描いた作品。女性はピンク色のパジャマを着ており、今であれば「このリア充野郎が!」と非難を浴びることだろう。
カール・ホルスーウ「読書する女性のいる室内」:覗き見感までは行かないのだが、こちらに気が付いていない女性を見ている雰囲気ではある。
カール・ホルスーウ「読書する少女のいる室内」:光る机には少女の姿が写り込んでおり、銀器の表現なども実に上手い。
ギーオウ・エーケン「飴色のライティング・ビューロー」:これもビューローの反射具合など、実に上手い。
さて、ここからハマスホイである。展示室には大きな窓枠のような飾りがあり、室内というのを強くイメージさせる雰囲気になっていた。

ヴィルヘルム・ハマスホイ「夏の夜、ティスヴィレ」:地面が全体の1/5くらいしか描かれず、圧倒的に空の色彩である。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「古いストーブのある室内」:初めての室内画だそうで、黒いストーブと真っ白な扉の対比が印象的。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「夜の室内、画家の母と妻」:妻と言っても婚約者時代に実家を訪問した際の様子らしい。画家の母と妻の間には全くふれあいのようなものが感じられず、妙な空虚さと美しさと怖さがある。後で妻に「あなたのお母さん、私の事気に入らないようね!」かなんか、絶対言われていそうだ。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「若いブナの森、フレズレクスヴェアク」:ここまで来て、写実というよりもハマスホイの記憶のフィルタで一度ろ過されたものが描かれているのではないかと思うようになる。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「背を向けた若い女性のいる室内」:これぞハマスホイのイメージ通りの作品だ。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内-開いた扉、ストランゲーゼ30番地」:白い扉が3つも開かれた状態で描かれており、人の不在を強く意識させる。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内、蝋燭の明かり」:蝋燭の火が届く範囲を表しているのか、画面に楕円の領域があり、誰もいない室内で蝋燭が2本静かに燃えている。これは傑作だ。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「クレスチャンスボー宮廷礼拝堂」:四角い建物の上にある、ドーム状の屋根が印象的。淡い緑の色彩もいい。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」:画家が見ている所から、一室はさんでさらに向うの部屋に妻がいる。この距離感は何なのか。そして手前を見ると、机と錫のトレイが生々しい。

実に地味な画が多かったのだが、ハマスホイの作品の中には塗りのあっさりしたものと、かなり丁寧に塗っているものがあり、一見同じような感じでも良しあしは相当違うと思った。中に何点か、何の面白みもない構図に見えるのだが、見ていて見飽きない作品があるのだ。静かな印象の作品が多いので、比較的落ち着いていることができて、良かった。
最後に一言。「ハマスホイとは俺のことかとハンマースホイ言い」(字余り)。とにかく展覧会名を聞いた時から、これが言いたかった。これ以降、日本ではハマスホイで定着するのかな?
ミュージアムショップではデンマーク絵画ということで期待していたのだが、予想通りアクアヴィット(オールボー)が売っていた。しかし、市販の1.5倍くらいの値段だったので、バカバカしくて買うのはやめた。ハマスホイ系統のものは全体的にデザインが良く、Tシャツもかなり欲しくなったが、こういうところのTシャツは高い。断念である。
「ラメセス2世像」:胸部のみの石像だが、かなり大きい。身長4mはあるな。
「王像頭部」:今度は赤碧玉の朱色を生かした小さな頭部像。細工が細かい。
「男性像頭部」:メソポタミア新シュメール期(紀元前2050年頃)のものだが、現代アート的なものを感じる。
「女性像頭部」:後頭部が長くひょろっとしている異形の像だが、それでも美しいことには間違いない。エジプト新王国時代、アマルナ文化のもの。
「ブレスレット」:エジプト第3中間期、第21王朝時代のもの。赤、青、金の配色で、今つけても全く不思議ではないデザイン。
「杯」:そこに女性の顔のレリーフがあり、それを彫るには相当大変だったと思われる。
「杯」:模様のあるメノウをそのまま杯の形にしたもの。
「飾り板」:中央アジアバクトリア・マルギアナ複合(←それ何?)のものだが、まあ、「カニ星人」と呼ぶしか無いような姿が刻まれている。
「仮面」:マヤ文明の仮面だが、ジョジョの奇妙な冒険の「スタンド」はこれを参考にしているのでは?
「女性像「スターゲイザー」」:アナトリア半島西部のもので、紀元前3300年~2500年くらいのもの。抽象彫刻というか、宇宙人が来ていたんだなというか。
「仏立像」:中央アジア後グプタ文化のもの。光背はもともと植物を表していたのかもしれない。
「アイベックス」:古代南アラビア文化の石像。本来より立派な角をしており、何かの象徴だったか。
「杯」:アケメネス朝ペルシアのもの。豹の顔をしたガラス製の杯で、貴重なものだろう。
「飾り板」:虎が描かれているのだが、その縞模様にラピスラズリやカーネソアン他の貴重な石が使われているもの。
「留め金」:ヘレニズム文化の驚くべき細かい彫金。

先が急がれるので、ここで本館に戻り、駆け足で展示室をまわる。
室生寺「釈迦如来坐像」「十一面観音菩薩立像」:本館の仏像彫刻コーナーは撮影不可のものが多くなってきた。いずれも撮影不可にして、国宝。
熊野速玉大社「橘蒔絵手箱及び内容品」:足利義満が奉納したもので、内容品がほぼ残っており、当時の化粧を知る上でも非常に貴重なのだとか。国宝。
京都・金地院「渓陰小築図」:今回の国宝室にはちょっと地味なこれが展示されていた。

この後、平成館の展示もサーッとみて、何とか東博は終了。最近、法隆寺宝物館に全く行けないのだが、とにかくちょっと見て回るだけで時間と体力を消耗する、恐ろしい東博マジックである。
続いて、恐る恐る東京都美術館へ。
■東京都美術館「ハマスホイとデンマーク絵画」。幸いなことに、待ち行列などはまったくなく、まあまあ快適に見ることができた。
ヴィルヘルム・マーストラン「フレゼレゲ・ラフェンベア(旧姓ヘーイロプ)の肖像」:デンマーク絵画はストレートな写実絵画が中心だ。結婚した女性の場合、必ず旧姓も記されているようだった。そういうルールなのかな。
クレステン・クプゲ「フレズレクスボー城の棟-湖と街、森を望む風景」:透明感のある広い景色は、北海道、さらには帯広を思わせる。
ダンクヴァト・ドライア「ブランスー島のドルメン」:ドルメンとは巨石記念物で、1830年代以降のデンマーク絵画によく登場するとのこと。
オスカル・ビュルク「遭難信号」:遭難の知らせがあったのだろう。不安顔で外を見る女性。漁師の生活は国が変わっても同じである。
オスカル・ビュルク「スケーインの海に漕ぎ出すボート」:ともすれば温和で平穏なものばかりに思えるデンマーク絵画だが、これは海の男の力強さを描いた作品。2017年に国立西洋美術館で「スケーエン:デンマークの芸術家村」という小展覧会が開かれたが、ここでは表記がスケーインに変わっている。外国語のカタカナ表記は難しいものだ。
ヴィゴ・ヨハンスン「台所の片隅、花を生ける画家の妻」:女性はこちらを向かずに花を活けている。親密派(アンティミスム)という感じだ。
ヨハン・ローゼ「夜の波止場、ホールン」:水のひんやりとした感じがする、北欧の夜の風景。2002年に北海道立近代美術館で開催された「スカンジナビア風景画展」(←これが良い展覧会だった)を思い起こさせるね。
ユーリウス・ポウルスン「夕暮れ」:スーパーリアル作品の一種にピントの合わない部分をあえて作る技法があるが、画面すべてにピントが合っていない不思議な作品。
ヴィゴ・ヨハンスン「きよしこの夜」:室内で明かりのついたクリスマスツリーの周りを輪になって女性と子供が囲んでいる作品。男性は登場しないものなのか。
ラウリツ・アナスン・レング「遅めの朝食、新聞を読む画家の妻」:若い頃は貧しい生活をしていたが、20歳年下の妻を迎え、明るい朝食風景を描いた作品。女性はピンク色のパジャマを着ており、今であれば「このリア充野郎が!」と非難を浴びることだろう。
カール・ホルスーウ「読書する女性のいる室内」:覗き見感までは行かないのだが、こちらに気が付いていない女性を見ている雰囲気ではある。
カール・ホルスーウ「読書する少女のいる室内」:光る机には少女の姿が写り込んでおり、銀器の表現なども実に上手い。
ギーオウ・エーケン「飴色のライティング・ビューロー」:これもビューローの反射具合など、実に上手い。
さて、ここからハマスホイである。展示室には大きな窓枠のような飾りがあり、室内というのを強くイメージさせる雰囲気になっていた。

ヴィルヘルム・ハマスホイ「夏の夜、ティスヴィレ」:地面が全体の1/5くらいしか描かれず、圧倒的に空の色彩である。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「古いストーブのある室内」:初めての室内画だそうで、黒いストーブと真っ白な扉の対比が印象的。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「夜の室内、画家の母と妻」:妻と言っても婚約者時代に実家を訪問した際の様子らしい。画家の母と妻の間には全くふれあいのようなものが感じられず、妙な空虚さと美しさと怖さがある。後で妻に「あなたのお母さん、私の事気に入らないようね!」かなんか、絶対言われていそうだ。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「若いブナの森、フレズレクスヴェアク」:ここまで来て、写実というよりもハマスホイの記憶のフィルタで一度ろ過されたものが描かれているのではないかと思うようになる。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「背を向けた若い女性のいる室内」:これぞハマスホイのイメージ通りの作品だ。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内-開いた扉、ストランゲーゼ30番地」:白い扉が3つも開かれた状態で描かれており、人の不在を強く意識させる。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「室内、蝋燭の明かり」:蝋燭の火が届く範囲を表しているのか、画面に楕円の領域があり、誰もいない室内で蝋燭が2本静かに燃えている。これは傑作だ。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「クレスチャンスボー宮廷礼拝堂」:四角い建物の上にある、ドーム状の屋根が印象的。淡い緑の色彩もいい。
ヴィルヘルム・ハマスホイ「ピアノを弾く妻イーダのいる室内」:画家が見ている所から、一室はさんでさらに向うの部屋に妻がいる。この距離感は何なのか。そして手前を見ると、机と錫のトレイが生々しい。

実に地味な画が多かったのだが、ハマスホイの作品の中には塗りのあっさりしたものと、かなり丁寧に塗っているものがあり、一見同じような感じでも良しあしは相当違うと思った。中に何点か、何の面白みもない構図に見えるのだが、見ていて見飽きない作品があるのだ。静かな印象の作品が多いので、比較的落ち着いていることができて、良かった。
最後に一言。「ハマスホイとは俺のことかとハンマースホイ言い」(字余り)。とにかく展覧会名を聞いた時から、これが言いたかった。これ以降、日本ではハマスホイで定着するのかな?
ミュージアムショップではデンマーク絵画ということで期待していたのだが、予想通りアクアヴィット(オールボー)が売っていた。しかし、市販の1.5倍くらいの値段だったので、バカバカしくて買うのはやめた。ハマスホイ系統のものは全体的にデザインが良く、Tシャツもかなり欲しくなったが、こういうところのTシャツは高い。断念である。