「味のある本」として二冊 9月21日 のブログでした。
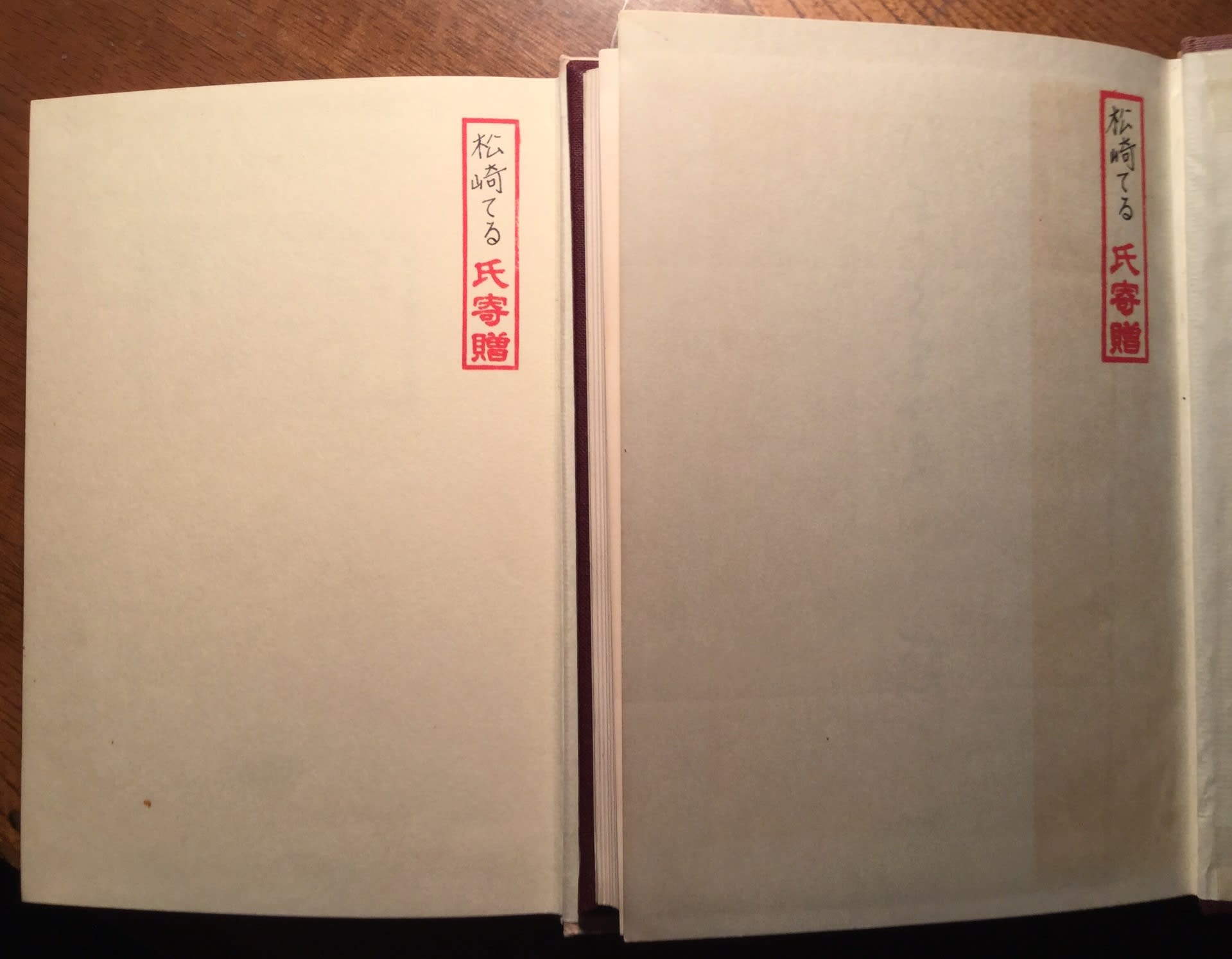
左の本『亀のごとく』を紹介した時、「上の二冊の右側が『くりや妻』で、未読ですので内容は後で触れたいと思います。」と書いていましたのでそのことと「夫・松崎貞次郎氏について触れなければなりませんので後日にします」とも述べていますのでそれについて書きます。
まず夫・松崎貞次郎氏について「松崎貞次郎」で検索しますと、

80年前の本の編者として名前がありました。著者の荒木貞夫については、
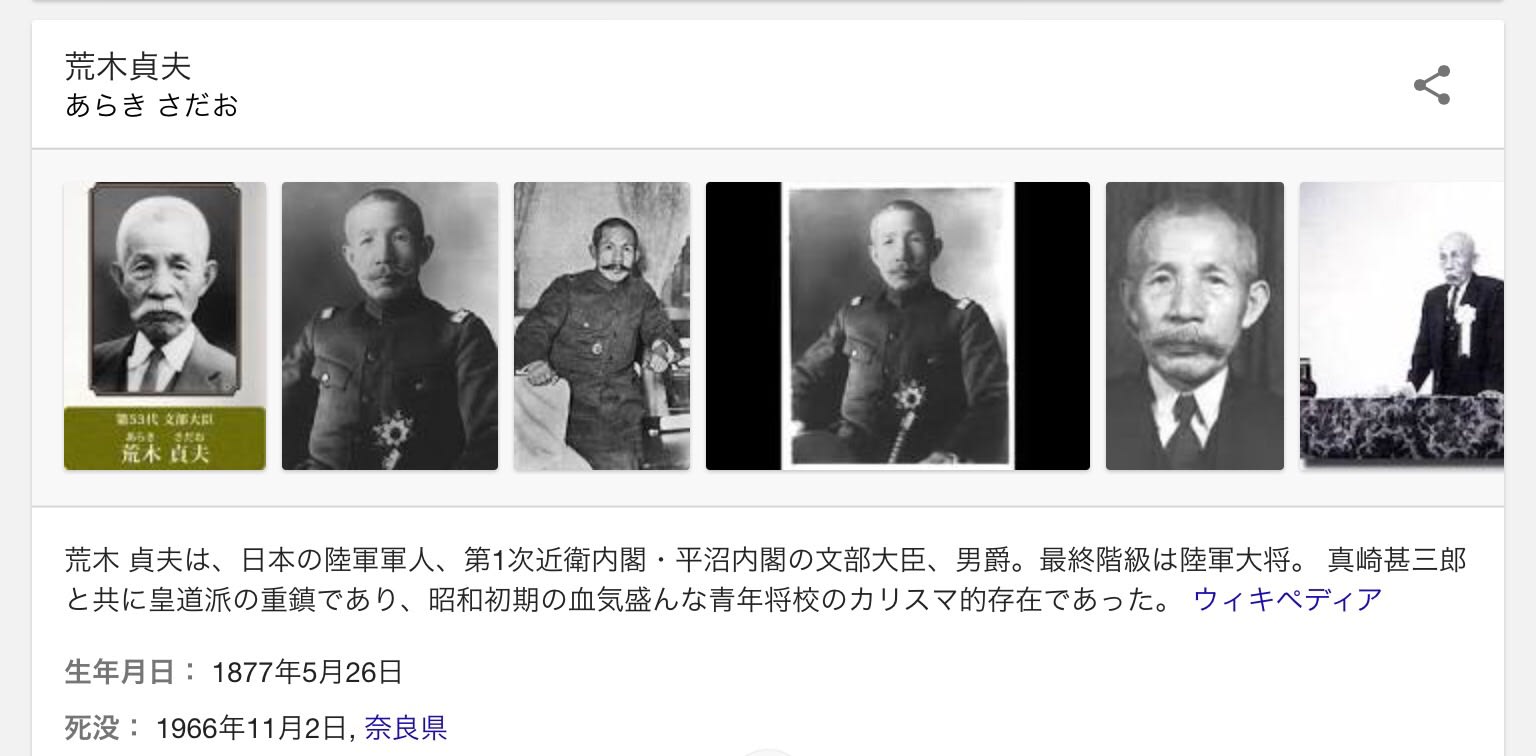
著者と本の名前からも少年少女への戦意高揚ものと思われます。
その松崎貞次郎について妻のてる女は、
【大正十年ごろであったと思う。島原(長崎県)中学二年生が「原内閣を倒せ」と獅子吼したのである。臨検席の巡査が忽ち「弁士中止」と叫んだ。沢山の聴衆もあっ気にとられて騒然となった。〜 その中学生が私の夫となった松崎貞次郎である。】
このあと「二人で上京し、同棲」「心の準備もなく結婚」し、てるさんは「萬朝報」に記者としては働くことになります、昭和四年頃です。貞次郎も新聞社に記事を提供する仕事に携わるようになっていました。記者を続けている時期でしょう、てる女は高浜虚子の文章会に列席するようになります。虚子もホトトギスを始める前に「萬朝報」につとめていた時期があり、爾来てる女の鎌倉へに移住もあり、生涯の師と仰ぐことになります。
貞次郎は通信配信の仕事が政治部で陸軍詰めになります、満州事変から山東出兵へと中国大陸への侵出を広げていく時期です。この山東出兵を1日早くスクープしたのが松崎貞次郎でした。そのこともあり長崎県の代議士の知遇を得て政界に関係することになりました。これが先に見た本の編者になる発端だったのでしょう。
話を今日の本『随筆 くりや妻』に移します。
一言でいうと先にこちらを読んでいたら『亀のごとく』は読まずに返していたかも知れません。てる女と貞次郎夫婦の波乱に満ちた前半の人生を知らなければ『くりや妻』への興味は半減していたでしょう。内容が詰まらないというのではありません。随筆として雅味というか趣のある筆運びです。それだけに二冊の内容の違いに興味が湧きます。
松崎てる女には「亀のごとく」の面と「くりや妻」の面があるのです。俳句をたしなみ虚子を師と仰ぐ鎌倉夫人、と左翼青年の妻であり新聞記者であったてる女、どのような人生にも時代の印したものの深さは一面ではつかみきれない、この人はこういう人だと思った時その反対面・意外と思える面へ関心を向けることが必要だということでしょう。
時代が矛盾に満ちていれば当然そこを生きてきた人間が一筋縄ではないことは当たり前なのですが……。















