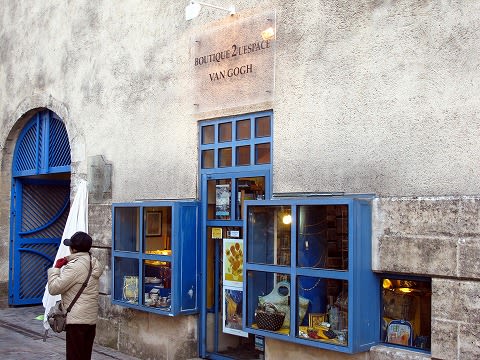サン・ジャン大司教教会 CATHEDRALE SAINT-JEAN

フルヴィエールの丘の麓に12世紀から13世紀にかけて建てられたこの教会は、ロマネスクから
ゴシックへの移行期だったため2つの様式が入り混じっています。
写真はソーヌ川に架かる橋の上から見たサン・ジャン大司教教会。丘の上のフルヴィエール
教会とともに二つの教会が見られるビュー・ポイントです。

有名な天文時計 L’horloge astronomique。
14世紀に造られたフランスで最も古い天文時計だそうで、今でも毎日4回、美しい音色
とともに上の人形たちも動き出して時を告げています。

祭壇の左手奥にあるマリアの礼拝堂。ペテロとパウロの生涯を描いたステンドグラス。

そのステンドグラスの解説板です。

丸天井とステンドグラス

キリストの生涯を描いたステンドグラスの一部。近くにルイ9世が葬られています。

ソーヌ川を渡ってリヨンの繁華街へ向かいます。

ベルクール広場 PLASA BELLECOUR
17世紀に作られた広場に立つルイ14世の騎馬像と、新しい大きな観覧車が不思議な雰囲気を
醸し出しています。

しばらく辺りをぶらつくうちに、すっかり暗くなりました。

今日の夕食はポーク料理のレストランへ。


店中、ブタだらけでウェイターもジェスチャーたっぷりで面白い店でした。

フルヴィエールの丘の麓に12世紀から13世紀にかけて建てられたこの教会は、ロマネスクから
ゴシックへの移行期だったため2つの様式が入り混じっています。
写真はソーヌ川に架かる橋の上から見たサン・ジャン大司教教会。丘の上のフルヴィエール
教会とともに二つの教会が見られるビュー・ポイントです。

有名な天文時計 L’horloge astronomique。
14世紀に造られたフランスで最も古い天文時計だそうで、今でも毎日4回、美しい音色
とともに上の人形たちも動き出して時を告げています。

祭壇の左手奥にあるマリアの礼拝堂。ペテロとパウロの生涯を描いたステンドグラス。

そのステンドグラスの解説板です。

丸天井とステンドグラス

キリストの生涯を描いたステンドグラスの一部。近くにルイ9世が葬られています。

ソーヌ川を渡ってリヨンの繁華街へ向かいます。

ベルクール広場 PLASA BELLECOUR
17世紀に作られた広場に立つルイ14世の騎馬像と、新しい大きな観覧車が不思議な雰囲気を
醸し出しています。

しばらく辺りをぶらつくうちに、すっかり暗くなりました。

今日の夕食はポーク料理のレストランへ。


店中、ブタだらけでウェイターもジェスチャーたっぷりで面白い店でした。