以前読んだジョゼフ・カルメット『ブルゴーニュ公国の大公たち』(国書刊行会)はとても面白い本であったが、フランス史から見たブルゴーニュ公国はどうなのだろう?と、ジュール・ミシュレ『フランス史【中世】Ⅴ』(第5巻)を図書館から借り、ようやく読み終えた。
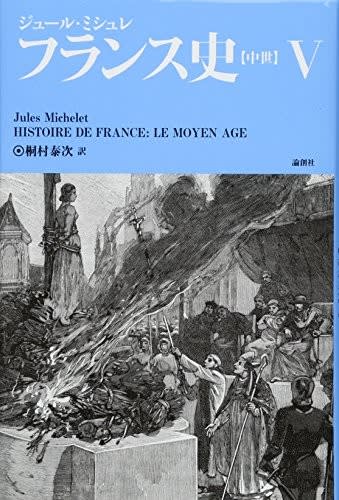
ジュール・ミュシュレ(Jules Michelet, 1798-1874年)は19世紀フランスの歴史家であり、まぁ、なんと!「ルネサンス Renaissance (仏)」の造語者とされている。現代における歴史家としての評価はわからないが、アナール派に影響を与えたと言われており、私的にもなにやら頷けるものがある。
さて、【中世】Ⅴは百年戦争期を扱っており、英仏の思惑と攻防、そして、フランスという国家の統一までを描く。もちろん、フランス王と対立するブルゴーニュ公の思惑も、ジャンヌ・ダルクの奮闘と悲劇も登場する。ミュシュレの描く乙女は瑞々しくも賢く美しい。
しかし、私的にⅤで特に興味深かったのは、ブルゴーニュ公のフランドル支配におけるフランドル諸都市との軋轢の理由の一つとして、ゲルマン法とローマ法の違いに言及していることだった。
「低地ドイツだけでなくドイツ人全般にいえることだが、彼らは、わたしたちのような他のどこかの人間(autres welches)とくに成文法しか頼りにしない疑い深い南国人には、あまり敬意を抱かない。彼らにとって法律は人間の良心と誠意への確固たる信頼に基づくもので、耳で聴くものであった。フランドルで重要な裁判集会は、自由な人間が真理を共有するための集いであり、あくまでも「真理の率直で平和的な解明」をめざすものであった。各人は、たとえ自分にとって不利であっても、ほんとうのことを話さなければならなかった。実際は必ずしもそのとおりでなかったとしても、これがゲルマン法の理想であった。・・・しかし、フランドル伯とブルゴーニュ人やフラッシュ=コンテ人の法律家たち(レジスト legistes)は、こうしたフランドル人原初的規範を理解しようとは全くせず、これらの言葉のフランドル的意味を無視して、あくまでローマ法的に解釈し、行政官(magistaras)を任命し、そこから「loi(法律家・代訴人)」を選べば充分であると考えた。」(p320~p321)
確かに、ブルゴーニュ公国はフランスの高等法院のシステムをフランドルでも採用しているからね 。
。
そして、もう一つ私的に興味深い記述があった。
「ブルゴーニュ公は、その公国においても、フランスにおいても、あくまで政治的封建体制の首長であり、ほんとうの意味での封建領主ではまったくなかった。本来の封建制度の法を作りあげていたもの、領民をして自分たちに重荷をかけてくる人々に尊敬と敬愛の気持ちを抱かせていたもの、それは、領主が根底的に土着の人だったということである。すなわち、領主一家がその土地で生まれ、その土地に根を下ろし、みんなと同じ生活をしている人、いうなれば『ゲニウス・ロキGenius loci』(訳注・土地の神霊、氏神)だったからである。ところが、その全てが、十五世紀には、結婚や相続、王からの贈与などのために覆されてしまっていた。」(p368)
フィリップ・ル・アルディとフランドル女伯マルグリットの結婚により、フランドルはブルゴーニュ公領に編入された。が、ここで私が「おおっ!」と呻いてしまったのは『ゲニウス・ロキGenius loci』が登場したからである 。
。
以前、H先生の講座で紹介された、鈴木博之『東京の地霊(ゲニウス・ロキ)』を読んだことがあった。

鈴木先生(H先生の先生)の「ゲニウス・ロキ」は、ある土地から引き出される霊感とか、土地に結びついた連想性、あるいは土地がもつ可能性といった概念を言っていた。なので、池上俊一『フィレンツェ- 比類なき文化都市の歴史』(岩波新書)を読んだ時も、これはフィレンツェのゲニウス・ロキについてではないかと思ってしまった 。
。
しかし、このミシュレの「ゲニウス・ロキ」についてを読むと、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」の坂東武者なんて、まさしく土地に密着した「ゲニウス・ロキ」の関係なんじゃないかと思えてしまうのだよ。氏族は土地の名前だしね。
ということで、次は「中世 Ⅵ」(第6巻)を読まなくちゃ。ルイ12世とシャルル・ル・テメレール の確執と、ル・テメレールの死が描かれているはずだから。そして、できたら続けて「Ⅶ ルネサンス」(第7巻)も読みたいな 。
。



















