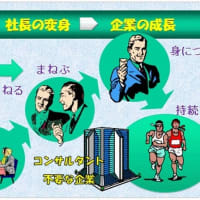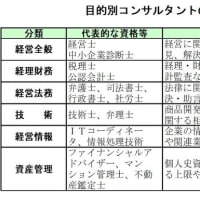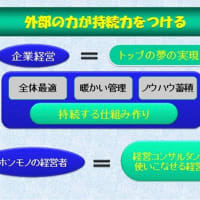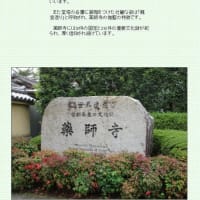■【日本庭園を知って楽しむ】5-06自然風景式庭園 船着(き) (ふなつき)
若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間に旅をしたのか、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。
*
旅のテーマは寺社や庭園めぐりです。
*
日本には「日本庭園」と呼ばれる庭園だけではなく、「イングリッシュガーデン」など、海外の庭園形式をした庭園も多数あります。寺社を訪れたときに、想定していなかったところに、庭園を発見することがあります。
下手の横好きで、【カシャリ! ひとり旅】を続けていますが、その一環で訪れた庭園を順次紹介してまいりたいと思います。
*
■■5 庭園を見る視点・要素 自然風景式庭園
庭園を鑑賞するにあたり、庭園を構成するものが、どの様な意味合いを持つのかを知っているのと、そうでないのとでは、鑑賞の度合いが大きく異なります。
ここでは、自然風景式庭園を構成するものについて、その鑑賞のための基本的な知識を持っておきたいと考えます。
*
■5-06 船着(き) (ふなつき)
自然風景式庭園には、池泉がつきものです。庭園生活を豊かにするために、古くから船遊びに興じていたようです。その際に、舟を着けて乗り降りするための施設を『舟着』と呼びます。
平安時代の寝殿造庭園で発展し、釣殿から乗船し、管弦の楽人が同行し、飲めや歌えやの大騒ぎがあったという記録もあります。
室町時代には「西芳寺」の合同舟(ごうどうぶね)という舟着場が作られました。それを模して、「東山殿(現銀閣寺)」の夜泊舟(よどまりぶね)という屋根付きの舟小屋がつくられました。浄瑠璃寺の庭園(浄土式庭園)には、池岸に階段が設けられ、ここから中島の弁財天祠に渡ります。
近世では、書院造系庭園として、太閤秀吉の伏見城には、「舟入御殿」がありました。それを西本願寺の「飛雲閣」に移築し、舟から直接建物に出入りできる舟入(ふないり)の間として残っています。
「桂離宮」では御舟小屋だけではなく、ほかの主要な建物や池岸に舟着がありました。ここから桂川に舟を出し、丹後や有馬などの、当時の観光名所にまで脚を伸ばしたそうです。御船小屋の中には、「歩月(あゆみづき)」という舟があり、桂川でお月見をしました。

*
(【Wikipedia】、宮元健次氏、重森完途氏・コトバンクを参照して作成)
*
■ 日本を代表する庭園
都道府県別
リスト http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm
- 写真・旅行
- 【カシャリ!ひとり旅】 北海道
- 【カシャリ! ひとり旅】 青森
- 【カシャリ! ひとり旅】 岩手
- 【カシャリ! ひとり旅】 秋田
- 【カシャリ!ひとり旅】 福島
- 【カシャリ!ひとり旅】 宮城県
- 【カシャリ!ひとり旅】 山形県
- 【カシャリ!ひとり旅】 茨城
- 【カシャリ!ひとり旅】 埼玉
- 【カシャリ!ひとり旅】 群馬県
- 【カシャリ!ひとり旅】 神奈川県
- 【カシャリ!ひとり旅】 東京散歩
- 【カシャリ!ひとり旅】 静岡県
- 【カシャリ!ひとり旅】 山梨県
- 【カシャリ!ひとり旅】 兵庫
- 【カシャリ!ひとり旅】 京都
- 【カシャリ!ひとり旅】 北陸
- 【カシャリ!ひとり旅】 九州
*
![]()
ユーチューブで視る 【カシャリ!庭園めぐりの旅】
写真集は、下記URLよりご覧いただくことができます。
静止画: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmeisho.htm
映像: http://www.glomaconj.com/butsuzou/meisho/indexmovie.htm
【 注 】 映像集と庭園めぐりは、重複した映像が含まれています