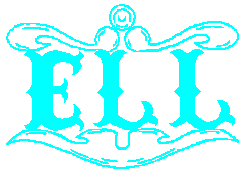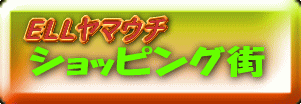日々のパソコン案内板
【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)
【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】
【PDFの簡単セキュリティ】
【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】
【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】
【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】
【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】
【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】
【手書きで書くように分数表記する方法】
【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】
【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】
【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】
私がまだ26~7歳頃のことなのですが・・・
当時、婦人服の小売店を営んでいたんですね。
当時の店舗に管轄の派出所の方が時たま巡回で訪れるようになり・・・
そのうち、歳も近いということもあり彼らと個人的にも親しくなったんです。
と・・・ある日、そのうちの一人の警察官の方が
「一口〇千円の出資で知り合いを勧誘していけば儲かるし、これはネズミ講じゃないから大丈夫」・・・と
私はそのような投資話には興味がないと断ったのですが・・・
その数年後、その会は摘発されてました・・・その時、警察官も引っ掛かるんやね~とおもいましたね。
時は流れ・・・40数年経っていても未だにこのような話が横行してるんですね・・・
皆さんも甘いもうけ話には決して乗らないようにしましょうね。
例え一時儲かったとしても、あぶく銭なんてものは決して残る筈もないわけですから・・・ね!!
今朝はマルチ取引に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、9月13日読売新聞朝刊より抜粋~



 「今にして思えばメリットしか見ていなかった」。山梨県の男子大学生(21)は、後悔の念で一杯だ。
「今にして思えばメリットしか見ていなかった」。山梨県の男子大学生(21)は、後悔の念で一杯だ。
昨年12月、高校時代の先輩に「必ずもうかる」と誘われ、投資商品に30万円を支払った。しかし、その後一度も配当がない。状況を聞くと「今度はいける、年利で300%だ」と別の投資を持ちかけられた。配当は仮想通過で、仲間を誘えば「ボーナス」もつくという。1口27万円の商品を2口申し込んでしまった。
今度はパソコン上では配当が順調に増えていた。しかし、いざ換金を申請しても業者は応じず、先輩に尋ねても「待て」の一点張り。この夏、弁護士に相談して「だまされた」と悟った。大切な親の仕送りやアルバイトでためた計84万円は戻らぬままだ。男子学生は「甘かった。しかし信頼させておいて裏切る行為は許せない」と憤る。
中でも最近は「HYIP」(ハイプ)と呼ばれる投資の情報がインターネットで飛びかう。「High Yield Investment Program」(高配当投資プログラム)の略で、通常では考えられない高金利をうたい、仲間を勧誘すれば、さらに儲かるとの触れ込みだ。大半が詐欺とみられる。男子学生が誘われたのもHYIPだった。相談を受けた弁護士の荒井哲朗さんは「経済常識に反しており、まっとうな投資ではない」と話す。荒井さんら弁護士有志は被害対策弁護団を結成。8月の締め切りまでに全国から200人超の参加申し込みが殺到した。
ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)も被害を拡大させている。
2015年、京都府内の大学生ら18人が、違法な投資に金を払わされたとして、大阪市のインターネット関連会社らを相手に損害賠償を求める集団訴訟を京都地裁に起こした。ある原告は勧誘された際に「一人紹介すれば12万円稼げる。フェイスブックで友達を誘えば」と勧められたという。SNS上でこの会社の幹部が豪遊する姿を見て、「稼げる」と信じた原告もいたという。弁護団の河野佑宣 さんは「SNSは勧誘の手段だけでなく、広告の役割も果たしている」と話す。
マルチ取引は、仲間を誘うことで自らも加害者になりうる。小池さんは「お金がないと言っても『借りればいい』と返され、断り文句にならない。興味がない、と言い切ることが大切」と呼びかける。
若者の消費者被害が後を絶たないことから、消費者庁は、被害の要因を心理的要因などから分析する検討会を発足させる。被害者からの聞き取り調査などを経て、対応策を検討する。第1回会合は14日に開かれる。
当時、婦人服の小売店を営んでいたんですね。
当時の店舗に管轄の派出所の方が時たま巡回で訪れるようになり・・・
そのうち、歳も近いということもあり彼らと個人的にも親しくなったんです。
と・・・ある日、そのうちの一人の警察官の方が
「一口〇千円の出資で知り合いを勧誘していけば儲かるし、これはネズミ講じゃないから大丈夫」・・・と
私はそのような投資話には興味がないと断ったのですが・・・
その数年後、その会は摘発されてました・・・その時、警察官も引っ掛かるんやね~とおもいましたね。
時は流れ・・・40数年経っていても未だにこのような話が横行してるんですね・・・
皆さんも甘いもうけ話には決して乗らないようにしましょうね。
例え一時儲かったとしても、あぶく銭なんてものは決して残る筈もないわけですから・・・ね!!
今朝はマルチ取引に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、9月13日読売新聞朝刊より抜粋~
成人年齢の18歳引き下げが議論されている。実現すると18、19歳も親の同意なしにローンなどが契約できるようになり、消費者被害の拡大が懸念される。違法性のある「ブラックバイト」も後を絶たない。被害防止には消費者教育の充実などが求められる。今の若者を狙っているものは何か、事情を探った。
※
マルチ取引 ある商品の販売員が新たに販売員を勧誘し、手数料などの報酬を得ながら販売網を拡大していく仕組み。違法ではないが、勧誘トラブルを防ぐため特定商取引法で「連鎖販売取引」として勧誘方法などを規制している。一方、破たんが確実なものは「ねずみ講」とされ、無限連鎖講防止法で禁止されている。マルチ取引 学生に被害拡大



「年利300%」甘い勧誘 SNSで広告

昨年12月、高校時代の先輩に「必ずもうかる」と誘われ、投資商品に30万円を支払った。しかし、その後一度も配当がない。状況を聞くと「今度はいける、年利で300%だ」と別の投資を持ちかけられた。配当は仮想通過で、仲間を誘えば「ボーナス」もつくという。1口27万円の商品を2口申し込んでしまった。
今度はパソコン上では配当が順調に増えていた。しかし、いざ換金を申請しても業者は応じず、先輩に尋ねても「待て」の一点張り。この夏、弁護士に相談して「だまされた」と悟った。大切な親の仕送りやアルバイトでためた計84万円は戻らぬままだ。男子学生は「甘かった。しかし信頼させておいて裏切る行為は許せない」と憤る。
◇
若者の間でマルチ取引※の被害が相次ぐ。各地の消費生活センターなどに寄せられるマルチ取引に関する相談は、常に20代が突出している。昨年は1万731件のうち、4282件と4割を占めた。中でも最近は「HYIP」(ハイプ)と呼ばれる投資の情報がインターネットで飛びかう。「High Yield Investment Program」(高配当投資プログラム)の略で、通常では考えられない高金利をうたい、仲間を勧誘すれば、さらに儲かるとの触れ込みだ。大半が詐欺とみられる。男子学生が誘われたのもHYIPだった。相談を受けた弁護士の荒井哲朗さんは「経済常識に反しており、まっとうな投資ではない」と話す。荒井さんら弁護士有志は被害対策弁護団を結成。8月の締め切りまでに全国から200人超の参加申し込みが殺到した。
◇
若者が被害に遭うのは、経験や知識が十分でないことが大きい。国民生活センターの小池輝明さんは「加えて、学生は広い交友関係を持ち、若手社会人はある程度自由に使えるお金がある。こうした環境にあることも要因の一つ」とみる。ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)も被害を拡大させている。
2015年、京都府内の大学生ら18人が、違法な投資に金を払わされたとして、大阪市のインターネット関連会社らを相手に損害賠償を求める集団訴訟を京都地裁に起こした。ある原告は勧誘された際に「一人紹介すれば12万円稼げる。フェイスブックで友達を誘えば」と勧められたという。SNS上でこの会社の幹部が豪遊する姿を見て、「稼げる」と信じた原告もいたという。弁護団の河野
マルチ取引は、仲間を誘うことで自らも加害者になりうる。小池さんは「お金がないと言っても『借りればいい』と返され、断り文句にならない。興味がない、と言い切ることが大切」と呼びかける。
若者の消費者被害が後を絶たないことから、消費者庁は、被害の要因を心理的要因などから分析する検討会を発足させる。被害者からの聞き取り調査などを経て、対応策を検討する。第1回会合は14日に開かれる。