「潮の干満差を利用し、浅瀬に造った石積みで魚介類を捕る古式漁法石干見(いしひび)を残」そうと活動が続けられています。13日には大分県宇佐市長洲で「世界石ひびサミット」が開催され、世界文化遺産登録を目指すそうです。世界?〜石干見は日本の浅瀬だけでなく韓国や台湾にもあるそうなんです。
「石干見は国内では18〜19世紀から記録があり、半径数百メートルの半円状に石垣を積んだ大型の定置漁法。広い浅瀬があり、干満差が大きい有明海や周防灘沿岸などで盛んに造られたが高度成長期に激減し、かって200基以上あった長崎県の島原半島では数基、宇佐市では5基のみが残る。」「現役で使用されている例は長崎県諫早市と沖縄県宮古島市だけだ」そうです。「現存数では東アジアが群を抜いており」、田和正孝教授(関西学院大漁業地理学)によりますと「石干見は自然の力を使い、乱獲につながらない持続可能な漁法。環境教育のシンボルとなる」と指摘されています。
写真の石干見は<ダブルハート>を描いています。海の中の現代アートみたいです!
(下:2019年12月13日西日本新聞-吉川文敬「石干見サミット世界遺産目標古式漁法、きょう宇佐で開幕」より)

「石干見は国内では18〜19世紀から記録があり、半径数百メートルの半円状に石垣を積んだ大型の定置漁法。広い浅瀬があり、干満差が大きい有明海や周防灘沿岸などで盛んに造られたが高度成長期に激減し、かって200基以上あった長崎県の島原半島では数基、宇佐市では5基のみが残る。」「現役で使用されている例は長崎県諫早市と沖縄県宮古島市だけだ」そうです。「現存数では東アジアが群を抜いており」、田和正孝教授(関西学院大漁業地理学)によりますと「石干見は自然の力を使い、乱獲につながらない持続可能な漁法。環境教育のシンボルとなる」と指摘されています。
写真の石干見は<ダブルハート>を描いています。海の中の現代アートみたいです!
(下:2019年12月13日西日本新聞-吉川文敬「石干見サミット世界遺産目標古式漁法、きょう宇佐で開幕」より)












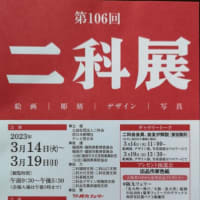





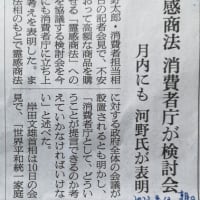

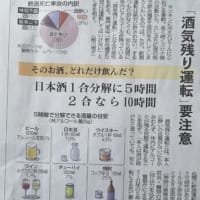
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます