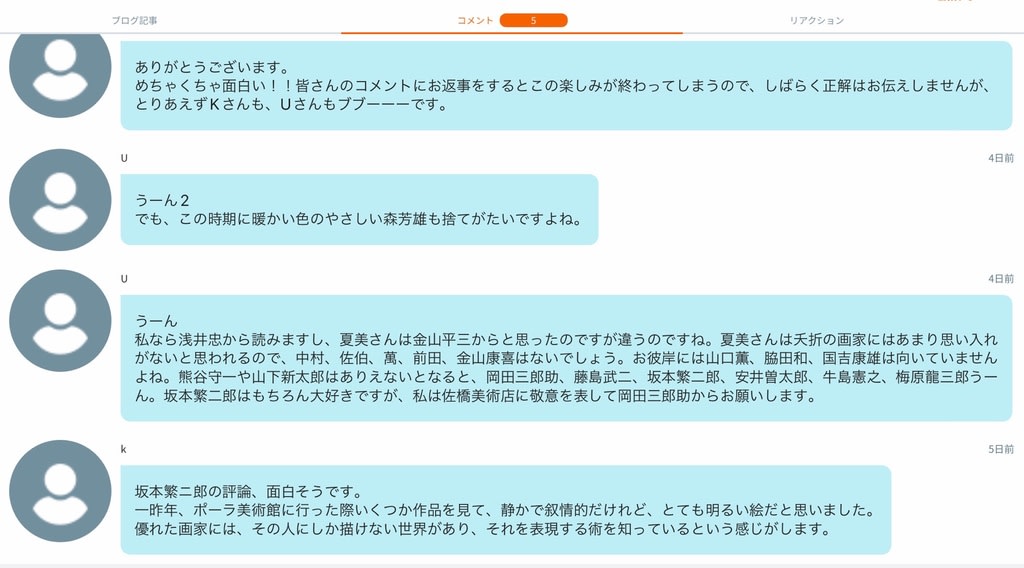結局ですね~私は梅原の章を一番初めに読み、次に岡鹿之助→金山平三→熊谷守一→楽しみに後にとっておこうと思っていて、とうとう我慢しきれなくなって山口薫→小磯良平→小絲源太郎の順に読みました。これから脇田和に入ります。
大変参考になったのは、やはり梅原と守一でしょうか。
梅原の章のつづきから
梅原が何よりも信頼しているものは、自らの体質、自らの感覚、おのれの天分である。というのは結局は、梅原は自分の仕事を観る人たちを最も信頼している画家だということにもなるわけだ。すぐれた芸術の作家は、すべて自分の仕事が人から理解されるかされまいかなどという疑いを抱くまい。そういう疑いを抱かないこと自体が天分本来の条件である。自分を納得させるためにやっている仕事であってみれば、人を納得させるかどうかの疑いは問題の外だ。その少しも危惧するところのない自己信頼の力が人々の信頼に呼応するのである。
人々はその信頼の虜になる。人々の心にはすでに帰依の微候が萌す。帰依するものにとっては、梅原の芸術は闊達無障に歩き出せば出すほど、いかにも無縫のものに見えてくる。梅原の芸術をめぐっておこなわれるおびただしい礼讃は、すべてその帰依の言葉である。全く見当違いの礼賛の言葉でも、もっともらしい嘆賞の言葉でも、ひとしく帰依の言葉であってみれば、言葉の内容などはどうでもよいのだ。
この著作のなかで今泉氏は自らも梅原の芸術に帰依してみようと決意をします。その作品を愛してみなければ、結局梅原の芸術を理解することも解釈することもできないと述べています。
梅原の作品を毛嫌いする人は、梅原が何も考えずただ才能に従って簡単に、自由気ままに、作品を仕上げていることを想像しているように思います。確かに作品からそう感じることもあります。そして私もずっとそう思っていました。けれど、実際に梅原の作品と暮らしてみると、きっと梅原には梅原なりの人としての苦しみもあったのだろうと思えてくるのです。
梅原は69歳の時、フランス文学者であった39歳のご子息を喪っています。また夫人が急逝された際には表立って誰にも頼らず荼毘に付し、その火葬場にも行かず、自宅に戻った夫人の遺骨が花に埋もれている様子を大きな画布に描き続けたと今泉氏は紹介しています。梅原なりの鎮魂の作業であり、その後少人数で夫人を偲ぶ食事会を催された際には、「私は不人情者だから、少しでも早くこの気持ちを思い諦めて、絵を描くことに没頭したい」と泣きながら挨拶をされたと書かれていました。
「思い諦めて」
そんな言葉を、普段何も考えていない人が口に出せるでしょうか?
梅原龍三郎という画家は、「真理」の近くにいた人だということが、「不人情だから」「思い諦めて」という言葉だけでも感じられるように思います。真理というよりは「自然の摂理」といった方がぴったりくるかもしれません。
今泉氏は梅原に帰依するとしながらも梅原がその才能をやたらに浪費しているように思えてならない。梅原の仕事に本質的な意味での進歩はあったのか?と書いています。
多くの画家がその画業を通し、精神を磨き、段階を経て真理に一歩づつ近づくというイメージが、美術評論というジャンルを育てたと言ってよいように思います。が、結局は真理に近づく作業というのは、「自分を諦めていく」ということ。
梅原のあの一気呵成の筆のリズム感は、この諦める力の強さと無関係ではないように思えます。普通の画家が画業を通して得ていくその諦観を、梅原はすでに持っていたといえるように感じるのです。だからこそ、梅原の作品には評論は要らないのです。

画家梅原龍三郎は、自然から触発されることなしには絶対に制作しない。何千枚の薔薇図を描いてきた現在でも、また新たな薔薇の実物を眼前にしなければ薔薇の絵を描こうとしない。自然から触発されることが、この画家にとって絵画表現の永遠の大道なのである。
梅原の作品と暮らしていると、その温かさにどっぷりと浸っている自分に気がつきます。 梅原の描く自然観に癒されるのです。
私には、今のこの悲しみを梅原のように一気呵成に「思い諦める」力など無いけれど、こうして梅原の作品に温かさを感じられているうちは、きっときちんと自分の悲しみを見定められているだろうと信じ、いつかこの悲しみが静かで美しい姿に変化してくれるよう祈りたいと思っています。
またこの著作集については折に触れて、書かせていただきたいと思っています。よろしければ、お付き合いください。