「スイス8日間の旅」のレポート途中ですが中断して、今日は日曜日に歩いたカン
トリーウオークのレポートです。
======================================
2012年6月10日(日)
前日梅雨入りしたが、今朝は晴れた。カントリーウオークのグループの第194回
例会を開催する。集合地は、JR宇都宮線と東武伊勢崎線の久喜駅。4組に分かれて
10時16分に西口をスタートした。
== 久喜市総合運動公園から久喜菖蒲公園へ ==
中央二丁目と三丁目の間の通りを進むと、どっしりとした蔵造りの家が残っていた。

南一丁目の中ほどの公園に、富士塚のような盛り土の山がある。御嶽講の信仰者が
明治27年(1894)につくったもので、山頂には御嶽神社が祭られていた。

公園の南側で、地元の人が山車の組み立てをしていた。7月12日と18日に開催
の、関東一という「提燈(ちようちん)祭り」の準備のようだ。

南四丁目に回り、車の少ない住宅地の路地を進む。文化会館の横に出るつもりが、
路地が尽きて家庭菜園などの畑のところに出た。

畑の尽きたところで雑草地を抜けて、文化会館の広場に入る。プラネタリウムのあ
る丸ドームの前で水分補給の休憩をした。

道路の北側は久喜市役所である。

歩道にイチョウ並木のある市役所通りを南へ、空に浮かぶ綿雲を見ながら少し進む
と、「水と緑のふれあいロード」の、広範囲のエリアマップが立っていた。傍らを流
れる新川用水沿いの遊歩道である。

近くの畑にソバが花盛りだが雑草も多く、こぼれ種が咲いたのだろうか…。


県道87号と合するY字路の手前で田んぼのあぜ道を横切り、久喜市総合運動公園
に入った。
クローバの咲くメインアリーナでは少年サッカーチムが試合中で、父母の声援が賑
やか。


桜並木の西側の気持ちよい緑陰を、体育館に向かう。ピンクのシモツケが、たくさ
ん咲き競っていた。

テニスコートの横から備前前堀川沿いに出て、県道3号を横断する。すぐ先で東北
自動車道の下をくぐり、西側の田んぼの中を工業団地の工場に沿って迂回し、備前前
堀川の小さな橋を渡る。

アジサイの咲く小谷の集落を抜け、備前前堀川と備前堀川を渡り、昼食地の久喜菖
蒲公園の大きな休憩舎に、11時55分に着いた。

公園の大部分を占める、大きな池の中から上がる噴水を眺めながら、休憩舎横の緑
陰で昼食とする。
== 田園地帯から二つの館跡へ ==
ミーティングと記念撮影後、13時15分に出発した。池の北側の遊歩道を中ほど
まで進み、久喜菖蒲工業団地落成記念碑の横から公園を抜ける。

工業団地を横断し、再び備前堀川と備前前堀川を渡ると、早苗田の広がる田園地帯。
西の空に黒雲が広がり、天候が気になる。

所久喜(ところくき)集落に入り、八幡神社本殿の「楠木正成父子桜井の別れ」な
どが刻まれた精巧な木彫を眺める。

すぐ先の民家の、門構えの奥のうっそうとした屋敷林は、市の保存樹林に指定され
ていた。
集落の東も田園地帯、盛り土無しの平地を走る東北自動車道下を東に抜けて江面集
落へ。近年再建らしい新しい本堂の善徳寺で、小休止して水分補給をする。

さらに田園地帯を北へ、苅り入れ時となった麦畑も広がる。

NHKラジオ放送の2本のアンテナを見ながら進み、県道146号に接した下清久
の清福寺に行く。

ここも本堂は新しく、その前にご神木の大イチョウが立つ。そばに赤いポストが祭
られ、かわいい動物たちの並ぶペット慰霊塔と水子地蔵塔、本堂の俳壇前には男女の
とげぬき治蔵などの飾り物が並ぶ。

イチョウの背後には、真新しい金色の観音蔵を祭ったお堂もあるという、ユニーク
な寺院だった。

すぐ先、電波塔のところで県道に分かれて進むと、赤鳥居の奥、大イチョウの下に
ひっそりと赤旗神社がある。村人が平家の武士たちを祭って神社を造ったとか。ちな
みに赤旗は、源氏の白旗に対抗する平家の旗の色。

大イチョウは雌木らしく、下にイチョウの幼木がたくさん生えていた。
近くの常徳院と雷電神社はこの地を治めた清久氏(きよくし)の館跡(やかたあと)。
りっぱな本堂ときれいに整えられた常徳院に入ると、Tさんが近くで声をかけられた
という副住職さんが戻られ、勧められ本堂に上がる。

源平の時代この地を治めた清久氏のこと、檀家を持たない祈祷寺だったこと、近年
修復した仏像のことなど、寺にまつわることを副住職さんから詳しく伺った。
寺で40分近く経過したので先を急ぐ。養護学校の北側を通過し、諏訪神社の横か
ら新川用水沿いの遊歩道を歓喜院の横まで進む。
久喜本の住宅地を東へ抜け、県道3号を横断して本町六丁目の千勝神社に寄り、本
殿の龍などの精細な彫刻を眺める。

北に見える森の木々にゴイサギやシラサギがたくさん群がり、コロニーになってい
るらしい。森のある甘棠院(かんとういん)は二代目古河公方(こがくぼう)、足利
政氏(まさうじ)の館跡で墓もあるという。

でも、寺は門は閉じて入れない。門前から本堂と豊富な樹木に覆われた境内をのぞ
くのみとする。
近くの光明寺は。本堂前にきれいな芝生が広がり、庭木もよく整えられている。

南側にある薬師堂は、白鳳10年(682)行基菩薩の開創とか。いまは色あせて
はいるが社殿の木彫は極彩色で、建立当時の彩りを想像させてくれる。

7月の堤燈祭りの看板が並ぶ県道146号を進み、16時51分に久喜駅に戻った。
(天気 晴後曇、参加 17人、距離 13㎞、地図(1/2.5万) 久喜、歩行地
久喜市、歩数 22,500)
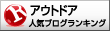 アウトドア ブログランキングへ
アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村
トリーウオークのレポートです。
======================================
2012年6月10日(日)
前日梅雨入りしたが、今朝は晴れた。カントリーウオークのグループの第194回
例会を開催する。集合地は、JR宇都宮線と東武伊勢崎線の久喜駅。4組に分かれて
10時16分に西口をスタートした。
== 久喜市総合運動公園から久喜菖蒲公園へ ==
中央二丁目と三丁目の間の通りを進むと、どっしりとした蔵造りの家が残っていた。

南一丁目の中ほどの公園に、富士塚のような盛り土の山がある。御嶽講の信仰者が
明治27年(1894)につくったもので、山頂には御嶽神社が祭られていた。

公園の南側で、地元の人が山車の組み立てをしていた。7月12日と18日に開催
の、関東一という「提燈(ちようちん)祭り」の準備のようだ。

南四丁目に回り、車の少ない住宅地の路地を進む。文化会館の横に出るつもりが、
路地が尽きて家庭菜園などの畑のところに出た。

畑の尽きたところで雑草地を抜けて、文化会館の広場に入る。プラネタリウムのあ
る丸ドームの前で水分補給の休憩をした。

道路の北側は久喜市役所である。

歩道にイチョウ並木のある市役所通りを南へ、空に浮かぶ綿雲を見ながら少し進む
と、「水と緑のふれあいロード」の、広範囲のエリアマップが立っていた。傍らを流
れる新川用水沿いの遊歩道である。

近くの畑にソバが花盛りだが雑草も多く、こぼれ種が咲いたのだろうか…。


県道87号と合するY字路の手前で田んぼのあぜ道を横切り、久喜市総合運動公園
に入った。
クローバの咲くメインアリーナでは少年サッカーチムが試合中で、父母の声援が賑
やか。


桜並木の西側の気持ちよい緑陰を、体育館に向かう。ピンクのシモツケが、たくさ
ん咲き競っていた。

テニスコートの横から備前前堀川沿いに出て、県道3号を横断する。すぐ先で東北
自動車道の下をくぐり、西側の田んぼの中を工業団地の工場に沿って迂回し、備前前
堀川の小さな橋を渡る。

アジサイの咲く小谷の集落を抜け、備前前堀川と備前堀川を渡り、昼食地の久喜菖
蒲公園の大きな休憩舎に、11時55分に着いた。

公園の大部分を占める、大きな池の中から上がる噴水を眺めながら、休憩舎横の緑
陰で昼食とする。
== 田園地帯から二つの館跡へ ==
ミーティングと記念撮影後、13時15分に出発した。池の北側の遊歩道を中ほど
まで進み、久喜菖蒲工業団地落成記念碑の横から公園を抜ける。

工業団地を横断し、再び備前堀川と備前前堀川を渡ると、早苗田の広がる田園地帯。
西の空に黒雲が広がり、天候が気になる。

所久喜(ところくき)集落に入り、八幡神社本殿の「楠木正成父子桜井の別れ」な
どが刻まれた精巧な木彫を眺める。

すぐ先の民家の、門構えの奥のうっそうとした屋敷林は、市の保存樹林に指定され
ていた。
集落の東も田園地帯、盛り土無しの平地を走る東北自動車道下を東に抜けて江面集
落へ。近年再建らしい新しい本堂の善徳寺で、小休止して水分補給をする。

さらに田園地帯を北へ、苅り入れ時となった麦畑も広がる。

NHKラジオ放送の2本のアンテナを見ながら進み、県道146号に接した下清久
の清福寺に行く。

ここも本堂は新しく、その前にご神木の大イチョウが立つ。そばに赤いポストが祭
られ、かわいい動物たちの並ぶペット慰霊塔と水子地蔵塔、本堂の俳壇前には男女の
とげぬき治蔵などの飾り物が並ぶ。

イチョウの背後には、真新しい金色の観音蔵を祭ったお堂もあるという、ユニーク
な寺院だった。

すぐ先、電波塔のところで県道に分かれて進むと、赤鳥居の奥、大イチョウの下に
ひっそりと赤旗神社がある。村人が平家の武士たちを祭って神社を造ったとか。ちな
みに赤旗は、源氏の白旗に対抗する平家の旗の色。

大イチョウは雌木らしく、下にイチョウの幼木がたくさん生えていた。
近くの常徳院と雷電神社はこの地を治めた清久氏(きよくし)の館跡(やかたあと)。
りっぱな本堂ときれいに整えられた常徳院に入ると、Tさんが近くで声をかけられた
という副住職さんが戻られ、勧められ本堂に上がる。

源平の時代この地を治めた清久氏のこと、檀家を持たない祈祷寺だったこと、近年
修復した仏像のことなど、寺にまつわることを副住職さんから詳しく伺った。
寺で40分近く経過したので先を急ぐ。養護学校の北側を通過し、諏訪神社の横か
ら新川用水沿いの遊歩道を歓喜院の横まで進む。
久喜本の住宅地を東へ抜け、県道3号を横断して本町六丁目の千勝神社に寄り、本
殿の龍などの精細な彫刻を眺める。

北に見える森の木々にゴイサギやシラサギがたくさん群がり、コロニーになってい
るらしい。森のある甘棠院(かんとういん)は二代目古河公方(こがくぼう)、足利
政氏(まさうじ)の館跡で墓もあるという。

でも、寺は門は閉じて入れない。門前から本堂と豊富な樹木に覆われた境内をのぞ
くのみとする。
近くの光明寺は。本堂前にきれいな芝生が広がり、庭木もよく整えられている。

南側にある薬師堂は、白鳳10年(682)行基菩薩の開創とか。いまは色あせて
はいるが社殿の木彫は極彩色で、建立当時の彩りを想像させてくれる。

7月の堤燈祭りの看板が並ぶ県道146号を進み、16時51分に久喜駅に戻った。
(天気 晴後曇、参加 17人、距離 13㎞、地図(1/2.5万) 久喜、歩行地
久喜市、歩数 22,500)
にほんブログ村














