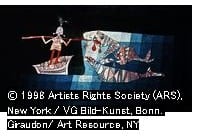小林秀雄氏の評論は、私たちの時代では、高校から大学のころ多くの人が一度は触れているのではと思います。
小林秀雄氏の評論は、私たちの時代では、高校から大学のころ多くの人が一度は触れているのではと思います。
私にとっても、本当に久しぶりの「小林秀雄」です。
本書は、小林氏が1929年文壇に登場して以来の時間を14の期に分け、その時々の作品からの「言葉」を精選して並べています。
前後の文脈を捨象した抜粋という形式には賛否があろうかと思いますが、刺激になることは確かです。
まず、1期。27歳の作「志賀直哉」から「ものを見る」ことについてです。
(p16より引用) 私は所謂慧眼というものを恐れない。ある眼があるものを唯一つの側からしか眺められない処を、様々な角度から眺められる眼がある、そういう眼を世人は慧眼と言っている。・・・私が恐ろしいのは決して見ようとはしないで見ている眼である。物を見るのに、どんな角度から眺めるかという事を必要としない眼、吾々がその眼の視点の自由度を定める事が出来ない態の眼である。
「複眼的にものを見る」とか、「別の視点で」「視座を変えて」とかと言われますが、小林氏は、そういった次元を超えた「眼」を捉えています。
「見る」ことの対象が芸術であった場合、それは「鑑賞」という言葉と近似します。
32歳の作「文学鑑賞の精神と方法」からの小林氏の言葉です。
(p43より引用) ただ鑑賞しているという事が何となく頼りなく不安になって来て、何か確とした意見が欲しくなる、そういう時に人は一番注意しなければならない。・・・生じっか意見がある為に広くものを味う心が衰弱して了うのです。意見に準じて凡てを鑑賞しようとして知らず知らずのうちに、自分の意見にあったものしか鑑賞出来なくなって来るのです。・・・こうなるともう鑑賞とは言えません。ただ自分の狭い心の姿を豊富な対象のなかに探し廻っているだけで、而も当人は立派に鑑賞していると思い込んでいるというだらしのない事になって了います。
だとすると「鑑賞」とはどんなものでしょうか。
どうやら、何かによることなく、素直に対象に対しそのものとして広く味わう・・・ということのように思われますが、人は、何らかの判断軸や価値観をもって、それに照らして対象を位置づけるものでしょう・・・。
これと似たような「見る」ということについて、47歳の作「私の人生観」のなかでは以下のように語っています。
(p136より引用) 大切な事は、真理に頼って現実を限定することではない、在るがままの現実体験の純化である。見るところを、考える事によって抽象化するのではない、見る事が考える事と同じになるまで、視力を純化するのが問題なのである。
また、その後の文脈でも宮本武蔵の「五輪書」に触れた以下のような言及があります。
(p139より引用) 「意は目に付き、心は付かざるもの也」、常の目は見ようとするが、見ようとしない心にも目はあるのである。言わば心眼です。見ようとする意が目を曇らせる。だから見の目を弱く観の目を強くせよと言う。
この点は、以前、このBlogで「五輪書」を紹介した際、「目付け」についての「観の目」でお話した点と一脈通じています。
 |
人生の鍛錬―小林秀雄の言葉 価格:¥ 756(税込) 発売日:2007-04 |