1日の松戸記念の決勝。並びは吉田‐神山‐諸橋の関東と根田‐中村‐海老根の千葉で佐藤と筒井と小川は単騎。
牽制が長引き渋々といった感じで根田がスタートを取って前受け。4番手に佐藤,5番手に筒井,6番手に吉田,最後尾に小川で周回。残り4周のバックの出口から早くも吉田が動き,残り3周のホームでは根田を叩いて前に。早くも誘導は退避しました。意外にも単騎の選手に動きがなかったため,この時点で4番手に根田,7番手に佐藤,8番手に筒井,最後尾に小川という一列棒状に。このまま残り2周のホームも経過し,バックで吉田がスピードを上げていって打鐘。ホーム前のコーナーから根田が発進。神山のブロックもありなかなか前まで出られず,バックに入ってからまたも神山のブロックを受けて不発に。牽制に行った神山の内にマークの諸橋が斬り込んだため,最終コーナーで神山は浮いてしまいました。直線は諸橋が踏み込んで優勝。結果的にマークする形になった佐藤が半車身差で2着。佐藤の後ろの筒井も半車身差の3着に続きました。
優勝した新潟の諸橋愛選手は前回出走の共同通信社杯から連続優勝。8月には弥彦記念を優勝していて記念競輪は5勝目。松戸記念は初優勝。このレースはメンバーと並びを見た段階で一筋縄では収まりそうもないと思えました。吉田の逃げを根田が捲るのも展開としては想定できましたが,まさか諸橋がラインの神山の内に斬りこむとは思ってもいませんでした。このシビアな競走ぶりがこの優勝を大きく引き寄せたといえるでしょう。これは今後もこういう競走をしますよということでしょうから,そういうことも予想の範疇に入れていかなければならないことになったといえそうです。
5月27日,土曜日。妹の土曜出勤でした。施設は変わりましたが月に1度の土曜出勤は継続しています。この日は山下公園の散策でした。
5月31日,水曜日。新川崎に行っていましたが,移動中に哲学関連の本を読了しました。
『スピノザ哲学論攷』を読了してから概ね半年で,僕はスピノザ関連の書籍を2冊読了しています。ここでそれらをまとめて紹介します。というのはこのうち1冊は,哲学そのものに関係する部分に対する関心は薄いので,本論としてでなく別枠で取り扱うからです。それが『スピノザ―ナ』の15号です。
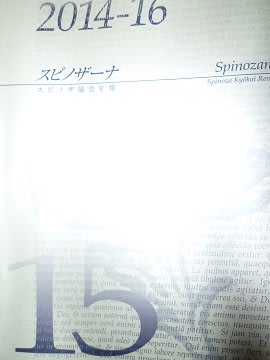
この『スピノザ―ナ』は,日本のスピノザ協会が発行している年報です。僕はスピノザ協会の会員ではありませんが,この年報は一般に販売されていますからだれでも読むことができるものです。年報となっていますが,現在は毎年発行されているわけではありません。実際に僕が読み終えた15号は,2014-16となっています。14号は2015年1月に発行されていて,15号は今年1月の発行ですから,14号と15号の間には2年の間隔がありました。協会の総会ではこの冊子を隔年発行とするということが了承されていると編集後記にありますので,次は2019年の1月に発行される予定ですが,実際に発行できるかどうかの見通しが立っているわけではないと思われます。というのも実入りに合わせた刊行頻度になるとありますから,経済的に余裕がなくなれば,これが最終号となる可能性すら残っているからです。
2016年7月に選出されたスピノザ協会の運営委員が6人いて,この6人がそのまま15号の編集委員となっています。『スピノザの世界』などの上野修,『宮廷人と異端者』の共訳者のひとりである桜井直文が6人の中に名を連ね,上野の論文が1本,15号に掲載されています。平尾昌弘,高木久夫のふたりも編集委員で,論文の発表者です。ほかに木島泰三と鈴木泉が編集者に名を連ねていますが,このふたりと桜井の論文は15号にはありません。15号のほかの執筆者は矢島直規,吉田和弘,柏葉武秀,寅野遼の4名。『スピノザ哲学研究』の工藤喜作の絶筆も掲載されています。
牽制が長引き渋々といった感じで根田がスタートを取って前受け。4番手に佐藤,5番手に筒井,6番手に吉田,最後尾に小川で周回。残り4周のバックの出口から早くも吉田が動き,残り3周のホームでは根田を叩いて前に。早くも誘導は退避しました。意外にも単騎の選手に動きがなかったため,この時点で4番手に根田,7番手に佐藤,8番手に筒井,最後尾に小川という一列棒状に。このまま残り2周のホームも経過し,バックで吉田がスピードを上げていって打鐘。ホーム前のコーナーから根田が発進。神山のブロックもありなかなか前まで出られず,バックに入ってからまたも神山のブロックを受けて不発に。牽制に行った神山の内にマークの諸橋が斬り込んだため,最終コーナーで神山は浮いてしまいました。直線は諸橋が踏み込んで優勝。結果的にマークする形になった佐藤が半車身差で2着。佐藤の後ろの筒井も半車身差の3着に続きました。
優勝した新潟の諸橋愛選手は前回出走の共同通信社杯から連続優勝。8月には弥彦記念を優勝していて記念競輪は5勝目。松戸記念は初優勝。このレースはメンバーと並びを見た段階で一筋縄では収まりそうもないと思えました。吉田の逃げを根田が捲るのも展開としては想定できましたが,まさか諸橋がラインの神山の内に斬りこむとは思ってもいませんでした。このシビアな競走ぶりがこの優勝を大きく引き寄せたといえるでしょう。これは今後もこういう競走をしますよということでしょうから,そういうことも予想の範疇に入れていかなければならないことになったといえそうです。
5月27日,土曜日。妹の土曜出勤でした。施設は変わりましたが月に1度の土曜出勤は継続しています。この日は山下公園の散策でした。
5月31日,水曜日。新川崎に行っていましたが,移動中に哲学関連の本を読了しました。
『スピノザ哲学論攷』を読了してから概ね半年で,僕はスピノザ関連の書籍を2冊読了しています。ここでそれらをまとめて紹介します。というのはこのうち1冊は,哲学そのものに関係する部分に対する関心は薄いので,本論としてでなく別枠で取り扱うからです。それが『スピノザ―ナ』の15号です。
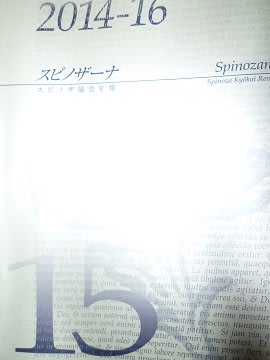
この『スピノザ―ナ』は,日本のスピノザ協会が発行している年報です。僕はスピノザ協会の会員ではありませんが,この年報は一般に販売されていますからだれでも読むことができるものです。年報となっていますが,現在は毎年発行されているわけではありません。実際に僕が読み終えた15号は,2014-16となっています。14号は2015年1月に発行されていて,15号は今年1月の発行ですから,14号と15号の間には2年の間隔がありました。協会の総会ではこの冊子を隔年発行とするということが了承されていると編集後記にありますので,次は2019年の1月に発行される予定ですが,実際に発行できるかどうかの見通しが立っているわけではないと思われます。というのも実入りに合わせた刊行頻度になるとありますから,経済的に余裕がなくなれば,これが最終号となる可能性すら残っているからです。
2016年7月に選出されたスピノザ協会の運営委員が6人いて,この6人がそのまま15号の編集委員となっています。『スピノザの世界』などの上野修,『宮廷人と異端者』の共訳者のひとりである桜井直文が6人の中に名を連ね,上野の論文が1本,15号に掲載されています。平尾昌弘,高木久夫のふたりも編集委員で,論文の発表者です。ほかに木島泰三と鈴木泉が編集者に名を連ねていますが,このふたりと桜井の論文は15号にはありません。15号のほかの執筆者は矢島直規,吉田和弘,柏葉武秀,寅野遼の4名。『スピノザ哲学研究』の工藤喜作の絶筆も掲載されています。















