昨晩の第14回レディスプレリュード。
逃げて結果を残していたサルサディオーネが最内枠に入りましたのでこの馬が逃げるのは予想通り。ただ半馬身差でララベル,さらに半馬身差で外に切り替えたマイティティーが続く形に。この後ろは2馬身ほどの間隔でクイーンマンボ。1馬身差でアンジュデジール。この後ろがまた2馬身ほどでホワイトフーガ。さらに後ろは5馬身ほど離れるという縦長の隊列に。最初の800mは50秒0のミドルペース。
3コーナーを回っても前の3頭は雁行状態。これらの外からクイーンマンボが追い,内を狙ったのがアンジュデジール。さらに外からホワイトフーガも追い上げてきました。直線に入ると外から4頭目のクイーンマンボが少しばかり内に切れ込むような感じで先頭に。ここから後続をぐんぐんと引き離していくワンサイドゲームで圧勝。大外を追い込んだホワイトフーガが8馬身差で2着。ララベルとマイティティーの間に進路を取ったアンジュデジールはハナ差で3着。
優勝したクイーンマンボは関東オークス以来の勝利で重賞2勝目。そのときの内容が強く,古馬相手の初戦は2着でしたが,ダート競馬は一般的に3歳馬の対古馬初戦は苦戦するものなのでまずまずの結果。前走の芝は結果を残せませんでしたがまたダートに戻り,能力はホワイトフーガの方が上かもしれないけれども斤量と距離適性からこちらが優勝候補の筆頭ではないかと考えていました。ですがこれほど離して勝てると思っていたわけではありません。JBCレディスクラシックに向かうことになると思われますが,斤量関係こそ不利にはなるものの,優勝候補の筆頭という評価でいいのではないかと思います。牡馬相手でも戦える馬かもしれません。父はマンハッタンカフェ。母の父はシンボリクリスエス。3代母がキーフライヤー。母の半兄にスズカマンボ。
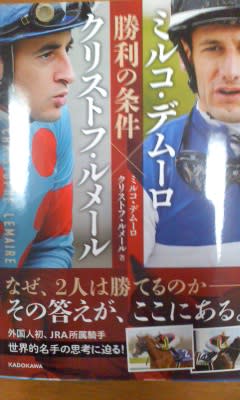

騎乗したクリストフ・ルメール騎手はレディスプレリュード初勝利。管理している角居勝彦調教師は第12回以来2年ぶりのレディスプレリュード2勝目。
『スピノザ―ナ15号』の矢島直規の論文に関する疑問とは概ね次のようなものです。
この論文の結論が示される直前の部分で,スピノザは理性ratioの導きに従って生活し,それによって他者との一致を達成するべきだと主張したとあります。論文ではその根拠に第四部定理三三だけが示されていますが,第四部定理三五もその根拠になり得るでしょう。原則論としていえば,これは間違いではないと僕は思います。なお,スピノザがそのように主張したと解しているのは,矢島自身であるかもしれませんが,ヒュームDavid Humeがそのように解釈したと矢島が解していると読むことができるような文章になっています。
これに対してヒュームは,理性とは無関係な人間の一般的傾向が社会秩序を形成するという立場で,論文においてはこの立場が自然による秩序形成の立場といわれています。そしてヒュームはその立場に留まることによって,理性に基づく社会形成の理論を否定したのだとされています。このとき,理性に基づくこの理論が,社会契約といわれています。
まず,僕が疑問に感じるのは,ここではあたかもスピノザの理論とヒュームの理論が相容れないような対立的理論として描かれている点です。確かにスピノザは理性に従うことを自然すなわち受動passioに従うことよりもよいことであると考えていたのは間違いありません。ですが,僕の考えでいえば,たぶんスピノザはヒュームがいっているような理論のことを肯定します。それが社会契約論と対立的であるということを踏まえたら,僕はここで示されているヒュームの理論は,たとえば社会契約説を唱えるホッブズThomas Hobbesの理論よりも,スピノザには肯定しやすい理論になっていると思います。最も単純にいえば,いくら理性に従うことがよいことであるといったからといって,第四部定理四が示しているように,ここでいわれている自然の力potentiaは,理性の力を上回るからです。第四部定理三のいい方に倣えば,自然の力は理性の力を無限に凌駕するでしょう。
したがって,人間が何らかの秩序を形成するというときに,自然の力を無視するような理論はスピノザにはあり得ません。大事なのは秩序の内容に関わるのです。
逃げて結果を残していたサルサディオーネが最内枠に入りましたのでこの馬が逃げるのは予想通り。ただ半馬身差でララベル,さらに半馬身差で外に切り替えたマイティティーが続く形に。この後ろは2馬身ほどの間隔でクイーンマンボ。1馬身差でアンジュデジール。この後ろがまた2馬身ほどでホワイトフーガ。さらに後ろは5馬身ほど離れるという縦長の隊列に。最初の800mは50秒0のミドルペース。
3コーナーを回っても前の3頭は雁行状態。これらの外からクイーンマンボが追い,内を狙ったのがアンジュデジール。さらに外からホワイトフーガも追い上げてきました。直線に入ると外から4頭目のクイーンマンボが少しばかり内に切れ込むような感じで先頭に。ここから後続をぐんぐんと引き離していくワンサイドゲームで圧勝。大外を追い込んだホワイトフーガが8馬身差で2着。ララベルとマイティティーの間に進路を取ったアンジュデジールはハナ差で3着。
優勝したクイーンマンボは関東オークス以来の勝利で重賞2勝目。そのときの内容が強く,古馬相手の初戦は2着でしたが,ダート競馬は一般的に3歳馬の対古馬初戦は苦戦するものなのでまずまずの結果。前走の芝は結果を残せませんでしたがまたダートに戻り,能力はホワイトフーガの方が上かもしれないけれども斤量と距離適性からこちらが優勝候補の筆頭ではないかと考えていました。ですがこれほど離して勝てると思っていたわけではありません。JBCレディスクラシックに向かうことになると思われますが,斤量関係こそ不利にはなるものの,優勝候補の筆頭という評価でいいのではないかと思います。牡馬相手でも戦える馬かもしれません。父はマンハッタンカフェ。母の父はシンボリクリスエス。3代母がキーフライヤー。母の半兄にスズカマンボ。
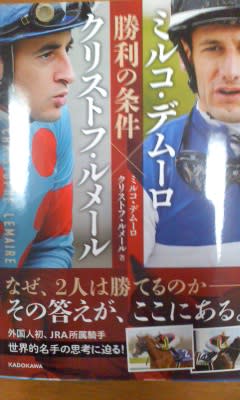

騎乗したクリストフ・ルメール騎手はレディスプレリュード初勝利。管理している角居勝彦調教師は第12回以来2年ぶりのレディスプレリュード2勝目。
『スピノザ―ナ15号』の矢島直規の論文に関する疑問とは概ね次のようなものです。
この論文の結論が示される直前の部分で,スピノザは理性ratioの導きに従って生活し,それによって他者との一致を達成するべきだと主張したとあります。論文ではその根拠に第四部定理三三だけが示されていますが,第四部定理三五もその根拠になり得るでしょう。原則論としていえば,これは間違いではないと僕は思います。なお,スピノザがそのように主張したと解しているのは,矢島自身であるかもしれませんが,ヒュームDavid Humeがそのように解釈したと矢島が解していると読むことができるような文章になっています。
これに対してヒュームは,理性とは無関係な人間の一般的傾向が社会秩序を形成するという立場で,論文においてはこの立場が自然による秩序形成の立場といわれています。そしてヒュームはその立場に留まることによって,理性に基づく社会形成の理論を否定したのだとされています。このとき,理性に基づくこの理論が,社会契約といわれています。
まず,僕が疑問に感じるのは,ここではあたかもスピノザの理論とヒュームの理論が相容れないような対立的理論として描かれている点です。確かにスピノザは理性に従うことを自然すなわち受動passioに従うことよりもよいことであると考えていたのは間違いありません。ですが,僕の考えでいえば,たぶんスピノザはヒュームがいっているような理論のことを肯定します。それが社会契約論と対立的であるということを踏まえたら,僕はここで示されているヒュームの理論は,たとえば社会契約説を唱えるホッブズThomas Hobbesの理論よりも,スピノザには肯定しやすい理論になっていると思います。最も単純にいえば,いくら理性に従うことがよいことであるといったからといって,第四部定理四が示しているように,ここでいわれている自然の力potentiaは,理性の力を上回るからです。第四部定理三のいい方に倣えば,自然の力は理性の力を無限に凌駕するでしょう。
したがって,人間が何らかの秩序を形成するというときに,自然の力を無視するような理論はスピノザにはあり得ません。大事なのは秩序の内容に関わるのです。















